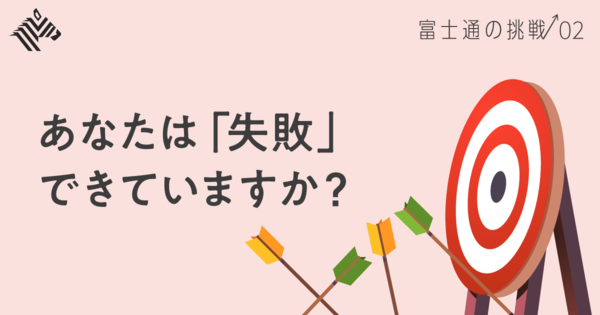【富士通】本当に「挑戦できる」組織が大切にする発想
コメント
注目のコメント
大切なのは、失敗を経験すること、そこから学びを得ること、得た学びを周りに広めることだと思う。
挑戦によりポテンシャルのある失敗はできるが、そのポテンシャルを顕在化させるには、むしろ学びの抽出が重要。学びが直接的/具体的すぎると、全く同じ場面では活かされるかもしれないが、ずれた場面では活かせなくなってしまう。つまり、1の失敗から1の学びしか得られない。学びを一段抽象化すると、異なる場面でも学びのエッセンスが活かされる。
例えば、「地震が来たら机の下に隠れる」という学びを、一段抽象化すると、「災害時には安全な場所に避難する」となる。そうすると、安全な場所とは机の下に限らず、高台の上や体育館など様々なものが出てくる。そうなると、地震だけでなく、「津波が来たら高台に避難する」「豪雨が来たら体育館に避難する」というように、異なる場面にも活かせるようになる。
いかに一つの失敗を他の場面にも応用できるように汎用化するかが、学びの肝ではないか。
もうひとつ、それを個々人に閉じるだけでなく、組織に広げて、失敗を経験していない人もあたかも経験したかのように学びを活かせるようにする共有も大切。ここは逆に、抽象化された学びだけではイメージが湧かなかったり、当たり前のものにしか見えない可能性がある。むしろどんな具体的な場面に直面し、そこからどんな失敗を経験し、どんな思考回路によって学びを抽出したのかというストーリー単位で共有することが有効ではないか。イメージが湧くことで、「では自分の身の回りで起き得て、且つこの学びが活きるのはどんな場面か?」と想像が湧き、失敗を経験していないにもかかわらず学びを活かせるようになる。
この組織単位を、部署・企業・業界・社会・国家とより大きな括りまで広げることができれば、より失敗のレバレッジが効くことになる。私自身は、大企業に所属したことがありませんので、これまで「やりたい放題」と言っても過言ではないくらい好きなことをやらせていただきました。
担当外の仕事をやる、勝手に他部署の人を巻き込んで仕事をする、は日常茶飯事です。前職時代を含めて。
したがって、「挑戦が当たり前の富士通を作る」と聞いたとき、「大企業では、挑戦できないが当たり前ではないのですか」は、素の質問でした。
大企業に所属している知人の話を聞くと、確かに人が豊富にいる分、「分業」と「仕組み」が確立されているな、といった印象があります。
皆さん、優秀な方ばかりなのですが、美鳥一人に妙な「担当」という者が割り当てられている分、その人のポテンシャルを十分に発揮できていないのでは、と思ったこともあります。
もちろん、豊富なリソース(人もお金も)、確立された仕組みがあることは、大企業に所属したことがない身としては羨ましい、または参考にしたいと思うことも多々あります。「もっとチャレンジしろ」とだけ言われても、チャレンジを応援・推奨するような文化だったり、チャレンジの結果の失敗を許容する文化が前提としてないと、型にはめられた“正解”だけを追求する社員がマジョリティであることは変わらないと思います。
挑戦することの重要性は、大企業であろうがスタートアップであろうが、ベテラン社員であろうが若手社員であろうが変わらないはずで、挑戦できないことを会社や環境や上司のせいにすることも違います。
ビジネスにおける正解は一つではないこと、仮に一つしかない場合もアプローチ方法は複数あること、正解を見つけるのは自分自身であることを当たり前に感じられる人が増えるといいですね。