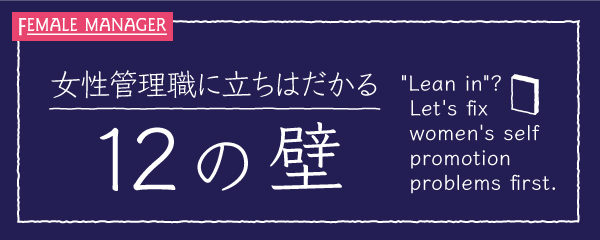
「管理職になるのが不安の壁」はこう乗り越える
下駄を履いて部長になるのも、組織への貢献だ。
2014/11/26
安倍内閣は「社会のあらゆる分野における、指導的地位に女性が占める割合」を2020年までに30%まで引き上げると宣言。だが、急遽、管理職になった女性社員の中には、明らかな能力不足を指摘されるケースもある。では、先達の女性管理職たちは、どうやってスキル不足やテクニック不足、あるいは周囲の理解不足といった”壁”を乗り越えてきたのか?連載第9回は、前回に引き続き、女性が管理職になりたがらない要因となる不安の正体やその乗り越え方について取り上げる。「漠然とした不安」を理由に一度は課長の打診を断った日立ソリューションズの伊藤直子さんが、半年後の再打診を受け入れようと思った理由は何か。
第8回:女性が「管理職の打診」に反射的にNOと言う理由
管理職にならずに定年まで過ごす自分をシミュレーション
伊藤さんは、自分自身に二つの問いを立てたという。
「一つは、『今ではない』としたら、いつやるの? という問いです。今の自分にはまだ早いのであれば、3年後ならいいのか。それとも、5年後? 10年後? 考えてみると『○年後なら大丈夫』という明確な答えは出ませんでした」
仮にずっと課長にならなかったとすればどうなるかも想像してみた。すると、現場の主任として定年までやっていくという選択をすることになる。
「でも、技術者として優秀な人は他にもたくさんいるし、体力的にも難しいだろうと感じました。それならば、課長という立場を今受け入れてもいいんじゃないかという思いに至ったんです」
同時に、伊藤さんが向き合ったのが、「そもそも課長って何をやるの?」という問いだった。伊藤さんが上司から課長職の話を受けた年齢は社内の男性の昇進ペースと比べても早い方で、突如つきつけられた「まだ見ぬ課長の世界」に戸惑った。そこで伊藤さんは、課長の仕事とは何か、冷静に分析をしてみたのだという。
「結論として腑に落ちたのは、単に“役割分担”なのだという構造の理解です。ビジネスを動かしていくには、現場でお客さんからの受注案件をこなす人と、チーム全体の進捗や業績を管理し、予算を振り分けていく人のどちらも必要です。そのどちらがエライというわけではなく、同等に重要な役割を負担しています。私は前者の役割から、後者の役割へと変わるだけに過ぎないと考えてみると、『むしろそっちのほうが向いているかも』と前向きな意識が生まれました」
二つの納得を得て、伊藤さんが課長職を受け入れた日から10年が経つ。その時の決断を伊藤さんはあの時の決断は「間違っていなかった」と日々感じている。もともと子ども時代のニックネームは常に「あねご」だったという伊藤さんは、男性中心のカルチャーの中でも姉キャラをいかんなく発揮。裏表がなくサッパリとした性格と、目標を明確にして「やるべきこと・やるべきではないこと」を見極める判断力が信頼を集めていると周囲も認める。
始まった女性の「幹部候補教育」
女性活躍推進の追い風の中で、「“管理職になりたくない”の壁」を前に立ちすくむ女性たちは少なくない。「私は管理職になるのはまだ無理」と首を振る女性たちの姿に、伊藤さんは10年前に最初の打診を断った自分自身を重ねる。
「単純に、心の準備がないのだと思います。男性は社会に出てすぐに“将来の管理職候補”として鍛えられる経験も多く、いざその打診が来た時にも自然に受け入れられるのでしょう。女性はまだその意識が低く、シミュレーションも不足している。できれば若いうちから管理職になるというキャリアを自分ごととして考える機会に触れられるといいと思います」
伊藤さんの実感が示すとおり、女性管理職育成に熱心な企業の多くは、キャリアの早期からのリーダーシップの意識を高める目的の研修を強化している。同社もまた、入社3年目の総合職女性を対象に、1.5日間かけて将来のキャリアパスについてイメージを広げ、深める目的の研修を実施。“リーダーになる道を前向きに受け入れる”ための土壌をつくるべく、リーダーシップを磨くことで得られる仕事のやりがいなどを伝えてきた。「今年からは、会社として女性社員のリーダーシップへの期待をより強調する内容へとアップデートした」とダイバーシティ推進センタ長の小嶋美代子さんは説明する。
「もちろん、管理職になる道がすべてではないし、なりたくない人に押し付ける意図はありません。ただし、会社としての期待をハッキリと伝えることが重要と考えています。トップメッセージとして『あなたたちに頑張ってほしい。ぜひリーダーになってほしい』と明確に伝えることで、『実はもっと頑張りたいと思っていた。その気持ちを口に出してもいいんですね』と表情を変える女性もいるんです」(小嶋さん)
下駄を履かせられてもいいじゃない
2012年、課長としてマネジメントに打ち込んでいた伊藤さんに、今度は部長職の打診があった。伊藤さんは今度は迷わず「やってみます」と回答した。
「実は、ちょっと“ダイバの匂い”を感じたんです。企業がダイバーシティ策を打ち出している時期だったので、この話もその一環なのかなと直感しました。『下駄を履かせられるみたいで嫌』と拒否反応を示す人もいるようですが、私の場合は、それはそれでいいかなと思いました」
なぜ、伊藤さんはそれでもいいと思ったのか?
「なぜなら、それも一つの組織への貢献の形だと考えたからです。ダイバーシティという戦略を会社として推進しようと決めて何か目標値を設定したのであれば、それは組織の共通ゴールです。私がその数字の中の1になれるのなら、惜しみなく差し出そうと思いました」
マネジャーとしての業務上の判断においては、「『やらない』という選択をする理由がないのならば、やる」という基準を重視しているという伊藤さん。自身のキャリアの選択も「キャリアアップしたい!」という感情的な熱情から沸き上がるものではなく、冷静な合理的判断に基づくものだったのだろう。
同社の中部エリアで女性初の部長となった伊藤さんは、日立グループの中でも注目される存在になっている。しかし、本人としては今の立場は自然に歩んできた結果でしかない。「キャリアプランを緻密に考えたことは一度もないし、淡々と働いてきただけ。たまたま私は女性で、子どもも産みました。その私の姿が今日になって何か価値があるのであれば、若い後輩たちに背中を見せていきたいと思います」
※本連載は毎週水曜日に掲載します。

