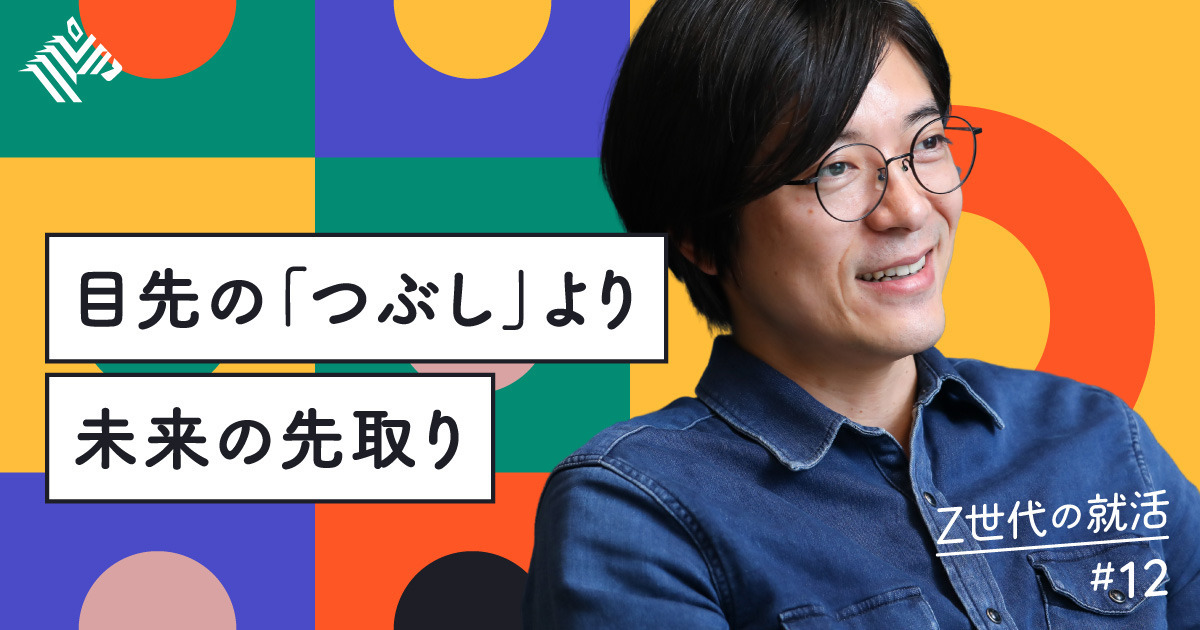【森山大朗】天職探しは無駄。スキル獲得より時代の変化を読め
コメント
注目のコメント
「やりたいことなんて、そう簡単に見つからない」のは本当にそう思います。多くの成功者は「好奇心」をキーワードにあげますが、これもわかったようなわからない言葉ではないでしょうか?
自分の潜在力を知るにはやってみること、「とにかく手を動かして、経験して、自分の身体知(身体に根ざした知)で判断するしかない」。今の若い方は日経を読まない方も多いかもしれませんが、「私の履歴書」に出てくる企業経営者のほとんどは「たまたま」その会社に入っているのです。「つぶしの利く」スキル獲得よりも、テクノロジーの変化を捉えて、その波にいち早く乗れ。急成長する領域にいれば自分も勝手に成長するーー。SNSでも人気のスマートニュースの森山大朗(たいろー)さんのキャリア論は、潔い。
「価値の受け手」として時間を消費するのではなく、「価値のつくり手」を目指そうというメッセージも胸に響きます。急成長している企業では、多くの成長と学びを得られるのは、実体験として、とても共感します。急成長中は、組織がまだ出来上がっていないので、経験がまだ足りない立場でも、多くのチャンスが舞い込んできます。成熟している企業では、まだやらせてもらえない仕事が、早い時期に経験できます。私自身も何度も「ラッキー!」と思ったものです。
ただし、そういった変化がある環境が楽しくて、ポジティブに捉えるか、もっと安定した環境で変化がない方が良いかは、自分次第であり、どちらが正解とも言えないのも、現実です。色々な職場や仕事をすることで、自分が居心地良い好きな環境、仕事のタイプが見えてくるものかと。
「今だったらメタバースを」というのは、一理ありますね。例えば、オンラインショッピングがようやくスタートし始めた頃、急成長企業に勤めていたのですが、EC立ち上げを携わることができた経験は、今でもとても役立っています。同時に、今流行りの分野だから、、、ではなく、とにかく自分が楽しいと思う方向へ進むことも大事ですね。自分自身しか描けないキャリアパスですから。