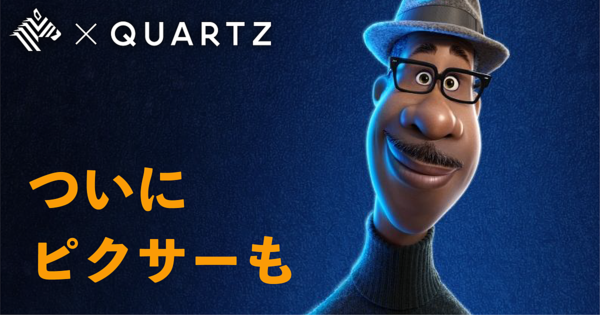【新年】ハリウッドの「デジタル化」はこう進む
コメント
注目のコメント
今後どんな領域でも生じる状況を端的に示してくれている良記事。
「消費者の行動パターンが方向性を示してくれるまで、映画会社は試行錯誤を繰り返すでしょう」というのがまさにそうで、どんな業態もプラットフォームのデジタル化によりこれまでとは扱える1.コンテンツ、2.チャンネル、3.スケール、4.頻度や単位、がすべてモノベースから情報ベースへと移行するため、大きく構造が異なる新しい方程式(関数)が必要になる。さらには仮に方程式がある程度分かっても、各項ごとの係数(パラメーター)がちょっと違えばビジネスモデルは大きく変わる。さらにさらにパラーメーター自体がメタデータによってリアルタイムに変化する関数化するという状況も、どんどん日常になってくる。
そうしたメタデータとメタ関数どうしの関係性を探るという作業は、ある程度までは新しい理論探索と演繹・帰納によるモデル開発(R&D)を行うしかないし、その先は実地(実際の消費者を取り込んだ場面)での実証実験を通して、関数もパラメーターも微調整をしていくしかない。このプロセスを早く、大きく動かせないとこれからのマーケットは取れない。
どんなに複合的な関数と動的なパラメーターのシステムでも、一定のスケールごとに安定的な系が存在する(自然界がまさにそう)。新しい業態ごとに存在するはずのこうした安定系のありかと形を探るのがこれからのビジネスのポイントだし、数学者や実証実験場が不可欠であることのベース。
その点ピクサーやHBOなどは、それでも新しい業界が既存領域(式の構造)から大きく逸脱していないからまだ扱いやすい。一般にはこれまでの企業どころか業態をも超えてこうした動きは複合化・複雑化しているから、実際に理論モデルの開拓やシステム開発、実証実験のハードルもはるかに高くなる。その最たる例がいわゆるスマートシティで、今や都市そのものを実証実験場として「持た」なければ、次のプラットフォーム(それを記述する関数とパラメーターのセット)を取りに行けない。
いきなり都市レベルの理論構築と実装はどうやっても無理なので、まずは小さく仮設の実証実験場を作りながら、理論モデルを段階的に複合化させ、パラメーター取得のノウハウを業態をまたぎながら構築していくような機会構築と投資が不可欠。今日本でこのサイクルに十分なスケールで投資できている企業、とても少ない。映画館が、庶民の娯楽の王様であった時代がありました。家族そろって、あるいはカップルがデートで行く定番が映画館でした。
今や映画館には行かない、ストリーミング配信が主流になる、というのがこの記事の趣旨です。この変化は予測されていたことですが、加速したのは新型コロナウィルスでしょう。
今なお、やっぱり会議は会議室でやらないと、とか、飲み会は居酒屋でやらないと、とか、授業は教室でやらないと、とかいった意見の人はいるし、そうすぐに完全にいなくなるわけではないでしょう。しかし、会議室も、居酒屋も、教室も、そして映画館も減っていくでしょう。
家族はいったいどこで手軽な娯楽にアクセスできるのか、カップルはどこでデートすればいいのか、という問題はあります。たぶん、デートをする人たち自体が減っていくのでしょう。家族という人の小集団も減っていく可能性は高いでしょう。遅かれ早かれ映画館を減らすことになったのは、そういう社会の変化でもあります。
この記事で問われているのは、映画館からストリーミング配信に移行するのは避けられないとして、どのように配信するのか、Netflixにコンテンツを売って後は全部任せるのか、あるいは、独自配信のプラットフォームを立ち上げるのか、ということです。記事で示唆されているのは、ディズニーのディズニープラスだけは単独でやりあえるのではないか、ということです。
日本については、独自のグローバルな配信プラットフォームをつくりあげることのできた企業は一つもありませんでした。ただ、収益性が著しく低かった日本のアニメ業界などにとっては、Netflixが(日本のテレビ局などと比べて)破格の高値でコンテンツを買い取ってくれるのは、まさに救いの黒船で、展望が一気に開けた観があります。しかし、コンテンツのグローバル対応はせざるをえないでしょう。
今後もNetflixの一人勝ちが続けば、今のグーグルによる世界的寡占と同じような問題になるでしょう。文化もビジネスとはいえ、普通のビジネスとは違う、といえます。従来、世界の国々の社会があまりにも異なることで、文化は多様であり続けてきました。文化というものにとって、類例のない危機なのかもしれません。先週のQuartz英語版の特集<Field Guide>「How movie theaters avoid extinction(映画館はいかに絶滅を回避するのか)」から、映画館を飛び越え、ストリーミングでの配信へとシフトする映画事情について迫った記事をお届けします。
米国では、映画館はかねてから苦境に立たされており、追い打ちをかけたのが、昨年からのパンデミックでした。Quartz Japanでは、経営危機に直面する映画館チェーン最大手のAMCに迫った内容をお届けしています👉「New Normal:映画館は生き残れるのか」(https://qz.com/emails/quartz-japan/1925753/)
劇場とストリーミングで同時公開された作品としてはディズニーの『ムーラン』が話題となりましたが、このときは、Disney+の月額料に加えて、映画を個別に「買う」必要がありました。
しかし、ワーナーが『ワンダーウーマン 1984』を、ハリウッド映画としては初めて、追加料金なしで劇場とストリーミングサービス、HBO Maxで同時公開しエポックに。
そして、ついにディズニーが『ソウルフル・ワールド』を追加料金なしで、ストリーミング配信を開始。日本でも年末に傑作だと話題になりました。
日本では鬼滅の刃の大ヒットで、まだまだ映画館の存在感が際立っていますが、世界でストリーミングシフトが進むなか、日本のコンテンツがグローバルで勝つための戦略も見つめ直す必要があるように思います。
Quartz Japanでは、平日朝夕と日曜日にニュースレターという形でコンテンツをお届けしています。もちろん、この特集を含むQuartz英語版の記事もすべて読み放題です。ぜひ、7日間のフリートライアルでお試しください!
登録はこちらから👉https://qz.com/japan/