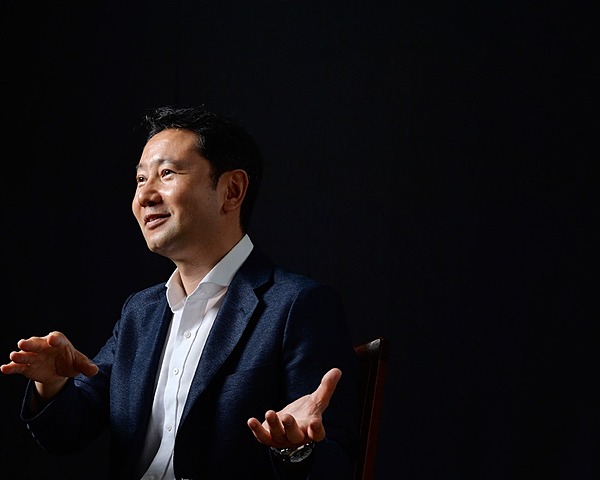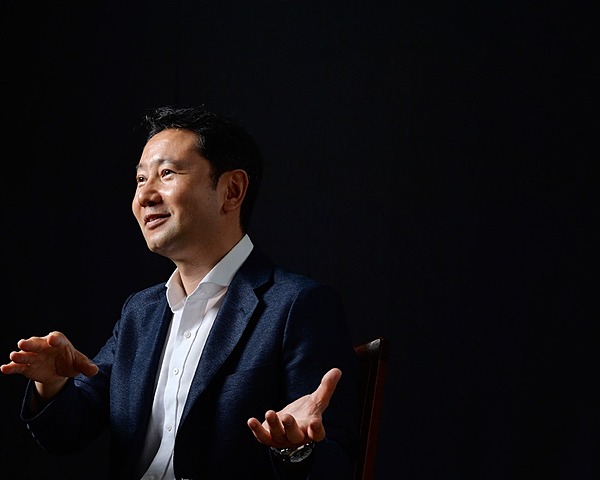2020/10/15
【松村圭一郎】「違和感」をヒントに。社会やビジネスを「自分ごと化」する方法とは
NewsPicks Brand Design / Chief Editor
等身大のスケールから「世界」を感じ取る
── 松村さんは、なぜ人類学者を目指したんですか。
大学生のころに国際政治や国際関係論が流行っていて、それらの講義が面白そうだと思い、たくさん受けていました。同時に、文化にも興味があったので文化人類学の講義にも出ていたんです。
でも、両方の視点で世界について考えていくうちに、国際政治や国際関係論のスケールがどうもピンと来なくなりました。
地球儀をぐるぐる回しながら、アメリカではどんな理論が出てきたかとか、ロシアではルーブルが暴落してどうなったかとか。地球規模でものごとを考えているんですが、私の実感からは乖離しているように感じられて、これは自分がやらなくてもいいなと思えてきたんです。
一方、文化人類学の授業では、島根半島にある漁村でフィールドワークをやりました。みんなで合宿して、お年寄りたちから話を聞く。そうやって見聞きしたことは本当に小さなスケールなんですけど、等身大の個人を通して、より大きな世界や歴史が見えてきたんです。

写真提供:松村圭一郎
── 個人と世界は、どうつながったんでしょうか。
その漁村では、おじいさん、おばあさんが口を揃えて言及する出来事がありました。1960年代に、イタヤガイという貝が大発生したんです。
集落では、イタヤガイが大量に捕れて潤ったことで、わらぶきの屋根が瓦ぶきに変わり、家電製品をみんなが買い始めた。その時期を境に集落の生活がいかに変わったかという話を、みんながするんです。
そんな話はおそらく、日本史の教科書のどこにも載っていない。極めてローカルな出来事です。でも、人びとが語る小さな集落の歴史から、日本の高度経済成長や近代化が引き起こした変化のリアルな姿が透けて見えてきた。
あの時代の日本の社会や経済をミクロな視点で見ていくと、こういう小さな出来事がたくさんあったのかもしれないと気づいたときに、人類学って面白いなと思ったんですね。
── そうやって見えた経済や歴史は、実感を伴っていたんですね。
はい。国際関係論のように俯瞰するのではなく、自分の足でお年寄りを訪ね、そこからまた人を紹介してもらって訪ね歩く。そうやって点と点が線で結ばれ、だんだん大きな絵が浮かび上がってくる。こういう等身大の視点で世界を捉えることが、学問になることに驚きました。
私たちが世の中について考えるとき、たいていは「経済」や「国家」といった抽象的な概念に囚われています。でも、人類学はそういったお仕着せのスケールをずらし、生活者の視点、自分が生きているスケールからものごとを考えるんですよ。
エチオピアの農村とグローバル
── 生活者視点の景色が大きな概念とつながると、世の中を自分ごととして捉えられそうです。
そうですよね。ただし、私たちはなかなか自分自身の体験と、その外側に広がる大きなスケールの物語とのつながりを実感できません。それが、日本や世界で起きている諸問題に、無力感を覚えてしまう一因です。
語られている問題のスケールが、「私」の等身大からかけ離れている。繰り返し語られてもつながりが見えないから、自分が何をやっても世の中は変わらないと感じてしまう。同じことは、会社や大学など、もっとスケールの小さな組織でさえ起こっているでしょう。
私は、その状況を変えるヒントが、人類学の視点にあると考えています。それは、漁村の人びとの体験を通して戦後の日本社会の問題を捉え直したり、巨大で複雑なグローバル経済をも、生活者のスケールと行き来しながら再検討したりするアプローチです。
── 海外のフィールドワークでは、どんなことをするんですか。
現地では特に何もしていないというか、単に村で一緒に生活しているんです。ただ、そこで見聞きしたことが、もっと大きなスケールや、より長いスパンで語られる情報とどう相関しているのかを考えさせられます。
私は1998年からエチオピアの農村のフィールドワークを始めたのですが、90年代半ばに、その村でもみんなが語る「変化」が起きたんです。日頃はほとんど飲まなかった瓶ビールを飲み始めて、それを酔っぱらってコーヒーの木にかけたりしていた、と言うんです。
それはなんだったんだろうと調べていくと、エチオピアで農産物価格が自由化されて、世界市場でもコーヒーの価格が高騰したことで、村で栽培していたコーヒー豆の値段が急上昇していました。
その後、今度は2001年ごろにコーヒー危機が起きて価格が暴落し、それが村人の生活を直撃しました。生活も慎ましやかになって、トタン屋根を売り払い、わらぶきに戻るとか。ベトナムでコーヒー生産が急増し、世界的に供給過剰になったことが原因のひとつといわれています。小さな村の出来事がグローバルな市場経済と直結していて、点と点とがつながっていくんです。
── なるほど。面白い。
日本で見るニュースでも、相場の上下とか、どの国がコーヒーの生産を拡大しているとか、世界的に供給過剰になっているといった情報は報じられます。でも、日本の経済は規模も大きく複雑なので、そういった情報が自分の生活にどう関わっているのかが見えにくいですよね。
ところが、エチオピアのコーヒー生産者の近くにいると、彼らの背中越しに世界市場が見えてくる。国際情勢や相場の値動きが、こういうふうに人の生活に影響を及ぼすんだと、もっと直接的に実感できるんです。

写真提供:松村圭一郎
── その実感を得ると、ニュースを見る目も変わりますね。
そう。いつもニュースの先に生きている人がいるという感覚で受け止めるようになりました。実感によって、大きなスケールの見え方や感触が変わります。人類学者は等身大のスケールを足がかりにして、もっとマクロなスケールと往復しながらこの世界の出来事を理解していくんです。
さらにいうと、同時代だけでなく、人類史というとても長い時間のスケールも使います。たとえば、エチオピアはなぜコーヒーの原産国なのか。
歴史を辿ると、アラブの商人たちがエチオピアでコーヒーの木を発見し、アラブ世界で飲まれるようになった。そのコーヒーが世界的なマーケットを形成した背景には、西洋諸国による植民地化の歴史も深く関わっています。
このように時間の尺度を変えることでも、生活の背後にある構造や関係が見えてきます。
── そうやってさまざまなスケールを行き来する思考法は、人類学者に限らず役立ちそうな気がします。
まさにそうなんです。人類学者が足場にしているのは、生活者の視点です。グローバルとか、マクロとか言いましたが、実は、この生活者の視点とは別のスケールで生きている人なんて、世界のどこにもいないんですよね。
誰だって家族や組織や共同体とつながり合い、その動きの延長線上に国家や経済もあります。逆に言えば、誰もが自分の仕事や生活のなかで、マクロだと思い込んでいる世界の変化や社会課題の一端に触れているはずです。
その手触りこそが、個人が何をやっても変わらないように見える大きな問題を解きほぐし、少しずつでもよい方向へ変えていくきっかけになると思います。
道具は、時間をかけて馴染ませるもの
── 現在はコロナ禍の影響もあって、働く環境や生活が世界規模で変わりつつあります。この状況を人類学的に見るとどうなりますか。
おっしゃるように、新型コロナウイルスによって、慣れ親しんできた状況がガラッと変わってしまいました。
この変化は、これまで自分たちがどんな先入観や慣習に囚われてきたかを可視化させました。「通勤電車に乗ってオフィスに座っているって必要なの?」というように、これからどういう別の在り方が可能なのかを考えるようになったと思います。
これは、誰もが否応なく「ニュー・ノーマル(新しい常態)」というフィールドに放り出され、人類学的な状況に置かれたようなものです。そうであれば、この変化を捉えるために「実感」を手放さないことが重要です。

写真:Fiers / iStock
いま目の前で何が起こっていて、それはどういう意味を持つのか。まわりを注意深く観察し、感じ取った違和感の原因や構造を問い続けることが、ソリューションを見つけること以上に価値を持つ。これが、人類学の基本的な姿勢ですから。
── どうすれば、違和感みたいなものをうまくつかまえられるでしょうか。
自分が見聞きする情報を、安易に既存のフレームに落とし込まないことですね。
人類学者だって、フィールドワークで興味深い出来事に出会っていても、その面白さや価値に気づけないことはよくあります。
目の前でこれまでの理論を刷新するようなことが起こっているのに、その新しさや特殊性が見えていない。なぜかというと、すでに知っている理論や概念に当てはめて考えてしまうからです。
人類学では「贈与」や「交換」といった概念を使って物のやりとりを説明しますが、これらは社会構造や人間関係を捉えるための「道具」です。
ビジネスで使われる言葉もそうですよね。「イノベーション」などの抽象化された概念や、「ソサエティー5.0」や「SDGs」みたいな大きな枠組みでものごとを捉えて、新しい変化や時代状況を理解しようとしています。
気をつけないといけないのは、抽象化された概念を、実感が伴わないまま使ってしまうこと。そうすると、小さな差異や特徴がこぼれ落ちてしまい、概念と実態がどんどん乖離して、思考や論点が噛み合わなくなってしまいます。
── わかります。大きな概念ほど、人によって捉え方がバラバラだったりします。何が噛み合っていないのかもわからないまま、話が堂々巡りになってしまったりして。
そうなると、状況が硬直して動かなくなってしまいますよね。その場合の簡単な解決法は、難解な概念を持ち出すことなく、よく使い慣れた、日常的な言葉を使って考えることです。
ペンでも腕時計でも同じですが、いい道具は、生活のなかで繰り返し使うことで自分に馴染んできます。

松村氏が着けているのは「Seiko Astron Global Line 5X series SBXC063」。1969年にセイコーが世界に先駆けて発売したクオーツウォッチ「クオーツ アストロン」の流れを受け継ぎ、2012年、世界初のGPSソーラーウォッチとして誕生。ブランドのルーツである「絶対精度の追求」と、それを実現するための「絶え間ない進化」を体現したグローバルモデルだ。
スケールの大きな概念でものごとを把握することも大切ですが、実感を伴わない抽象的で高尚な言葉より、使い慣れてその意味が腑に落ちている言葉の方が、道具として扱いやすい。結果として、より深い理解や精度の高いコミュニケーションができるでしょう。
それも詰まるところ、言葉に「実感」が伴っているからです。
── 等身大の視点や思考には、実感が伴う。それが、より大きな概念を解きほぐす手がかりにもなるんですね。
私はそう考えています。どうにかして変えたいと思う大きな問題があったとして、「レボリューション」って、たぶんガラガラポンでちゃぶ台をひっくり返すようなやり方だけではないと思います。
古典的な人類学では、欧米のような近代化された社会は交換による市場経済で回っていて、「未開」とされる社会は贈与経済で回っていると、明確に線を引いて切り分ける傾向がありました。
この世界観では、社会に不満や違和感があっても、もう一方のやり方に転ずるか、資本主義ってこういうものだから、などと諦めるしかありません。交換の領域と贈与の領域が、断絶しているからです。
しかし、最近の人類学では、市場経済や資本主義の社会で商品交換ばかりが行われているように思われてきた私たちの営みのなかにも、贈与的なロジックがちゃんと重要な領域を占めていると考えるようになりました。
言われてみれば当然なんですが、我々だって物や時間をお金と交換するだけではなく、与えたり与えられたり、協力し合ったりして生活を成り立たせています。
つまり、「私たち」の関係は交換と贈与が複雑に組み合わさることで成り立っていて、それぞれの社会によって文脈の配置が違うだけ。
そうやって世界を捉えると、まったく文化が違うとか、特殊な経済制度の社会がある、とは言えなくなります。どんな社会でも、複数の異なる論理が並存していて、それを個人のスケールで一つひとつの関係に向き合いながら、ずらしたり、別の論理の領域を広げたりすることができる。
そういう視点に立てば、自分たちの周囲の世界から少しずつ変えていくことが可能になると思いませんか。
── そうですね。個々は小さいけれど、自分の目の前の関係が大きな概念や組織や仕組みを構成しているわけですから。
固定的な概念に囚われると境界線が引かれ、違いばかりに目が向いてしまう。すると、ついつい相手に変わってほしいと思ってしまう。「私は変わらないから、あなたが変わってください」というコミュニケーションでは、世界どころか目の前の関係も変わるとは思えません。
生活における実感や自分の経験のなかのいろんな側面を注意深く観察することで、まだ認識されていない新しい問題の糸口にも気づくことができる。
自分の実感を既成概念に閉じ込めたり、境界線を引いて分断したりするのではなく、相手のよいところを自分に取り込み、自分から相手にも移していく。そういう交わりの場をつくり、お互いに変容しうる学び合いの関係に立つことが、何かを変革する最初の一歩になるんじゃないでしょうか。
編集:宇野浩志
構成:斎藤哲也
撮影:森カズシゲ
デザイン:月森恭助