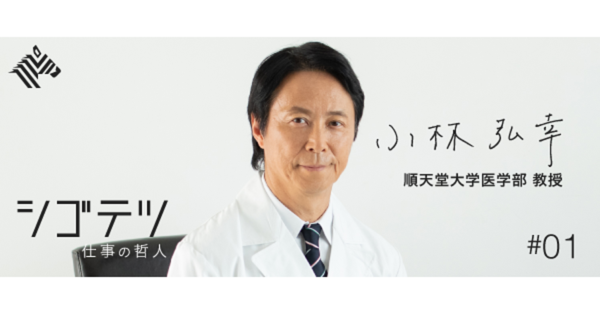【小林弘幸】コロナに負けず、心身の健康を維持する毎日の習慣
コメント
注目のコメント
小林先生とは報道番組でご一緒していた期間が長くあります。
いつも良い香りのする姿勢のきれいな先生です。笑
心と体は繋がってます。
自分の競技は採点競技でした。
技の難度を常に上げ、完遂度を上げていくことが求められる競技です。さらにその技を「他人と合わせる」同調性が求められる競技でした。
競技引退後も、「技=仕事」の難度を上げて完遂し続けるには心と体の相関を大事にして整えておくことが重要だと意識してます。
なんちゃって。
でもベロベロに飲み過ぎる時もあれば、永遠に寝倒す時もある。子供達が大きくなってからはこれらができるのが至福。今回の「シゴテツ -仕事の哲人-」は、順天堂大学医学部教授の小林弘幸さんです。ウィズコロナの時代に、心身の健康を維持する方法をアドバイスしていただきました。
---
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、「新しい生活様式」への転換が求められている今、環境の変化に心身が追いつかず、疲労や不調を感じている人も多いだろう。
そんなストレスフルなときこそ、「自分でコントロールできるルーティンを作ることが重要」と語るのは、順天堂大学医学部教授の小林弘幸氏だ。
免疫にも重要な役割を果たす自律神経と腸を研究する小林氏に、自身が実践する生活習慣や仕事の哲学を交えて、心身の健康を維持し、仕事で高いパフォーマンスを発揮するための極意を聞いた。インタビューは5月18日にリモートで行った。(全7回)
■第1回 コロナに負けず、心身の健康を維持する毎日の習慣
■第2回 自律神経のバランスを整える方法
■第3回 腸内環境を整えて免疫力を高める
■第4回 手書きで「3行日記」をつける
■第5回 疲れたときほど体を動かす
■第6回 「誰も信じるな」は外科医の鉄則
■第7回 本の出版は外来に代わる医療の一つ『心身の健康を維持し、仕事でも高いパフォーマンスを発揮するには、生活をパターン化すること』『パターンを作ることで、迷いがなくなり、貴重な時間やエネルギーを無駄にすることも少なくなる』とあります。
確かにこの一面はあると思います。人間が1日に使える脳のエネルギーには限りがあり、無駄なことに思考を使わないために、ルーティン化する。スティーブ・ジョブズが、毎日黒のタートルネックを選んでいたことに代表されると思います。
一方で、あまりにルーティン化に寄りすぎると、新しいことに挑戦する機会に乏しくなり、刺激のない日々を送ることになるのでは?と言う疑問も生まれます。自分の中でルーティン化する時間と、余白を作って新しいことに挑戦していく時間とをバランスよく組み込むことが大切なのではないかと感じています。