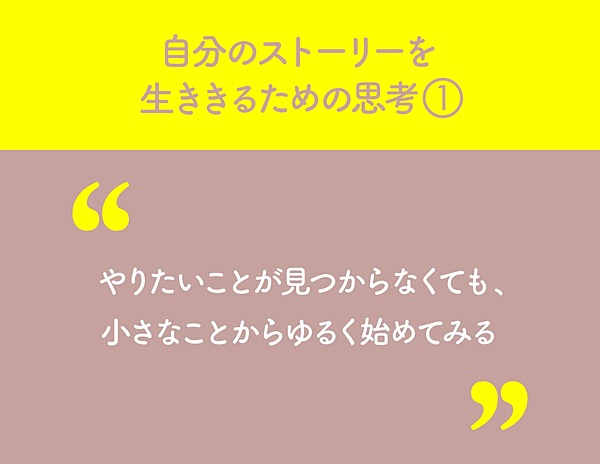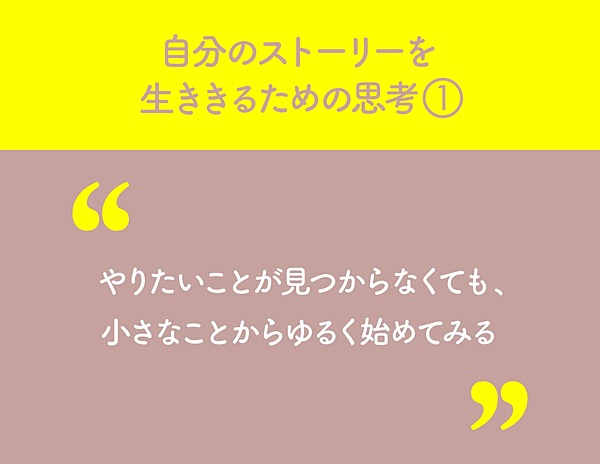【穐山茉由】「学び」と「好き」に制限をかけず、複業で自分のストーリーを“生ききる”
2020/5/6
働き方改革が進み、個々のワーカーが自らの価値を高め、自分らしく生きるための多様な働き方を受け入れる企業も増えつつある。しかし、現実には何にチャレンジすべきか見えない、または業務量のコントロールがうまくいかないことで疲弊する人も。
自分自身の価値を高め、人生を豊かにするパラレルワークには、どんな形があるのだろうか。
外資系ファッションブランドのPRと、映画監督という異色のパラレルワークを実現しているのが、穐山茉由氏だ。
人気ブランドの敏腕PRとして活躍しながら、初の長編作『月極オトコトモダチ』が第31回東京国際映画祭へ正式出品されるという衝撃的なデビューを飾った。
ビジネスパーソンとしての役割を全うしながら、映画監督としてのキャリアをスタートさせるまでのストーリーと、自ら人生を切り拓くためのヒントについて聞いた。

1982 年、東京都生まれ。大妻女子大学家政学部被服学科を卒業後、OEMメーカーを経て外資系ファッションブランドのPRに転身。31歳で映画美学校に入学、勤務を続けながら映画制作を学ぶ。修了制作『ギャルソンヌ ―2つの性を持つ女―』が第11回田辺・弁慶映画祭2017に入選。2018年には初の長編『月極オトコトモダチ』が、第31回東京国際映画祭 日本映画スプラッシュ部門へ正式出品。さらに「MOOSIC LAB 2018」で長編部門グランプリほか4冠達成。気鋭の若手映画監督として注目を集める。
「自分も何かを表現したい」、PRを続けながら映画学校へ
制約があるからこそ、生まれる価値もある──。
会社員として忙しく働きながら、映画を作る「二足のわらじ」の生活を続ける中で、実感したことのひとつです。
高校生の時からファッションに興味があって、大学は被服学科に進学しました。新卒で就職したOEMメーカーから外資系ファッションブランドの広報に転じて、仕事はとても楽しく充実していました。
PRはデザイナーなどのクリエイティブチームがつくり上げたブランドの世界観を社会に広く発信していく役割で、刺激的でやりがいもある仕事です。でも、PRが生きている場所は、あくまで自分ではなく他の人が創造した世界です。
メーカーから転職し、ものづくりの現場から離れた寂しさもあって、「自分自身でも何かを表現したい」という気持ちがムクムクと生まれてきました。
そうはいっても、特にやりたいことがあったわけではなくて。写真の勉強をしてみたり、メンバーを募ってバンドを組んでみたり、気になったことは何でもトライしていました。
その中のひとつが映画でした。井口奈己監督の『人のセックスを笑うな』という作品に出会って、その空気感に惹かれたことで、映画を撮ることに興味を持つようになったんです。
はじめは初心者向けの映像制作ワークショップに参加するという、ゆるいスタートです。そこからひとつずつステップを踏むように、小さなチャレンジを重ねていきました。
これらの体験の中で指摘されたのが、「あなたは人を巻き込むのが上手だから、向いているんじゃない?」ということです。
確かに映画は一人で作れるものではなくて、様々な専門家のチームワークで成り立っています。
私は企画や脚本を書く作業も楽しめるタイプだとわかったし、何より周囲の人たちの協力を仰いで調整を重ねるプロセスは、普段職場で進めているプロジェクトと同じようなものなので、苦になることもなかったんです。
映画を撮ること自体は自分にもできるかもしれないと感じる一方で、今作っている映像はとても満足できるものじゃない。自分の作った作品で人の心を動かしたい、そのための技術を学びたい、と強く思うようになったんです。
思い切って会社を辞めて大学に通うことも考えましたが、そこまでのリスクを取ってしまうと、逆に腰を据えた学びができなくなる不安もありました。
そこで、土日や夜間も通える映画美学校に、PRの仕事を続けながら通うことに決めました。
31歳の新入生、学びを重ねて成長する喜びを知った
入学当時、私は31歳。同級生のほとんどは20代です。遅いスタートであることに焦りも感じましたが、だからこそ限られた時間を最大限に活用して結果を残したいと思いました。“学びのチャンス”は絶対に逃したくなくて、授業も制作も休まず参加していました。
幸い、勤務先は外資ということもあって、業務以外の時間を尊重する文化があり、責任を果たしていれば何をしようと自由でした。
学校に通うことを明かしても、誰にも否定されることなく応援してもらえたし、学校のある日は上司に残業を肩代わりしてもらったこともありました。
学校とはいえ映画制作の世界は、普段接しているアパレル業界とはまったくタイプの異なる人ばかりで、しかも男性が中心です。まったくの素人で、しかも会社員という逃げ場を確保したまま通う自分は、周囲から軽く見られているんじゃないかと警戒することもありました。
でも、そんな風に感じたのは自分が必要以上に身構えていたからで、飛び込んでしまえばそんな偏見なんてだれも持っていないと気づきました。
価値観やバックグラウンドは違っても、映画が好きとか良い作品を作りたいという気持ちは共通していて、それだけですごいチームができるんです。
30歳を過ぎて右も左もわからない状態からスタートした私でも、日々学びを積み重ねていくと、ある日突然違う景色が見えてきます。いくつになってもそんな体験を繰り返せることがうれしくて、もう夢中になって取り組んでいました。
初めての長編作品、「やりたい」気持ちに突き動かされた
卒業制作作品が、ある映画祭に入選したことをきっかけに、今度は長編映画を撮ってMOOSIC LABという映画祭に出品しないかというお誘いを受けました。実現すれば、私にとって初めての長編作品になります。
この数少ないチャンスは、絶対に逃せません。
自分の名刺代わりになる作品にするため、「仕事以外のリソースをすべて捧げよう」と決め、なけなしの貯蓄もすべて、制作費に投じました。
それからは、睡眠時間を大幅に削らざるを得ないハードな日々……。今思い出しても、相当ムチャな生活でしたが、あの頃はとにかく「やりたい」という気持ちに突き動かされていたんです。
公開時期は決まっていたので、まさに時間との戦いです。予算にも時間にも限りがある中で、どこまでやれるか。この時に限りませんが、私の映画作りにはいつもこのテーマが重くのしかかっていました。

©2019「月極オトコトモダチ」製作委員会
ただでさえ多くの制約がある中でスタートしているのに、途中でさらに厳しいハードルが加わることもあります。でも、思い返せばこれも悪いことばかりじゃない。
その時は悔しいし、途方にくれたりもしたけれど、不思議と「だったら、もっといいものにしてやる!」という闘志も湧いてくるんです。ギリギリの環境下だからこそ生まれるアイデアもあるということも学びました。
撮影は5日間の夏季休暇とその前後の土日を合わせた9日間で行い、なんとか期限に間に合わせることができました。
記念受験のようなつもりで応募した東京国際映画祭で正式出品されることが決まったときは、ずっと応援してくれた上司に真っ先に報告しました。自分のことのように喜んでもらえて、「やっぱりここは私の大切な居場所なんだ」と感じたことを覚えています。
「好き」「やってみたい」という気持ちは、大切で尊いこと
忙しい会社員がいきなり映画づくりを始めるなんて、無謀だと感じる人もいるでしょう。実際、最初から自信があったわけではないし、確固たる将来のビジョンがあったわけでもありません。
私はただ、自分が「好き」と思えることを大切にしたかった。単純に好きと思えることを発見できた──それ自体がとても大事で尊いことだから、絶対に制限したくなかったんです。
さらに、それを行動に移すというのはハードルが高いこと。それでもやってみたいと思えるなら、その気持ちにはきちんと向き合わなければいけないと思いました。
自分の感覚を信じるって、そう簡単なことではないかもしれません。私だって、今でも躊躇することがあります。
そんなときは、小さくてもいいから、アウトプットをする。自分の中だけにしまっておくと消えてしまいそうなものも、実はとても大事なものかもしれないから。
身の回りの人との会話やSNSでの発信でもいいので、自分の「好き」や「気づき」を恐れることなく発信することで、整理されて自分に返ってくると感じています。
2つの世界に身を置くことが良いバランスに
今は勤務先に労働契約を見直してもらい、勤務は週3~4日程度で、映画制作も仕事として請け負える働き方になりました。会社を辞めて映画一本に絞るという選択肢もありましたが、映画制作にチャレンジして改めて、会社員の良さも再確認できたんです。
映画は作品ごとにチームを組んで、終われば解散します。次に何が起こるかわからない世界で、それが面白さでもあります。一方で会社の仕事は、年間を通してある程度見通せるし、自分のデスクがあって「ここが居場所なんだ」と思えます。
映画の世界で冒険を続けていくには、精神的にも経済的にも安心できるホームがあったほうがいいし、異なる2つの世界に身を置いていることが自分の中で良いバランスにつながっていると感じています。
映画を作る立場になったことで、作り手の目線を持てるようになったこともPRの仕事に生きていますし、PRとしてブランドの作品を客観視しながら発信し、フィードバックを得ていく積み重ねも、多くの人に受け入れられる映画作りには役立つ視点になると思っています。
フルタイム勤務をしながら『月極オトコトモダチ』を作っていた当時の生活はあまりにハードで、これをもう一度できるかと言われたらきっと無理です(笑)。
でも、長い人生の中で、自分の時間もエネルギーもお金もすべて投じて熱中した経験は、私の大切な財産であり、自信になりました。
映画制作でもPRの仕事でも、ノートPCは欠かせない相棒です。カフェなどで作業することも多く、常に持ち歩いているので軽くて薄いのは必須条件。動画を編集するうえで、スペックも妥協できません。
ノートPCは撮影現場にも必ず持って行って、香盤表を確認したり映像をチェックしたりと一日中使います。パワフルなバッテリーも心強いですね。

「二画面に分けて表示させることが多いので、モニターがワイドな『ASUS ExpertBook B9』は理想的」(穐山氏)
年明けから次回作の企画を練っていたところに、コロナウイルスの感染が拡大し世界が一変しました。もう「コロナ前」と同じことが考えられなくなってしまい、大幅な見直しを迫られています。
映画に関わる人が休業を余儀なくされる中で、文化を守るために今、自分に何ができるのか、改めて考えているところです。
人が生きていくうえで、何も考えずに流されていくのは簡単です。でも、もっと自分の頭で考えることを大切にしてほしい。
当たり前だった生活が失われていく中でも、観る人が既成の価値観や常識を疑い、考えるきっかけになる作品を作っていきたいと思っています。
(構成:森田悦子 編集:奈良岡崇子 写真:大畑陽子 デザイン:堤香菜)