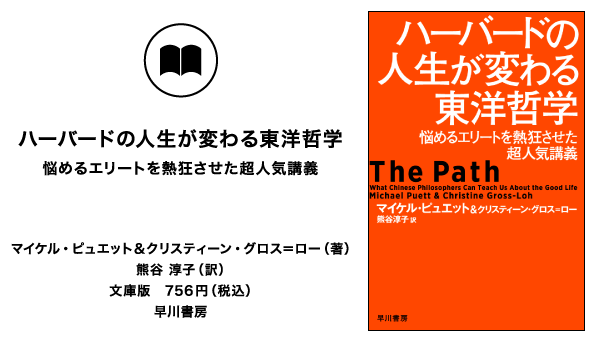あらゆる視点から世界を見る
昔、荘子は自分が蝶になった夢を見た。喜々として飛びまわる蝶そのものだった。楽しく気ままに舞い、自分が荘子だという自覚さえなかった。ところが、ふと目覚めると、まぎれもなく荘子だった。
いったい、荘子である自分が蝶になる夢を見たのだろうか、それとも蝶である自分が荘子になる夢を見ているのだろうか。荘子と蝶とにはかならず区別があるはずだ。このような移り変わりを物化(ぶっか、物の変化)という。
有名な「胡蝶の夢」の話のなかで、紀元前四世紀後半の中国の思想家、荘子は、わたしたちを常識的な世界の見方から脱却させようとする。
わたしたちは視野がせばめられているせいで、世界を存分に体験することも、世界と深くかかわることもできずにいる。荘子によれば、最大の問題は、人の視点が限られていることだ。
きみがたんなる人間ではなく、本当は人間になった夢を見ている蝶だとしたらどうだろう。人間であることを超えて、あらゆる視点から世界を見るとはどういうことか理解できれば、おのずと人生を存分に体験できる。
わたしたちはすでに、おのずと世界を存分に体験するとはどういうことか知っている。
「フロー」体験をしているときがそうだ。フローとは、なにかの活動に完全に没頭し、今していること──サッカーでも油絵でも読書でも──への歓喜にわれを忘れる心理状態をいう。この超集中状態になることを「ゾーンにはいる」という人もいる。
しかし、わたしたちはゾーンの瞬間を非常に限定されたものととらえ、特定の活動だけに起こることだと考えがちだ。適切な条件がすべてそのとおりに整った特別な瞬間にだけ起こることだと思っている。
ふつうは、修練を積んだところで、人生のあらゆることにこれと同じような興奮をおのずと感じられるようになるはずはないと考える。ところが、荘子の見方はまるで違う。すべての視点から世界を見ることを学び、〈物化〉を理解できれば、宇宙のあらゆることへの理解が深まると考えた。
そして、現実を経験する典型的なやり方から抜け出せるようになれば、日々の平凡な生活の一瞬一瞬で〈おのずから〉の境地にいたるとはどういう意味かがわかると説いた。
魚はただ〈道〉に従って泳ぐ
老子と同じように、荘子は道教の思想家と考えられているし、荘子の教えを題材とした、本人の手によるものとされる『荘子』も道教の書ということになっている。しかし、おそらく荘子はどの思想学派に属すこともいやがっただろう。
老子と荘子という大きくかけ離れた二つの書物と二人の思想家が同じ学派に分類されてきた唯一の理由は、どちらも〈道〉を重視しているということだけだ。
けれども、それぞれの思想家にとって、道は異なるものを意味していた。
荘子にとっての道は、落ち着いて穏やかになることでも、世界を徹底して区別のないものととらえることでもなかった。人はけっして道になることはできない。ものが育つ土壌になることができないのと同じだ。荘子にとって道とは、たえまなく流転し変化するあらゆるものと完全に一体化することだった。
『荘子』は、いかに世界のあらゆるものが、移動と相互作用、流転と変遷のダンスをたえず踊りつづけながら、ほかのあらゆるものに転変しているかを繰り返し強調している。時がたつにつれ、あらゆるものがおのずからほかのなにかの一部になる。この変化と移行の過程は刻々と起こっている。
草は育ち、死ぬと腐敗し、その〈気〉はほかのものに注がれる。草にいる虫は鳥に食べられ、その鳥は今度はもっと大きい鳥や動物に食べられる。その大きい生きものもやがて死に、腐敗し、大地の一部になり、土や草やそのほかの要素に変化する。
終わりのない変化と転変の循環のなかで、あらゆるものがゆっくりとほかのあらゆるものになる。草は死んだらほかのものになろうと意図してなどいない。変化はただ起きる。季節は移り変わろうと意図してなどいない。移り変わりはただ起きる。
鳥が飛ぶのは、翼を用いるという天賦の才があるためだ。風向きや下の地形の変化に合わせて空中に浮いてただよう。鳥はおのずから道に従っている。
魚は泳ぐ。魚もえらとひれを用いるという天賦の才を授かっている。それを使って流れに合わせて水中を動きまわる。魚もおのずから道に従っている。立ち止まって、「よし、流れがこっちに向いているから、ここで向きを変えたほうがいいな。よし、今度はあっちだ。あの岩をうまくよけなくては」などと考えたりしない。ただ泳ぐだけだ。
荘子は〈陰〉と〈陽〉ということばを引き合いに出している。陰と陽は、暗と明、柔と剛、弱と強などを指す。荘子によると、道は、相反するように見えながら、実際は互いに補完しあうこの二つの要素がたえまなく影響しあう過程だという。
陰陽は常に循環して互いにバランスをとる。冬には〈陰〉である寒、暗が優勢になる。それから状況が変化し、〈陽〉である暑、明の季節、すなわち夏がおとずれる。陰陽のエネルギーのたえまない必然の相互作用は、四季の移り変わりを生むだけではない。宇宙のすみずみにまで見られるすべての転変を特徴づけている。
〈道〉に従わないのは人間だけ
変化が満ちあふれる世界のなかに、たった一つ例外があると荘子はいう。全宇宙でただ一つおのずから道に従わないもの。それはわたしたち人間だ。
わたしたちだけが、おのずから道に従っていない。それどころか、流転と変化に抵抗することに全人生を費やしている。
わたしたちは自分の意見が正しい(そして、ほかの意見は当然ながらまちがっている)と言い張る。ライバルの成功にイライラをつのらせる。変化を恐れるあまり将来性のない職から抜け出せない。そしていつのまにか、陰陽の相互作用を乱し妨げている。これは、わたしたちの天賦の才である理性のためだ。
では、かわりにどうすればいいのか。人間にとって、おのずから道に従うとは本当のところなにを意味するのだろう。
わたしたちはこの「おのずから」とか「自発的に」ということばを聞き、それが意味するところは知っていると考える。なんといっても、わたしたちは自発性をあがめる文化に生きている。
先が読めるのはつまらないと感じる。多すぎる規則は息苦しく感じる。自由な発想のもち主や、変わり者になることを恐れない人や、ふと思いついて大学を中退して起業した孤高の天才を賞賛する。わたしたちは、自発性を自分らしくあることや、幸せの向上や、個人の充足感と同一視している。
そのため、「さあ、自発的に自分がやりたいことをやるぞ」などと考えるかもしれない。今やっていることをやめてダンスに興じる。仕事をやめ、貯金をなんとか工面して世界一周の旅に出る。これこそ自発的ということではないだろうか?
じつは、荘子にとってはそうではない。わたしたちの考える「自発的」は、荘子の考える「おのずから」とほとんど正反対だ。荘子の「自発性」は、みずから進んで自分の好きなことを好きなときにすることではない。
わたしたちが「自発的」と考えているものは、欲望を解き放つことだ。だが、四六時中そのような生き方を貫くことはできない。だから、たまにハンググライダーをしに出かけ、衝動買いをし、新しい趣味をはじめる。自由は週末にとっておき、ほかの日はいつもどおりすごす。
真の「自発(=おのずから発する)」のためには、世界での考え方とふるまい方を改め、終わりのない流転と変化にたえず身をさらさなければならない。訓練した自発というものを想像する必要がある。訓練した自発性などというと撞着語法のように聞こえるが、これから見ていくように、実際はなんの矛盾もない。
技よりもまさる〈道〉に重きを
荘子のよく知られた寓話を一つ見てみよう。包丁(ほうてい、丁〔てい〕という料理人)の話だ。
包丁が肉牛を扱いはじめたころは、牛刀を手に取り、目の前の肉をめった切りにしていた。最初はうんざりするだけだった。ところが、時とともに繰り返し牛をさばくにつれて、しだいに悟るようになった。さまざまな肉目や腱に逆らうのではなく、皮、肉、骨のあいだのあらゆるすきまを見つけられるようになった。
どの牛も違っているが、どれも境界や関節や組織の筋道──もともと切り離しやすい部分──がある。慣れと修練とによって、包丁はどんな肉の塊にも通じるそのようなパターンを感じとれるようになった。まるで舞いを舞っているようにリズミカルにさばき、牛刀の動きに合わせてなんなく肉が離れ落ちる。
とはいえ、このようにさばくには、考えすぎても分析的に取り組んでもいけない。どの肉も同じではないからだ。荘子によれば、〝技よりもまさる〈道〉〟に重きをおく必要がある。
自分の神性に働きかけて、世界とつながり世界とうまく感応できるようにする。意識的な理性ではなく精神を使うことで道を感じる。そうなってはじめて、肉のさまざまなふぞろいを感じとれるようになる。
腕のいい料理人でも一年に一度は包丁(ほうちょう)を取り替える。刃(は)がこぼれるからだ。並の料理人なら一月くらいで取り替える。包丁を折ってしまうからだ。けれども、わたしの牛刀は一九年も使っていて、数千の牛を料理してきたが、その刃先はたった今砥石(といし)でといだように鋭い。
牛の骨節にはすきまがあり、牛刀の刃先には厚みがない。厚みのないものをすきまのあるところに入れるのだから、広々として刃先を動かすゆとりがある。だから、一九年も使っているのに、牛刀の刃先がたった今といだばかりのように鋭いのだ。
包丁(ほうてい)は訓練した自発性というものを心得ていた。注意したいのは、包丁が牛刀をうっちゃって踊りほうけているうちに〈おのずから〉の境地に達したのではないことだ。
平日に肉をさばき、週末には羽目をはずしていたわけではない。何度も何度もひたすら肉をさばきつづけるという謙虚な姿勢によって、やがて流れに身をまかせてさばけるようになり、ついに〈おのずから〉の境地に達した。
しかもただ受け身なだけではない。道の天理に逆らわずに従いつつも、肉片を切り離すたびに新しくつくり出しつづけたものがあった。包丁は日々の生活に組み込まれたいつもの活動のなかに満足感と自発性を見いだしていた。
話の最後に、包丁の仕事ぶりを見て感嘆した君主が言う。「まったくすばらしい。わたしは包丁の話を聞いて、養生の秘訣を学んだ」
自分のあり方そのものを鍛える
経験豊かな料理人は、レシピもなしに手の込んだ料理を手早く作れる。経験と修練とセンスだけで、塩こしょうをどれだけ入れれば料理に命を吹き込めるか、クリームリゾットをどのくらい火にかければいいかを正確に見きわめる。これは訓練した自発性だ。
ベテランの教師は、クラスが手に負えない状況に陥ろうとする瞬間を察知して、なにをすればすべての生徒が落ち着きを取りもどすか素早く把握する。長年の経験によって、ちょうどいいときにもっとも効果的な形でおのずから反応できるよう鍛えられたからだ。
複雑な技術──外国語でも、楽器でも、自転車でも、水泳でも──を学ぶとき、はじめのうちは、意識して十分に練習する必要があることはだれでも知っている。
ピアノの稽古をしたことがあるなら、はじめはどんなにむずかしかったか、鍵盤をたたく自分の指がどんなにぎこちなく感じたか、音符と鍵盤を結びつけるのがどんなにややこしかったか、指をばらばらに動かしながら同時に鍵盤のうえで両手を右へ左へと滑らせるのがどんなにたいへんだったか覚えているだろう。
はじめはなんだかさっぱりわからないし、音もきれいに出ない。それどころか、きみが「自発的に」威勢よく鍵盤をたたきはじめると、まちがいなく周囲の迷惑になったはずだ。
ところが、時とともにじわじわと、きみは音をつなぎ合わせて、まとまったメロディーらしきものを弾けるようになる。やがて右手と左手を同時に使い、和音やアルペジオを奏で、もっと高度な曲に挑戦するようになる。
ここからが本当の楽しみのはじまりだ。暗譜した曲を演奏し、即興で新しい曲を弾くことさえできる。ピアノの前にすわることが喜ばしい行為になり、音楽を奏でることで胸が躍り元気になれる。こんなふうに自由におのずから演奏できるようになったとき、きみは道に従っていることになる。
一流ピアニストが自分の音楽や聴衆とどれほどぴったりかみ合っているか考えてみよう。
ピアニストは、鍵盤にどう触れれば自分と音楽と聴衆のあいだで感応する音色を出せるか正確に感じとることで、喜びを感じている。すばらしい技術をもって世界を感じ、反応する能力によって、ピアニストは道に従っている。十分な練習こそ、ピアニストがこのような喜びに満ちた自由にたどり着いた方法だ。
わたしたちがする練習もこれと同じだ。十分に練習することで、交通渋滞のなかで車を巧みに走らせたり、テニスで絶妙なロブをあげたり、職場で説得力のあるプレゼンを準備したりできるようになる。
いちいち考えなくても、どうすればうまくいくかちゃんと心得ている。楽々こなせるようになるまで習熟したことは、ありふれたことであれ高尚なことであれ、訓練した自発性の例だといえる。
重要なのは、荘子の教えを深く心に刻むと、優れたテニス選手や熟練した従業員や腕のいい料理人になるだけではない点だ。人生への取り組み方がなにもかもがらりと変わることになる。ピアニストはただピアノを弾くためだけに練習してきたわけではない。世界のなかでの自分のあり方そのものを鍛えてきたのだ。
※ 本連載は今回が最終回です。
(バナーデザイン:大橋智子、写真:peterspiro/iStock)
本記事は『ハーバードの人生が変わる東洋哲学 悩めるエリートを熱狂させた超人気講義』(マイケル・ピュエット&クリスティーン・グロス=ロー〔著〕、熊谷 淳子〔訳〕、早川書房)の転載である。