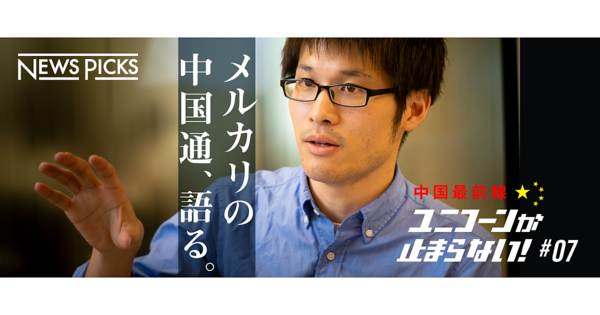【メルペイ家田】僕が、中国ビジネスを学んできた理由
コメント
注目のコメント
メルカリきっての中国通として知られる、家田さんへのインタビューしました。
中国に対する「上から目線」への疑問が、大学で中国を学びはじめたきっかけの一つだったといいます。そのセンスがあったからこそ、大学時代から現地に飛び、新しい時代のサービスの動きを感じ取れたのでしょう。
インタビューでは、バイク便のライダーのような人たちが、スマホ上の消費者金融サービスなどで、ぐるぐるキャッシュを回転させながら、その日暮らしをしている様子が描かれています。わたしもWechatPayで、メッセンジャーのように中国元をサクサクとやりとりする体験をして、これは何なんだろうとビビりました。
9億人が使っている金融トランザクションを、そもそもどんなインフラで支えているのか。そのコストや技術は、どこまで進化しているのか。中国のサービスを研究すると、おそらく多くのビジネスマンは、ものすごくたくさんの新しい疑問とインスピレーションに出会えるのではないでしょうか。規制に関して仰る通りで「やっちゃいけないことを決める国」が中国、「やっていいことを決める国」が日本。
例えばセグウェイは、2016年ごろやたら中国都市部で使ってる人を見かけた。日本だと、道路交通法で決めてないから「乗っちゃダメ」、中国だとまだ法整備してないから「とりあえずOK」、となる。
「乗り捨て」のモバイクも、「白タク」のDidiも、同じ形でとりあえず試し、一気に広まって、規模が大きくなったら規制するのが中国型。
日本は新しい突飛なことをしようとするといちいちお伺い立てたり、法の穴を見つけなきゃいけないので、そりゃあ時間がかかってスピードで負けるよな、と。
なので日本企業に対して、中国をR&D、テストマーケティングの場として使うことを勧めたりもする。(合弁などやり方考えないとだが)
一連の超急速なデジタル変化は2015の「インターネット+」という政策で一気に加速したと言われていて、これも本質は、デジタル化とデータ取得・活用という方向づけと規制緩和。
データによる14億人統治とデジタル産業育成に、強い国の意志を感じる。
家田さんは中国ウォッチャーなら誰でもというくらいメンバーになってる「中国スタートアップ」のFacebook グループの管理人を、学生の頃からやられている有名人。
自社ブログでTAPやOMOについて書かれている「中国で『決済革命』の次は『OMO』だ」も、非常に賛同できるところが多い。
https://www.mermirai.com/entry/china「歴史的に見て、日本はずっと中国に学んできた」という家田さんの指摘は、その通りだなと思いました。
今回の特集取材を通じて一番印象に残ったのは、中国起業家の「つべこべ言わずにやってみる」チャレンジ精神と、「成功したい」という純粋な熱量。
これからも続々と生まれるであろう中国のユニコーンや、個性豊かな起業家たちをどんどん取材していきたいです。