
時代に合わせて「場」を変える。課題を解決する空間づくり
丹青社 | NewsPicks Brand Design
2018/2/28
社会が変われば、求められるビジネスの形も変わり、「場」や「空間」の在り方、使い方も変化する。丹青社は、高いクリエイティブ力によって、変化を続ける社会に対応し、さまざまな手法で既存の空間に新たな価値を生み出してきた。それは、空間を「編集する力」とも言える。
ショップなどのリアルな空間は、これからどのように変化するのか。数々の人気作を生み出してきた編集者であり、コルク代表の佐渡島庸平氏と、丹青社の社長、高橋貴志氏が語り合う。
ショップなどのリアルな空間は、これからどのように変化するのか。数々の人気作を生み出してきた編集者であり、コルク代表の佐渡島庸平氏と、丹青社の社長、高橋貴志氏が語り合う。
「体験」まで含めて空間をデザインする時代
佐渡島:丹青社さんはかなり幅広く空間デザインを手がけてらっしゃいますが、内部にはどんな部門があるんですか。
高橋:商業施設やホテル、空港などを担当するコマーシャルスペース事業部、イベントやショールーム、オフィス等を担うコミュニケーションスペース事業部、店舗のチェーン展開をサポートするSE事業部、博物館や科学館などを手がける文化空間事業部の4つです。
その中に、プロジェクトを推進する営業、制作・施工を担当する技術者が所属しています。
クリエイターであるデザイナーとプランナーは、4事業部とは別の「デザインセンター」に集約されています。これは多様化・高度化したクライアントの要望によりよい形で応えるため。
たとえば「ショールームをつくりたい」という依頼にも、企業博物館のようなものからショップやカフェの併設まで、いろいろなバリエーションがある。経験を積んだクリエイターが分野の垣根を越えて、もっとも能力を発揮できる形を模索して現在の組織になりました。
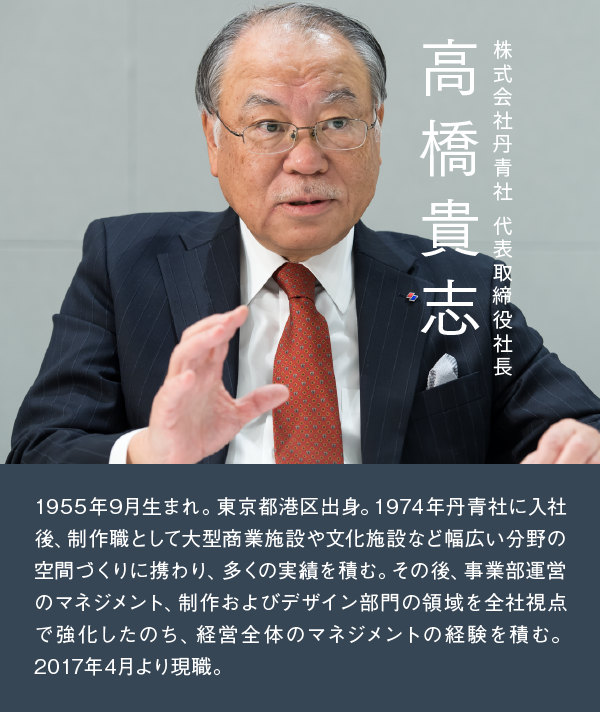
佐渡島:なるほど。時代の変化で、デザインの在り方にも変化があるんでしょうね。
高橋:変化は大きいですよ。今では、空間を「モノ」としてデザインするだけではなく、デジタル技術も導入しながら、いかに五感に訴えて「体験」をどうデザインするかが求められている。
東京ドームシティの「宇宙ミュージアムTeNQ(テンキュー)」などはそのいい例ですね。

[宇宙ミュージアムTeNQ(テンキュー)/事業主:(株)東京ドーム]プロジェクションマッピングや直径11mの大型円形高解像度シアターを取り入れる一方で、最先端の惑星探査の研究現場が見られる東京大学総合研究博物館との産学連携プロジェクトも内包。

エンターテインメント要素と学術文化要素を掛け合わせた施設になっている。
(撮影:フォワードストローク)
(撮影:フォワードストローク)
佐渡島:3Dのプリンターやシミュレーターなど、新しい技術の登場によって、プロジェクトの進め方や発想自体も変わるのでしょうか。
高橋:ビジネスのスピードアップに伴い、クライアントとのコミュニケーションも質とスピードを上げていく必要があります。その手段のひとつとして最新技術の導入は有効です。
これまでも、手で描いていたものがCADになり、さらに3DCADに進化してきました。平面ではなく3Dになったことで、具体的なイメージを持ってデザインを検討していただけるようになりました。
佐渡島:しかし、店舗のデザインはかなり難しそうですね。時代の変化が大きすぎる。しかも、クライアントに最先端の空間デザインを提案しても、クライアント側のオペレーションがついてこないとその価値が発揮できない。
高橋:おっしゃる通り、そのアンマッチを起こさないためにも、クライアントが「その空間で本当に実現したいこと」を見定めることが重要です。
切り口を変えて提案したり、時には、いろいろな場を一緒に見てディスカッションを重ねたりして、本当の課題を見つけ出すようにしています。
空間デザインは「編集」に似ている
髙橋:当社の場合、調査・企画から、デザイン・設計、制作・施工や演出、運営まで、一貫して手がけます。
クライアントの要望にお応えするために最適なチームをつくってデザインに落とし込み、時には外部のクリエイターともコラボレーションして、ひとつの空間をつくりあげる。
空間づくりを行う会社の役割は、空間づくり全体の「プロデュース」であり、これは一冊の本を手がける編集に近いのではないか。編集者の佐渡島さんから見て、この考えはどうですか。
佐渡島:そう聞くと、たしかに近いですね。
ただ、依頼者のいるデザイナーと、僕らがエージェントしているクリエイターはちょっと種類が違います。彼らは自発的な思いつきを形にする。ですから、「世間がこうだから」という理由じゃ動かないんですよね。
僕ら「編集者」は、エッジが立ったクリエイターを発掘して、彼らの作品に磨きをかけ、商品として流通できるものに仕上げることが仕事です。
たいていの人は、自分の感情を前面に押し出しても、世の中に受け入れられないという認識なので、世の中に擦り寄ってしまうことも多い。でも、そうしないほうが価値が高まりますからね。
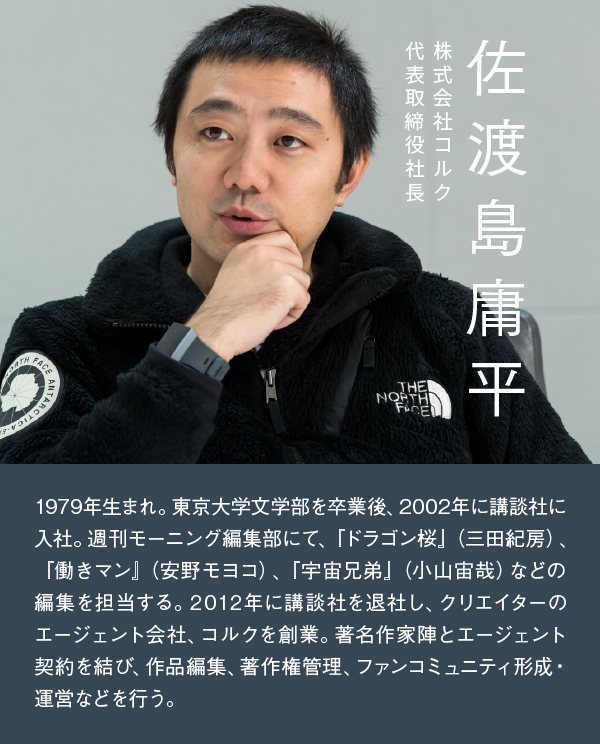
高橋:空間づくりに携わるデザイナーにも「クリエイティブマインド」は必要です。これまでになかったことを考え、新たなものを提案するチャレンジをしないと、クライアントそれぞれが抱える課題を解決するデザインになりませんから。
クライアントが求める機能を満たして、美しく整えるだけでなく、その先の未来につながるものを生み出すために感性を磨き続けなければいけない。
そこで当社では、世界で活躍するクリエイターを招いたセミナーや海外研修など、クリエイターのインプットを増やす機会づくりを強化しています。売るモノを持たない当社の財産は「人」ですから、個々のクリエイティビティを伸ばすサポートは積極的に行っていきます。
環境を変えるとコミュニケーションが変わる
佐渡島:丹青社はリノベーションも手がけていらっしゃるんですよね。これは今後も増えていくんでしょうか。
高橋:リノベーション案件の増加は必然でしょうね。
当社でお手伝いした事例では、2017年10月にオープンしたミライザ大阪城もそうです。もともと旧陸軍第4師団司令部庁舎だった、もと大阪市立博物館を、今回さらに公園の便益施設としてコンバージョンするというご計画でした。
近年、文化観光が注目されていますが、歴史あるものをありのまま見せればいいというものではありません。施設だけでなく、その周辺や背景を読み解き、魅力を引き出せば、文化資源の価値を高めた上で、より多くの人と繋ぐことができます。
既存のものを守りながらも、新たな技術や素材、演出、あるいは他業種・他分野のノウハウをどのように組み合わせて、いかに伝えるか。これが空間づくりを行う私たちの腕の見せどころです。

[ミライザ大阪城/事業主:大阪城パークマネジメント(株)]施設のある本丸エリアには、ゆっくり時間を過ごせる飲食施設がなく、滞在時間が短く機会損失していた。今回、施設の持つ歴史的価値とポテンシャルを生かした商業化計画を策定。丹青社が核テナントの誘致も行い、エンドユーザーとの間を結ぶ場を創出した。

階段、手すり、柱、躯体(くたい)、ステンドグラスなど、既存建築を極力生かし、パブリックスペースをリノベーションしている。(撮影:ナカサ&パートナーズ)
佐渡島:僕は、今の世の中で「全部新しい」ということはあり得ないと思うんです。
変化というのは、一度に起こるわけではなく、5%ずつぐらい変えていくうちに、気がついたら全部が変わってるという形で起こるんじゃないでしょうか。人間の細胞も、そうやってゆっくり変わっていきますよね。
でも日本では、オフィスはすぐ新築のビルになって、全部変わることが多い。欧米のように、これからは日本でもリノベーションを繰り返すのが当たり前になっていくと思いますよ。
高橋:働き方改革の一環として、オフィスのあり方を見直す企業も増えていますね。私たちの本社も2015年9月に移転し、それをきっかけに働き方を見直そうと改革を進めている最中です。
組織内に200人を超えるデザイナー・プランナーを抱え、「空間づくり」を生業としている当社がつくったオフィスを、好事例として見学に来られる企業様も多いです。
佐渡島:それは僕も興味があります。実際にどんな改革をしたんですか。
高橋:クリエイティビティ向上と生産性向上の両立を念頭に、オフィスの場所やしつらえと同時に、勤務制度やITなどの仕組みも変えました。
フリーアドレスの導入には、当初、抵抗感を持つ人もいましたが、ハード面のサポートと同時に、ソフトの面でも取り組み、早々に定着しました。
気分や目的に応じて働く場所を選べるように、遊び心あるデザイナー家具などもちりばめて、多様なスタイルの執務スペースを用意したのも効果的でしたね。

フリーアドレスの丹青社のオフィス。「コミュニケーション&コラボレーション」をテーマに、移転後もオフィスの改善を重ねられるよう、社内横断の体制をつくっているほか、理研ベンチャーと共同開発したアプリを使って「こころの動き」を定量的に測定し、ワークスタイルの見直しにも取り組んでいる。
佐渡島:コルクでは、逆に席を固定にしているんですよ。立ち上げたばかりのベンチャーは、役職や部門があやふやなことが多い。うちも最初はそうでしたが、人数が増えて、部門もできてきたので、それに見合ったコミュニケーションの設計が必要だと思い、あえての固定席です。
定期的に席替えして、席を部門っぽく分けてみたり、横断的になるようにしたり、いろいろと試しています。
高橋:席替えは面白いですね。環境を変えると、コミュニケーションも変わりますから。
佐渡島:ええ。コミュニケーション量が変わると人間関係が変わり、結果、アウトプットも変わってきます。
高橋:丹青社の新オフィスでは、コミュニケーションが活発になることを期待して、ミーティングなどに使用できるコミュニケーションスペースを外回りに設けたんです。
一般的なオフィスでは、窓側にマネジャーの席があることが多い。でも、窓の近くは一番環境のいいところです。外を見ながら話したほうが気持ちいいですから。

窓際に配した、丹青社の開放的なコミュニケーションスペース。

デスクに向かうだけでは生まれない、“ちょっとした”でも“重要”なコミュニケーションを生む空間デザインがポイント。
佐渡島:うらやましいです。うちは入ってるビルが古いので、天井は低いし、窓もそんなに大きくない(笑)。いたるところに植物を配置するなど、快適な環境をつくる工夫をしていますよ。
高橋:少しの環境の変化が大きな成果をもたらすこともあります。空間づくりを通じて、働きやすくて生産性が上がる環境を増やすお手伝いをしていきたいですね。
これからの時代のリアル店舗の役割とは
高橋:現在、紙の書籍が売れないとか、書店がどんどん減少しているという話がありますが、佐渡島さんはこの状況をどうご覧になっていますか。
佐渡島:僕は、今のままの書店では今後のニーズに合わなくなると感じています。昔は本を手に入れることが難しかったから、「本が手に入る」ということが書店の存在価値だった。
時代が変わってワンクリックで買い物ができるECが出てきたけど、ECは構成がごちゃごちゃしていて見づらいし、何があるかわからない。だから、書店はディスプレイの場所になった。
ECと書店しかなければ、リアルの書店に行かないと見つからない本があったでしょう。でも、今は、本に詳しい人をツイッターで50人くらいフォローすれば、セレンディピティも担保される時代です。
書店に求められているのは、「どの本を買うか」という意思決定の後押しなのではないでしょうか。人にとって、意思決定ってストレスですから。

高橋:書店に限らず、物販店や飲食店などでもそれを感じます。
エンドユーザーのニーズとリアル店舗のギャップを埋めるために、ECとリアル店舗を併用する今のライフスタイルや、変化を続けるエンドユーザーの考え方、時間の使い方に柔軟に対応する必要があるでしょう。
佐渡島:リアルショップの概念は5〜10年で大きく変わるでしょうね。
僕が今書店を作るなら、本当にいい本を1万冊だけ置いて、専門領域の違う10人くらいのコンシェルジュを雇い、「これはどうですか」と現物を見ながら選んでもらう形態をとります。その場でネット注文して、本は家に届く。
バックヤードもなくて、固定費も在庫管理も全然違うし、どうやって利益を出すかも変わってきます。
高橋:リアル店舗はなくなるのではなく、さらに形を変えていくでしょうね。より広い視野、高い視座で空間づくりに取り組めば、空間を編集する力を生かして、店舗の在り方や人と人とのコミュニケーションの未来が見えてくると思っています。
今までも時代の変化に合わせて新たな空間をつくってきたように、これからもリアルの「場」の可能性を広げていけるのが非常に楽しみです。
佐渡島:同感です。変化があれば、挑戦する楽しみがありますから。
(編集:大高志帆 構成:唐仁原俊博 撮影:片桐圭)
丹青社 | NewsPicks Brand Design



