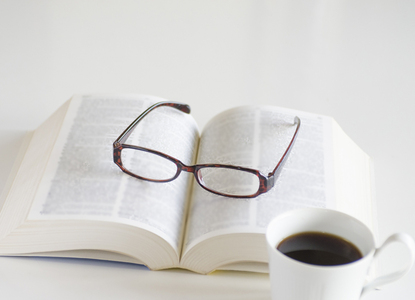
休日、本を読むなら、実用書派? 歴史・哲学派? - 何気ない人生の選択33
コメント
注目のコメント
「30代までは実用書派が多くて、40代以降になると歴史・哲学派が増えていきます」
私自身は、10代から歴史・哲学を読むことが多かったです。
今は、マンガ、雑誌、小説、歴史、哲学から経済、政治、趣味、実用書と呼ばれるものまで幅広く、いつも3冊並行で読んでます。
マンガ・雑誌・小説、堅い学術書とその間に位置づけられそうな新書やハードカバーです。
1冊をずっと集中して読むこともありますが、違うジャンルのものを複数並行して読んでいると、頭の切り替えが出来て、集中して読書できる気がします。作家の司馬遼太郎さんは、昭和の軍人に対しては批判的な小説家として知られています。特に自身が戦車隊員だった時の衝撃的な体験により、戦車隊のことは必ずしもよくは書いていません。バイアスがかかっている、という点で、Furuyamaさんの「彼らは歴史家ではなく歴史小説家」という指摘は的を得ていると思います。
仕事柄、本に囲まれて生活しているが、本の難しさは「人に勧められて読むものよりも、自分で見つけて読むもの」の方が、心の琴線に触れる率が高いということ。
そこが本の難しさで、なぜか周波のあった本から得るインスピレーションには多大なものがある。
文中の出口氏の言葉が重い。
「(一般的なビジネス書)よりも失敗した人間やいいかげんな人間が克明に描かれている歴史書や優れた小説のほうが、はるかに役に立つ」
つまり、そうした事例から「何か」を引き出せる能力があるかどうかが読書家の秘訣なのだろう。
実は私も、この意見には大いに賛成で、「成功者よりも失敗者から学べることが多い」と思い、5/20に『敗者烈伝』というノンフィクション本を出すことになっている。
これは歴史上、失敗して破滅した25人の人物の事績を追い、なぜ失敗したかを克明に分析した本である。
その多くは戦術的な面よりも、人間性に起因するところが多く、自らを律することができれば、防げたものが大半であったことに驚く。
つまり歴史の敗者から学べるものは、すぐにわれわにも役立つものばかりなのだ。
宣伝が過ぎると嫌われるのでやめておくが、敗者から学べるものは実に多い。
とくにこうした時代だからこそ、「勝つ」方法よりも「負けない」方法を学ぶべきではないだろうか。
