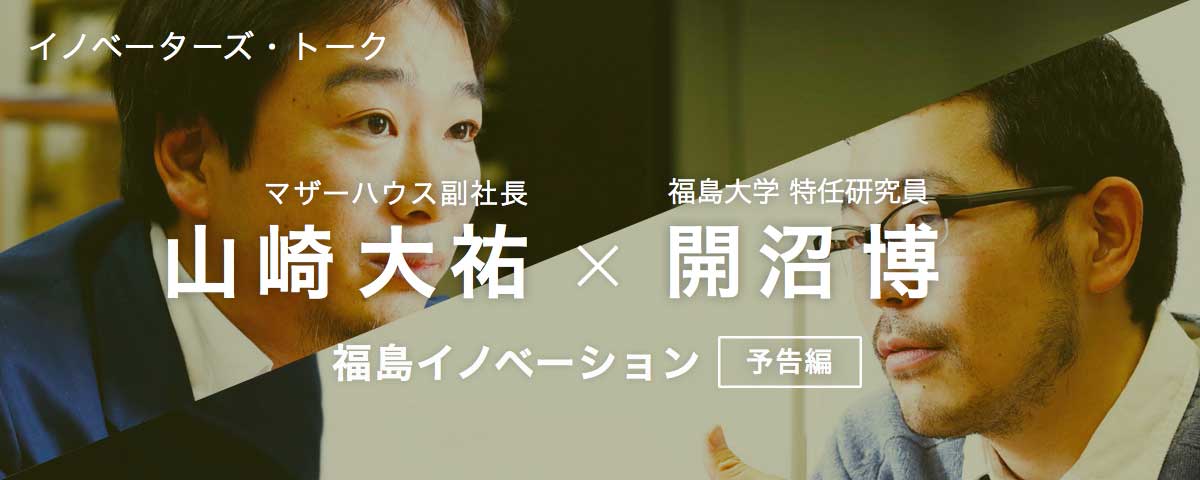
イノベーターズ・トーク
【山崎大祐×開沼博】今こそ「福島イノベーション」の話をしよう
2015/11/23
独自の視点と卓越した才能を持ち、さまざまな分野の最前線で活躍するトップランナーたち。彼らは今、何に着目し、何に挑もうとしているのか。新連載「イノベーターズ・トーク」では、毎週2人のイノベーターたちが、時代を切り取るテーマについて議論を交わす。
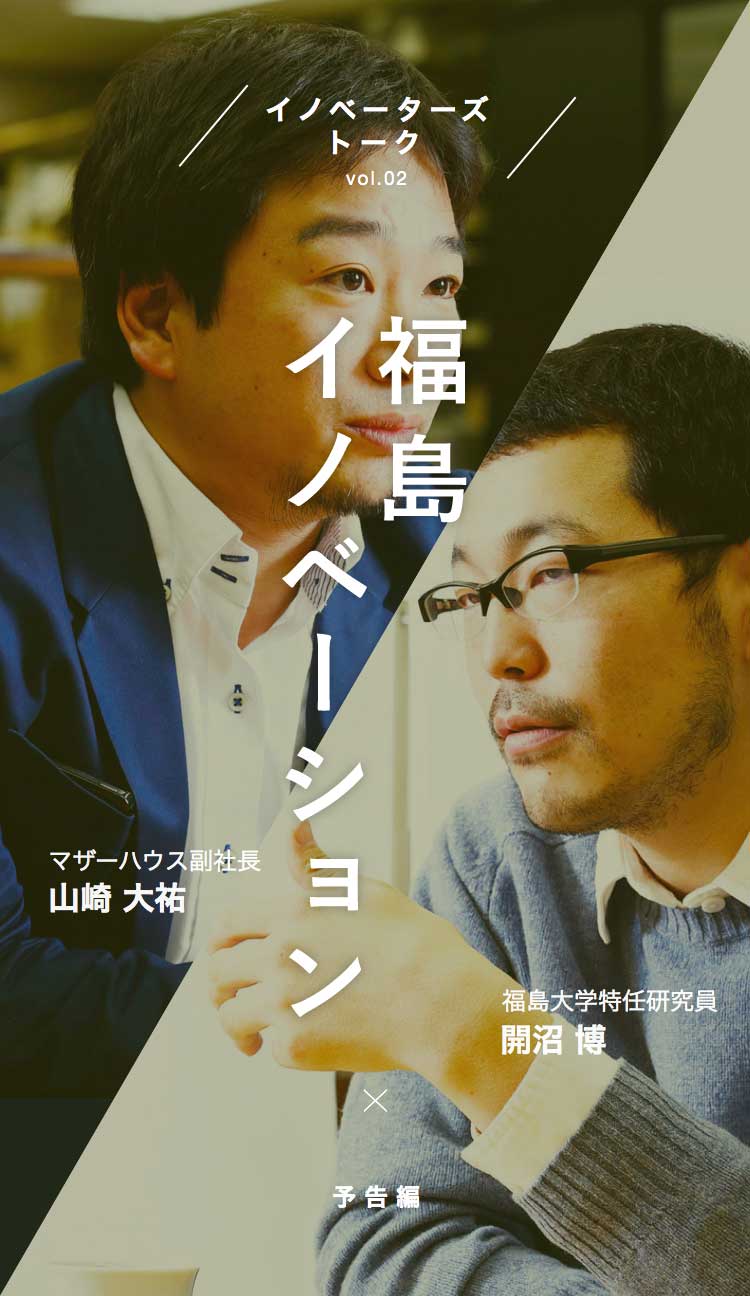
第2回には、マザーハウス副社長の山崎大祐氏と、福島研究の第一人者である、開沼博氏が登場。
これまで福島と縁のなかった山崎氏は、いわき市と福島第一原発を訪れて、大きな衝撃を受けたという。そんな山崎氏が、開沼氏に素朴な質問をぶつけながら、福島の課題とポテンシャルを探っていく。起業家と研究者の対話を通じて見えてきた “福島イノベーション”の可能性とは何か?
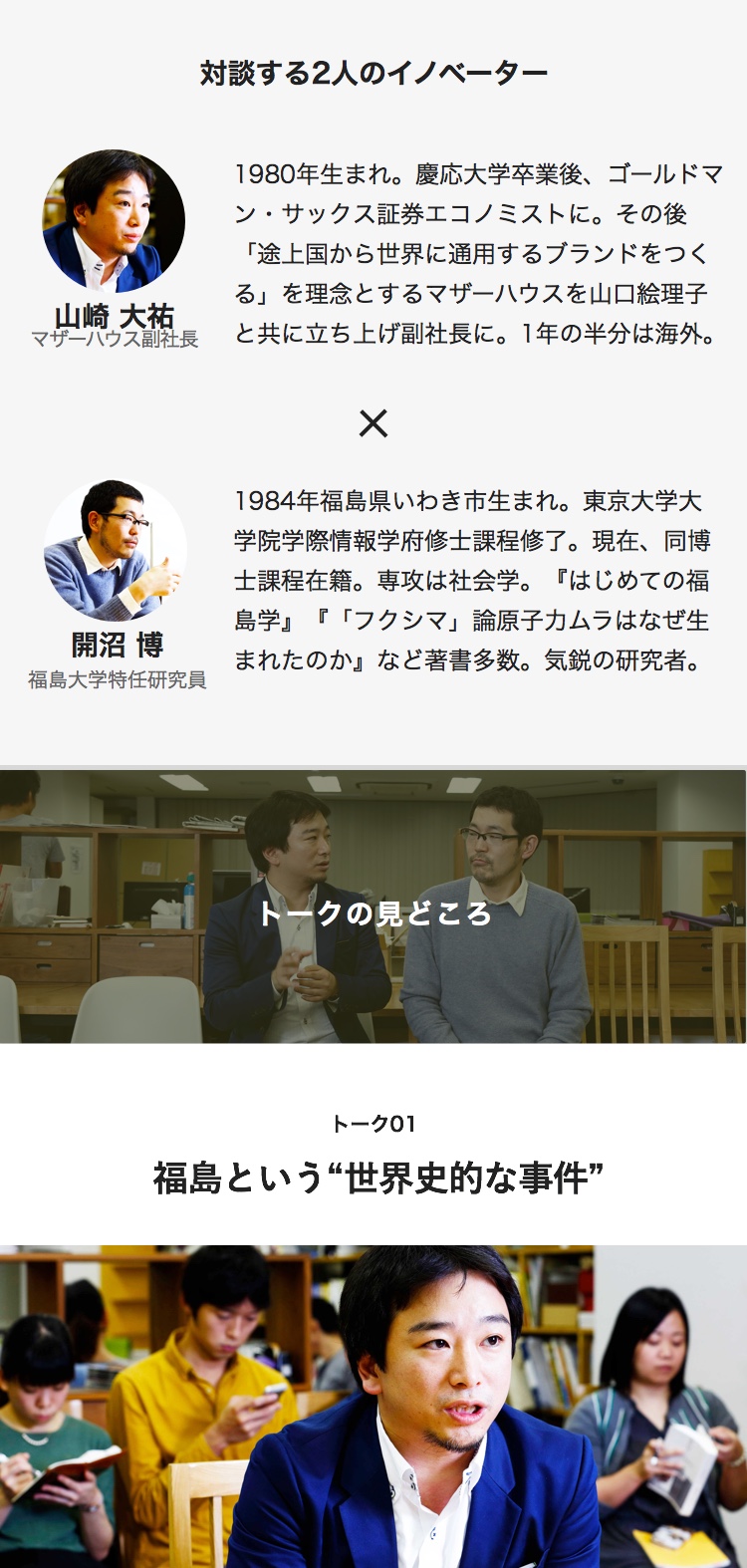
日本ではすでに「福島」への関心は色あせつつある。
しかしグローバルでは、日本に関する話題でトップにのぼるのは福島。世界を飛び回る山崎氏が各地でまず聞かれるのは「福島は、今どうなっているの?」という問いだ。
日本と世界の間には、福島をめぐって大きな認識のギャップがある。どうすれば日本国内で、福島により関心を持ってもらえるのか。そして、「かわいそう」という福島のネガティブなイメージをどうすれば変えることができるのか。
そのカギは、「プロダクトの力にある」と山崎氏は言う。
第1回福島という“世界史的な事件”をどう語るべきかに続く。

昨年末、福島を訪れた山崎氏は、福島にとても大きな可能性を感じた。そして、「僕は福島に関わりたい。むしろ福島に興味を失うことのほうがもったいない」と思ったという。
それに呼応するように、開沼氏は「医療分野では、福島が世界最先端になっている」と指摘する。
ただ、その一方で、企業の視点からすると、福島には絡みづらい面があることも事実だ。そうした壁を乗り越えて、福島発「リバース・イノベーション」を実現するポイントは何か。
第2回福島から生まれる「リバース・イノベーション」に続く。
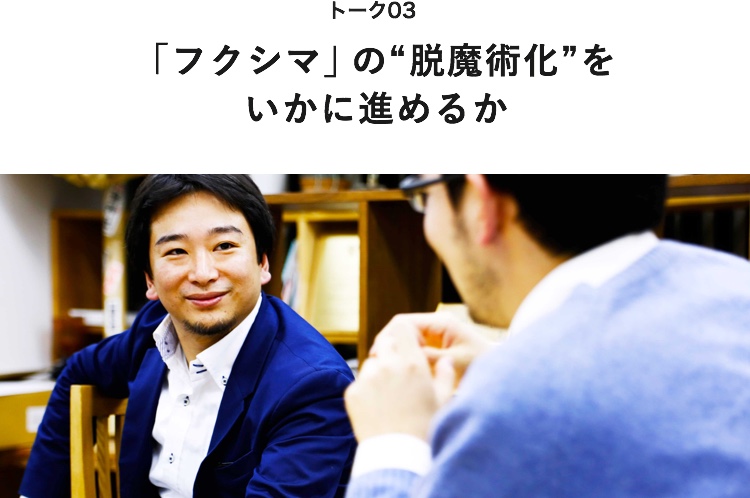
今、日本中で福島についての誤った認識が広がっている。いわば、魔術的に語られていると言っていい。
たとえば、全国の意識調査によると、福島の人口の24%が県外に流出しているというイメージがあるのに対し、実際の人口は2.5%しか減少していない。
では、この福島の魔術を解くために大事なことは何か? 2人は、とにかく福島に一人でも友人や知り合いなどを持つこと、福島の現場に行くことの大切さを強調する。
実際、山崎氏も福島第一原発を訪問して、あまりの小ささに驚いたという。
第3回「フクシマ」の“脱魔術化”をいかに進めるかに続く。

福島で今、大きなイシューとなっているのが「負の再分配」。つまり、皆が見て見ぬふりをしている嫌なことを、どう皆で分担して請け負うかという問題だ。
その典型が、原発の廃炉の作業や核のゴミ処理だ。廃炉のように世間になかなか感謝されにくい仕事を、40年間続ける人たちがいるという事実は重い。
この「負の再分配」の問題は、「今後、日本全国でますますせり出してくる問題であり、将来、高齢化し始める中国やインドなどの新興国でも出てくる話かもしれない」と開沼氏は言う。
第4回「負の再分配」がかっこいい、という文化をに続く。

1986年に原発事故が起きたチェルノブイリは今、観光地として栄えている。
それと同じように、福島も「ダークツーリズム」の場として売り出すことはできないのか。開沼氏は「絶対やるべき」だと話す。
山崎氏も、開沼氏に賛成。自身の会社で行ってきた、バングラデシュへのツアーでも、大きな発見があったという。
「大事な体験を本当に気持ちいいかたちで背中を押してあげることができたら、一生忘れない体験になって、一生の付き合いができるはずだと僕は思っている。僕が福島に行った経験というのは、たぶんそれに近い」と語る。
第5回「ダークツーリズム」の可能性に続く。
第1回:11月23日(月)公開
福島という“世界史的な事件”をどう語るべきか
第2回:11月24日(火)公開
福島から生まれる「リバース・イノベーション」
第3回:11月25日(水)公開
「フクシマ」の“脱魔術化”をいかに進めるか
第4回:11月26日(木)公開
「負の再分配」がかっこいい、という文化を
第5回:11月27日(金)公開
「ダークツーリズム」の可能性
(デザイン:甲斐琢巳/写真撮影:大隅智洋/映像制作:古田清悟、久藤拓実)

