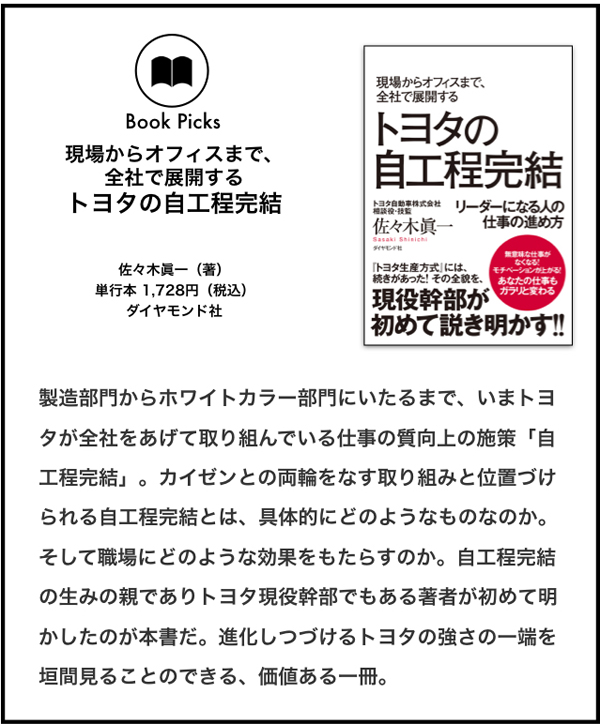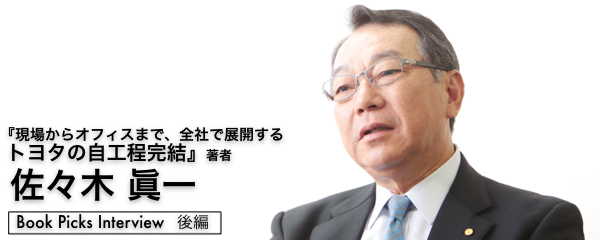
『現場からオフィスまで、全社で展開する トヨタの自工程完結』著者 佐々木眞一氏インタビュー(後編)
つまらないミスをしている暇はない。トヨタは次なる高みを目指す
2015/11/21
時代を切り取る新刊本をさまざまな角度から紹介する「Book Picks」。隔週金曜日は、話題の新刊著者インタビューを前後編に分けて掲載する。今回取り上げるのは、『現場からオフィスまで、全社で展開する トヨタの自工程完結』。「自工程完結」とは聞き慣れない言葉だが、これが過去最高の営業益を更新しつづけるトヨタの新たな生産性向上の取り組みであり、製造現場のみならずホワイトカラーまでをも巻き込んで驚くべき成果を上げていると聞けば、NewsPicks読者なら耳を傾けないわけにはいかないだろう。自工程完結とはいったいどのような施策なのか。どのような経緯で始まり、トヨタの職場にどのような変化をもたらしているのか。施策の旗振り役として取り組んできたトヨタ自動車の佐々木眞一氏に、詳しくお話を伺った。
前編:トヨタが取り組む「ホワイトカラーのカイゼン」
正しいマニュアルなら、マニュアル人間でもいい
──自工程完結はどのような手順で取り組むのでしょうか。
佐々木:自工程完結の手順を簡単に申し上げれば、(1)目的・目標を定める、(2)その目的・目標を達成するためのプロセスを設計する、(3)そのプロセス一つひとつが正しく行われるための条件を整える、となります。
特に定例的な仕事をするときには、どういう手順で仕事を進めたかを書き記しておけば、次の仕事に役立てることができます。次に使った際にそのつど内容をアップデートすることで、異動で担当者が代わったときにもゼロから仕事を覚える必要がなくなります。
これはいわゆる「マニュアル」ですが、一般的なマニュアルとは違います。
従来のマニュアルというのはたいてい、ただ「アウトプットイメージ」が書かれているだけです。そのアウトプットをどうやって出していくのかという、意思決定のプロセスは書かれていません。しかしそれでは、本当の意味でのマニュアルにはならないのです。
──本に書かれていた「正しいマニュアルならマニュアル人間で十分に通用する」という一節(同書159ページ)を読んでドキッとしましたが、マニュアルの意味が違うのですね。
おっしゃるとおりです。一般的に「マニュアル人間」というと、自分の頭でものを考えず、指示書がなければ何もできない人のことを指します。
しかし私がこの本で言いたいマニュアル人間とは、
要するに物知り人間のことです。アウトプットイメージだけが書かれたマニュアルではなく、意思決定のプロセスもきちんと書かれているマニュアルならば、人はそこからたくさんの知恵を得ることができますから。自工程完結とは、知恵をたくさん持っている人を育てる取り組みとも言えます。
抵抗感を示す社員こそリーダーに
──意思決定のプロセスが書かれたマニュアルがあれば、異動したてのスタッフや新入社員は大助かりでしょうね。一方ベテランスタッフの中には、自分が長年かけて培ってきた暗黙知をマニュアルに明文化されることに抵抗感を覚える方もいたのではないでしょうか。
ええ、いました。だいたいどこの組織にも、何か問題が起きたとき「あの人に聞けばわかる」とまわりに思われているその道の専門家がいるものですが、彼らにとっては抵抗のあることだったと思います。
しかし見方を変えれば、その人たちの知恵がなければ自工程完結を進めることはできないということです。彼らこそが、どこが車の水漏れに影響するかを工場の中で一番よく知っているような人たちですから。
そこで、逆にそういう人を自工程完結のリーダーにしてしまったんです。「どのあたりが危なそうか、水が漏れてから『ここだ』と言うのではなく、漏れる前から『ここが危なそうだ』と、工程すべてを見て歩いて指摘してほしい」と。そうすると、その人はリーダーシップを発揮せざるをえなくなりますよね。
「おまえの知っていることを全部吐き出せ」「素人でもできるようになったから、もうきみは要らないよ」ではなくて、「素人でもできるようにするのはきみの役割だよ」と働きかけるんです。その人の持っている知恵がどれだけ役に立つか、それを語ることを心がけました。
自工程完結で変わる管理者の役割
──自工程完結を取り入れる前と後とで、マネージャーの仕事に変化はありましたか。
一番大きく変化したことといえば、仕事の管理のしかたです。
それまでは、管理者の仕事といえば部下の仕事の失敗を早く見つけることでした(笑)。失敗を見つけたら、手助けするなり叱咤(しった)激励するなりして、軌道修正を図ります。このような業務管理のしかたは、問題解決型の管理ですね。
しかしこれでは対症療法になりがちです。問題が起きた、すぐ対処しなければ、とやっているとモグラたたきのようなもので、原因を追究することが後回しになってしまいます。
それが、自工程完結を取り入れたことで、管理者は部下がうまく仕事をこなせるようにお膳立てをするのが仕事になりました。業務環境を整えるという役割へと変化したのです。
同じ管理でも、部下がミスすることを前提に管理するのと、うまくいくはずだという前提で管理するのとでは大きく違います。うまくいくことを前提に管理できるようになると、仮に何かミスが起きたとき、「うまくいくはずなのに、なぜミスが起きたのか」というふうに、管理者の意識が「なぜ」の部分に向くようになります。
フィードバックのかかる管理体制になれば業務プロセスの改善につながりますから、管理能力は飛躍的に向上すると思います
──なるほど、自工程完結で仕事のやり直しが減るだけでなく、管理者の仕事も大きく変わるのですね。ところで、自工程完結の考え方を頭では理解できたのですが、いざ「わが社でも取り組もう」となったときにどこから着手すればいいのか迷いそうです。
実は、自工程完結を頭(目的・目標設定)からやろうとすると難しいんですよ。一番簡単なのは、失敗事例を見つけて、その再発防止というところから着手するといいと思います。
過去の失敗事例をひもといていくと、「こんな目標じゃ世の中に通用しなかったな」とか「意思決定の順番がまずかった」「事前に誰それに意見を聞いておくべきだった」といった失敗要因が何かしら見えてくるはずです。
そこで、次回の企画段階で計画書に改善点を盛り込めば、それは自工程完結に一歩近づいた計画書になっているわけです。
ライバルにまねされたらどうする?
──自工程完結を製造現場だけでなく全社的な取り組みにしたきっかけは、ホワイトカラー部門の意思決定スピードを欧米並みに早めるためとのことでした(前編参照)。それが実現したいま、トヨタの強さの新たな秘密である自工程完結をこのように本に書いて発表することにご懸念はないのでしょうか。外国のメーカーがトヨタから学ぼうと虎視眈々(たんたん)と狙っていると思うのですが……。
本を書いておいてこんなことを言うのはなんですが、この本を読んだからといってすぐにまねできるものではないと思っています。世の中に「トヨタ本」はごまんとありますが、いまだにトヨタ生産方式についてはトヨタ自身がアドバンテージを保っているのと同じです。
本はひとつのきっかけにはなるでしょうけれど、これを読んでいただいたからといって、いきなりわれわれのアドバンテージが失われるとは思いません。

佐々木眞一(ささき・しんいち)
トヨタ自動車相談役・技監
1970年3月北海道大学工学部機械工学科卒業。同年4月トヨタ自動車工業(現トヨタ自動車)入社。1990年4月トヨタ モーター マニュファクチャリングUK品質管理部長。1995年1月トヨタ自動車堤工場工務部長。1996年6月取締役就任。2003年6月常務役員就任。2004年6月トヨタモーターエンジニアリング・マニュファクチャリングヨーロッパ取締役社長。2005年6月専務取締役就任。同年10月トヨタモーターヨーロッパ取締役社長。2009年6月取締役副社長就任。2013年6月相談役・技監就任
──本書の最後に「『自工程完結』を使ってホワイトカラーに時間ができたとき、さらなる付加価値をどう付けるのか、ということこそが、次の課題になる」(同書237ページ)と書かれています。自工程完結を目的にしてはいけないのだと。では、自工程完結によって生まれた時間でトヨタは何に取り組みますか。
車はいまや街の至る所を走り回っていますが、一方では交通事故の元であったり、渋滞の元であったりします。排ガスだってゼロになったわけじゃない。そういう課題に対して、われわれがやるべきことはまだまだたくさんあります。
だから、つまらないことで失敗している暇はないのです。一刻も早く自工程完結を根づかせ、わかりきったことで失敗する場面は極力なくしたい。そして、自工程完結によって生み出された時間で実証実験をしたり新しい領域にトライしたりして、社会インフラとしての車の可能性を追求したいのです。
その結果、車を通じて少しでもお客さまが笑顔になっていただけたら、冥利に尽きますよね。