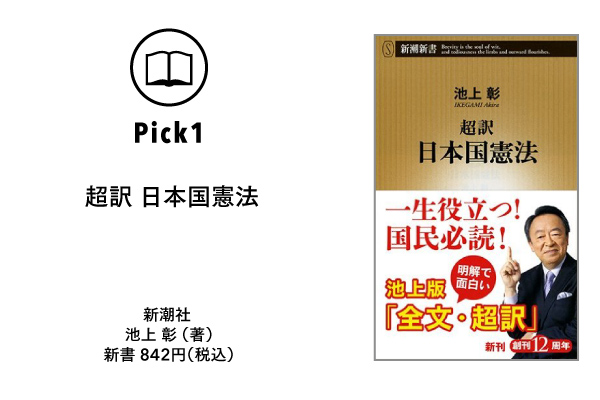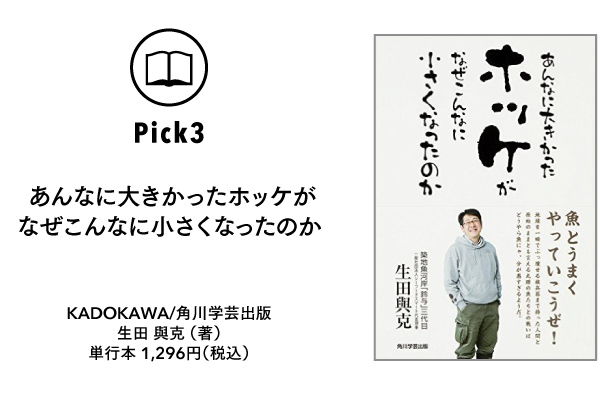編集部がピックアップする新刊3冊
「この国のかたち」を考える。憲法、飛鳥時代、水産資源
2015/9/9
時代を切り取る新刊本をさまざまな角度から紹介する「Book Picks」。毎週水曜日は「Editor’s Choice」と題して、NewsPicks編集部のメンバーがピックアップした新刊本を紹介する。
今回は『超訳 日本国憲法』『天上の虹 第23巻』『あんなに大きかったホッケがなぜこんなに小さくなったのか』の3冊を取り上げる。
憲法に関する昨今の書籍は、安全保障関連法案の動きに関連づけた9条論が中心だ。『超訳 日本国憲法』は、9条だけでなく憲法の条文をすべて掲載し、難解な文章は池上彰氏が施した「超訳」付きである。また、いくつかの重要な論点については、平易で簡潔な解説がなされ、比較対象として米国、中国、北朝鮮の憲法も収録されている。
日本国憲法は、その成り立ちから「押しつけ憲法」などとさまざまな議論がある。ただ、戦後70年間、日本がこの憲法を国家の礎としてきたことは揺るぎのない事実であり、「この国のかたち」の根幹である。
しかし、普段、憲法を意識して生活することはほとんどない。大学の法学部で学んだり、法務関係の仕事、あるいは、筆者のように公務員試験などのきっかけがない限りは、憲法と向かい合う機会は少ない。義務教育の場でも憲法については、ごくわずかな時間しか取り上げられない。
憲法を学ぶことは、単に日本の憲法に詳しくなるだけではなく、人権や義務についても学ぶ、考えるということでもある。国家制度の根っこが憲法であることを考えれば、人生のどこかでしっかり学ぶ機会が必要であろう。
この本では池上氏の「わかりやすさ」が光っている。筆者は池上氏の「わかりやすさ」については、時に危険なデフォルメ化だと感じる場合もある。
たとえば、中東情勢については、宗派間対立を強調しすぎて、宗派とは関係のない部族対立、社会・政治などの影響が捨象されてしまい、誤ったイメージ形成につながりかねないという懸念を抱いたこともあった。池上氏の「わかりやすさ」の善しあしについては、筆者の知人たちの間でも、しばしば議論に上がっている。
しかし、『超訳 日本国憲法』は池上氏の本領が発揮されており、素直に評価したい。政治的なイデオロギーや池上氏の個人的見解を極力排して、シンプルに「憲法には何が書いてあるのだろうか」という素朴な疑問に答える内容になっている。
日本国憲法は条文によっては、現代人にとって非常に読みにくく、理解が難しい箇所もある。池上氏は現代人には難解な条文については「超訳」を試み、平易な条文はあえてそのまま残すという方法で各条文を良い意味で淡々と、リズミカルに紹介していく。
そして、現代政治で論点として取り上げられることが多い条文については、主要学説や判例を簡潔に紹介している。ほかの憲法関連の書籍にありがちな、特定の考え方に誘導するような議論は展開せず、客観性を保とうとした努力の跡がうかがえる。むしろ、法律の専門家でなくても、入門書あるいは簡易レファレンスとして活用できる本書のような書籍がなかったことのほうが驚きだろう。
9条論ばかりではなく、本書を手に取って戦後日本の礎となった憲法全文と静かに向かい合う時間をつくってみてはいかがだろうか。
憲法の次は、飛鳥時代にタイムスリップしたい。少女漫画の『天上の虹 持統天皇物語』を紹介する。この漫画は、名君と名高い女帝、持統天皇(鸕野讚良、在位690〜697年)がヒロインである。持統天皇の治世は、日本の各種制度の源流がかたちづくられた時代であり、日本史では重要な時期の一つと言えるだろう。
しかし飛鳥時代について、筆者は、学校の歴史の授業で習ったぼんやりとした知識しかなかった。大宝律令、遣唐使……という程度の認識だった。高校で日本史を選択しなかったツケか。
本書の1巻は、妻が近所の公立図書館で借りてきた。何気なく読んだところ、飛鳥時代の面白さに一気に引き込まれてしまった。最終巻となる23巻が今年3月に出版されたことを知り、Book Picksに取り上げるべく、筆者は自宅近くの漫画喫茶にほぼ1日こもり、23巻まで一挙に読破した。
『天上の虹』は持統天皇の幼少時代からスタートし、23巻で天智天皇(中大兄皇子、持統天皇の父、在位668〜672年)の崩御までの一生が描かれる。天智天皇、天武天皇(大海人皇子、持統天皇の夫、在位673〜686年)、そして持統天皇の治世が詳細に書き込まれている。この3人の天皇が行った政策は、その後の日本という国家の形成に多大な影響を与えた。
具体的には、明治期まで影響がみられる律令制度、現在の霞が関の省庁名にも名前をとどめる官僚制度、そして中央集権体制、日本書紀と古事記という正史の編さんなどがある。持統天皇は外交にも注力する。
当時の日本にとっては、超大国として東アジアに君臨していた唐に対して、下にみられず、いかにして対等の外交関係を結ぶかという課題があった。669年を最後に休止していた遣唐使は、持統天皇が上皇時代の702年に再派遣され、正式な外交関係が再開された。
まだしっかりとした制度がなく、「日本とはなにか」というアイデンティティもままならない時代であった。その時代に、壮大な国家ビジョンを持っていた持統天皇たちが示したリーダーシップと発想は、現代日本人の模範にもなるだろう。
本書は漫画だからといって、時代考証がおろそかにされているわけではない。里中満智子氏は23巻の後書きで、1500冊以上にも及ぶ文献を読み、事実関係、あるいは有力説に従って忠実に描いたと主張している。
もちろん、資料に乏しく、事実関係が明らかではない時代でもある。その点について、里中氏は史実を踏まえる慎重さを持ちつつも、歴史ロマンとしての想像力を働かせ、当時の人々や歴史をダイナミックに描く。
持統天皇については、政治手腕は高く評価されているものの、冷淡な性格だという見方もある。しかし、里中氏は、持統天皇を一人の女性、親、妻としても捉え、最高権力者の苦悩と個人的な感情の相克を見事に描き出している。
また、本書は、重要な場面に万葉集の名歌をちりばめている。筆者は受験生の頃に、意味も吟味せずに試験のために万葉集を暗記した記憶があるが、『天上の虹』では当時の人々が歌に込めた想いが生き生きとよみがえる。
万葉集の時代の言葉の美しさは、繰り返し読めば読むほど心に染み入る。忙しい現代社会とは違うゆったりとした時間の流れの中に、当時の人々の心の豊かな機微が感じられる。
飛鳥時代から平安時代にかけては、女性天皇が多く存在した。そして、現代日本の「この国のかたち」の基礎が形成されたのが持統天皇の治世。『天上の虹』を読んでいて筆者は、まるで古代の人々が、不透明な先行きを抱える現代日本人に対して、国の基本に立ち戻れという示唆をしているように思えてならない。
『天上の虹』は、1983年に講談社の少女漫画雑誌『mimi DX』で連載を開始した。今年3月に出版された23巻で32年に及ぶシリーズが終了した。里中氏のライフワークと言える大作である。
里中氏が手がけた漫画には、『ギリシア神話』『名作オペラ』『旧約聖書』などもある。これらの作品も難解なテーマをわかりやすく、かつ学説や資料を十二分に踏まえて描かれている。里中氏のそのほかの作品もぜひ手に取っていただきたい。
3冊目は、水産資源管理を扱った生田與克著『あんなに大きかったホッケがなぜこんなに小さくなったのか』を取り上げる。
著者の生田氏は略して「あなホケ」と呼んでいる。生田氏は築地魚河岸「鈴与」を3代目社長として切り盛りする傍ら、水産資源の保全活動と啓発を行う団体「シーフードスマート」の代表理事も務める。魚を知り尽くした人物である。
ラジオや動画番組でも活躍しており、軽妙な江戸っ子口調で笑いを誘いながらも、水産を中心とした社会問題を鋭く指摘する。「あなホケ」でも随所に江戸っ子口調がちりばめられ、読みやすい本となっている。
各種報道の通り、マグロ、サンマ、ウナギと日本の水産資源は危機的な状況に置かれている。「あなホケ」では、一昔前は簡単に取れた魚が全然取れなくなってしまったというエピソードが紹介されている。そして、漁師は儲からない職業になってしまった。
現在の日本の漁業について生田氏は、回転寿司など安い魚のニーズが強いため、漁業者は「子ども」や「赤ちゃん」の魚を乱獲して、単価が下がり、そして漁師の収入も上がらないという「乱獲、乱売、乱食」のスパイラルに陥ってしまっていると指摘する。
タイトルにつけられたホッケはかつては、大きな魚の代名詞であったが、確かに、最近の居酒屋で出てくるホッケは小ぶりなものが多い。これも魚が成長する前に乱獲をした弊害の一つである。
生田氏は日本の水産資源管理の在り方に対して、手厳しい批判を展開する。日本では総漁獲可能量(TAC)が設定されている。TACは生物学的許容漁獲量(ABC)をベースに決定される。
ABCは専門の科学者がその魚の持続可能性について議論したうえで決める数量であり、その数量までならば将来にわたりその魚を食べ続けられるということになる。本来ならば、TACはABCより小さく設定されなければ、持続可能性が失われてしまう。
しかし、生田氏によれば、日本ではTACがABCを大きく上回る状況がみられるという。一方で、漁師が高級取りとして人気職業になっているノルウェーなどでは、厳密に水産資源管理が行われている。単価は高くなってしまうものの、漁場そのものが痩せてしまっては、肝心の魚を食べられなくなってしまう。
ノルウェーなどの水産資源管理について生田氏は、「漁獲枠個別割当制度(IQ)や譲渡可能個別割当制度(ITQ)を導入して、乱獲を防ぎ、成果を上げている」という。IQは「捕ってよい総数量を、漁が始まる前にあらかじめ一人ひとりの漁師、漁船、漁業会社等に分配しちゃう」(原文ママ)方式であり、ITQはIQの発展系で漁業者ごとの事情に合わせて漁獲量を事前取引する仕組みである。
生田氏はITQを「オレは去年、船を新しくしたから、今年は余計に捕りたいなという漁師と、ウチは経常利益がバッチリ出ているし、今年はそんなにムキになってやらなくてもよいなぁと考える漁師」(原文ママ)の間で漁獲量を譲渡する制度と説明する。
日本人にとって魚はなくてはならない食材の一つだ。生田氏によれば、「日本は世界でも最も漁場に恵まれた国」である。豊かな漁場を取り戻すには、国の取り組みが必須だ。もちろん、漁獲量に制限を加えれば、漁業者からの反発が予想される。
ノルウェーなどの漁業先進国もそうした経験をした。食文化を守り、漁業をより高収入で豊かな産業とするためには、政府が関係者を説得しなければならない。ただ、生田氏によれば、海の回復力は強く、数年我慢すれば豊かな漁場が戻るという。
築地の現場経験に裏打ちされた「あなホケ」は、持続可能な漁業を実現するための問題点の指摘だけではなく、政治リーダーシップの必要性も示唆している。生田氏は単なる魚屋ではない。日本という「この国のかたち」の重要な一部を成す魚食文化について、「あなホケ」をスタート地点として考えてみてはいかがだろうか。
(文:川端隆史)