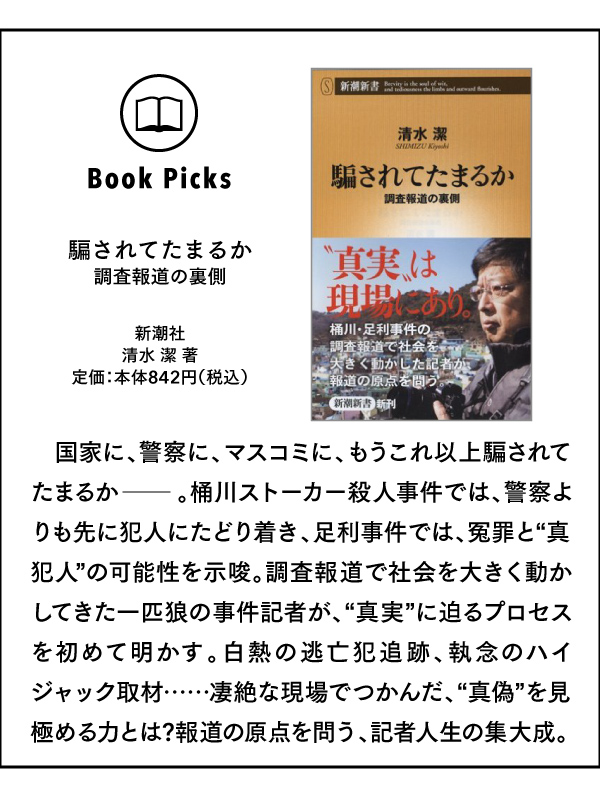『騙されてたまるか 調査報道の裏側』著者・清水潔氏インタビュー(前編)
冤罪事件を暴いた名ジャーナリストが記者を志した原点
2015/9/4
時代を切り取る新刊本をさまざまな角度から紹介する「Book Picks」。隔週金曜日は、話題の新刊著者インタビューを、前後編に分けて掲載する。今回は、桶川ストーカー殺人事件や足利事件で警察よりも先に真犯人の存在を示唆し、ペンの力で社会を動かしてきたジャーナリスト・清水潔氏へのインタビューを敢行。「権力を監視する」という役割を放棄しつつある既存メディアを、どのような視線で捉えているのか。新しいジャーナリズムへの期待とは。一匹狼の事件記者が、報道に対する問題意識を語る。
自分が報じなかったら、世に出ないことを報じる
──清水さんはこれまで、事件の取材手法を詳細に記し「記者の教科書」とも呼ばれる『桶川ストーカー殺人事件―遺言』や、冤罪事件にまで発展した『殺人犯はそこにいる 隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件』を執筆しています。
なぜこのタイミングで、過去の取材や自身の取材の信念について、新書にまとめたのですか。
清水:前の2作は、取材した事件の経緯が複雑で、到底短い記事やニュースでは詳細な部分が伝わらないと思い、1冊のノンフィクションというかたちでまとめました。
しかし、2冊目の『殺人犯はそこにいる』を書いているときに、調査報道の定義や記者クラブの問題点などにも言及することがあって、こうしたことをちゃんと書いたほうがいいという気持ちが出てきたんです。
だから、今回の本では、前の2作で取り上げた2つの事件のほかにも、ほとんど表に出してこなかった取材過程も含めて、調査報道の「裏側」を書き込んでみました。
当然ジャーナリストたちの参考にもなるだろうし、一般の人にも「ああ、こうやって調べていくと真実がわかるのか」とか、逆に「ジャーナリストとはいえ、だまされることも多いんだな」と現場のことを知ってほしい。そんな思いで書きました。
──本作のテーマは、まさに「調査報道とは何か」ということだと思います。清水さんにとっての「調査報道」を改めて定義するならば?
「自分がこの事実を報じなかったら、世の中に出ないことを報じる」のが調査報道だと思っています。
著書では「速度のスクープ」という書き方をしましたが、「どうせこんなの、すぐに発表される」ということを速く報じてもあまり意味がありません。
たとえば、捜査本部が捜査に着手したとか、容疑者を逮捕したとか、裁判が始まったとか。これらはいずれ、必ず表に出てくる情報じゃないですか。そうした情報を一刻も「早く」伝えようという強い気持ちはありません。
誰も気づいていないことを調べて、新たな事実を明らかにする。その事実を伝えていく。それが僕の思う調査報道です。
さらに付け加えると、発表される情報は必ず発表者に都合のいい方向にコントロールされていきます。ほら、僕だって、さっきから自分に都合のいいことしか言わないでしょ?(笑)
だから、発表されたものもきちんと検証しなくちゃいけない。これも調査報道の大事な役割だと思います。
「小さな戦い」を積み重ねていないと、権力に立ち向かえない
──清水さんはジャーナリストとして活躍していますが、一般的にジャーナリストの才能は、天性のものでしょうか、それともトレーニングで身に付くものでしょうか。
一つ言えるのは、トレーニングしていなかったら、ジャーナリストとして食っていけないということです。
たとえば、安保法制の報道では、当初は大手マスコミは批判的な報道が全然できていなかった。むしろスポーツ新聞や女性誌のほうが頑張っていたぐらいです。
ネタ元である政権に対して、批判的なもの言いをするのは、間違いなく度胸がいることです。なぜそれができないかといえば、これまで記者たちが「小さな段階」で戦ってきた経験が少ないからでは。
たとえば、警察の幹部と口論したり、あるいは大事なことを隠蔽(いんぺい)する相手に対し「私はあなたの言い分を聞きに来たのだから、きちんと説明していただけないならば、こちらの一存で書きます」と言い切るような、いい意味での戦いを積み重ねていないと、大きな権力と戦うことなど到底できない。
若いうちから記者クラブの世界だけに浸かっていて、取材の“足腰”が弱っている人が、いきなり強大な権力と戦うのは不可能なんです。
だから、権力がちょっと弱くなって、支持率が下がってくると「じゃ、そろそろ行きますかね」といって横一線でたたき始める。それが日本のメディアの現状なんです。情けないよね。
──なぜ日本のジャーナリズムには批判精神が足りないのでしょう。
記者の就職活動の段階から始まっているのでは? 「公務員になろうか、マスコミに行こうか、銀行に行こうか」みたいな考えで就職活動をスタートさせますから。
懸命に勉強して、やっと自分の行きたい会社に入った人たちは、必死にしがみつこうとするじゃないですか。だから、入社した瞬間に「守り」に入る。
メディア人の中には、「役人になろうと思ったけど、マスコミのほうが自由で給料いいよね」という考えの人までいる。だから、この国のマスコミは反権力に結びつかない。
「首相動静」を見ると「◯◯新聞社社長と会食」「△△テレビ社長と懇談」といったことが書いてあります。
社長が首相とご飯を食べているから、記者が政権批判できない、というわけではありませんが、こうした情報が出ることで、サラリーマン記者の皆さんは「首相と社長、仲いいんだ」と勝手に忖度(そんたく)し、追及の手を緩める。問題の一つにはサラリーマン記者の自己保身能力もあると僕は思いますよ。
僕なんかチンピラで、「もともと失うものなんか何もねえよ」みたいな人ですからね。37歳くらいまで、カメラマンだったんですよ。
脇に立つカメラマンとして、記者の取材手法を勉強
──新潮社の写真週刊誌『FOCUS(フォーカス)』に所属していましたね。
ええ、カメラマンって記者と取材に行くでしょう。15年間のカメラマン生活で、多くの記者の取材方法を、じっと横で見てたんですよ。
「こうやって説得するのか」「こうやって、わなにはめるのか」(笑)。「こうやって誠実に取材交渉していくのか」と、自動的に取材の勉強ができた。あの経験は、僕にとっての財産です。
取材後に、一緒に行った記者の原稿を見ると、「ああ、なるほど。この面白い発言をリードにしているのか」と気づくことができる。
そのうち、家に帰って自分でも原稿を書き始めたんですよ。「だいたいこれぐらいの行数だ」ってわかるから、その行数に収まるよう、一生懸命書いてみる。そして、記者が書いた原稿のゲラと比べてみる。すると「ああ、やっぱりうまいなあ」と、差を感じる。
あの頃は「シャドー原稿」と呼んでましたが、1年ぐらい、こつこつとやってました。
それで、フォーカスの編集長が代わったときに「記者になりたい」と手を挙げてみたら、なんとか登用してもらえた。
──記者になりたいという気持ちがずっとあったのですか。
そうですよ。僕は大学に行くのもやめて、20歳ぐらいまでは今の仕事とは全然関係ないことをやっていたんです。
でもあるとき、「世の中にはいろいろなことが起きてるのに、俺って何も知らないんだな」と思う機会があった。そこから新聞や雑誌を真面目に読み始めた。
特に印象に残っている報道が、九州の小倉で、裁判官が被告と関係を持ってしまった事件です。「僕と付き合ったら、君の判決を軽くしてあげるよ」と被告の女性にもちかけた、トンデモ判事がいたんですよ。
ところが彼は、悪行がバレそうになった途端、町議選に立候補した。公務員が立候補すると自動的に裁判官を失職する。そして退職金をもらった。クビになる前に退職金をもらって消えるつもりだったのでしょう。
どの媒体も当初は批判的な報道を展開していたけれど、「今の法律じゃ裁けない」という結論になり、次第にトーンダウンしていった。その中で、ある新聞が諦めないでこのテーマを長く追い続けた。
結果的に、「おかしいじゃないか」という世論が高まり、判事は、女性の体を収賄したという考え方をもって(公務員職権濫用罪)、懲役1年の実刑判決を受けたんです。
事件自体はそれほど大きく報じられたわけじゃないけど、たまたま僕はそれを読んでいて、「裁判官の犯罪だって許さない、これがマスコミの強さなんだな」と印象に残った。それが記者を志した原点ですね。
当時のマスコミにはフリーや派遣は少なく、そこで働くのは今よりも大変でした。でも、どうしても記者になりたいと思っていろいろ調べたら、新聞社のカメラマンの中途採用は、あまり学歴が問われないとわかった。それで新聞社の写真部に入って、一から修行したんです。いつかどこかで記者になってやる、って思いながら。
振り返れば、記者を目指したきっかけも、今やっていることとつながっていますね。
(聞き手:野村高文、ケイヒル・エミ、構成:ケイヒル・エミ、撮影:遠藤素子)