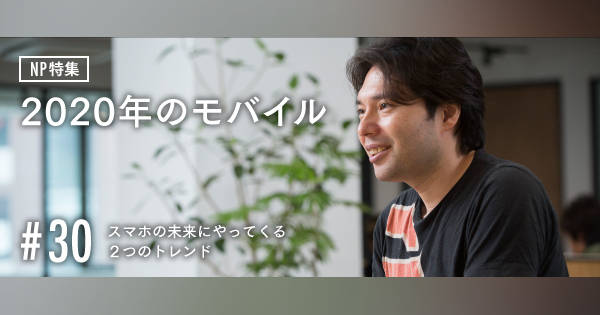スマートニュース創業者・鈴木健「スマホの未来にやってくる2つのトレンド」
コメント
注目のコメント
将来のスマホ像がリモコン化・ハブ化が未来?かは記事のまとめ方として、少しだけ違和感かもです。動かすものが今より分かりやすいハードが少し多く追加されますが、すでに情報の「リモコン化」「ハブ化」をしているのがモバイルデバイスのはず。
ネットの情報を操作するか、リアルのハードの操作が追加されるかの違いがそう見えるのではないでしょうか。
昔からモバイルは「ゲートウェイ」で語られていることも多く、そこにリアルが加わるとApplePayみたいなペイメントであったり、IoTであったり、O2Oだったり、というワードに変換されるのがこの示唆の趣旨でしょう。
スマニュー、AIの話でも分かるよう、裏はテクノロジの塊で構成されているサービス。smartモードの広告やヘッダー、フッターやグロナビを見事なまでに消し切っているロジックは賞賛するしかないですね(^^;
彼らはサービス設計ももちろんですが、この記事でも知見が語られているよう、裏のロジックで持っている技術はニュースキュレーションの中でも突出していると感じています。
私個人の嗜好としては複数ソースをサマリーしてくれているLINE NEWSの方が好きですが、ここは好みの世界ですね。
----------------------
【モバイル2020の連載を見終えた感想】
モバイル2020、自身の専門分野がモバイルということもあり、みなさまに長文で迷惑を掛けながらも自分なりに持っている知見でコメントを全記事にしてきました!(30日完走(^ ^))
そこで思ったことですが、まず「連載」とは何か?連載とは「続き物」として続けて掲載すること。 さて、今回のモバイル2020は「連載」だったのか、うーん(^^;
30日を完走した編集部にはお疲れ様でした!は正直な気持ちです。
課金ユーザとしてもう少し、個別の記事の掘り方や未来に向けた示唆、そして新たな知識に対する期待値は高かったです(ハードル高すぎ?)。
今後も課金ユーザーにとって月額課金したくなる!ような連載記事の質の向上を願い、連載コメントを締めたいと思います。
(追記)
柿原さん>
Googleのアナリストさんにそう言っていただいて非常に恐縮です。また、柿原さんのコメントは理論整然としていて、私より価値のあるコメントだと思っております。
柿原さんにお褒めいただいたのもモチベーションでコメントしておりました。
これからも、アナリストらしい深く、かつ整理されたコメントを期待しております。
コメントいただいたみなさま>
ありがとうございます!私が記事に勝手に肉付けしたり、方向を違う議論にしてしまったりと、ご迷惑に感じた方も多かったと思いますが(特にNP編集部のみなさま。。)、たまに賛同いただくコメント、本当にうれしかったです。
私も日本のモバイル業界が世界に負けないよう、コメントの内容に恥じないようモバイル業界の発展をがんばってまいります。スマートニュースほとんど関係なく、あれこれのインタビューという感じでしたが、非常に面白かった。シンギュラリティは漠然としか知らなかったので理解できて良かったです。
触覚研究者としては、最後の方のマルチモーダルの辺りの深掘りした話を聞いてみたかったです。現状は視聴覚、特に視覚に頼りすぎているので、もう少し別のモダリティを活用できても良いですよね。点字を読める視覚障害の方がスピーチをすると、原稿に目を落とさないで常に前を向いているので、とても堂々と見える、という話を聞いたことがあります。他のモダリティの活用から、マルチモーダルとしての進展あたり、今後の流れになると面白いです。