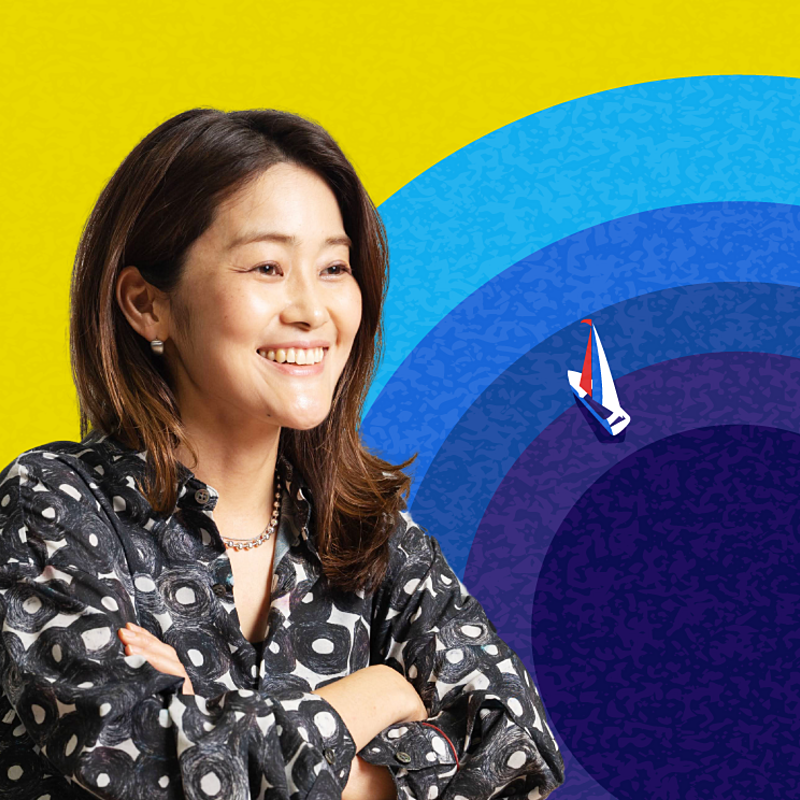
2024/6/28
【へラルボニーCOO】越境で実現する「やりたい」を諦めない思考法
ある企業が、世界のファッション業界に新たな旋風を巻き起こしている。
岩手県盛岡市から、障害を持つアーティストの作品を「異彩」として世に放つ事業を展開する「 ヘラルボニー」だ。
2024年5月23日、フランス・パリで行われた「LVMH Innovation Award 2024」では、日本企業として初めて「Employee Experience, Diversity & Inclusion」カテゴリ賞を受賞した。

© Claire Jaillard(へラルボニー公式HPより引用、左から2番目が株式会社ヘラルボニー 海外事業責任者 小林恵さん)
今秋には初の海外拠点をパリにオープンするなど、今日本で勢いのあるスタートアップの一社として注目されている。
昨秋、新たにそのメンバーの一員となった執行役員COO・忍岡真理恵さんは、数々の「越境キャリア」を経験してきたオールラウンダーである。

司法試験合格、経済産業省の官僚、MBA留学、民間企業への転職、そしてスタートアップへ──。
「『こうあるべき』という固定観念と、思えばずっと戦い続けてきました」と語る彼女は、どのようにしてヘラルボニーという居場所にたどり着いたのだろうか。
彼女の人生をひもときながら、キャリアやライフの岐路に立った時の思考法を伺う。
合格切符を捨てたら、死にきれない
── さまざまな「越境キャリア」を経験してきた忍岡さんですが、その始まりは学生時代だったそうですね。
学生時代は弁護士を目指してロースクールに通っていました。弁護士になれるまであと一歩というところで、法曹ではなく官僚の道に進もうと決めたのが、いわゆる私の「越境キャリア」の始まりです。
大学時代に弁護士を目指すと決めたのも、他でもない自分でした。幼少期から「国のためになる仕事をしたい」「女性として資格を持っていた方が良さそう」と考えていたからです。
ただ、ロースクールのクラスメイトだった現職の経済産業省の官僚との出会いがきっかけで、「国の仕組みを変える」仕事に興味を持ち始めたんです。

その方の日本を変えたいと強く思っている姿に感銘を受け、胸が高鳴りました。
自分のやりたかった仕事にやっと出会えたかもしれない。そんな感覚でした。
── ロースクールといえば、法曹になる人がほとんどですよね。
まさに「名門と言われる弁護士事務所に入れない人は落ちこぼれ」という世界です。
司法の道ではなく国家公務員になることを決めた時点で、周りからは「あの人は負けを認めたのね」と思われてしまう。
私自身も、それまで学費などを全面的にサポートしてくれていた両親の顔を思い浮かべて、葛藤し続けました。
── それでも、最後には決断した。
司法試験のために積み重ねてきた自分の努力を、家族のサポートを、一度全部捨てることになるので、本当に迷いました。
それでも、目の前にある「やりたい仕事」を諦める理由にはならなかった。
主流を外れることで、最初は周りの目も気になります。でも、どうせ半年くらいたてばみんな忘れちゃうんですよね。
── 意思が強いですね。
いえ。実は、国家公務員になることを決断してからも、みんなが名門事務所に内定している姿を見るたびに、「これで良かったのか」と自分に問いかけて葛藤していたほどです。
今振り返ってみれば、留学や離婚、転職など、人生は葛藤の連続です。最後は自分で「えいっ」と決めて、それを正解にしていくしかありません。
── 他にも、これほどまでに葛藤された経験が?
もっと悩んだのは、官僚時代にMBA留学に行くことをを決めた時です。大学院に合格してから、息子を授かったことが分かったんです。
渡米した時、息子はまだ、生まれてたったの「10カ月」でした。
生後間もない子供を異国の保育園に預けて、日中は学校に通う。母が専業主婦だったこともあり、自分の母のような母でいられない罪悪感がありました。
実際に「もういいや。合格切符は諦めよう」と思っていた時期もあります。
── そんな葛藤を乗り越えて、渡米を決断できたのはなぜだったのでしょうか?
いつか死ぬ時の自分を思い浮かべて「今諦めたら絶対に後悔する」と思ったからです。

MBA留学に行かない決断をしたせいで「あの時チャレンジしておけば良かった……」と後悔するおばあちゃん姿の自分を想像し、いてもたってもいられなくなりました。
少なからず「もったいないからやってみたら」と声をかけてくれた人が周りにいたのも、大きな後押しになりました。
アメリカで剥がれた、価値観のよろい
── 忍岡さんのように「迷ったらやる方を選ぶ」のは、簡単なようで難しいと思います。
私も最初から大胆な決断をできる人間だったわけではありません。
今思えば小さな話ですが、大学時代に所属していた法律系のサークルで、部長のようなポジションを先輩から打診されたことがありました。
学部やサークルも男女比率が7:3くらいでしたし、何かの「長」は男性が務めるのが暗黙の了解という雰囲気だったため、深く考えずに「私なんて……」と断ってしまったんですね。
当時は、女性だから一歩引いたという感覚はなく「大変そうだから」とか、安易な気持ちで断ってしまった。
でも、いざ他の人がそのポジションについているのを見た時に「本来ならあそこに自分がいたのに、自分で手放してしまったんだ」と猛烈に後悔しました。
その悔しい気持ちが忘れられず、それからは、もらったチャンスは必ず使うスタンスを貫いています。
── 「トップは男性であるべき」という思い込みは、女性の中にも根強く残っていますよね。
「こうあるべき」という固定観念と、思えばずっと戦い続けてきました。
MBA留学に行く時も、行ってからも、転職する時も。大学時代の情けない自分に対する反省を、忘れたことはありません。
特にMBA時代は、周りにいる日本人のママ友が、いわゆる「駐在妻」の専業主婦だったこともあり、自分の中にも少なからずある理想の妻/母親像とのギャップに悩むこともありました。

子供を預けて自分の「やりたい」を追求しようとしている自分は、このままでいいのか。
働くお母さんに育てられた人を見つけると、つい「寂しくなかった?」「どう感じていましたか?」と聞いてしまうぐらい不安でした。
── そんなつらい時期が……。どのようにして乗り越えたのでしょうか?
ある日突然気にならなくなったのではなく、かなり時間をかけて価値観が剥がれていった感覚です。
あとは、日本以外の国から、私と同じく母親でありながら留学してきている人たちとの交流も、変化のきっかけになりました。
世界各国から留学で来たお母さんたちと関わっていると、「それでいいの!?」と思う子育ての形を毎日のように目にします。
── 例えばどんな子育ての形が?
旦那さんが専業主夫だというキルギス人女性や、旦那さんと息子を地元に残してきた中国人女性、シングルマザーのアメリカ人女性など、私が出会っただけでも、多種多様な事情を抱えているお母さんが多くいました。
離乳食作りひとつをとっても、日本人は「こう作らねばならぬ」と細かな手順で自分の首を絞めてしまいがちです。
でも、アメリカの公園を見渡せば、元気にアボカドをボリボリ食べている小さい子がいる。
理想とのギャップに幾度となく落ち込みながらも、そんな世界のお母さんたちに勇気づけられながら、徐々に自分に自信を持てるようになりました。

息子にプレゼンして、選択を正解に
── 2年間のMBA留学で、日本で凝り固まった価値観を剥がすことができたという忍岡さん。今考える理想の母親像はあるのでしょうか?
息子のハッピー度合いが、母親としての私の成績表だと思っています。
MBA留学に行ったり、海外出張に行ったり、自分の母みたいないつも一緒にいてくれるお母さんにはなれなかったけれど、彼は彼なりに、私のことを誇りに思ってくれているのを感じます。
「出張で1週間会えなくて寂しいね」と言うと「いつものことだし、行ってきなよ」と送り出してくれたり、帰ると「お土産は?」と当たり前のように私を迎えてくれたり。
時には「ママって会社で偉いんでしょ」と働いている私を褒めてくれることもあります。
私もそんな彼の幸せそうな笑顔を見て、今のところ「母親としての成績は及第点かな」なんて思えています。
── すてきな関係ですね。そのような関係を築くためのコツがあれば、教えてください。
自分の幸せも、息子の幸せも、諦めないことです。
私が「迷ったらやる方を選んでしまう人間」であることは、息子がいても変えられない事実です。
とはいえ、さまざまな場面で葛藤してきたわけですが、今でこそ、子供のために自分の「やりたい」を殺すことはできないと割り切っています。
「自分はこういう人間です」と息子にプレゼンするつもりで、自分の選択を正解にしていくしかありません。

そういう意味では、帰国と同時にコンサルティングファームに転職したのも、そこを去る決断をしたのも、息子に胸を張れる母親であるか、自分に問いかけた結果でした。
── 状況によって、ありたい姿は変化するんですね。官僚を辞めてコンサルティングファームに転職したのはなぜだったのでしょうか?
これだけ聞くと、自信家に聞こえるかもしれませんが、日本にいた時には見えていなかった「自分の可能性」に気付けたからです。
日本で働いていた時は、MBA留学が終われば当たり前のように経産省に戻り、9時から17時まで定時で働くのだと思っていました。
ただ、アメリカで出会ったクラスメイトたちに、そんな「当たり前」などありません。
人身売買に巻き込まれたインドの女性を支援する事業や、途上国で生産したクッキーを高級スーパーで販売する事業など、自由にやりたいことや自身のミッションを追求する友人の姿に刺激を受けました。
そんな彼らのルーツをたどれば、元外交官だったり、証券会社出身だったり、鍛えられたビジネスマインドに裏打ちされていた。
私もずっと「国のためになる仕事がしたい」とがむしゃらに働いてきたけれど、それをビジネスとして、資本主義の中で勝てるレベルに育てることに、憧れを抱くようになりました。
この強い憧れが、ヘラルボニーとの出会いにつながっていたのだと思います。
つながる、社会の端っこにいた感覚
── ヘラルボニーと出会ったのは、いつ頃だったのでしょうか?
コンサルティングファームからマネーフォワードに移り、5年ほどたった頃です。
名刺入れを新調しようと検索していた時、デザインに一目ぼれしたのが最初の出会いです。調べていくうちに、ただかわいい名刺入れを売る会社ではなく、「異彩」を社会に送り届けるブランドだと知りました。

── 当時、マネーフォワードからの転職は考えていたのですか?
40歳という節目を迎える直前の時期だったこともあり、なんとなく「いつまでもこの居心地の良い場所にいていいんだっけ」と考え始めていました。
もちろん、会社での評価や役割、事業内容に満足していなかったわけではありません。
ただ、ロースクールを辞めた時のように「目の前にすてきな仕事があるけれど、一生これを仕事にしたいわけではない」とモヤモヤしていました。
自分の未来を想像すると、留学時代に間近で見ていた、自分がやりたい社会貢献を「ビジネス」として成長させていくクラスメイトの姿がよぎる。
想像を繰り返すうちに、どうしても、今の延長線上にその憧れを実現できる、ハッピーな未来があるとは思えませんでした。
── ということは、すぐにヘラルボニーへの転職を考え始めた?
実は、実際にヘラルボニーに履歴書を送ったのは、そこから1年ほど後のことです。
離婚してシングルマザーになっていたので、マネーフォワードの安定したSaaSビジネスから離れることにおびえていた部分もあります。
エージェントの方に、社会貢献を軸とした事業会社を探してもらい、自分の幸せと息子の幸せをどちらも諦めない道を模索しました。
── それでも、見つからなかった?
見つからなかったというより、1年ほどさまざまな会社を見たからこそ「ヘラルボニーの一員になりたい」という気持ちが強くなりました。
出会った時から、直感的に「この会社はとんでもないことになる」という予感はしていたものの、他の会社が取り組んでいる社会貢献も社会にとって確実に必要なものです。
強烈に引かれるヘラルボニーの魅力は、なかなか言語化できないままでした。
── それが、1年の転職活動を経て、言語化できたんですね。
はい。ヘラルボニーとは「負を正にするビジネス」ではなく「負を負と思わせないビジネス」だと確信しました。
世の中がみんな「かわいそうだな」「助けてあげなきゃ」と思うことを、「美しいでしょ?」「ほらきれいでしょ?」といたずらっ子のように言いながら、世に送り出す。
障害のある方だけでなく、「普通」になれなかったすべての人のストーリーを肯定する事業なんだと気付いたんです。
母として、妻として、一人の人間として、普通でない道を選んできた私も、肯定してもらったうちの一人でした。
「負けを認めたのね」
「お母さんが働いているのはわがままだ」
「子供がかわいそう」
そういう社会のネガティブな声を全部はねのけて、「俺たちはすごいんだぞ」と私の代わりにドヤ顔をしてくれているような、そんな企業なんです。
みんながそれぞれ普通を外れて「社会の端っこにいた感覚」と、松田兄弟のストーリーを重ねることで、将来世界を巻き込んだムーブメントを起こす姿がイメージできました。
「これこそが日本の企業なんだぞ」とアメリカに戻ってドヤ顔する自分も思い浮かんでしまい、すぐに応募しました。

── これから忍岡さんが実現したい未来を教えてください。
まずはヘラルボニーのCOOとして、資本主義に負けないビジネスの成長と、松田崇弥・文登兄弟の世界観を、どちらも実現するサポートをしていきたいと思っています。
資本主義のど真ん中を歩んできたキャリアですが、それと同時に社会の端っこにい続けた人生でもあったので、そのバランス感覚には自信があります(笑)。
なんといっても、これまでの葛藤や挫折という伏線が、ヘラルボニーに出会えたことで、すべて回収されていますので。
これからもピクニックを楽しむような気持ちで、母としても、忍岡真理恵としても、輝いている自分で人生を埋めていきたいです。
取材・文:井上茉優
取材・編集:川口あい
デザイン:田中貴美恵
撮影:曽川拓哉
取材・編集:川口あい
デザイン:田中貴美恵
撮影:曽川拓哉
