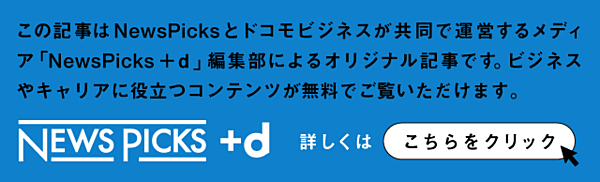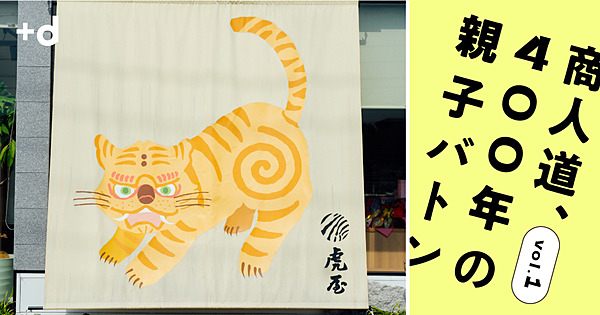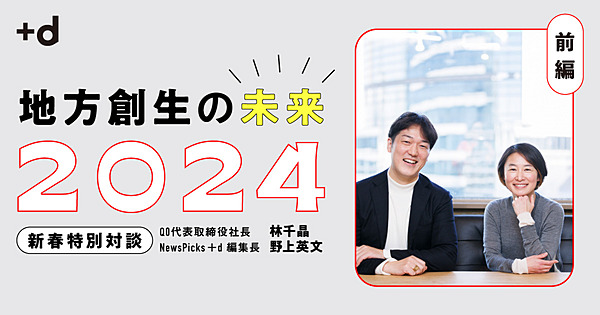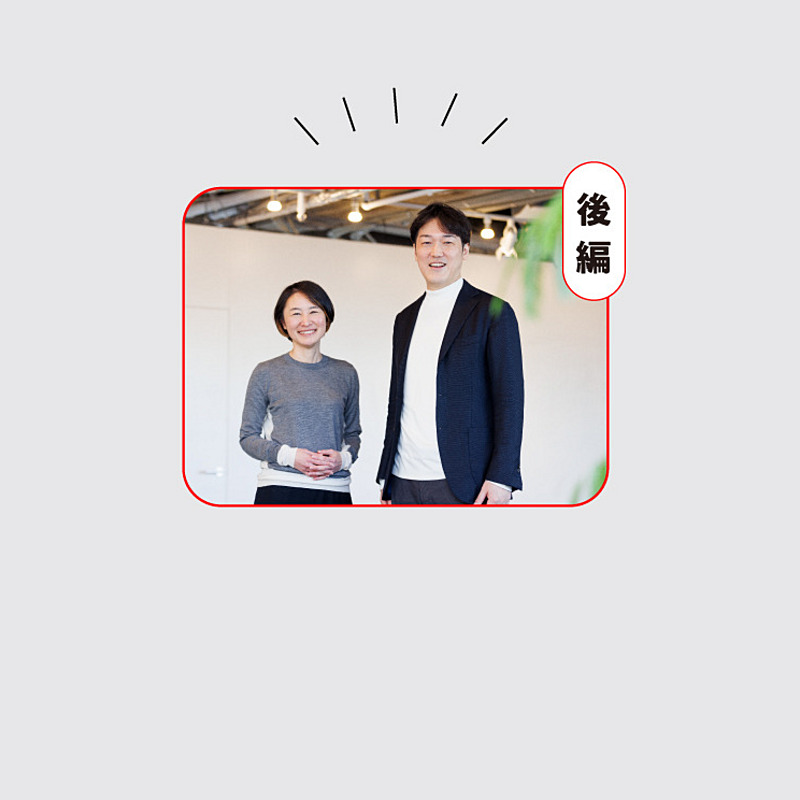
2024/1/13
地方の未来を左右するインバウンドのチャンスとリスク
秋田から価値転換による新しいビジネス創造に注力するQ0代表取締役社長・林千晶さん。地方創生に詳しい林さんとNewsPicks+d編集長の野上英文が、これからの地方ビジネスについて語り合う新春特別対談。後編では地方の課題について考えるとともに、2023年にNewsPicks+dで注目された記事から未来へのヒントを探ります。(第2回/全2回)
INDEX
- 「地方から起業を」というマインドの醸成
- 地域密着×最先端の優良企業・コープさっぽろ
- 世代ごとに変化を起こす事業承継を
- 地方から世界というポテンシャル
- 中を熟知した知見×外からの視点の両輪が必要
- 2024年、地方ビジネスの鍵となるインバウンド
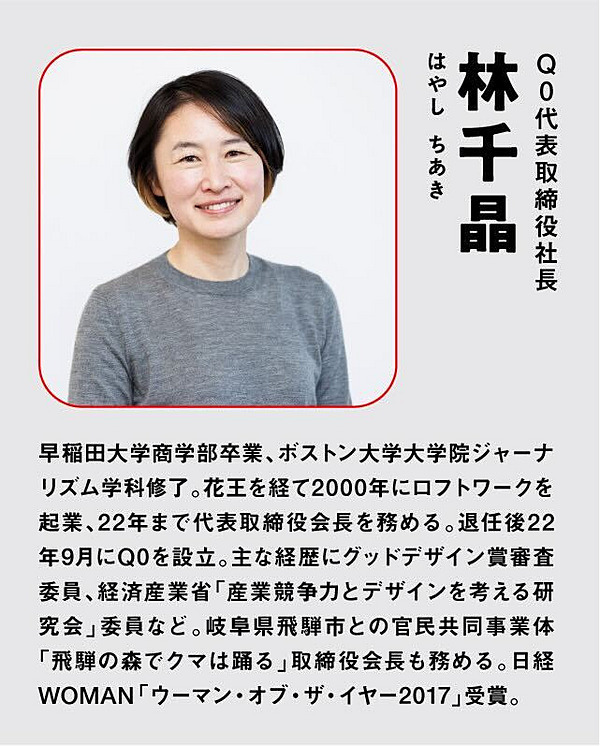
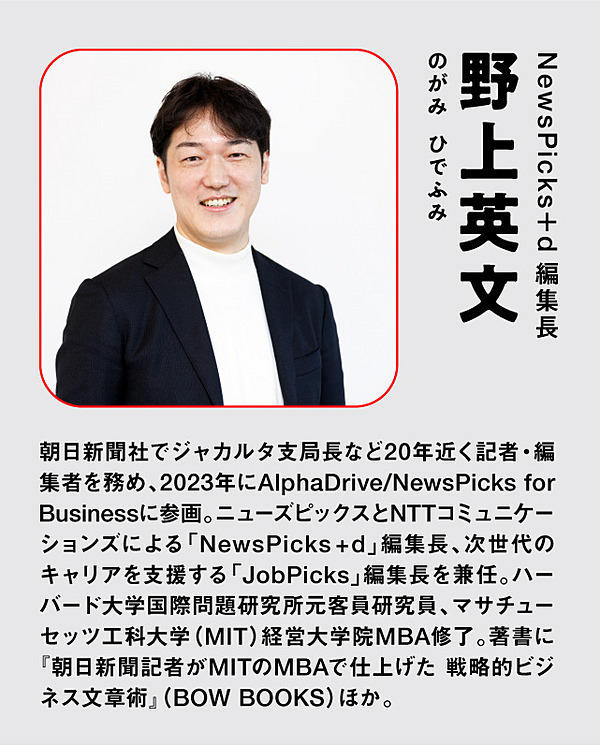
「地方から起業を」というマインドの醸成
野上 前編では、林さんが地方という静脈から新しい価値創造を仕掛けていくという思いを伺いました。林さんが今後増やしていきたいという地域に根ざした「地域起業家」ですが、どんな課題がありますか。
林 担い手はいても、「私にできるかな」という不安がネックだと感じています。
野上 その不安はどこからくるのでしょう。
林 秋田は開業率2〜3%で低迷するなど、起業家が少ない県なんです。だから、秋田なんかで起業なんてできるわけないという刷り込みがあると思うんですね。そういう意識が、起業をネガティブなものにしてしまっている。
確かに起業は東京だからできることも多くあります。地方で東京のような起業家をつくろうとしても、やっぱり東京にはかなわない。
野上 新しい地方の起業家のロールモデルが必要そうですね。
林 それが「地域起業家」です。地域起業家は地域じゃないとできないし、実際そうやって地域に根ざして起業する若手も出てきています。彼ら彼女らがこれからのロールモデルになってくれるはずです。

野上 前編で林さんが紹介してくれた「アート×マタギ」とか「日本酒×農業」みたいな、2軸を組み合わせた存在というのもユニークです。
林 なぜ2軸なのかというと、1軸で成立するほどマーケットが大きくないから。だったら、2つかけ合わせればいい、という発想です。
野上 もうひとつ、事業をスケールさせてこそ、という起業の発想を転換していくというのもありそうだなと感じます。
これは東京の企業ですが、障がい者向けの服をつくるSOLITは、日本ではスケールだけで判断すると、スケールアップだけを重視する投資家とソリが合わなかったそうです。しかし、その後、その企業は日本を飛び越えて、世界で評価される企業へと成長しています。
東京を中心とする起業家モデルは、いかにスケールしてJカーブを描くかという話になりますが、もっと地に足をつけた新しい起業モデルが出てきてもいいと思います。
林 それが事業をサステナブルなものにしてくれます。そういう意味でも、地域起業家の定義ももっとしっかりさせる必要があります。東京の起業家がKPIの成長を目指すのとは違って、地域起業家の目標はスケールにはありません。
じゃあ、何が目標なのかというと、SDGsや環境との連動です。もう少ししたら、今のようなスケール前提のKPIは古い価値観になっていくんじゃないでしょうか。
地域密着×最先端の優良企業・コープさっぽろ
野上 なるほど。必ずしもスケールが目的ではない事業が、地方からどんどん生まれてくるんですね。
林 私は、2024年は生活協同組合コープさっぽろと連携して、北海道でもどんどん活動していくつもりです。北海道といっても、札幌だけではなく全域。道東のような北海道の地方でチャレンジしていきます。
野上 コープさっぽろは生協ですから、株主ではなく組合員に還元するビジネスモデルです。まさに地域に根ざしている。
林 コープさっぽろは超優良組織で、売り上げにあたる事業高は3140億円(2022年度)。組合員数は北海道の総世帯の約8割をカバーしていて、2025年度には9割を超えるといわれているほどです。
野上 トラックが地方に出かけてそこで購入する、というようなモデルですか。
林 事業の柱は3つあって、ひとつは店舗。ライバルはイオン北海道です。2つめが宅配のeコマースで、こちらのライバルがAmazon。3つ目は移動型店舗で、北海道全域で100台くらいのトラックが買い物が困難な地域に生活必需品を届けています。「共助の最先端」というだけでなく、ビジネスモデルとしてもイオンやAmazonといった超大手と競合する先進的な組織です。

コープさっぽろの移動販売「おまかせ便カケル」
林 最先端の取り組みをして利益は組合員に還元する。その一連の流れがすごく新しいなと感じています。
野上 地域と共にあるという感じがすごくしますね。
林 強さの秘密は、株主ではなく、自分たち「コモンズのためにある」というビジネスモデルだと思っています。例えばスクールランチ事業というのがあるのですが、これは少子化で給食事業が維持できなくなった地域に、「スクールランチ」という形で給食を提供するというもの。
給食事業は法律で事業を提供する条件が厳格に決まっているので、それを避けて「スクールランチ」という形で届けているんです。

コープさっぽろが2021年からスタートした、学校へ温かい昼食を届ける事業「スクールランチ」
野上 確かに子どもが少ないと採算が取れないから給食事業が成立しません。給食がないとお弁当になって家庭の負担も増えてしまう。
林 さらに問題なのが、お弁当ではどうしても格差も生じてしまうんです。同じ釜の飯を食べることは人と人をつなぐと思うんですが、お弁当ではその役割は果たせません。
これこそ、これからの少子化・高齢化・人口減少という新しい社会課題に最先端で取り組んでいる事例といえます。そこがすごく面白いし、これからもっと重要になってくるはずです。
野上 林さんがコミットしている秋田や北海道では、この先、日本全国が直面する課題にすでにがっつり向き合っているということですね。
林 「少子化」というとネガティブなイメージがありますよね。でも、北欧なんかは日本と比べて人口も少ないし、1人あたりの面積も広いんです。そう考えたら、まだまだ日本にも明るい未来があるはずです。
人口がもう増えることはない、減っていくというのは事実です。でもそれを「少子化」とは違う言葉で、もっとポジティブに捉えて未来を語れたら、人々はより豊かな暮らしを手に入れられるんじゃないでしょうか。
野上 旧来型の価値観では、人口が増えることこそが経済の原動力で、それを前提にビジネスや地域のあり方、働き方が成立していました。でも、その前提がガラリと変わるのだから、それに合わせた新しい働き方、生き方をデザインしていくべきだということですね。
世代ごとに変化を起こす事業承継を
野上 地域での刺激的な新しい動きをいろいろ教えていただきましたが、NewsPicks+dでも、独自性や意欲にあふれた地方企業を数多く取材しています。今回は2023年に多くの読者から共感を得た記事を3本セレクトして、林さんにご意見を伺っていきたいと思います。
まず最初が、広島で何百年も続いている老舗和菓子屋・虎屋の事業承継に伴う業態転換の記事です。息子の代になって、和菓子屋というより地域マルシェのような店に業態転換したという内容です。
事業承継は地方にとって大きなテーマですが、その課題感をどのようにご覧になっていますか。
林 私は事業承継というのは、同じことをそのまま継続するのではなく、時代に合わせて自分の代で少なくとも1回は大きな変化を起こすことだと思っています。産業や領域によって、その変革が10年なのか、50年なのかという期間は違ってくるでしょうが。
この記事では、先代のお父さんも自分の代で変化させてきたし、息子さんも事業をガラリと変えていますよね。そうじゃないと時代についていけないというのが、お二人ともわかっている。
野上 自分の代でしっかり変化を起こせないと、次にバトンを渡すことも難しい?
林 そう思います。時代は常に変化しているから、その時間の流れについていくための変化は絶対必要。特にこれからはルールが大きく変わるので、その中で何が求められているかをキャッチし、変わっていかないといけません。これから事業を承継する人は、これまでの定説に縛られず、どんどんチャレンジしていったほうがいいですね。
野上 この記事で紹介している虎屋は、重厚長大な老舗から和菓子っぽさを一切なくした店に変えて、地域の人たちに和菓子づくりを担ってもらっている。そんな点もユニークです。
林 この息子さんは、地域でつくったものを集めることで、地域のハブとなることを目指していますよね。そうやって人を集めて、地域を牽引しています。そういう記事の内容を拝見して、やはり力のある企業が地域を引っ張る役割を担うんだなというのは、改めて感じました。
地方から世界というポテンシャル
野上 2つ目の記事は和歌山の島精機製作所です。この会社のように地域から一気に世界に飛び出すポテンシャルについては、どう思いますか。
林 島精機製作所は私が代表を務めていたロフトワークのクライアントで、私も2017年くらいに伺っています。ユニクロとパートナーシップを組んだのもちょうどその頃です。
お父さんの代のときに、機械で洋服をつくるために半導体までつくっていた。だからあのホールガーメント機ができて、3Dニットが生まれたんです。
野上 そこから一気に世界へ打って出ているわけですが。
林 東京の会社は成功したら次はグローバルとなりますが、地方は東京を目指して、国内で終わっちゃうパターンが多いですよね。
私は岐阜県飛騨市で「飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)」という会社もやっているんですが、バイリンガルでウェブサイトをつくったら……。
野上 海外から注文が?
林 来るんですよ。それを狙っていたわけではないのですが、国産材を英語で情報発信する会社はほかになかったんです。そうしたら海外から問い合わせが舞い込むようになって、有名ホテルのすしカウンター用に何百万円もする木材が売れたりもしました。
だから、地方でも、事業としてグローバルへのポテンシャルはちゃんとあるんです。特に世代交代、事業承継のときには、今までと違うことがビジネスになる可能性にどんどん取り組んで、グローバルも視野に入れていけばいいと思います。
中を熟知した知見×外からの視点の両輪が必要
野上 3つ目が京都の伝統産業・扇子を扱う企業がルームフレグランスや町家のレンタルスペースを手がけて、業績をV字回復させたという記事です。
林 この新規事業をしかけた4代目の娘さんは、全然違う企業を経験してから家業に入っていますよね。その経験があったから、ニーズを見抜くことができたんだと思います。イノベーションを起こすときは、その事業の中身やオペレーションを熟知していることが半分、残り半分は外の目線で見ることが必要です。
野上 その半々というのは、人的資本の観点から考えて、経営者と社員をどう組み合わせていけばいいんでしょうか。
林 経営者が地域で動くなら、右腕は外から呼んだほうがいいし、逆に経営者がどんどん外に出ていくなら、中を担うのは社内で下から上がってきた人がいいですよね。
野上 その両輪で回していくということ?
林 両輪じゃないと、イノベーションは起こせないと思います。
2024年、地方ビジネスの鍵となるインバウンド
野上 非常に興味深いお話をいろいろ伺えましたが、最後に2024年に向けて、地方創生はどうなっていくのか。地方経済の担い手のみなさんにぜひアドバイスをお願いいたします。
林 ひとつはインバウンドへの対応です。前編で秋田の寒天の食文化の話もしましたが、そうやって100年単位で培ってきた文化は、インバウンドにすごく力を発揮します。
野上 確かに、みんな知らないだけですからね。そんな寒天の総菜を見たら、食べてみたくなります。ニューヨーク・タイムズの「2023年に行くべき52ヶ所」のリストで、盛岡市がロンドンに次ぐ2番目に選ばれたのも、そういう文化への魅力を感じているからだと思います。
林 その一方で、インバウンドに流されないことも、同じくらい大事になってきます。インバウンドに流されてしまったら終わってしまう。
野上 その心は?
林 人口が増えている時代に、都市型のチェーン店が地方にどんどんできた現象と同じになるからです。人が増える前提で均質化して、それが今、どんどん潰れています。地方の旅館もそういう形で事業拡張したところは借金を抱えて出口がなくなり、倒産するしかない状態も増えていると思います。
野上 何百年もかけてつくってきた文化でインバウンドは取り込むけれど、それに流されずに地に足をつけて、サステナブルであり続けるということですね。
確かに、インバウンドの流れはますます強くなりそうですから、それとどう付き合っていくかは大きなポイントとなります。

林 インバウンドに合わせて単純に人も増やそう、施設も拡充しようというのは違いますよね。もちろん、5年、10年単位で拡充するのはありでしょうが、目先のインバウンド需要目当てで1年単位で売り上げを増やそうとするのは、結局、自分の首をしめることになる。
大事なのは、上限がどこにあるか、何がキーファクターか考えることです。長年続いているもの、例えば食品などは、売り上げにもちゃんと上限を設けています。この味や品質を維持するには、この量が適切というのがきちんとある。
本質的な価値をどう提供するか。そこをしっかり考えていくことが必要でしょうね。
野上 本当にそうですね。林さんとお話ししていて、2024年は、地方から新しいビジネスの機運がどんどん生まれてきそうだなと感じました。これからどんな挑戦が始まるのか、今から楽しみです。
文・編集:久遠秋生
撮影:大畑陽子
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
撮影:大畑陽子
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)