
2023/5/21
【週末に読む】「目的なしに誰かと過ごす」スキルの大切さ
米ニューヨーク・タイムズの名物ポッドキャスト「エズラ・クライン・ショー」。ホストのエズラ・クライン記者が、各界の第一人者とビッグイシューについてじっくり語り合う。
今回のゲストは、バーモント州のシャンプレーン・カレッジで、コミュニケーション論とクリエイティブ・メディア論の教鞭をとるシーラ・リミング准教授だ。
新刊『Hanging Out: The Radical Power of Killing Time』の中で、彼女は現代社会に広がる「孤立」の問題を「静かな破局」と呼んで警鐘を鳴らしている。
リミング准教授が最も問題視するのは、人々にとって「パートナーや家族、職場の人間以外の人々と一緒に過ごす時間」が激減しているという、深刻な事実だ。
あらゆる人々が社会的なつながりを容易に持てるよう、私たちの社会を再構築することは可能なのだろうか? 「孤立」の背景をひもといていこう。

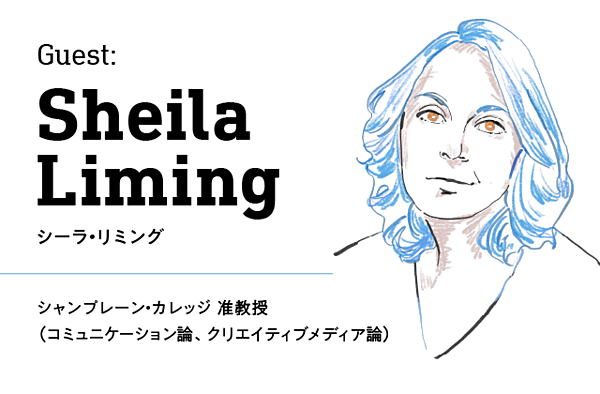
INDEX
- ①「孤立」する人が増え続ける理由
- ②自ら「孤立」を選ぶ人々
- ③「高学歴な人」ほど孤立する
- ④「家族」を再定義する
- ⑤「共同生活」が根づかない理由
①「孤立」する人が増え続ける理由
エズラ・クライン さっそくですが、リミングさんは著書の中でこう書かれていますね。
「現代社会が『孤立』をもたらしているのは、もはや周知の事実です。しかも、状況は改善するどころか、悪化の一途をたどっているようです」
なぜそう思われるのでしょうか?
シーラ・リミング 孤立の増加には、さまざまな要因があると思います。
ひとつは「時間」の減少です。より正確には、自由に使える時間、つまり決められたスケジュールや目標がなく、ただ誰かとぶらぶら過ごしたり、交流したり、会話を交わしたり、気ままに使える時間が減っていることです。
もうひとつは、「(人と交流するための)空間」の減少です。まず、パブリックスペースの減少。それから、私たちの生活空間が広範なエリアにどんどん拡散していることも挙げられます。いわゆるスプロール現象ですね。
このように、人と人の間に空間が広がることで、お互いの距離を縮めることが難しくなり、ますます分断が生まれていくのです。

(Yuichiro Chino/Getty Images)
クライン ご本では、「孤立・孤独・分断」の末に、私たちは「ただ誰かと一緒にいる」というスキルを失ってしまうと指摘されていますね。これは、これまであまり論じられてこなかった点ではないかと思います。
本のタイトルでもある、「ぶらぶら過ごす(hang out)」とはどういうことなのか、また、それができなくなると何が起きるのか、聞かせてください。
