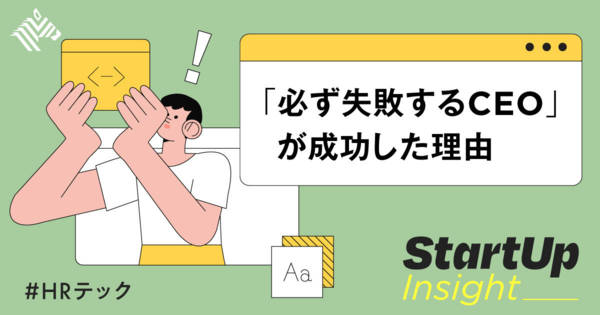任せたら大当たりした「エンジニア偏差値」
コメント
注目のコメント
Findy代表の山田です。
「必ず失敗するCEO」という刺激的なタイトルで紹介いただきました。笑
新規事業については前職含めて自身が企画から立ち上げを主導したものは6戦全敗で、1勝9敗にはほど遠い状況です。
新規事業は何度も挑戦していますが、本当に難易度が高く努力だけで立ち上がるものではありません。マーケットの状況やデリバリーのセンス、運も味方にできるかなどなど、実行力+アルファが必要だと思っています。
そんな中で、Findyの新規事業の肝になったエンジニアのスキル偏差値についても記事内で言及頂いています。
この機能は、もともと課題であったエンジニアとテック企業の壁、例えば技術力に対する理解が双方で進まない等をなんとかして解決できないかという視点から始まりました。
そこで、エンジニアが普段から利用しているGitHubのオープンソース活動を解析した上で、スキルを可視化し、転職活動で活用いただけないかという思いで開発しています。もちろん、これまでも職歴や学歴、経験したプロジェクトの履歴なども有効な手段ではありましたが、技術力そのものを直接的にアピールできる何かができないかという着想です。
また、こうした可視化が、技術力の理解で苦戦しているテック企業の人事にとっても有益になるのではと同時に考えていました。
もちろん、このスキル偏差値が技術力を測る全てではなく、オープンソースの活動をしていない人もいれば、マネジメントに長けている人もいます。最近ではそうした経験の要素を加味した年収予測のアルゴリズムなども提供しています。
同時に、入社したエンジニアが活躍できているかを含めてエンジニア組織の生産性を見える化できるFindy Team+も始めました。
こうしたプロダクトを通して、Findyとしては日本初のテックイノベーションを最大化するべく「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる」というビジョンに向けて全力で進んでいきたいと思っています。
優秀なソフトウェアエンジニアが本当にたくさんいる日本。そんな彼らとテック企業が適切に結びつけば、もっともっと面白い革新的なプロダクトが生まれる国になると思っています!実はエンジニアに限らない本質的なアプローチ。
鍵は評価軸だろう。
今回はエンジニアを対象としているが、それを例えば営業担当者とか、新規事業企画者とか、他の業務にも適用しうる。
その際、評価軸も当然変わってくる。
重要なのは、個人の能力と組織の備えるべき能力の両方を共通で評価できる軸であること、客観的且つ収集用意な情報から評価しうる軸であること、だろう。
それを満たした評価軸を設定し、実際に登録者を募り、データを集める中で精度を高める、、、確かに参入障壁は高い。
但し、新規事業含めて事業ポートフォリオ転換を進める企業が多い昨今、「今の組織に必要な能力と、今いる人材が持つ能力にはどこにどんなギャップがあるのか?」「そのギャップ充足には、どんな人材をどれだけ採用・育成する必要があるのか?」を論理的に導出し、採用までケアするビジネスの需要は高いだろう。
偏差値のように単なる高低だけでなく、能力のように高低とは異なる違いに基づいて評価できると、それぞれの人が居るべき理由がより明確に共有されるため、組織の多様性もより担保しやすくなるだろう。取材では経営者の話を聞く機会が多々あるのですが、皆さん本当に個性豊かです。
数字で事業を語りつくすかた、絵が浮かぶほど鮮明にビジョンを語る方、果てしなく思想が深い方、とんでもなく頭の回転が速い方…
ファインディの山田代表との取材ですが、事業を語る上で、これほど人の名前がポンポン出てくる経営者も珍しいなと思いました。
初めて買ってくれたお客さん、助けれくれた人、社内の頼れるメンバーたち。人を大事にするからこそ、大事にされ、社内にも「任せられる」凄腕メンバーが集まる山田代表の求心力はファインディの強みのひとつだと感じました。