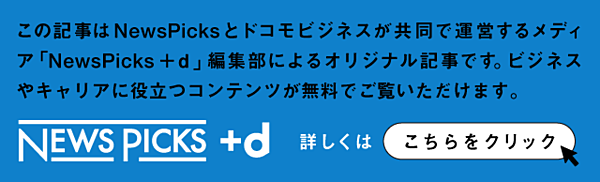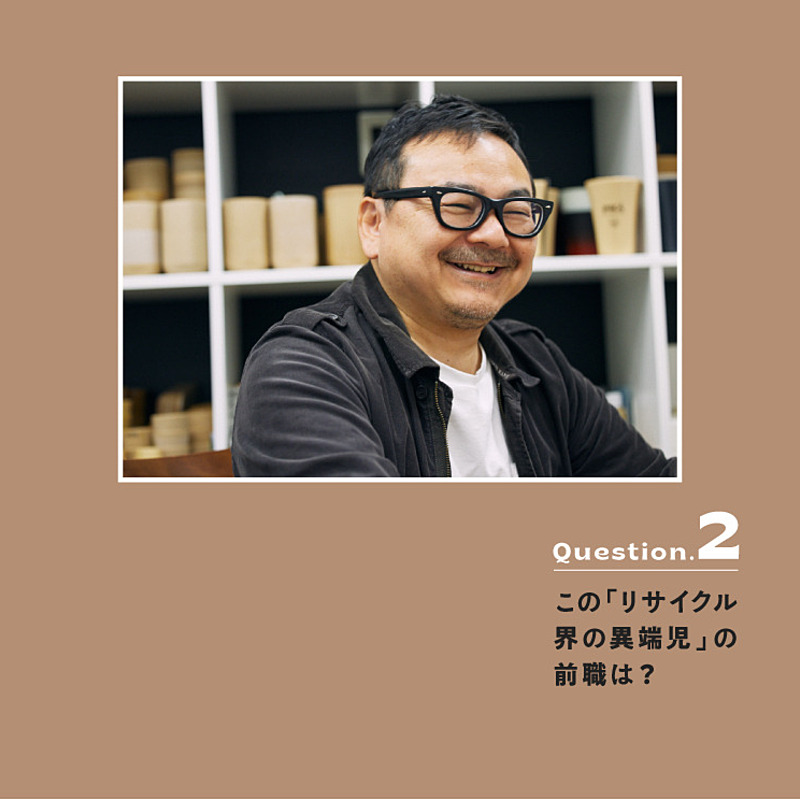
2022/8/26
【外務省→起業】「自腹でも」なんとかしたかった夢の新素材作り
紙とポリ乳酸(トウモロコシやサトウキビ搾汁のデンプンを発酵して得られる乳酸を主成分とする素材)を使用した、植物由来成分99%以上の新素材「PAPLUS®(パプラス)」。その誕生物語の第2回です。
外務省時代に途上国で目に焼き付いたプラスチックゴミ問題と、それに対する日本の国際的な意識の低さを「なんとかしたい」と考えていた深澤さん。紙のリサイクルに携わったことをきっかけに、プラスチックの代替素材の開発に乗り出しますが、問題は山積みでした。
外務省時代に途上国で目に焼き付いたプラスチックゴミ問題と、それに対する日本の国際的な意識の低さを「なんとかしたい」と考えていた深澤さん。紙のリサイクルに携わったことをきっかけに、プラスチックの代替素材の開発に乗り出しますが、問題は山積みでした。
INDEX
- プラスチックと紙の課題は山積み
- ものづくり名人との出会い
- “均一でない”ことが魅力に
- 夢とロマンなら語れる

深澤幸一郎(ふかさわ・こういちろう)/大学卒業後、外務省に入省。本省、在イギリス日本国大使館、在ガーナ日本国大使館等に勤務。在職中、途上国勤務で内戦や誘拐事件における邦人保護を経験するとともに、ゴミ廃棄問題に関心を持つ。2002年退職後、日本企業の海外向けPRマーケティング会社を設立。2015年環境配慮型素材ベンチャー、カミーノ設立。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。ケンブリッジ大学修士。趣味は英語落語。
プラスチックと紙の課題は山積み

捨てられる紙を使って、プラスチックの代替素材を作る――。
紙のリサイクルから出発した会社「カミーノ」の新しいチャレンジが始まったわけですが、それは同時に、プラスチックという素材のすごさを思い知ることでもありました。
「これほど脱プラが叫ばれている中でも、植物由来の樹脂製品が世の中になかなか普及していかないのは、価格も割高なうえ、作るのが難しいからです。
素材を溶かして、型に流し入れて、固めて、型から外す。これが、射出成形という樹脂を使った製品の作られ方の基本です。一般的な石油由来のプラスチックは、溶かすと水のようにサラサラになるから、一瞬で型に流し入れられるし、すぐに固まって、型からポコっときれいに外せる。機械で大量生産できるから、価格も安くなる。
一方、植物由来の樹脂は、植物成分の割合が多くなるほど、溶かした時に水飴のようにドロドロになるんです。型にもなかなか流れていかない。流れても固まらない。固まったら型から離れない。いちいち面倒くさいわけです。こんなんじゃ大量生産できないよ、というのが、これまでプラスチックで物を作ってきた皆さんの認識だったわけです」

「紙」のもつ特性も、難題でした。
「強度がないんです。水にも弱いし。だから紙で作れるものは、どうしても強度を要求されない製品に限られてしまう。
そこで、どうしたら強度を増すことができるのか、いろいろと考えました。重ねるとか、固めるとか。石油由来のプラスチックを混ぜればいいんでしょうけれど、そうすると僕のやりたかったことと違ってくるの。他にないかと調べていくうち、植物からできているプラスチックみたいなものがあるらしい、ということがわかりました。なかでも、トウモロコシやサトウキビのでんぷんから作られている『ポリ乳酸』っていうものがあって、それは大量に生産できて、普及はしてないながらもメーカーもあるようだと。
だとしたら、紙とこの『ポリ乳酸』を混ぜ合わせることができたら、ほぼ石油成分を使わないプラスチックみたいなものができるんじゃないか…と、素人ながらに考えたんです。
それを周囲に話したところ、みんな『???』って(笑)」
つれない反応にもめげず、歩みを進めたのは、「ポケットマネーを出してでもやりたいと思うほど興味がわいてきた」から。でも素人の深澤さんには、バイオプラスチックの専門家が必要でした。そんな人を探し始めたとき、運命的な出会いが訪れます。
ものづくり名人との出会い
「石油由来のプラスチック問題解決のために、コツコツと十数年にわたり研究を続けている人物が福島にいるということを知りました。小松道夫さんという、バイオプラスチックの第一人者で、海外ではすごく評価されて、300件近い特許を取っているようなすごい研究者…なのですが、プラスチック問題に対してのんびり構えていた日本では当時、植物由来のプラスチックはあまり注目されていなかった。
日本では、『800度以上で焼却できる焼却炉があり、有毒ガスも出ないので、プラスチックは燃やしてしまえばいい』というスタンスでした。でも、欧米ではそのような焼却炉はなく、そもそも『プラスチック=悪』という単純化された構造が根付いているから、『燃やせばいい』では済まないわけです。
たまたま共通の友人がいたこともあり、小松さんとなんとかつながることができて、一緒にやりましょうと意気投合して開発が始まったのが、2017年のことでした」
“均一でない”ことが魅力に

「これが試験用に作った最初のPAPLUS®です」と深澤さんが見せてくれたのは、15センチ角ほどの板状のもの。茶色の中に、マーブル状の模様があります。
「これは、ガスの跡なんです。先ほど、石油由来のプラスチックはサラサラで扱いやすく、植物由来の樹脂は水飴状で扱いにくいと言いましたが、小松さんは、長年の研究によって、ドロドロの樹脂に窒素などのガスを入れたりすることで、成形しやすくする技術を発明していたんです。だからこのマーブル模様は、ガスがシューッと流れた跡。ガスの流れ方までは調整できませんから、同じ模様は二度と現れません。
均一なものを大量生産することを求められるプラスチックの世界では、『同じものがない』というのは大問題です。でも、ものづくりや、アートに関心のある人たちにとっては、『面白いね』となる。それぞれ表情が違うことで、手づくり感とか、温かみを感じさせることにつながります。石油の大量使用を減らそうという世の中の流れとも親和性があると思いました」
本来ならば混ざり合わない成分を混ざるようにしたり、製品を取り出しやすい金型を作ったり。植物由来の樹脂がもつ課題をひとつひとつクリアして、「植物由来成分99%以上」という世界最高水準の数字を実現。PAPLUS®は、2018年10月に、ドイツで開催されたプラスチックの世界3大見本市のひとつでお披露目となりました。翌2019年には、初めての製品を、イギリスのオーガニックコスメブランド『ニールズヤード レメディーズ』のノベルティとして発表。
「作ったのはタンブラーだったのですが、本当は、まだ完成には至ってない状態でした。私たちとしてはもう少し精度を上げていきたいところだったんですが、先方から、『完璧になるまで世に出さない慎重さは、日本の悪いところ。そんなことをやっているうちに、ほかの会社からいろいろ新しいものが出てきてしまう。まずは、こういう素材が世の中にあるんだ、と知らしめて、実際に使ってもらうことが大切だ』と言われました」
夢とロマンなら語れる

面白いのは、深澤さんが完全な文系人間だということ。
「化学とか正直苦手です。でもロマンは語れる。『こんなことができたらいいなあ』と、とんでもない夢を見て、馬鹿にされるタイプです(笑)」
逆に言えば、だからこそ「できるはずのない植物由来の樹脂製品」が実現したともいえます。
「けれど、プラスチックそのものが全部ダメ、ということではないと思うんです。やっぱり植物由来のものを作るのは想定していた以上に大変で、そのことが身にしみているうちの社員や関係者は、みんな、プラスチックの大ファンですから(笑)。こんなに安くて色もつけられて、なんにでもなれるなんて、万能の素材じゃないか。これぞイノベーション! プラスチック万歳! です(笑)。
問題は、プラスチックとの付き合い方だと思うんです。便利だからたくさん使うし、安いからありがたみも感じずどんどん捨ててしまう。人間はそれでいいかもしれませんけど、実はそれで動植物がひどい目に遭っていて、地球環境も汚染されていることがわかった。
我々としては、プラスチックは全部やめよう、と言いたいわけではないんです。ただ、必要もないものをわざわざプラスチックで作って使い捨てて、ゴミを増やす、そういう高度経済成長期的な昭和のライフスタイルは、もう時代に合わないじゃないですか、という提案です。特に2020年代に入ってからは、サステナビリティがグローバルに叫ばれています。今の世界の現状に合った暮らし方、ものの選び方をする、そのきっかけを作ることができれば」
次回は、「カミーノ」の今後の展望についてうかがいます。
*Vol.3に続く
取材・文:剣持亜弥
撮影:高木亜麗
編集:南 ゆかり
デザイン: 山口言悟(Gengo Design Studio)
撮影:高木亜麗
編集:南 ゆかり
デザイン: 山口言悟(Gengo Design Studio)
真のゴミゼロ対策を考える
ユニーク起業「カミーノ」の軌跡