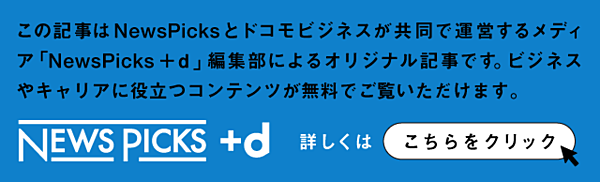2022/8/5
【長野】農+ワーケーション。リモート収穫で共感とファンを生む
柔軟な働き方の浸透に伴い、注目度を高めてきたワーケーション。都会でなくても希望の職に就けて、働き続けることができたり、これまで気づかなかった地域の魅力を享受しながら滞在することができたり、とそのメリットは大きい。体験した人たちが、さらに二拠点移住や完全な移住、そして新たなビジネス展開に踏み出すなど、ワーケーションは大きな可能性へとつながりつつあります。
各自治体が工夫を凝らすワーケーション。訪れる人々にその土地のファンになってもらい、移住やビジネスへとつなげるにはどうしたらいいのでしょうか。自治体と企業が連携し、成功へと導いているさまざまな地域の事例を、リポートしていきます。
第1回目は、長野県須坂市。農業で企業や人を引き寄せている事例を紹介します(全2回の前編)。
各自治体が工夫を凝らすワーケーション。訪れる人々にその土地のファンになってもらい、移住やビジネスへとつなげるにはどうしたらいいのでしょうか。自治体と企業が連携し、成功へと導いているさまざまな地域の事例を、リポートしていきます。
第1回目は、長野県須坂市。農業で企業や人を引き寄せている事例を紹介します(全2回の前編)。
INDEX
- ブドウ畑で農作業、ハウスの中でディスカッション
- ITベンチャーと地方の農家が「オンライン果物狩り」でタッグ
- 農家と自治体が感じるメリット
- 会社単位で参加を募り、ターゲット企業を明確に
- 互いのアイデアとコラボレーションから生まれた新施策
ブドウ畑で農作業、ハウスの中でディスカッション

5月某日、長野県須坂市のブドウ畑に、東京都や愛媛県の5つの企業から13人のビジネスパーソンが集いました。
彼らは市内のゲストハウスに最長で2泊3日滞在し、1日目はシャインマスカットがたわわに実るハウスの中で「巨峰の人気の再生」についてディスカッションを行い、2日目は早朝から畑作業を手伝いました。その合間には、宿でPCを開いてリモートミーティングを行ったり、市役所や県庁を訪問したりする人も。
これは「農+ワーケーション(ノウタスワーケーション)」というプログラムで、地元の老舗ブドウ農家である「岡木農園」と東京のIT企業のノウタスが、須坂市役所の協力も得て開催したものです。
畑での作業の様子はNHKや信濃毎日新聞、ローカルテレビ局などでも報じられ、地方や農家の課題解決につながるワーケーションのあり方として注目を集めています。

ブドウ畑で車座になって話をする参加者たち(提供:ノウタス株式会社)
ITベンチャーと地方の農家が「オンライン果物狩り」でタッグ
ノウタスの髙橋明久代表取締役CEOは、大手コンサルティング会社でDXや地方創生に関わる仕事をした後、ノウタスを創業しました。目指すのは、日本の農業の9割以上を占める家族経営の農家の持続可能性を高めることです。
昨年、自宅にいながらブドウ狩りやリンゴ狩りを楽しめる「オンライン果物狩り」のイベントを複数回開催しました。
家庭やイベント会場と農園をZoomでつなぎ、参加者と農家がコミュニケーションを取りながら果物を収穫、翌日には参加者に送付して食の体験まで楽しんでもらうというものです。コロナ禍で旅行も難しい中、自宅にいながら自然に触れ合えるイベントとして参加者の満足度は高く、多くのメディアにも取り上げられました。
岡木農園とノウタスとの関係はこのときから始まり、いまでは農園代表の長男である岡木宏之さんが、ノウタスの取締役CSO(チーフ・ストラテジー・オフィサー)も務めています。
髙橋 「オンライン果物狩りを始めるとき、この企画に乗ってくれそうな農家さんとして共通の知人に紹介されたのが岡木農園でした。岡木さんをノウタスの取締役にお誘いしたのは、オンライン果物狩りやワーケーションなど我々の提案に積極的に協力してくれたのに加え、もともと金融機関で働いていたというバックグラウンドがあって話が通じやすく、農業の今後に対する思いで共感する部分が多かったからです」

左から、岡木宏之さんと髙橋明久さん
農家と自治体が感じるメリット
岡木さんは、大学卒業後に長野県内の信用金庫に就職。融資の担当として中小企業の経営者から多くを学ぶ傍ら、農園のホームページを作ったり販路を開拓したりと、家業を手伝ってきました。自身が「日本一おいしい」と感じている岡木農園のブドウを、もっと世の中に知ってもらい、価値を高めたいという思いからだったと言います。
2019年からは信用金庫を辞めて家業に専念し、地元の大学生と一緒にシャインマスカットを使った低アレルゲンスイーツを開発したり、高校生と一緒に「シャインマスカットの粒売り」という販売形態を考案して「無印良品 銀座店」で販売したりと、新しい取り組みに次々と挑戦してきました。
そんな岡木さんがワーケーションの会社員たちを受け入れてみて感じた一番のメリットは、「消費者と直接コミュニケーションが取れる」という点だと言います。
岡木 「通常、農家は農協を通して販売するので、お客様のニーズや課題といったものが把握できません。ECサイトではレビュー機能もありますが、具体的な改善案に結びつくようなコメントはほとんど得られません。ワーケーションで来ていただいた皆さんにじかに意見を聞かせていただけるというのは、販促やブランディング、マーケティングの面でとても有効だと感じています」
髙橋さんは、農家でのワーケーションは地方自治体にとっても魅力のあるプランだと指摘します。
髙橋 「須坂市さんには『農業を観光資源として捉え、まちづくりにいかしていきましょう』という提案をし、大いに賛同いただきました。都会の人に農業を体験しながら地域の宿泊施設に滞在してもらい、町の良さも知ってもらう。それによってファンや関係人口を増やし、移住者を呼び込むという流れを作れるのではないかと考えています」

須坂市の三木正夫市長も、「農+ワーケーション」に期待をかける
地元で育った岡木さんによれば、善光寺を擁する長野市と栗菓子などで有名な小布施町に挟まれた須坂市は、観光客には素通りされがちだと言います。
しかし、立派な蔵が並ぶ古い町並みはとても美しく保たれており、高層ビルだらけの都会から来た人々にとっては、ゆっくり散策するだけでもワクワクする時間になるでしょう。ブドウだけでなくリンゴやモモ、プルーンなどの新鮮なフルーツの産地であり、そばやみそにおやきなど、食の楽しみにもこと欠きません。
そんな須坂市の魅力を知ってもらうきっかけとして「農+ワーケーション」は有効なツールとなり得るのです。
会社単位で参加を募り、ターゲット企業を明確に
「農+ワーケーション」が初めて開催されたのは昨年6月。須坂市の協力を得ての実証実験として、都内の外資系IT企業の社員が一人で須坂市の温泉旅館に滞在し、リモートワークをしながら岡木農園の農作業を手伝いました。
このときは個人の参加者を募るプログラムとして企画し、参加者には自然の中での農作業で心身をリフレッシュしてもらい、農園側は人手不足を補いながらファンを獲得する、ということが狙いでした。しかし実際にやってみると、思わぬ収穫があったと言います。
岡木 「岡木農園としては、以前からホームページでの情報発信やECサイトでの通販などに力を入れていました。それに対し、消費者目線でサイトのデザインや文章について意見をくださったり、ITエンジニアとしての立場から技術的な面でのアドバイスをしてくださったりして、多くの気付きがありました。とてもありがたい機会でした」

岡木農園は大正時代からの老舗農家で、岡木さんの父の代からブドウに特化するようになった
都会のビジネスパーソンが来てくれることには、単に農作業の手が増えるということにとどまらないメリットがあったのです。
そこで今度は、個人での参加者を募るのではなく、農家の生産性向上に対して有益なアドバイスをしてくれそうな会社や、事業におけるシナジーが見込めそうな会社をターゲットに声をかけることにしました。その結果、実現したのが、今回のワーケーションプログラムです。
参加したのは、自社のソリューションを地方の中小企業や農業分野にも展開していくことを考える企業などで、単なるリフレッシュやCSRといった目的以上の期待を持っていました。それゆえに、1日目のディスカッションに対する当事者意識も高く、大いに盛り上がったそうです。
互いのアイデアとコラボレーションから生まれた新施策
ディスカッションのテーマは「巨峰のリブランディング」です。
巨峰は昔から「ブドウの王様」と呼ばれ、愛されてきました。しかし最近はシャインマスカットの人気と価格がうなぎ上り。50年ほど前から巨峰を中心に栽培してきた岡木農園も、ここ10年ほどでシャインマスカットの栽培を増やし、いまでは栽培面積の大部分を占めています。しかし、地元の高齢の農家から巨峰の畑を借り受けたことをきっかけに、再び巨峰にも力を入れていこうと考えています。

巨峰の魅力や課題、その解決方法について議論した(提供:ノウタス株式会社)
そこで、ワーケーションの参加者たちとともに、「どうしたら巨峰を選んでもらえるか」について話し合いました。
皮ごと食べられて種もないシャインマスカットと比べると、巨峰は食べづらいという課題がありますが、そこも含めて価値を訴求できないか、という議論が盛り上がったと言います。
岡木 「巨峰はまだ収穫の時期ではないので、代わりにナガノパープルを召し上がっていただきながらお話ししました。皆さん、巨峰を食べた経験をお持ちで、あの酸味や甘味は他に代えがたいとおっしゃってくださるんですよね。皮をむくのが面倒でも、おいしいパンを求めて山奥のパン屋さんに通うように、ひと手間、ふた手間かけても食べたいもの、という訴求をするのがいいのではないか、というアイデアが出て、素晴らしいと思いました」
ここでの議論を経て岡木農園では、「温室栽培のシャインマスカットと巨峰」をセットで自宅に配送し、シャインマスカットについては市場価格を参考にした固定の価格を支払ってもらうが、巨峰の価格は顧客が自由に決定するというサービスの実証実験を行いました。
「顧客が商品を受け取ってから、自由に価格を決めて支払う」という方式は、ワーケーション参加企業のひとつであるネットプロテクションズの「あと値決め」という決済サービスを活用します。シャインマスカットと食べ比べた上で、巨峰の価値を顧客自身に評価してもらおうというこの企画、どのような結果となるのか注目です。
※後編へ続く
取材・文:やつづかえり
編集:岩辺みどり
写真:杉山亜衣
デザイン: 山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:岩辺みどり
写真:杉山亜衣
デザイン: 山口言悟(Gengo Design Studio)
人や企業がその土地のファンになる!ワーケーションの成功例
官民連携ワーケーション