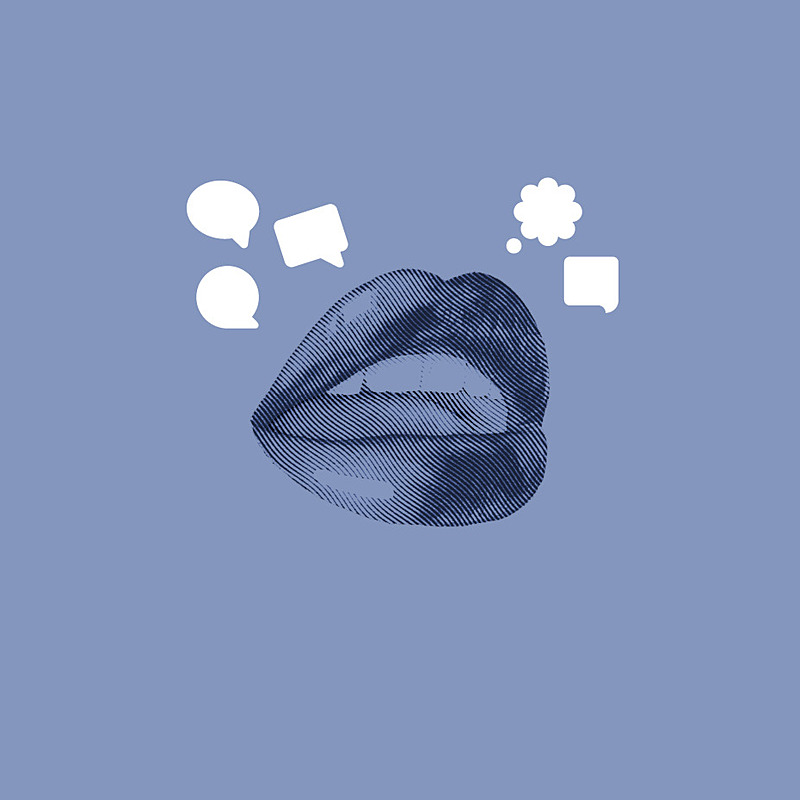
2022/4/15
【深津貴之×CXデザインファーム】顧客体験の時代、企業に不可避な「CX投資」とは
株式会社NTTマーケティングアクトProCX | NewsPicks Brand Design
「顧客体験(Customer Experience=CX)」や「CX戦略」といった言葉を聞く機会が増え、カスタマーサービスのあり方に変化が起きている。
「10年ほど前からビジネスにおける勝者の構造が一変した」とは、CXO(Chief Experience Officer)として数々のプロジェクトに携わるTHE GUILD の深津貴之CEOの言葉だ。
GAFAMのようなメガプラットフォーマーの台頭以降は、顧客との「つながり」が勝負を分ける時代。今や、どんな企業もCXを無視することはできないのだ。
それなのに、なぜ企業の「CX投資」は進まないのか。
どんな企業にも共通する、CXを向上させる秘訣とは。企業のCX向上を支援するNTTマーケティングアクトProCXと深津氏、CXを推進する実践者たちに話を聞いた。
INDEX
- なぜビジネスの勝者は一変したのか
- ジェフ・ベゾスが自ら顧客対応する理由
- 退会するとき、多くの人が嫌な思いをする
- 「粗大ゴミの申し込みが面倒すぎる問題」の解決策
- 「3コール以内に電話に出る」は本当に重要か
なぜビジネスの勝者は一変したのか
CX、つまりは顧客体験を重視する企業が、BtoB、BtoCを問わず増えている。
かつてはクレーム処理部門のように捉えられていた「カスタマーサービス」を「カスタマーサクセス」と改称するトレンドは、ひとつの表れだろう。

その理由について、CXO(Chief Experience Officer)として数々のプロジェクトに携わるTHE GUILD でCEOを務める深津貴之氏は次のように語る。
「2010年頃、いわゆるWeb2.0以降、ビジネスにおける勝者の構造が変わりました。GAFAMのようなメガプラットフォーマーの台頭によって、『より多くの顧客とのつながり』を持つ企業が勝つようになった。
それに気づいた企業は、顧客アカウントを最大化すべく、『お試し無料』で比較検討段階からプロダクトに触れてもらう仕組みや、サブスクリプションモデルを導入しました。
すると、かつての売り切りモデルとは違い、顧客が商品・サービスを購入する前から購入後まで、継続してCXを高め続ける必要がある。今、企業がCXに投資するのは非常に合理的なことなのです」

類似するモノやコトが巷にあふれてコモディティ化した今、商品・サービスそのものの魅力で「選ばれる」ことは難しい。
同時に、スマホの普及やSNSの進化によって、顧客は簡単に情報収集及び発信ができるようになった。
商品・サービスは単純に消費するものではなく、体験するもの、共感・共有するものへと変わる「コト消費」へのシフトも、CXに投資すべき理由のひとつだろう。
では、日本企業にCXの重要性は浸透したのか。
「まだ十分ではない」と話すのは、クライアント企業のCX向上を推進するNTTマーケティングアクトProCXの井上雅博チーフプロデューサーだ。

「CXに注力する企業が増えたといっても、日本全体で見ればまだ少数にすぎません。企業側、特に経営層が効果を感じやすいという理由から、CX投資の目的が業務効率化やコスト削減にすり替わってしまうことも多い。
すると、顧客を満足させるどころか、維持することすら難しくなるという本末転倒な状況も起こりえます。日本は『おもてなしの国』としてのイメージが強く、『顧客主義』を掲げる企業が多い半面、戦略的にCXを捉えることが苦手なのです」(井上氏)
当然のことだが、CXに注力するか否かを決めるのは経営層だ。日本企業全体のCXを向上させるカギは、この部分にあると言えそうだ。
ジェフ・ベゾスが自ら顧客対応する理由
深津氏によれば、企業がCX投資に踏み切れない理由は大きく2つ。ひとつは、経営層が「顧客の存在を身近に感じていない」ことだ。
一般的に言って、経営層は現場ほど顧客との距離が近くない。
大企業になればなるほど、業務を通して顧客と接する機会は減るだろう。顧客が「見えない」存在になれば、その体験を軽んじるのも当然と言える。

「CXがビジネスの成否を分ける今、それは致命的な判断ミスにつながります。企業には、一定数の顧客と会うことを昇進の条件にする、経営層が定期的に自社のプロダクトを使うことを義務付ける、といった仕組みづくりが求められるでしょう。
CX戦略で成功してきたAmazonでは、2年に1度、創業者のジェフ・ベゾスも含めた社員全員がカスタマーサービス研修を受けています。定期的に顧客対応を経験することで、顧客との近い距離感を保っているのです」(深津氏)
もうひとつは、経営層がUX(User Experience)、ひいてはCXを向上させるメリットを理解していないことだ。
これは、ビジネスへのインパクトが明確なことにしか投資できない、という井上氏の指摘にも通じる。多くの経営層にとって、顧客の体験は「よくわからない価値」なのだ。
深津氏は、日本企業が陥りがちなこの状況を「UXのUXが悪い問題」と表現する。

「企業がUXやCXへの投資に舵を切るためには、経営層がメリットを感じられる体験、つまりUXの必要性を感じるUXを設計する必要があります。多くの企業では、それができていない。UXのUXが悪いとは、そういう意味です」(深津氏)
企業が究極的に知りたいのは、CX投資がどれほどの収益をもたらすか、ということだろう。
そこで、井上氏が所属するNTTマーケティングアクトProCXでは、コンタクトセンターの運営で蓄積したデータから、それらの相関関係を定量的に示している。
「CXが収益に直結するとわかれば、これまで腰の重かった経営陣もCXに積極的に投資していこうと思うはずです」と井上氏。
日本企業が経営戦略としてCXに取り組めば、「おもてなし」がビジネスを伸ばすための明確な武器になるのだ。
退会するとき、多くの人が嫌な思いをする
では、CX戦略の肝はどこにあるのか。
企業の内と外からCXを推進するCXOたちの意見をまとめれば、「顧客と直接触れ合う部署だけでなく、全社で顧客を軸に連携する」ということになる。深津氏の意見はこうだ。
「僕はCXOの役割を『顧客を代弁する責任者』と定義しています。CXOがすべきは、全社が顧客を軸につながり、企業活動のすべてのプロセスでCXが設計された状態を構築することでしょう。
同じ会社でも各部門の考えや目標は微妙に異なります。そんな中でも顧客に喜んでもらうためには何をすればいいか。全社一丸となる方針を示すことが重要です」
たとえばネットで電化製品を購入した際、メーカーのコールセンターに電話をすると「ネット購入の窓口はこちらです」と案内され、問い合わせた先で「メンテナンスは別会社に委託しています」と言われ……といったことは往々にしてある。
企業にとってはベストなフローかもしれないが、顧客の「本当に問題が解決するのだろうか」という不安は、たらい回しにされるうちに企業への不信感へと変わっていく。CXとしては、控えめに言っても最悪だ。
顧客視点での全社連携ができていないと、企業の都合による不具合が起きてしまう。そうする間にも、CX戦略に長けた企業はどんどん先を行く。
CXコンサルタントとしてクライアント企業のCXを推進してきたNTTマーケティングアクトProCXの米林敏幸シニアプロデューサーは、CXの先進企業としてNetflixを紹介する。
Netflixでは、顧客がスムーズに退会できるよう、オフボーディングのCXに取り組んでいるのだ。

「わざと退会しにくいようなUIを設計する企業もありますが、退会時にネガティブな体験をした顧客の口コミが悪影響をもたらすことは、データからも明らかです。これは『必要なときにまた戻ってもらう』というNetflixのCX戦略のひとつ。
ここまで顧客視点で考え抜けるのは、全社が一枚岩となってCXに取り組んでいる証拠でしょう。経営層にはNetflixの成功を見て、その重みを感じてほしい。
そして、社内のリソースが足りないために従来の目標や施策をベースにした『CX改善』を行うなら、ぜひ私たちのような外部パートナーとタッグを組んで『CX戦略』を進めてほしいです」
「粗大ゴミの申し込みが面倒すぎる問題」の解決策
前述したように、CXは経営戦略において重要な要素にもかかわらず、日本企業・団体にとってその取り組みはまだ道半ば。この分野のスペシャリストに力を借りるのも一つの手段。
ある自治体の粗大ゴミ受付センターのUX改革は、NTTマーケティングアクトProCXが自治体のパートナーとなり、劇的にCXを向上させた好例だ。
当時、受付センターには「電話で予約するのが不便だ」「Webサイトからの予約も使いにくい」など、粗大ゴミが簡単に出せないことに対する市民の不満の声が寄せられていた。
「顧客の声=VOC(Voice of Customer)」を生かすのは、CXの観点で非常に重要であり、国内最大規模のコンタクトセンターを運営し、NTTグループのユーザーの声に応えてきたNTTマーケティングアクトProCXの得意とするところ。
その運営のなかでVOCがいかに貴重な経営資源であるかに気づき、VOCの分析とコンサルティングを専門特化で実施するセンター「奏色」を開設したのだ。
現在、20人を超えるVOC専門のアナリストが企業の伴走支援を実施している。
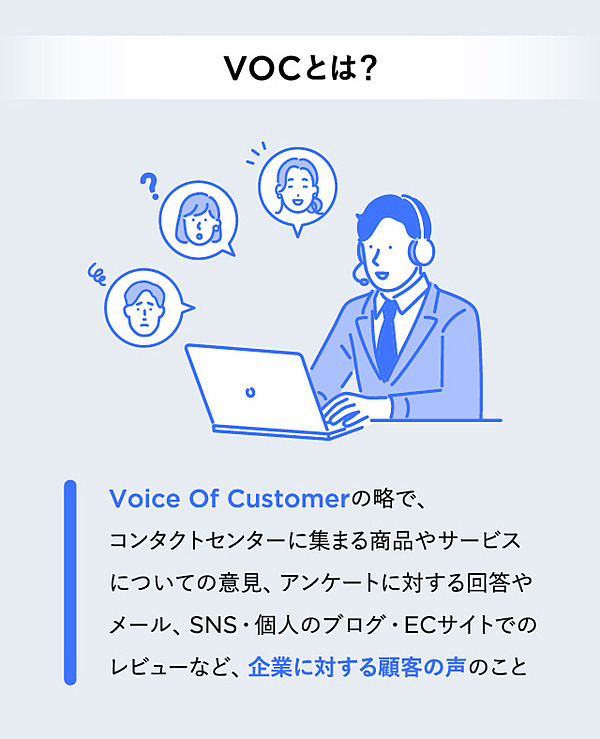
「コンタクトセンターは、店舗、ECサイト、アプリといったさまざまなチャネルで生じた課題をすくい上げる最後の砦。8割強の人が、自分で解決を試みてから電話しているということがわかっています。
つまり、コンタクトセンターに集まる声は、顧客のさまざまな要望が詰まっていて企業にとっては宝の山。私たちはそれを音声認識技術なども取り入れながらデータ化して徹底的に分析し、企業にフィードバックすることで、新たな企業価値の創出を支えてきました」(井上氏)
この自治体の場合、解決策は老若男女に広く普及しているLINEを使うことだった。LINE社と提携し、日本で初めてLINEで粗大ゴミの申し込みが完了する仕組みを構築したのだ。

「当初は、電話やWebからの申し込みがLINEに置き換わると考えていた」と井上氏。しかし結果は予想外のものだった。
「なんと、電話やWebからの申し込みの減少を数倍上回る量で、LINE申し込みが増えたんです。面倒くささから粗大ゴミを出せずにいた人がいかに多かったかがわかりました。
正直に言って、それまでのゴミはどうなっていたんだろうと思ったほどです(苦笑)。もちろん、市民満足度も飛躍的に上がりました」(井上氏)
これは「簡単に粗大ゴミを出したい」という要望を、顧客視点で受け止めた結果だろう。
単純にセンターの電話回線を増やすのではなく、LINEというチャネルを追加したことで利用者が増え、業務効率化も進んだのだ。
「3コール以内に電話に出る」は本当に重要か
このように見ていくと、CX戦略の重要性、そして、いかに落とし穴が多いものかがわかる。
「顧客の声を経営に生かさなくてはいけない。そこまではわかっていても、いまだにコールセンターに対して『電話が鳴ったら3コール以内に出る』『メールは24時間以内に返信』といった目標を設定する企業は少なくありません」と米林氏。
業務効率化やコスト削減と同様に、レスポンスの速さも数値化しやすいからだ。真の意味でCXの向上を目指すなら、目標に据えるべきは「満足度」や「解決率」だろう。
アメリカの最新調査では、オペレーターの熱意や親身な対応が顧客満足度に大きく影響することもわかっている。わかりやすい指標に飛びつけば、CXの本質を見失うことにもなりかねない。
「極論を言えば、コールセンターで問題が解決しなくても、一緒に悩んで、解決策を一生懸命調べてくれたら、満足度が高い可能性もあります。ただ、それは病気のときに優しくしてくれた人を好きになる感覚と近いんですよね。
顧客から寄せられる企業の課題は、ウイルスのようなものです。体内にウイルスが入ったら、一時的には体調が悪くなりますが、治れば抗体ができる。それと同じように、全社で課題を共有・解決していく仕組みづくりができれば、企業はどんどん強くなります」(深津氏)
デジタル化、グローバル化が進めば、CXの重要性はますます高まっていくだろう。
そのときになって後追いするのか、先んじて取り組むのか。ビジネスで「勝つ」ための選択は明らかだ。
執筆:田村朋美
写真:北山宏一
デザイン:久須美はるな
編集:木村剛士
写真:北山宏一
デザイン:久須美はるな
編集:木村剛士
株式会社NTTマーケティングアクトProCX | NewsPicks Brand Design


