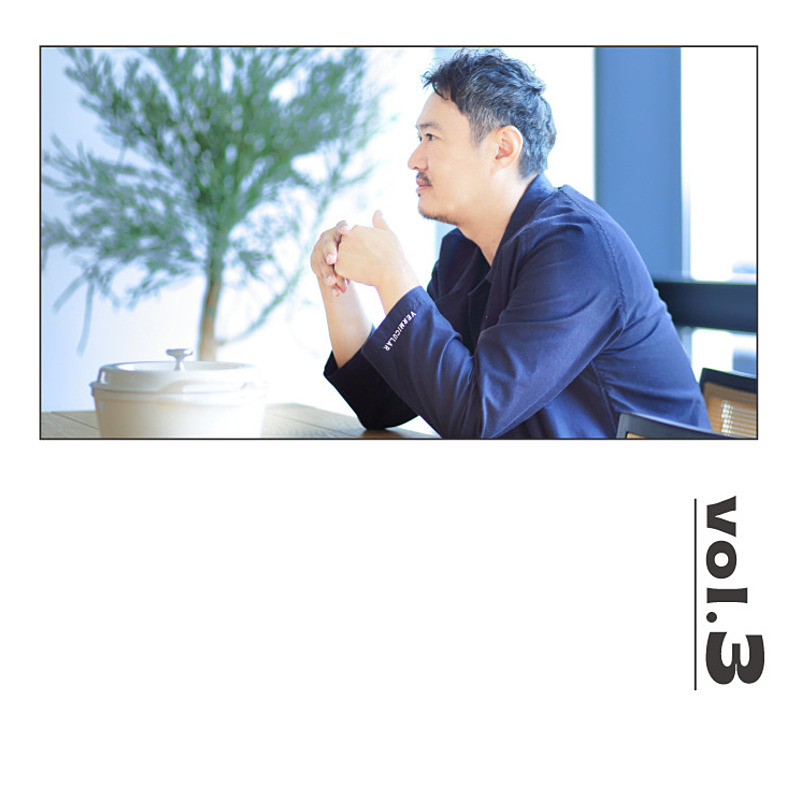
2022/1/18
【愛知】1万個試作も失敗続き…“世界一”を確信した瞬間
「調味料を使わなくなった」「息子が嫌いなブロッコリーを美味しそうに食べた」――。そんな反響が消費者から相次ぐ鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」。密閉性と緻密に計算された鋳物ホーローの熱伝達が食材そのものの旨みを引き出し、無水調理にもぴったりだという。
開発したのは「町工場」の「愛知ドビー」(名古屋市)。鋳造技術と精密加工の技術を組み合わせ、約3年かけて2010年にバーミキュラを完成させた。代表商品の鋳物ホーロー鍋「オーブンポットラウンド」の累計受注数は58万台(2021年9月末時点)に達している。アメリカ・アジアを中心にした海外展開も順調だ。
かつては倒産の危機に陥っていた愛知ドビー。自社にすでにある技術を活かしたBtoB(企業間取引)からBtoC(企業対消費者取引)への大胆な転換、「買ってもらって終わり」ではないファンとの繋がり方などを、家業を継いで成長軌道に乗せた土方邦裕社長に聞いた。(全4回の第3話)
開発したのは「町工場」の「愛知ドビー」(名古屋市)。鋳造技術と精密加工の技術を組み合わせ、約3年かけて2010年にバーミキュラを完成させた。代表商品の鋳物ホーロー鍋「オーブンポットラウンド」の累計受注数は58万台(2021年9月末時点)に達している。アメリカ・アジアを中心にした海外展開も順調だ。
かつては倒産の危機に陥っていた愛知ドビー。自社にすでにある技術を活かしたBtoB(企業間取引)からBtoC(企業対消費者取引)への大胆な転換、「買ってもらって終わり」ではないファンとの繋がり方などを、家業を継いで成長軌道に乗せた土方邦裕社長に聞いた。(全4回の第3話)
この記事はNewsPicksとNTTドコモが共同で運営するメディア「NewsPicks +d」編集部によるオリジナル記事です。NewsPicks +dは、NTTドコモが提供している無料の「ビジネスdアカウント」を持つ方が使えるサービスです(詳しくはこちら )。
INDEX
- 完成まで約3年、試作品は1万個以上
- 苦手なニンジン、試作品で調理してみると…
- 技術確立までさらに5年、納期延期も
- “メーカーのプライド”でアフターフォローを徹底

土方邦裕(ひじかた・くにひろ)/愛知ドビー株式会社代表取締役社長
1974年、愛知県生まれ。大学卒業後、豊田通商で為替ディーラーを務める。2001年、祖父が創業した愛知ドビーへ入社。3代目として家業を継ぐ。弟の智晴副社長と共に「バーミキュラ」を開発し、2010年より販売を開始。現在は海外にも積極的に展開し、大ヒットブランドに成長させている。
1974年、愛知県生まれ。大学卒業後、豊田通商で為替ディーラーを務める。2001年、祖父が創業した愛知ドビーへ入社。3代目として家業を継ぐ。弟の智晴副社長と共に「バーミキュラ」を開発し、2010年より販売を開始。現在は海外にも積極的に展開し、大ヒットブランドに成長させている。
完成まで約3年、試作品は1万個以上
――バーミキュラの実際の完成までにはかなり時間がかかったそうですね。
「3カ月もあればできる」。最初はそう思っていました。実際には、完成までに約3年かかりました。試作した鍋は1万個以上です。
まず鋳物をホーロー加工する段階でつまずきました。ホーローがうまく鋳物にひっつかない。コーティングがされなくて、ぶくぶく泡をふいたような感じになって、ホーローがすぐにはがれたり、穴があいたりする不良が出ました。
まだ日本国内では、鋳物ホーロー加工の技術が完成されていなかったんです。最初は、ホーローメーカーさんに、共同での技術開発をお願いしました。愛知県のあるBtoBの会社が手を挙げてくれて、1年は一緒にやっていました。でもなかなかうまくいかず、ベースの技術を身に付け、あとは自分たちで開発を始めました。
ホーローに関する専門家や文献に(弟の土方智晴・副社長との)兄弟であたり、成分の数値を調整しながら試作を繰り返しました。そうして試行錯誤の末にホーロー加工のめどがたったのですが、難しくてさらに時間がかかったのが、鍋のフタと本体との密閉性を高めることでした。

バーミキュラのホーローの加工作業=提供・愛知ドビー
ホーロー加工をするのに、800度で焼き付けるんですが、鋳物の組織変化が起こる「変態点」が720度近辺。800度より下なんです。つまりホーロー加工をするとどうしてもゆがみが出てしまいます。
なので、せっかく鋳物を削って密閉性を高めておいても、ぐねぐね曲がってしまう。当然、密閉性は壊れてしまいます。その相反するところのバランスをとるのは非常に難しい。しかも削る作業は0.01ミリ単位です。職人がつきっきりで、フタに20~30分、本体も20〜30分かかります。
開発の途中でリーマンショックがあり、2009年半ばごろには下請けの発注が激減して、週2日しか工場が稼働できない状況になりました。そんな中で鍋の試作にかかる費用がかさんで、もちろん赤字になります。当時すでにフランス製の鋳物ホーロー鍋には負けない製品ができていたので、まずはそれを量産して、徐々に(密閉性などの)クオリティーを高めてはどうか、という意見もありました。
ですが、「世界一の鍋をつくる」というコンセプトは曲げたくなかった。日本のものづくり、職人の誇りのためにも世界一にこだわって、最後まで開発を続けることにしました。
苦手なニンジン、試作品で調理してみると…
――「世界一の鍋ができた」と確信した瞬間は覚えていますか?
開発スタートから3年くらい経ったころ、できた試作品の鍋を使って、工場のすぐ近くの実家で副社長とカレーをつくりました。
とにかく水を入れずに、食材を弱火で加熱していきました。それだけで、すごい水分が出る。まずそれにびっくりしましたね。そこにカレーのルーを混ぜただけのものを試食しました。

提供・愛知ドビー
僕はニンジンがすごく嫌いなんです。なので、ニンジンがおいしくなるだろうとは、もちろん思っていなかった。でも、どの野菜もおいしいし、もしかしたらと思って、ニンジンも口に入れました。本当に嫌いなので、普通だったら口に入れないです。
食べてみたら、僕の苦手な味がしなくてとてもおいしかった。人生で初めてでした、そう思ったのは。驚いて、無水調理のすごさも感じたし、コンセプトがぴったりはまったと思いました。
この鍋がちゃんと量産できて、さらにブランドを確立していけば、みなさんに喜んでいただける商品ができあがる――そう確信した瞬間でしたね。
鋳物という素材は、保温性、蓄熱性が高い。また、ホーローという素材は、遠赤外線を出すんですね。この2つがアルミやステンレスの鍋にはない特徴なんですよ。これによって、おいしさが引き出される。ここが大きく違うところです。あの時のニンジンの味は、まさにこの鍋でしか引き出せないものでした。
技術確立までさらに5年、納期延期も
――技術的な難しさから、発売後も製造がストップすることがあったとか。
僕たちが確立したと思っていた技術が、ちょっとピントがずれていたのです。温度や成分の調整の部分などです。その日の気温や湿度によって調整が必要で、うまくできなくなってしまうことがありました。
発売してから、何度もそういうピンチがあって、本当に技術が確立したと言えるのは、2015年くらいだと思います。発売から5年間はまだ苦労していましたね。

メディアで紹介してもらうのが怖い時期もありました。ものができないのに、メディアで紹介してもらうと注文はくる。お客さまに約束した納期に遅れてしまうのではないかと、かなり心配しながらやっていました。ひどいときは、100個作って1個もできないとか。そんな時期もありました。
“メーカーのプライド”でアフターフォローを徹底
――もともと工業製品をつくっていたメーカーでしたが、その経験が生きた部分はありますか?
開発というよりも、バーミキュラを購入していただいた後のアフターフォローで、経験が生きていると思います。
うちの父は、ドビー機があまり売れなくなってきた時代でも、アフターフォローはなんとかしっかりやろうという姿勢でやっていました。壊れたときの補修部品も、全然捨てようとしないし、図面もいつまででも持っていた。ドビー機の事業をやめるときも、図面も部品も全部無料で商社に渡して、メンテナンスをお願いするところまでやっていました。
そこは僕も参考にしていて、実際に下請けでのBtoB事業をやめる時も、同じような考えでやめさせてもらいました。
うちがポンとやめてしまうと、供給が止まって困るお客さまもいるので。うちと同じような仕事ができる会社に僕たちからお声掛けをして、作り方も全部お伝えして、お客さまにあまり負担がかからないようにしてから、やめさせていただきました。
そういう部分は、やっぱりメーカーのプライドです。自分たちが作って買っていただいた製品に対してしっかりと責任を持って最後まで保証をする考え方は、今のバーミキュラにも通じるところがあります。
※Vol4.に続く(NewsPicks +dの詳細はこちらから)

取材:船崎桜
撮影:松村シナ
編集:中村信義
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
撮影:松村シナ
編集:中村信義
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
世界ブランド「バーミキュラ」のつくり方
町工場から生まれた“魔法の鍋”
