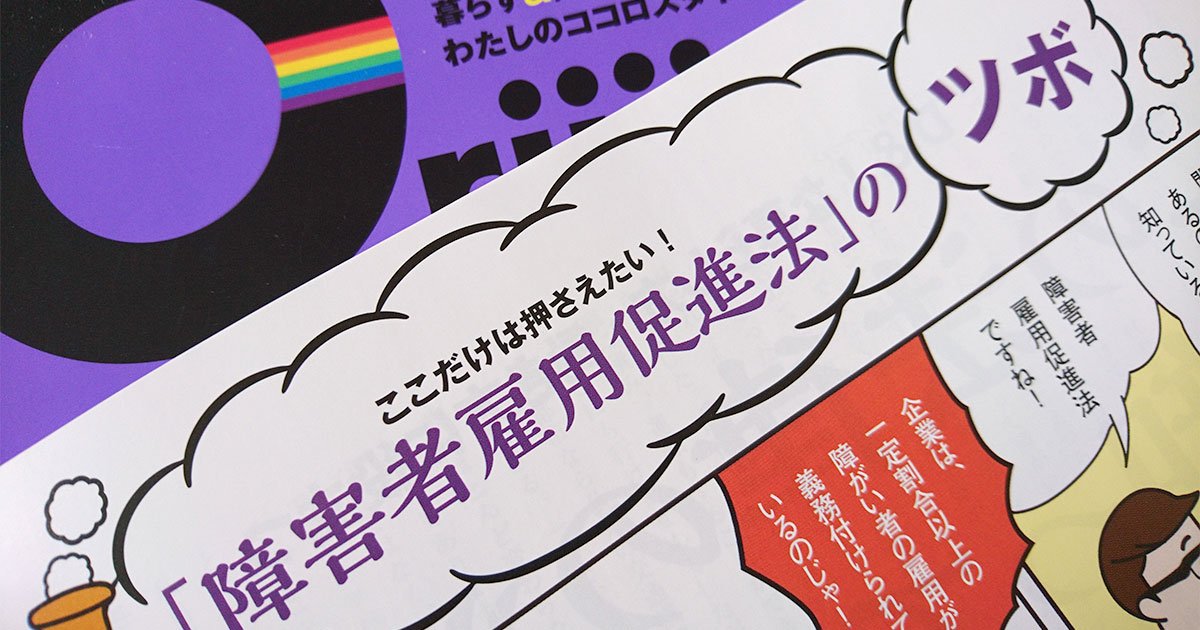
法律のツボで知る「ダイバーシティ&インクルージョン」【障害者雇用促進法編】 - Oriijin(オリイジン)
コメント
注目のコメント
あまり注目されませんが、実は障がい者雇用の促進や通所施設利用者の工賃改善は莫大な経済効果をもたらすポテンシャルを秘めています。
全国の就労対象人口は390万人。民間就労50万人、施設就労は30万人。民間就労者は一般的に月額13万円ほど、施設就労はA型で7-8万円、B型となると1.5万円ほどです。どの境遇においても、経済的余裕などありません。
しかし例えば、1人1人が就業によって毎月1万円自由に使えるお金が増えたら…どうなりますか?
私自身、企業とA型B型施設の共創を通じた工賃改善事業を生業としてるので、サポート施設利用者の方々がどれだけ買い物や欲しいものの購入を我慢して、諦めているか、よく理解してます。彼らに自由なお金があったら、自分のために、そして大事な家族のために、ほぼ何か買いたいものを買うだろうなと。
仮に就労対象人口390万人がフルで月間1万円使うとすると、その額、年間なんと4300億円です。
一方企業側から考えると、例えばお菓子や飲料メーカーがわかりやすいですが、仕事の一部を切り出して障がい者の就労につなげると、着実に自社のファンを増やす結果を生みます。
お世話になっている自分の働く会社を愛し、身内や親戚の働く企業には親近感が湧くでしょう。そこに前述の購買意欲が掛け合わさる時に、企業は新たな強力な固定客層を得ることになります。その規模は、人口の約2割。
だから、私自身、共創相手の企業には常々、障がい者支援は投資規模に比例して確実に何かしらのリターンを得られる自己投資だと、申し上げています。
業界改革の先鋒でもがく1企業として、単に国から突きつけられたノルマという"つまらない"見方ではなく、その裏の本質に多くの企業が気づき、目を向けてくれることを切に願います。
