
ヘルスケアを「再定義」せよ。デジタル×製薬による新たな医療の未来
武田薬品工業 | NewsPicks Brand Design
2020/1/14
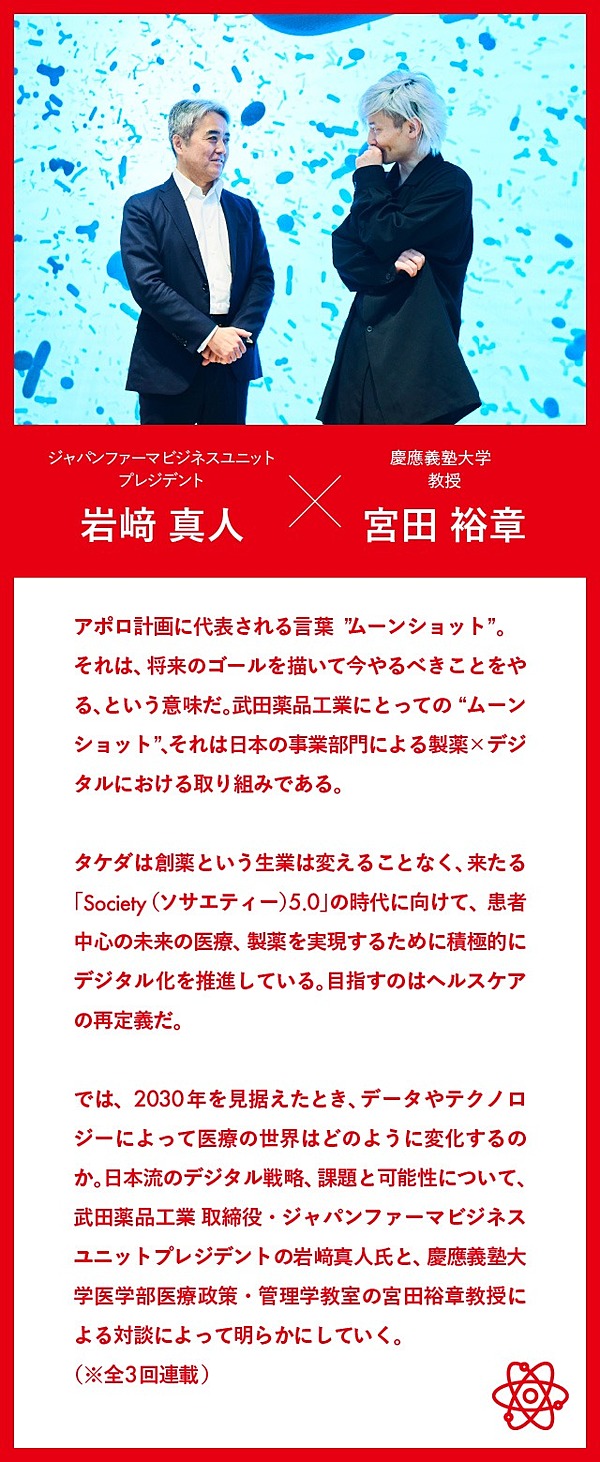
デジタルは脅威でもあり、最大のパートナーでもある
宮田 デジタルトランスフォーメーションという言葉に代表されるように、第四次産業革命によって医療に限らず全ての産業で大きな変革期を迎えています。
少し前から「ものづくりの時代」から「コトづくりの時代」へと言われていましたが、今起きている変革は、一人ひとりをデータで理解して、いかに体験価値をデザインして形にするか。
たとえば映像の世界では、これまでアカデミー賞を狙おうと思ったら“批評家コミュニティ”という“集団”に支持される映画を作れば良かった。
それが、今はニューヨークに来たインドの移民からの視点や、LGBTから見た世界など、マジョリティではなかった視点からの映像が作られるようになった。しかも作品のクオリティが一定以上なら世界に通用します。Netflixがわかりやすい例ですよね。

集団をなんとなく把握するのではなく、一人ひとりをデータで理解し、モノではなく価値を作る動きは医療業界にも訪れています。
集団平均から個別化の時代に変わり始めているし、病気の概念も「病気になってから対応する」のではなく「手前で防ぐ」考え方に変わっていますよね。
岩﨑 病気の概念だけでなく、薬の概念も確実に変わっています。私がデジタル化に興味を持ったのは2011年頃で、実際に世の中が変わると実感したのは、2014年にシリコンバレーを訪れたとき。「これは本気だ、世の中が変わる」と思いました。
同時期のダボス会議でも衝撃的な体験があって、隣に座ったシリコンバレーのスタートアップの社長がアプリを見せながら「これが薬になるんだよ」と話しかけてきたんですね。
どういうことか聞くと、今まで薬は飲んで体に作用させていたけれど、必ずしも飲む必要はなく、アプリで人の心に作用して状態が良くなるのなら、それは薬なんだと。
それを聞くまで、デジタルで人の健康をサポートするのは違う領域のビジネスだと思っていたのですが、製薬業界でもこの考えが主流になると確信しました。

デジタルは製薬会社にとっての脅威でもあり、新しい価値を生む最大のパートナーでもある。だから、武田薬品工業(以下、タケダ)の日本事業部門では、2015年頃(全社では2014年)からデジタルの専門家をチームに加えていろんな活動を進めています。
「競争領域」と「共創領域」はわけて考える
宮田 タケダのデジタルへの取り組みは、かなり早いですよね。これから製薬業界に求められるのは、薬を売ってそれで終わりではなく、薬を使った患者さん一人ひとりがその後どのような体験をするのかまでコミットするだと思います。
たとえば「仕事や子育てなど、一人ひとりの生きがいを実現するために病気をコントロールすること」「病気そのものの治癒が困難でも、その人らしく生きることができる」などです。
これまで睡眠薬は処方した後、実際にいつどのように使われたのか、どれだけの効果があったのかはわかりませんでした。
だけど、今はIoT機器があれば睡眠時間のデータが取れます。それだけでなく、日常の行動データから、生活リズムが崩れかかったところに介入して予防につなげられるかもしれない。
製薬会社にとって薬はソリューションの一部となり、人々のデータを活用しながら、人が自分らしく生きるためのビジネスに変わっていくのかもしれません。

岩﨑 当社では、大手製薬会社が自前主義で新しい薬を生み出す時代は20年前に終わっていると考えています。
これからは、IT業界とのパートナリングがデフォルトになっていきます。それによって、今まで十分生かしきれていなかった人の生活データを、正しく翻訳できるようになるはずです。
だからこそ、今までのように「競争」だけを考えるのではなく、他社と「共創」する領域をわけて考えていかなければならないと思っています。
提供者が共同体となり、患者中心の医療へ
岩﨑 ただ、共同体を作ってデータを共有しようとすると、規制や制度等、クリアしなければならない壁が立ちはだかります。
それを突破するには、アカデミアや行政に対して、しかるべき実例を示さないといけないと考えているんです。
そこで、タケダは米国の会社と共同でウェアラブルデバイスを使用して、パーキンソン病の患者さんの生活を測定・解析する臨床試験を進めています。
パーキンソン病は診断基準がはっきりしていて、遺伝子治療のアプローチも取られつつあります。患者さんも自分の意思を表明できるし、周りもどんなサポートをしたらいいかある程度わかる。
だけど、患者さんを中心とした関係者同士はまだつながっていない。それぞれがつながることでケアを一気通貫することが可能になり、結果、患者さんがより良いサービスを享受できるようになる。

だから製薬会社だけでなく、他業界も含めて医療サービスを提供する側が、データを共有する共同体となることで、患者さんに必要とされているソリューションを作る。
その実例を作れたら、今後の流れを変えるような大きなインパクトを世の中に与えられるのではないかと考えています。
宮田 今あるルールを変えるのはいつも民間からです。だからこそ、範囲を限ってでも実例を世に出すのはすごく大事ですね。
岩﨑 できない言い訳を探していては何も変わらないですからね。
そもそも患者さんは、薬を処方してもらうために病院や薬局に行くのも、リハビリをすることも大変です。もちろん、ケアするご家族にも負荷がかかる。
今の技術を使えば診断やリハビリをリモートにできるかもしれませんし、一人のリハビリは辛くても、自宅で他の患者さんとオンラインでつながり、会話をしながら取り組めたら、辛さは軽減されるかもしれません
遠く離れたところに住むご家族同士もオンラインでコミュニケーションできるようになれば、心の負荷が減るかもしれない。
今は、医療を提供する側の都合で患者さんが動いていることが多いですが、10年もしないうちに、患者さんが中心にいて、そこにいろんなプロバイダーがサービスを提供する「患者さん中心の医療」に確実に変わると思っています。

宮田 インフルエンザにしても患者さんが病院に行くのは、周りに感染させるリスクと本人が外に出て悪化するリスクが高い。
でもアプリで喉を診断し、電話一本でドローンが薬を届けるような動きはすでにあり、確実に日本にもその世界はやってきます。
未来を前提にヘルスケアをデザインする必要があり、タケダがデジタル業界と取り組んでいるプロジェクトは、まさに先を見据えた取り組みですね。
日本政府や経団連が提唱している「Society 5.0」でも、データを活用して新しい産業を作るために、コラボレーションやコ・クリエーション(価値共創)を実現させることが日本の可能性につながり、世界に向けても必要であるというビジョンを示しています。

今はデータが物事のベースとなる“データ駆動型社会”ですが、そのデータを持っているのはプラットフォーマーと呼ばれる大企業か国です。
これからの時代は、一部のプレイヤーがデータを独占するのではなく、共有して新しいマーケットを作っていく考え方が必要です。
もちろん、全てを共有するのではなく、所有と共有をしっかりわけながら、共創と競争の組み合わせをデザインしていくのが大切ですね。
官民学で連携し、データを共有財として社会に開く
岩﨑 日本が保有するデータの特徴的な点は、保健医療制度や母子手帳、健康診断、介護保険など、医療に関するさまざまなデータが蓄積されていることです。
もちろんプライバシー確保といった情報保護の観点は大切ですが、官民学で連携して全てのデータがプラットフォームでつながれば、実現できることが山のようにあると思うんですね。

宮田 おっしゃる通りで、官民学連携でデータを“共有財”として社会に開けば、新しい価値が生まれると思います。
実際に「世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター」にタケダも加わっていただいて議論していますが、そこで一つ用意しているのが「医療情報基本法」です。
違う言語で囲い込まれているさまざまな情報を、段階的にでも社会の中で流通させていく。
そして、データの活用を常に同意を求める運用だけではなく、人々の健康や医療の質の向上に向けた活用など、条件が担保される時には共有財としての利用を認める。
たとえば、災害で病院の機能が麻痺して、支援を必要とする透析患者に対して「プライバシーの問題から情報を得られないので透析できません」というような出来事が起きたとする。
でも、そこで断るのではなく「誰が、どの範囲のデータをどんな目的で使うのか」を明確にして、ログを残せばデータを適切に活用することはできるでしょう。
「デジタルバイオマーカー」で医療が変わる
宮田 もう一つ、日本が持つデータで大きなアドバンテージになるのは「健康な段階からのデータ」を蓄積していることです。それらのデータをつないで使えるようにすれば、病気になる手前から一人ひとりに寄り添えるようになると思います。

岩﨑 まさに、健康な人のデータがないと病気の人とは何が違うのか、健康な人はなぜ病気にならないのかは探れません。
血液や尿などから病気の進行等を調べた「バイオマーカー」で開発できる薬はほとんど世の中に出ており、これから有用になるのは、健康な状態の情報も取れる「デジタルバイオマーカー」。
たとえば、うつ病など症状が見えにくい疾患の場合、目の動きや脳波、起床時の状態など、いろんなデータを組み合わせることで、新しい対処法が見えるかもしれません。
宮田 デジタルバイオマーカーは、高齢者の健康状態と要介護状態の中間にあり、認知症にもつながりやすい「フレイル」状態の発見にも役立つと思います。
今は、「フレイルチェック」を人がやっているのですが、いくつか項目があるなかで大きな指標になっているのが「歩行速度」です。これは、スマホがあれば普段の歩行速度がわかるので、簡単に兆候が掴めますよね。

同じように、スマホやIoT機器などで簡単にデータを蓄積できる睡眠時間や活動量などのバイオマーカーがソリューションに変わっていくと思います。
MRの仕事はなくならない。必要不可欠な仕事に発展する
岩﨑 よく、こうしたデジタル化の話をしていると「MR(医薬情報担当者)の仕事はなくなる」と言われがちですが、私はそんなことはないと考えているんですね。
ただ、仕事の内容は劇的に変わります。2013年頃から社内でも「MRの定義はこれから変わる」と話しています。
宮田 7年前ですか! 早いですね。私もデータ活用の世界では、MRの役割も発展していくと思います。薬やドクターの知識がクラウドに格納されるようになると、MRは「一人ひとりの患者さんに、何が最善かを共に考えていく」職業になるのではないかと。
岩﨑 これからますます病態や薬のメカニズムは複雑になっていきます。
そうなると、患者さん一人ひとりを見ているドクターに日々接しているMRが、ドクターから求められているニーズを理解し、それを正しく会社に伝えられることが重要になります。
それをもとに会社が正しくアクションし、患者さんに返していく。

それに、患者さんは常に新しい治療法や臨床試験の情報を欲していますが、今の世の中には精度が不確かな情報が溢れています。
製薬会社には、正確な情報を提供する使命があり、その一翼は間違いなくMRが担うと考えています。
そのためにはMR自身が、デジタルをインフラとした新しい日本の「医療エコシステム」を正しく理解して、その一員になる必要がある。
この中に入れなかったら、何もできない状態になりかねないので、MRがそれを正しく理解するとともに、最先端のデジタルツールにも慣れてもらう取り組みも進めているところです。
宮田 将来の医療エコシステムの中で、溢れる情報の中から、相手に合わせて適正な情報を取捨選択する。薬という情報の伝え方そのものをデザインしていくことが、MRの新しい役割でもあるのですね。
MRの方々が持つ高い対人スキルで、患者さんとの接点を作りながら新しいニーズを発見する。そして、組織としては新たな医療エコシステムの構築にコミットし、新しい製薬会社のあり方をデザインするところまで踏み込んでいく。

今までの考えにとどまるのではなく、未来を見据えた新しい職種として発展し、業界だけでなく日本や世界にイノベーションを起こせるといいですね。
岩﨑 日本にはイノベーションが生まれる土壌はあると思うんです。あとは、リードする人が勇気と覚悟を持って行動に移すだけ。
我々がそのリーディングカンパニーになるというのは当社の決意でもありますし、私はその姿を次世代に見せていきたいと思っています。
(編集:海達亮弥 執筆:田村朋美 撮影:依田純子 デザイン:小鈴キリカ)
武田薬品工業 | NewsPicks Brand Design


