
変革期を生き抜く人の特徴は「モラリスト×エキスパート」
立正大学 | NewsPicks Brand Design
2020/1/8
東京・品川区と大田区、埼玉・熊谷などにキャンパスを構える学校法人立正大学学園が、11月26日(火)に「立正大学学園開校150周年プロジェクト発足イベント」を開催。
2022年の同プロジェクトの概要、大学とコラボ事業をする協賛団体・企業の紹介、新学部設立の構想のほか、在学中の学生に向けた対談も行われた。
立正大学学園は2022年に開校150周年を迎えるにあたり、新学部の設立、地域や企業との連携、キャンパス環境の拡充など150種類の事業やイベントを実施するという。
立正大学学園は2022年に開校150周年を迎えるにあたり、新学部の設立、地域や企業との連携、キャンパス環境の拡充など150種類の事業やイベントを実施するという。

その初発となる本イベントでは、プロジェクトに参画する熊谷市観光協会、しながわ観光協会、GWC、スリーエムジャパン、リバースプロジェクト、LINE Pay、レナウンの7つの団体や企業が登壇。各社・各団体が立正大学とのコラボレーション事業への意欲を語った。
その一つ、スリーエムジャパンのコンシューマー製品マーケティング部・石橋愛子氏は「使用済み製品の回収リサイクルプログラムを学生の皆様と一緒に盛り上げたい」と話した。
その一つ、スリーエムジャパンのコンシューマー製品マーケティング部・石橋愛子氏は「使用済み製品の回収リサイクルプログラムを学生の皆様と一緒に盛り上げたい」と話した。
熊谷市観光協会の藤間憲一会長は、「今は各地区でもさまざまなデータが個々に乱立しています。それを一つのデータに集約させ、まちづくりの向上につなげたい。新学部に期待しています」と、立正大学にエールを送った。
また、望月兼雄理事長による立正大学の歴史や、学長であり新設学部の学部長となる吉川洋氏による新設学部「データサイエンス学部」(仮称)構想への意気込みなど、立正大学の過去・現在・未来が分かる講演も。
さらにスペシャルゲストとしてお笑い芸人のキングコング西野亮廣氏の白熱トークや、吉川学長と作家の高橋源一郎氏による対談も行われた。どちらも、AI時代を生き抜くための知恵と勇気を与えてくれる内容で、会場を大いに沸かせた。
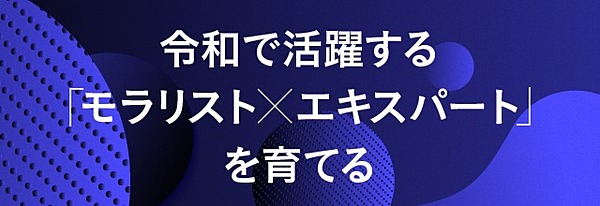
イベントの目玉の一つは、吉川学長と、作家の高橋源一郎氏との対談。高橋氏は、立正大学品川キャンパスからほど近い、白金高輪にキャンパスのある明治学院大学で教鞭をとっていた。ともに仏教系、キリスト教系と宗教系の大学であり、歴史の古さと伝統でも近しい両大学。2人が学生に感じるものにも、共通点があった。

今求められているのは、社会の変化に対応できる力
吉川 私どもは150周年を前に、「アクティブ&カラフル」をスローガンに新たなステージに進もうとしています。
立正大学の学生は、とかくおとなしいイメージがありまして、そこをもう少し積極的になってほしい、そして、多様に生きてほしいという思いがあります。
高橋 僕も、明治学院大学の学生さんを教えていた時、同じように感じました。僕らの学生時代は反抗的な人も多かった。それが今では、良くも悪くも実におとなしい。優しくて素直で真面目ですし、学生時代の僕と違ってちゃんと授業にも出るし、態度もいい(笑)。
ただ、そこに少し不安も感じます。社会生活で突発的な仕事を振られた時、日常生活で環境が激変した時、乗り越えられるのか、と。
例えば、学生さんを見ていると、インターネットで非難や中傷をされないよう、つまり目立たないよう、自分で我慢してコントロールしている様子が見られます。そうではなく、もっと大胆になってほしいんですよね。

吉川 立正大学としては、石橋湛山先生の時代から、学生には「モラリスト×エキスパート」を目指してほしいと伝えています。モラルを持ちつつ、大学を出た後は、専門的な知識を身につけてもらいたい。
そのためにも、学生が社会に出てキャリアを構築する上で、役に立つ講義なり教育なりを提供するのが、我々の義務です。
高橋 今後、社会でサバイブするためには、時代の変化に対応できる力がますます求められてきますからね。
吉川 まさに、そんな力を身につけていただきたいんです。遡ると、明治時代以降は、英語がしゃべれる人が必要になり、大学など高等教育でも英語教育を行うようになりました。そして現代では、データを活用することで、変化に対応する力が求められています。
高橋 今、我々がお話ししている場所は石橋湛山記念講堂ですが、石橋湛山もまさしくデータを活用したジャーナリストでした。石橋湛山は、第二次世界大戦中、どうやって反対するかを考えに考えた結果、データを出して抵抗しました。
つまり、「無謀な戦争をしていると、この小さな日本の国は滅んでしまう」ということを、データをもって理路整然と証明したんです。そこまで根拠を示されると、軍事的な政権でも簡単には潰せないんですよね。
さらにいえば、彼は敗戦する前から、戦後回復の準備についても考えていました。

今の社会は、学生たちにいろんな要望を伝えてきます。それを丸ごと受け入れるのではなく、「これはいい」「これはダメだ」「なぜダメなのか」と情報を取捨選択してよく考えた上で、社会に送り返すことが大事。
結局、何か社会の制度が変わった時、「社会の言うことを聞いていたからそうなった」って後から文句を言ってもダメなんです。
吉川 おっしゃる通り。大学でも、その基礎となる知識や考察力を、学生には十分に身につけてほしいと考えています。その一つとして、我々が今考えているのは、「データサイエンス学部」(仮称)という新設学部での学びです。

データを解析して、価値を生み出していく
吉川 データサイエンスとは何かというと、コンピューターの発達によってできた新しい学問分野です。近年発達したビッグデータは、膨大なデータの収集を可能にしました。さらに、そのビッグデータを解析することも可能になり、コストも大幅に下がってきました。
例えば、株価。私の専門分野である経済でいえば、株価の分析は数十年前からなされてきました。
その分析量を比較すると、数十年前の株価のデータは、詳しくても1日1日のデータ。それが現在では、0.5秒単位で全ての銘柄がいつどれだけ取引されたかというデータが簡単に収集され、分析されるようになってきたんです。
21世紀を迎えて、データが我々の社会を変えつつあります。データを分析することで、どんな価値を生み出すのか。それがこの新設学部の核になっています。
全方位、ありとあらゆる価値を創造することが考えられますが、中でも立正大学では、スポーツ、観光、社会、ビジネスの4本の柱を立てて、データ解析を使って価値を生み出していこうと考えています。
データサイエンス学部でも、それ以外の学部でも、私たちは世の中の学生が立正大学で学び、社会に出て行った時に社会で評価される学生になってほしい──そんな学生を育てるのが、我々の役割だと思っています。

イベントのとりを飾ったのは、キングコング西野亮廣氏によるスペシャルトークだった。お笑い芸人の他、絵本作家としての顔も持ち、さらに映画製作や美術館の創設、国内最大級のオンラインサロンを主宰するなど、芸能活動の枠を超えて活躍。
中でも3年前、自らが脚本を書きプロデュースした絵本『えんとつ町のプペル』は累計発行部数40万部と、大ヒットを記録した。
西野氏はこの経験を振り返りながら、現役大学生に向け、社会で挑戦するために必要なことを熱弁した。
中でも3年前、自らが脚本を書きプロデュースした絵本『えんとつ町のプペル』は累計発行部数40万部と、大ヒットを記録した。
西野氏はこの経験を振り返りながら、現役大学生に向け、社会で挑戦するために必要なことを熱弁した。

社会人の挑戦を阻むものとは
「僕はどちらかというと挑戦する人に対して『頑張れ頑張れ』って言う側なんですけど、背中を押すからにはそれなりの責任を伴うなと思って」
登壇した西野氏は、会場にいる学生たちを見渡しながら、語り始めた。
「これから社会に出て活躍をする上で、みんなの挑戦を止めてしまうものは何なんだ、阻むものはいったい何なんだ、と。これ結論は1つで、“お金”ですよ。
たとえば洋菓子店をオープンしたら、その洋菓子店の家賃など必要経費が捻出できなくなってしまった時点で、この挑戦は強制的に終わりになっちゃう。
お笑い芸人だって、生活費を捻出できなくなっちゃったら、芸人活動は強制的に終了。それが、どんなにいいパフォーマンスをしていようが、そこをクリアしない限りは挑戦が途絶えてしまう……ということですね。
つまるところ、挑戦を続けようと思ったら、『お金の問題』を解き続けなければならないんです。しかし、残念ながらこの国は、小学校の頃から社会に出るまで、お金の勉強をしない。カリキュラムに入ってないんです。
新時代の若者はお金の集め方がよく分からないっていう状態で社会に出てしまって、挑戦に失敗する確率をグッと上げられた状態で、『じゃ、戦ってください』と言われてしまっている。これはあまりにもかわいそう」

ここで西野氏は、自身の絵本作りの体験を振り返った。約3年前、『えんとつ町のプペル』という絵本を製作した際、従来の絵本の作り方を大きく変えて、約40人の分業制という方法を考えたという。
その時、最初に着手したのが「40人分のスタッフのお給料」の用意だった。
「40人分のスタッフさんのお給料を用意する。つまるところ、資金調達ですね。どうやってお金を集めたかというと、“クラウドファンディング”です。
今、お金を集める手段として、働いて稼ぐ、銀行など金融機関から借りる、クラウドファンディングで集めるという、3つの選択肢がある。僕が選んだ手段は、クラウドファンディングでした」
結果、西野氏は延べ1万人くらいから、合計約5600万円という大きなお金を支援してもらい、制作にローンチできた。

クラウドファンディングは「信用をお金に両替するための両替機」
なぜ、これほどの大金が西野氏に集まったのか。ポイントを2つ挙げた。
「1つ目『お金とは何か?』という問いに対して答えを持つこと。2つ目は『クラウドファンディングとは何か?』──この問いに対しても答えを持たなきゃいけない。
結論から先に言いますと、お金とは信用ですね。『信用を数値化したものがお金である』という言い方になるとちょっと難しいんですけど。まず『クラウドファンディングとは何か?』という問いに対しての答えを明確にしておきます。
クラウドファンディングって聞くと、みんな『なんとなくお金を集められるやつなんでしょ?』ぐらいにぼんやり思ってるかもしれない。けど、集金装置じゃないんです。『信用をお金に両替するための両替機』ですね。『あなたの信用をお金に両替しまっせ!』という両替機能しかついていないんです」
しかし、誰でもクラウドファンディングをしたらお金集められるという甘い話はない。社会的に知名度の高い人でも100万円集まってる人もいれば、1円も集まってない人もいる。
では、クラウドファンディングで集金できなかったタレントなど著名人は、信用に値しない人物なのか?
「タレントさんってすごく立場が弱くて。彼らの収入源って、スポンサーなんです。スポンサーさんが番組制作費払って、番組の制作費の一部がタレントさんのギャラになっているので、スポンサーさんに対して都合の悪いことは言えないんです。
つまり、グルメ番組で不味いもの食べても『美味しい』と嘘つかなきゃいけない。それが仕事です。けど、今はTwitterとか食べログとかぐるなびとかでバレちゃう。結果、彼らの信用度は下がってしまいます」

信用度を下げないためには、自分が嘘をつかないといけない状況に身を置かないこと。そういう仕事を潔く断ることが、信用を得るため、ひいては、お金を集める上では大事になってくるのだという。
「信用というものが非常に重要だから、嘘はやめましょうね、という話です。ここを気をつけて挑戦していくと、いい結果が出ると思います」
「お金の勉強」をやめないで
さらに、壇上でもう一つ大事なことを教えてくれた。いくつになっても勉強を続けることの大切さだ。
「クラウドファンディングは、今でこそ認知度がありますが、3年前はまだまだ『怪しい』だの『よく分からない』『嫌い』だのと言われ一般社会から敬遠されていました。その理由を因数分解していくと、“知らない”からなんですね。
僕はこれ、結構ヤバいなと思っていて。お金に関して知らないことを増やしてしまうと、お金の新しい選択肢を嫌ってしまって、どんどん貧しくなるんですね。それが、挑戦を阻んでいくんです」

新しいお金の稼ぎ方はどんどん生まれてきている。それについていかないと、お金のリテラシーは落ちていく一方だ。
「僕たちは30代になろうが、40代になろうが、50代になろうが、60、70、80、90になろうが、基本的には勉強をやめちゃ駄目だ。
クラウドファンディングやオンラインサロンのことを知らなかったら勉強しなきゃいけないし、ブロックチェーンのことよく分かってなかったら、その時点で勉強しないといけない。
それを、この国の人はだいたい大学卒業した瞬間に勉強すること自体やめてしまう。そしてどんどんお金のリテラシーが落ちていって、新しいお金の稼ぎ方っていうのを放棄して、次の世代をつぶしにかかるっていうサイクルに入ってく。
次の挑戦を殺さないため、いくつになっても勉強をし続けなきゃ駄目だと思います」
(構成:桜田容子 編集:奈良岡崇子 写真:桑原美樹 デザイン:堤香菜)
立正大学 | NewsPicks Brand Design


