
京大がスタートさせた「Society5.0時代」の人材育成
京都大学 | NewsPicks Brand Design
2019/6/21
ビジネスで大きな武器となるITだが、その基礎を理解するIT人材は絶対的に不足している。日本の大学教育をリードする京都大学では、10年前からIT教育に注力。その最先端の取り組みとして、この4月からは企業と共同で新たに「情報学ビジネス実践講座」をスタートさせた。
社会ニーズに応えるIT教育を大学として提供することを使命とし、Society5.0(※)時代に向けて大学として何を教育していくのか。IT教育にかける思いを京都大学情報学研究科の山本章博教授に聞くとともに、共同パートナー企業である日本総合研究所常務理事の西口健二氏から企業が求める大学のIT教育について意見を伺う。
社会ニーズに応えるIT教育を大学として提供することを使命とし、Society5.0(※)時代に向けて大学として何を教育していくのか。IT教育にかける思いを京都大学情報学研究科の山本章博教授に聞くとともに、共同パートナー企業である日本総合研究所常務理事の西口健二氏から企業が求める大学のIT教育について意見を伺う。
※Society5.0:日本政府が提唱する未来社会のコンセプト。IoT、ロボット、人工知能(AI)、ビッグデータなどの新しい技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れてイノベーションを創出し、社会的課題を解決する新たな社会のこと。

10年前から取り組む「ITリテラシー教育」
山本 世界的にAI・IT関連人材のニーズが高まる中、日本ではIT人材が絶対的に不足していることが深刻な問題となりつつあります。IT人材育成は、今後の日本の国際競争力にも大きな影響を与えるものであり、緊急性の高い国家課題のひとつです。
最近になってようやく国が主導となり、IT人材育成に乗り出し始めました。文系理系を問わない、基礎的な教養として「ITリテラシー教育」を本格的に推し進めようとする動きが活発になっています。
京都大学では、国が教育政策として進めようとしているITリテラシー教育に、10年前から取り組んできました。2009年にITリテラシー教育の拠点として「高度情報教育基盤ユニット」を設立。これは、情報学研究科、経営管理大学院など複数の部局が協力して全学部向けのIT教育を提供する組織です。
それまでの大学における一般的な情報基礎教育というのは、コンピューターの構造や使い方を学ぶ「コンピューターリテラシー」が主体でした。
しかし、高度情報教育基盤ユニットのコンセプトは、「コンピューターを使いこなすのではなく、情報を使いこなす」こと。「情報の使い方」を基軸としたITリテラシー教育は、当時としては非常に画期的なものでした。
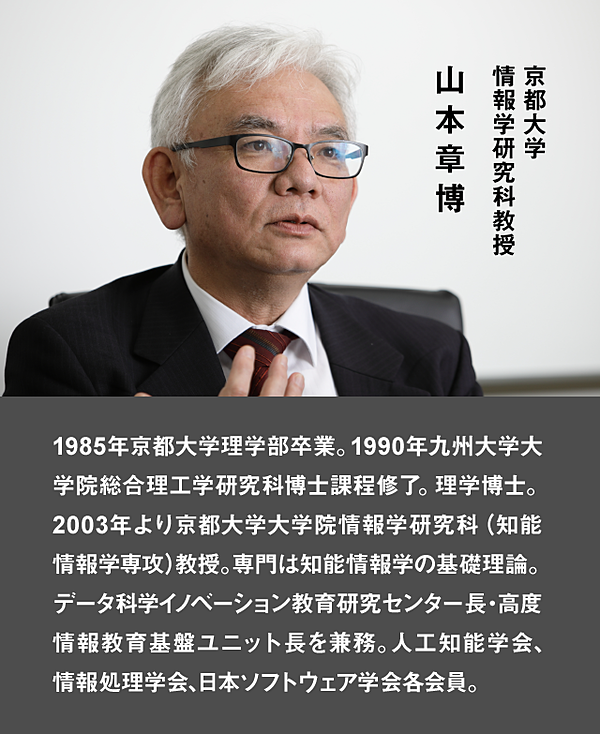
京大が目指したのは、IT(情報科学・計算科学)と情報社会制度・ビジネスに関する知識を持ち、イノベーションに貢献する人材を育成することです。その実現のために、学部レベルにとどまらず大学院レベルの高度な講義を行っています。
例えば、「情報の基礎」という授業では、情報がどう流れてきて、それをどう獲得するのか。獲得した情報をどのように正確に伝えるのか。その根本原理を学びます。
ほかにも「データ分析」「経営管理」「知財」など、情報を使い管理する上で必要なITリテラシーを網羅したカリキュラム設計となっています。
加えて、情報やITを使いこなすだけでなく、それらを使って社会のニーズを見つけ出す発想力も重要です。情報の基礎を学ぶことは、そういう柔軟な発想力を育てることでもあります。
文理を超えた「教養」としてのIT教育
一方で、京大は、2016年に文部科学省の「数理及びデータサイエンスに係る教育強化」拠点6校の1つに選定されました。
文科省は、AI・ビッグデータ解析などの技術革新には、情報学・統計学・数理科学の3分野への基本的な理解が不可欠だと考えています。この施策の背景には、これらの教養が文系・理系を問わず、社会で活躍する人材に求められていることがあります。

拠点校となったことで、京大は2017年、学部生向け全学共通教育を提供する「国際高等教育院」の附属センターとして、「データ科学イノベーション教育研究センター」を設置。
文理を超えた全学共通教育科目として、学部生から大学院生までを対象にデータサイエンスの講義を提供しています。
情報系が人文系や自然科学系、外国語系などと同列にリベラルアーツとして学べるようになりました。京大における教養としての「ITリテラシー教育」の基礎が完成したといえます。
大学と企業が連携した実践的なIT教育
さらにその進化形として、4月からスタートしたのが「情報学ビジネス実践講座」です。
これまで京大が培ってきた「ITリテラシー教育」、文理を問わない「全学共通教育」をベースに、企業の協力を得て、実社会での事例を踏まえながら実践的に学ぶことができるというのが最大の特徴です。

これまでの京大のIT教育に「情報学ビジネス実践講座」が加わることで、学理と実践の両面から「ITリテラシー」への理解を深めることができるようになりました。

企業の「生の声」で学ぶ、実践的なIT
具体的にどんな授業を行っているのかというと、例えば「情報と社会」の講義では「業務のIT化とは何か」を企業の事例から学生は学んでいきます。
一例をあげると、各業界はデータや情報をどのように捉え、それを扱うITシステムをどのように構築してきたのか。急速に進行するIT化にどう対応しているのか、具体的なケースを交えて講義を行います。

企業活動の判断に欠かせないビッグデータの解析については、テクニックがもちろん重要ですが、共通教育として学生に本当に学んでほしいのは、企業活動におけるIT(情報科学・計算科学)の本質的な役割です。
それを知るには、さまざまな業種におけるIT化の話を、企業の“生の声”として聞くことが一番の近道でしょう。
講義形式だけでなく、ワークショップ形式の授業も取り入れ、実例をもとに考えたり、討論する機会も多くあります。
ITは語学並みの教養である
2020年には先端IT人材が約5万人、一般IT人材は30万人不足するとも言われています(※)。
※内閣府「人工知能技術戦略実行計画の策定について」(2018年4月5日)
一方で、現代においてITリテラシーは語学並みの教養であり、現代の「よみかきそろばん」として、将来のキャリアプランには欠かせないものです。
小学生からプログラミングなど新しい情報教育が義務化されますが、今の中高生世代はそこからこぼれ落ちてしまっています。彼らをすくい上げるという意味でも、大学でITリテラシーを学ぶチャンスがあることは、大きな意義があります。
これまで京大では、実践的なIT教育を体系化し、進化させてきました。社会のリアルな企業活動のITと結びつくことで、「情報を使いこなす」教育がさらにレベルアップし、社会に貢献するIT人材を輩出できるようになるはずです。
それこそが、これからの大学教育に求められる役割のひとつです。大学のIT教育のあり方をリードしていくことは、京大の使命でもあると考えています。
企業が抱く、IT人材への危機感
企業との産学共同講座として設置された京大の「情報学ビジネス実践講座」。実は、この話を持ちかけたのは企業サイドである日本総研だった。ITが企業の競争力を左右する時代において、大学教育に企業が求めるものは何か。同講座の協力企業の1社である日本総研の常務理事の西口氏が語る。
西口 産学共同講座として「情報学ビジネス実践講座」が生まれた背景には、企業の持つ「大学のIT教育」への危機感があります。
大学が教える学問だけでは、実社会の実務にはすぐに結びつかない。IT人材が数十万人規模で不足すると言われる中、大学教育のあり方に産業界として疑問を感じていたのは確かです。

学生が企業に入ってすぐに求められるスキルは、かなり実務的です。企業にはどんなシステムが導入されていて、それをどのようなステップで開発するのか、ITにかかわるさまざまな経営判断はどうするのか──。
特にITはブラックボックス化していて、全体の流れを想像しにくい領域です。だからこそ、大学教育で基礎を理解しておくことが、社会に出たときに重要なのです。
また、企業としては、学生には文理関係なくITリテラシーを理解しておいてもらいたい。例えば、文系学生が多く就職する銀行。以前にも増してITの重要性が高まり、ITが銀行経営にとってますます大きな役割を果たしていくはずです。
体系的な学問とビジネスの実務の両輪
以前からITリテラシー教育に取り組む京大では、産業界の危機感にも強く共感してもらえました。それが、学問と実務の両輪でIT人材の育成を目指す「情報学ビジネス実践講座」となりました。
講義にはITを作る企業と使う企業など業種のバランスをとりながら、ANAシステムズ、NTTデータ、DMG森精機、東京海上日動、日本総研、NECの6社が協力企業として参加しています。

京大と行ったカリキュラム設計では、「将来につながる体系化したものをつくりたい」という、京大の並々ならぬ熱意も感じました。
今はグーグルが最先端でも、企業はその次を見据えています。 新しい概念や技術が生まれることも想定し、更新していけるカリキュラムを想定してつくりあげる点は、「さすがは京大」という印象でした。
IT教育で先端を走る京大と我々企業が組むことが、将来を担う学生たちにとって有益な学びとなってほしい。そして、より多くの優れたIT人材を育てて、社会で活躍してもらいたいと思っています。
京大といえば、いわずとしれた日本のトップ大学。その京大がIT分野の教育において、10年も前から先見の明を持って取り組んできたことは、「チャレンジし続ける京大」というイメージ通りだ。
「実践的なITの役割を知り、それを使いこなす」といった、これからの社会で誰もが必要とする知識やスキルこそ、大学教育で習得すべきもの。その先見性こそが、猛スピードでグローバルに進化するIT社会を勝ち抜く人材を育てていく力といえるだろう。
「実践的なITの役割を知り、それを使いこなす」といった、これからの社会で誰もが必要とする知識やスキルこそ、大学教育で習得すべきもの。その先見性こそが、猛スピードでグローバルに進化するIT社会を勝ち抜く人材を育てていく力といえるだろう。
(編集:奈良岡崇子 写真:合田慎二)
京都大学 | NewsPicks Brand Design

