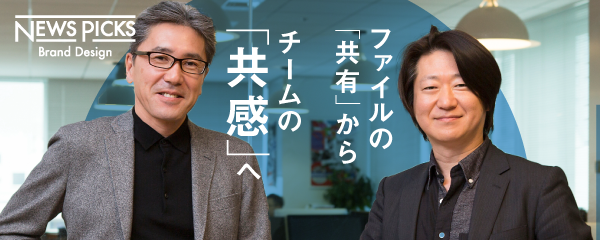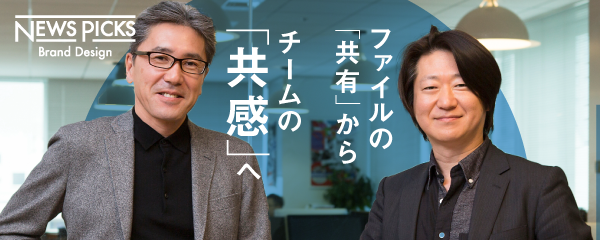Dropboxは「働き方」をどうアップデートするのか
2019/2/7
昨今叫ばれる「働き方改革」に、デジタルツールはいかに貢献しうるのか。日本マイクロソフト、Apple Japanを経て昨年Dropbox Japan代表取締役社長に就任した五十嵐光喜氏と、外資系コンサルティングファームを渡り歩き、2018年6月までPwCグループでデジタルサービス日本統括を務めた松永エリック・匡史氏がデジタル時代の組織とツールの重要性について語り合った。
「ファイルの同期」から「チームの同期」へ
──昨今、働き方改革の文脈で、「業務の効率化」や「知的生産性の向上」といったキーワードが、改めて見直されています。経営コンサルティングとしてデジタルイノベーションの現場を見てきた松永さんは、どのように感じていますか。
松永 今は本当に大きな変革期で、コンサルティング業界でも、近年はUI(ユーザーインターフェース)、UX(ユーザーエクスペリエンス)のデザイナーやグラフィックレコーダー、スマホアプリのエンジニアのような新しい人材と協業しながら、経営課題に着手することも増えてきました。
これだけITが浸透してくると、個人のデバイスの中には最先端のツールが入っている。でも会社に行くと、ユーザビリティの悪いツールがある。「なんで会社のやつはこんなに不便なのか」ということに、人々が気付き始めているんです。今が過渡期だと感じています。

バークリー音学院出身のプロギタリストという異色の経歴を持つアーティストであり、放送から音楽、映画、ゲームから広告まで、幅広くメディア業界の未来をリードするメディア戦略コンサルティングのパイオニア。アクセンチュア、野村総合研究所、IBM、デロイトトーマツコンサルティング、PwCコンサルティングでのデジタルサービス日本統括を経て、ONE+NATION Digital & MediaのCEOとしてデジタル時代のイノベーターとして活動。2019年4月から青山学院大学地球社会共生学部教授。青山学院大学国際政治経済学研究科修士課程修了。
──なるほど。働き方についてはいかがですか。
松永 同時に、働き方にも変化が生じています。従来の上意下達式ではなく、個々人のスキルやネットワークを活用したボトムアップのプロジェクトが力を発揮するようになってきている。
今まで会社が組成してきたプロジェクトが、今では自然発生的に生まれる。そうして実力があって、高感度な人間が集まって、プロジェクトが組成されて、目標に到達していく。そんな組織の枠を超えた「チーム」での働き方が広がっているように感じています。
五十嵐 我々の言葉で言えば「ファイルの同期」から「チームの同期」へとシフトしていくのは自然な流れだと思っています。

早稲田大学教育学部卒。1987年に株式会社東芝に入社。2005 年から日本マイクロソフト株式会社で、サーバー クラウド製品などの責任者を務め、2008年以降、業務執行役員サーバー プラットフォーム ビジネス本部 本部長、業務執行役員エンタープライズ パートナー営業統括本部 統括本部長、業務執行役員コンシューマー&パートナー グループ コミュニケーション パートナー営業統括本部統括本部長などを歴任。2013 年からApple Japan 合同会社で法人営業本部長を務めた後、2017 年から現職。2018年からはアジア太平洋地域全体の営業も統括。
──「チームの同期」とは具体的にどういうことでしょうか。
五十嵐 一言でいえば、メンバー間のコミュニケーションが活性化するということでしょうか。ほとんどの仕事は1人では成立しませんから、自分の考えや、ウェブ上のファイルをチームでシェアしますよね?
具体例を挙げると、今社内で「デジタル・ワイガヤ」という言葉を作っています。「ワイガヤ」は、ホンダさんが最初に作った言葉ですが、所属も部署も関係なく、集まって意見を言い合う。そんなことをデジタル空間で行えるということですね。
松永 ディスカッションに参加するきっかけはいくつもあると思っていて。例えば、プロジェクト自体に興味があるケース、業界や業種に関心を持つケース。あとは、人、ですね。面白いことをしている人に興味を持つケース。まずは参加することが一番大事で、次にどの切り口でプロジェクトに参画するか、自分は何をしたいのか考える人が勝つ。
五十嵐 現在のビジネス環境は国境も時間帯も関係なくブレーンストーミングして何かを作っていく。単なるファイルの同期を超えて、考えの同期をシームレスに行っていける環境を構築する。それが今、私たちが考えていることですね。
コンシューマービジネスへの誇り
松永 これまでのIT業界では、toB向けの企業がトップダウンで高価な業務システム、たとえばERPやSCM、CRMといった大型パッケージをクライアントに導入させるという構図がありました。
しかし、コンサルやSIerに丸投げのツールのユーザビリティは悪く、必ずしも、業務の効率化に直結しているとは言い難い状況があった。逆に業務をITに追われてしまうようなことも珍しくない。その結果、今度はRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)のようなムーブメントが来ているのです。
でもこれって、「改悪したものを改善している」ような不自然さを感じていて。だからこそ個々のコミュニケーションを円滑化する、ユーザビリティの優れたツールは本当に必要とされていると思います。
五十嵐 我々Dropboxは、コンシューマービジネスとして始まりました。最初は「どこからでも、自分のファイルにアクセスできたら」という個人の発想から生まれました。実はそこに、誇りを持っていまして。
C向けのサービスって、嫌われたら、お客様は、あっという間にいなくなるんです。ですので、ユーザーが使いやすいっていったところに関しては、ものすごい自信を持っています。
松永 ツールはプロジェクトメンバーのコミュニケーションを活発化させるものでないといけない。意味がないんです。「使いやすさ」はプロジェクトや企業の現場に浸透するための大きな分かれ道だと思います。
五十嵐 ツールを導入することが目的ではなく、使うことが目的ですからね。
松永 そうですね。もちろん、これまでもファイルを「共有」するツールは存在したわけなんですが、チームメンバーの「共感」を促すものではなかった。企業の理屈で便利なのと個人のレベルで便利なものは残念ながら同じでないのです。
──Dropboxというとまだ一般的には「ファイルを共有するソフト」というイメージがあると思うんですが、そこはいかがでしょうか。
五十嵐 Dropboxで共有できるのはファイルですが、そのファイル周辺には補完するための「メッセージ」や「考え」がありますよね。それをシェアできるソリューションとして、私どもは「Dropbox Paper」※という、いわば共有ノートブックのようなツールも提供しています。したがって2つのツールの組み合わせが大切です。
ブラウザ上でドキュメントを作成できるツールです。オンラインで動作することもあり、1 人でなく複数人で同時に 1 つのドキュメントを編集することができます。
具体的には、議事録のまとめ、To Doリストやタスクの整理、アイデアのブレーンストーミング等、チームのワークスペースとして活用できます。
※Dropbox Paper : ブラウザ上でドキュメントを作成できるツール。オンラインで動作することもあり、1 人でなく複数人で同時に 1 つのドキュメントを編集することができる。議事録のまとめ、To Doリストやタスクの整理、アイデアのブレーンストーミング等、チームのワークスペースとして活用が可能。
松永 必要なのはファイル共有というより、情報共有なんですよ。だから、コミュニケーションをシンプルかつ実のあるものにするには、共有するファイルの内容も工夫する必要がある。ワイガヤを引き起こすキッカケにならなければいけない。
僕の場合は、1枚のサマリーを作って「みんなでたたいてください」と共有する。自分を主張するのではなく、みなで議論するためにシンプルにします。必要であれば資料共有をシンプルにし、メッセージで補足する。例えば、目を通してほしいものに優先順位をつけるとか、目立つように工夫するとか。
五十嵐 そうですね。情報共有をしたうえでの、デジタルプロジェクトルームみたいな環境をDropboxは目指しています。
「みんなの意見を聞かせてほしい」とPaperでメッセージを添えてDropboxでスライドやサマリーを共有しておけば、いつ、どこにいても、「ワイガヤ」しながら読んだ人が自分のコメントを入力することができる。共有者はそれを読んで、新たな視点を得る。ディスカッションの元はコンテンツをストレスなく確認、編集できるということです。
松永 ツールがあって、使用手順も決められているのは、昔の使い方なんです。使い方はツールの提供者が考えるというよりもユーザー自身が考えて、活用して、成長する。ユーザー同士が便利な使い方で盛り上がれば、そこから自然とコミュニケーションが生まれていく。
一番ベストなのは、例えばDropboxが考え付かないような活用方法をユーザーが作る。ユーザー同士がその方法を共有し、さらに便利にしていく。そのコミュニティが別の仕事やアイデアに発展していく。それが起こりうるプラットフォームが一番強いのではないかと思います。
Dropboxは「働き方改革」とどうリンクするのか
──「働き方改革」が盛んに叫ばれていますが、どのような場面でDropboxは寄与しうるとお考えですか。
五十嵐 まず、個人的な感想ですが、「働き方改革」って上から目線ですよね。働き方を変えたまえ、というか。でも、本当に大切なのは部門別の売り上げや、社員の総労働時間ではない。本質的には一人ひとりの働きやすさやコミュニケーションの取りやすさが一番大切なのかなと。
やっぱり生産性が上がっていると思うときって、集中しているときなんですよね。その結果として企業の生産性につながっていくのであれば、個々人の行為をサポートするツールを提供するのが我々の役割ということです。要するに、トップダウンかボトムアップかというアプローチの違いです。
松永 その違いはすごく大きいと思うんですよ。去年、リンダ・グラットン ※ と一緒にパネルディスカッションをしたときに「日本の企業の評価制度についてどう思うか」と聞いたら、彼女が一言言ったんです。「誰の人生なの?」と。
要は自分の人生を生きろということです。僕から言えば当たり前のことなんですけど、それが今、個々人の働き方のトレンドになりつつあるんじゃないでしょうか。そうした社員の動きを許容できるか否かが、これからの企業の分かれ道だと思っています。
※リンダ・グラットン:ロンドン・ビジネススクール教授で人材論、組織論の世界的権威。著書に『ワーク・シフト』など
五十嵐 私自身、前職であるApple時代に大事なことを学びました。
ある家具屋さんでは、社員の方がお客様と接するときに、売り場共有の重い専用機を持ち出して在庫確認をしていました。そのお客様がそれを iPod Touch に切り替えて店員全員が持つようにしたのです。誰でもいつでも簡単にすばやく在庫確認できるようになったのはもちろんですが、その結果一番変わったのが社員の表情だとお伺いしました。自分の仕事のスタイルに対する自信が生まれてきた。お客様への姿勢にも表れて、お店全体にも活気が出てきました。
また、地下鉄で夜間大変な保線作業を行っている社員の方が、仕事で使っているiPadを家に持って帰ったら、自分の子どもが言うんですね。「お父さんカッコいい」。その結果、自分の仕事に対する誇りが上がる。そういった要素も、生産性に大きく寄与するはずなんです。その蓄積が、本質的な企業力につながっていくと思いますね。社員である前に個人なんです。
インパーソンのコミュニケーションが洗練されていく
──Dropboxのようなツールを有効活用することで、ビジネスにおいて直接的なコミュニケーションはどのように変わっていくと思われますか。
松永 より精度の高い「会う」というコミュニケーションができると思います。今までは、中身のない会議も多く、“無駄に会い過ぎていた”側面もあるのではないでしょうか。
これからは、多くのコミュニケーションがデジタル上で完結する分、直接的なコミュニケーションの熱量は上がっていくと思います。
五十嵐 もちろんより重要になっていくと思います。
互いに意見を戦わせるのは、実は勇気が要りますよね。みんな、ネガティブコメントを受け取りたくないですから。だから当たり障りのないことを言いがちです。そうすると本質的な議論にはなりません。
何かを主張する、アイデアを出すということは、同じぐらいの気持ちで傾聴しないといけない。自分の誤りとか、情報不足、視点の不足も真摯(しんし)に受け止める勇気がないといけない。
そこで多分、直接的なインパーソンのコミュニケーションが大切になってくるのでしょう。すべてのコミュニケーションが言葉だけだと、感情が伴わない分、エスカレーションしてしまうから。
松永 たしかにそうですね。
五十嵐 あと、私が個人的に感じているのは、特に日本だと、自分自身とロール(役割)を同一化しがちなんですね。でも海外のビジネスシーンを見ると、双方は分けて考えられていることが多い。例えば、私個人と、私のロールは違うんです。
そういう分割ができると、ロールとして持っているアイデアを「どう思う?」と共有したときに、どんなにたたかれても、自分はその対話をコーディネーションしている立場なので「たたいてくれてありがとう」となる。
こういった自分自身の保ち方を身につけるためにも、フェイス・トゥ・フェイスのミーティングや会話はより重要になっていくと思うんですよね。
(編集:中島洋一 構成:吉田直人 撮影:工藤裕之 デザイン:砂田優花)
この記事はDropbox Business国内販売総代理店のSB C&S株式会社のスポンサードにて作成されました。