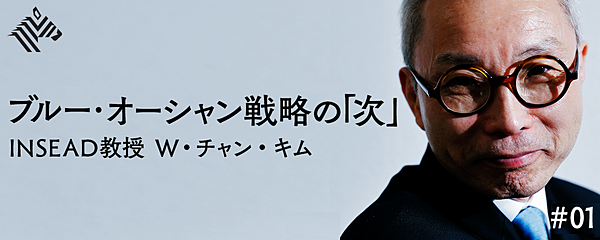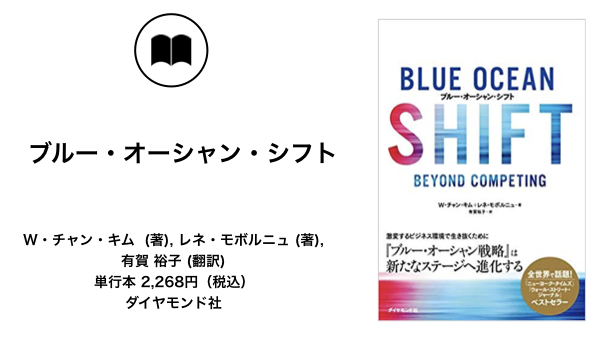【チャン・キム】ミレニアル世代へ。2つの重要な伝言
2018/11/15
NewsPicksの読者なら「ブルー・オーシャン戦略」という経営戦略論を聞いたことがある人も多いだろう。
ブルー・オーシャン戦略とは、INSEAD(欧州経営大学院)教授のW・チャン・キムとレネ・モボルニュが著したビジネス書、およびその中で述べられている経営戦略論で、競争者のいない新しい価値の市場を創造し、ユーザーに高付加価値を低コストで提供することで、利潤の最大化を実現する戦略だ。
既存の競争軸での価格競争を避け、新しい価値と価格競争力の双方を追求した“新しい価値の組み合わせ”を提供する市場を「ブルー・オーシャン」と呼ぶ。
反対に、多数の競争者で、同じ競争軸で激しい「血みどろ」の競争を繰り広げる既存の市場を「レッド・オーシャン」と呼ぶ。
ブルー・オーシャン戦略を実践する上で重要なポイントは、”技術革新“ではなく、新しい価値市場を創造するための「バリュー・イノベーション(価値革新)」という考え方により、市場の境界線を引き直すということだとチャン・キム教授は説く。

W・チャン・キム(W・Chan Kim)
INSEAD教授、同校ブルー・オーシャン戦略研究所(IBOSOI)共同ディレクター。世界経済フォーラムのフェローを務めるほか、ブルー・オーシャン・グローバル・ネットワークの設立者でもある。欧米・アジア太平洋地域の数々の多国籍企業において、取締役や顧問を歴任。経営思想界のアカデミー賞と言われる「The Thinkers 50」で、世界のマネジメントの大家トップ3に名を連ねる。2005年に発表したレネ・モボルニュ氏との共著『ブルー・オーシャン戦略――競争のない世界を創造する』が世界的ベストセラーに
『ブルー・オーシャン戦略』は44カ国語、累計360万部超を売上げ、大きなうねりを生み出した。
この本の発売後、世界中のリーダーやマネジャーがこの理論を取り入れ、事業戦略を大胆に考え直そうと動き出した。
しかし、多くは自分たちがレッド・オーシャンに閉じ込められていることには気が付けたが、ブルー・オーシャンへの移行(シフト)にどう乗り出せばいいのかは分からず、苦心していたという。
このような状況を受けて、『ブルー・オーシャン戦略』の刊行後10年以上にわたり、著者2人は世界中のブルー・オーシャン・プロジェクトの成功と失敗を、比較・分析した。
その研究の結果を受けて、最小限のリスクでブルー・オーシャンを創造、支配するための、具体的な手順と体系的なプロセスをまとめたものが、『
ブルー・オーシャン・シフト』だ。
この度『ブルー・オーシャン・シフト』の著者であるチャン・キム氏の来日をきっかけに、INSEADでチャン・キム教授に師事し、『ブルー・オーシャン・シフト』日本語版にて、日本企業ケースの執筆を担当したムーギー・キム氏が迫った独占インタビューをお届けする。
ミレニアル世代にこそ届けたい
ムーギー キム教授が提唱するブルー・オーシャン戦略、そしてブルー・オーシャン・シフトを、なぜ日本のビジネスパーソンが理解する必要があるのでしょうか。
特に日本の20~40代にとって重要な理由を教えてください。

ムーギー・キム
ブルーオーシャングローバルネットワーク。慶応義塾大学総合政策学部卒業。INSEADにてMBA(経営学修士)取得。外資系コンサルティングファーム、投資銀行、米系資産運用会社、香港でのプライベートエクイティファンド投資、日本でのバイアウトファンド勤務を経て、シンガポールにてINSEAD 起業家支援企業に参画。INSEAD時代にチャン・キム教授に師事し、ブルーオーシャングローバルネットワークの一員として、新刊『ブルー・オーシャン・シフト』では、付録の日本ケースの執筆を担当している。著書に『一流の育て方』(ダイヤモンド社)『最強の働き方』(東洋経済新報社)、『最強の健康法』(SBクリエイティブ)などがある。』
チャン・キム 20~40代のビジネスパーソン、特に20~30代のミレニアル世代は、大きな課題に直面しているからです。
その一つは、マネジャーの高齢化によって生じるコミュニケーションギャップです。
特に、日本ではこの課題を解決するのが難しいでしょう。
組織を動かすには高齢の上級管理職を動かす必要がありますが、日系企業の役員層はみな高齢です。
そのような中で意思疎通するには、高度なコミュニケーションが求められます。
一方で「イノベーションの創造」がこれからのビジネスでいままで以上に重要になるのは疑いの余地がありません。
それを踏まえて、ミレニアル世代は何をするべきなのか。
『ブルー・オーシャン・シフト』は、これらの課題を解決するために執筆しました。
『ブルー・オーシャン・シフト』が優れているところは、属性や役職など関係なく、誰でも使えるところです。
上級管理職でも、中間管理職でも、起業家でも、中小企業の社員でも大企業の社員でも、外国人でも、日本人でも理解できます。
しかも、デジタルの世界でも、リアルの世界でもどちらでも適用が可能です。
任天堂Wiiが生み出したもの
ムーギー なるほど。最初にブルー・オーシャン戦略が発表されてから13年が経ちましたが、それをアップデートさせたわけですね。前著との最大の違いは何ですか?
チャン・キム ブルー・オーシャン戦略を発表してから数多くの反響がありました。その中で感じたことは、ブルー・オーシャン戦略について多くの誤解があったことです。
「イノベーション」を生み出すには、主に3つの方法があります。
1つはディスラプション(破壊*注:完全に一致する邦訳は無いが、原文はDisruption, 本稿では便宜上、破壊・非破壊と表する)。
いまの世の中でディスラプションを無視することはできません。大企業こそ、自らのディスラプションを意識すべきです。
2つ目は、Non-disruptive(非破壊的)な創造です。これは後ほど詳細を述べますが、ミレニアル世代にもっとも受け入れられやすい考え方でしょう。
そして、もう1つは破壊と非破壊の中間的な方法です。たとえば、任天堂のWiiは良い例でしょう。
任天堂のWiiが市場に出てきたことにより、プレイステーションやマイクロソフトのXboxは売り上げの減少が起こったかもしれません。
その点では、Wiiも誰かが負けるというDisruptionを起こしています。
一方で、Wiiは新たな市場を創出しているという点では、非破壊的な創造をしています。Wiiはこれまでのゲームでは難しかった、子どもとお年寄りの交流を生み出しました。
任天堂のWiiは操作が非常に単純です。卓球やテニスのゲームもありますが、誰もが簡単に遊び方を覚えられます。
おじいちゃんは、孫が来たとき、「Wiiを一緒にやろうか。テニスをしよう」と誘うことができますよね。
そして孫は「いいよ、おじいちゃん。一緒にやろう」と言ってくれます。
これにより新たな幸せをもたらされ、Wiiのニーズが生まれています。もちろん、それにより市場を奪われた既存プレーヤーもいるでしょう。

(写真:jacktheflipper/istock.com)
このような「破壊と非破壊の中間」のような創造も存在します。
『ブルー・オーシャン・シフト』では、その点も触れているのですが、ブルー・オーシャンが単なるニッチ戦略や差別化戦略ではないことを強調したいと思います。
ブルーオーシャン戦略とは、ニッチ戦略と異なり市場は大きいものです。また単なる差別化戦略とは異なり、不要な競争軸は大胆に切り捨ててその余力を新規価値に割り振ることで、新たな価値と価格競争力の双方の実現を追求します。
そして重要なのは、破壊だけに頼らず、“新たな価値を創造する”というバリューイノベーションを実現することなのです。
2つのメッセージを込めた
それを踏まえ、『ブルー・オーシャン・シフト』では2つの重要なメッセージを込めています。
一つは、失敗を上手くコントロールして最小化しながらイノベーションを起こそうということです。
前著と異なり、10年以上かけて数多くの企業がブルーオーシャン戦略を実践し、失敗例の教訓も数多く盛り込み、その成功率を高めるための証明されたステップとツールを本書に収めました。
「失敗するのはいいことだ」と言われていますが、しかし、みな本心では「失敗したくない」という思いが強いでしょう。
だからこそ、失敗を最小限に抑えながらイノベーションを起こすための手引きが必要ですし、その証明されたツールとして『ブルー・オーシャン・シフト』を使ってくれたら嬉しく思います。
もう1つの、『ブルー・オーシャン・シフト』で伝えたかったメッセージは「非ゼロサムゲーム」の社会や組織を作ろうということです
誰かが勝つと誰かが負ける「ゼロサムゲーム」ではなく、そこに関わる全員が勝利できる可能性がある「非ゼロサムゲーム」を実現したいのです。
もちろん、イノベーションを起こすということは、何かを破壊することにつながります。
しかし、ミレニアル世代は「破壊」という考えを好まないですよね。「競争するために誰かと競うなんて嫌だ」という考えを持つ人が多い。
彼らは社会や組織、そこに属する人を傷つけず、全体がより良くなる、協力を重視した手法を探しています。
社会のためになることをやり、かつ自分も成長できる方法はないのか。
『ブルー・オーシャン・シフト』は、ミレニアル世代のこの問題に一つの解を示しています。
ムーギー 確かに、ミレニアル世代は競争ではなく、協力や社会貢献に対する意識が高いですよね。
このような非ゼロサムゲームで、従来の“競争”から”価値創造“に思考をシフトさせるのは、ミレニアル世代が幸せになるだけでなく、社会にとっても重要なことだと思います。
チャン・キム 現在問題なのは、破壊がイノベーションとイコールになっていることです。この考え方がビジネスパーソンに洗脳された状態になると非常に危険です。
これは、いまの経営陣がビジネススクールで学んだ頃、競争・破壊を通じたイノベーションが主流派であり、その影響がいつまでも続いているのです。
しかし、現代は破壊だけが手段ではないですよね。非破壊的創造や破壊と非破壊をハイブリッドした方法を選択できます。
任天堂のWiiは新たな価値を産み出し、これまでゲーム市場の非顧客であった、部屋に閉じこもって体を動かさずコントローラーと格闘するというビデオゲームに全く関心を示さなかった高齢者を含めた、大きく新しい市場を創造しました。
ミレニアル世代には“非破壊的な選択肢”があることに気づいてもらいたい。
そのために『ブルー・オーシャン・シフト』を書きました。
読者が同書に記されている多くの事例を参考にしながら、ブルー・オーシャンを生み出すことを願ってやみません。
※続きは明日掲載します。
(編集:上田裕、構成:山田雄一朗、撮影:竹井俊晴、デザイン:星野美緒)