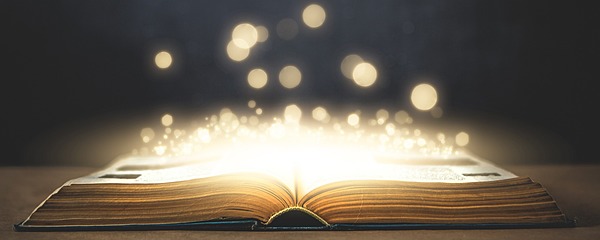
7歳のとき、図書館で見つけた本
ウォーレン・バフェットはおそらく、アメリカ史上、もっとも成功をおさめた投資家だと言えるだろう。
そんなバフェットが、自分のキャリアを歩み始めるにあたって勇気をもらった書籍だと語るのが『One Thousand Ways to Make $1,000』(1000ドルを稼ぐ1000の方法)だ。同氏が7歳のときに図書館で見つけた本だという。
何十年も前に絶版になっている本だが、筆者は先ごろこの本を発見し、読んでみたところ、すっかり圧倒されてしまった。
若かりし頃のバフェットが心を強く動かされたこの本の存在が、初めて広く知れわたったのは『フォーチュン』誌で彼の特集が組まれたときだった。そのなかで、この本はバフェットにとって「暗記しているも同然」として説明されている。
この本は表向き、F.C. マイナカー(F.C. Minaker)が書いたことになっているが、内容から察するに、実際は複数による共著だったようだ。
かなり古い本なので、違和感を感じる言葉づかいも見受けられる。けれども、それさえ気にならなくなれば、とても勇気を与えてくれる内容だ。
この本のなかには、子どもの頃のバフェットが繰り返し読みながら心に刻み込んだであろう、明確な教訓が5つ含まれていると筆者は思う。それらは、時を経ても古びることはない内容だ。
1. 明日を待たずに、今すぐ行動せよ
この本は、お金を稼いだ人たちの実例を、シンプルに次々と紹介している。なかには、1930年代当時の1000ドルよりもはるかに多くを手にした人がいる。短くまとめられたサクセスストーリーを次から次へとひたすら続けて読むことで、強烈なインパクトが残るのだ。
ルートビアのメーカーであるハイアーズ・ルート・ビア(Hires Root Beer)社を興した男性。大手百貨チェーン、J.C. ペニーの創業者。夫と死別し、なけなしの38ドルを元手に、100万ドル規模のコーヒーショップを築いたニューヨークの女性。
トマトジュース会社を大きく成功させた女性。道端でタイヤ修理業を始めた男性。そんな話が延々と語られている。
バフェットは、そうしたストーリーからインスピレーションを得ただけでない。利益が複利で増え、投資がより効果を上げるよう、若いうちに始めるべき主な理由を学んだのだ。
2. 自分がよく知る分野で勝負せよ
これも、バフェットがいまだに重んじているであろう教訓だ。すなわち「自らが精通するビジネスに投資する」ということだ。
この本で紹介されている人のほとんどが、すでに身につけていた専門的知識をベースにして起業している。この対極にあるのが、可能性のありそうな大きな市場を見つけ、その市場に向けた製品やサービスの開発に挑むというやりかただ。
「自分がよく知る分野で勝負に出る」。これを言い換えれば、ほとんどの起業家は、自らが自分の企業の顧客になり得るということだ。自分の趣味や精通している分野で何かを発見し、そこから巨大ビジネスを築き上げた起業家もいる。
3. 今しかない
読む前からすでに印象深かったのは、この本が1936年という世界大恐慌がどん底にあった時期に出版されたという事実だ。当時の失業率は20%近かった。
凶作で貧しい生活を強いられる米中西部の農民たちを描いたジョン・スタインベックの小説『怒りの葡萄』の時代だ。
この本の著者は、自分が本を書いている時代は経済的にきわめて苦しい時代であることを明確にしている。しかし本書は一貫して、当時の悲惨な経済状況を「何もしない言い訳」にせず「何かを始めるきっかけ」にするように主張している。
今すぐ始めよう。言い訳は許されない。
4. 普通の人でも特別な人になれる
本書には、裕福な家庭に生まれた人はほとんど登場しないし、ハーバード大学やイェール大学の名前は一切出てこない。外部からの投資を受けた人は実質的におらず、いたとしても、それは会社が大きく成長してからのことだった。
彼らの大半が、ごく普通の人だったし、多くの場合、世界大恐慌という世情を背景に苦労しながら起業している。
一方のバフェットは、決して貧しい家庭に生まれたわけではなかった。実際、バフェットがこの本を見つけた2年後に、彼の父親は連邦議員に選出され、家族全員でワシントンD.C.に移り住んでいる。
しかし、バフェットが始めた事業や非常に若いころに投資したビジネスを考えてみると、彼が自らに問いかけていたのは、82年前に書かれた本書が全体で訴えかけていた問いと同じ内容のように思える。
その問いとは「ほかの人に任せてよいのか」「どうしてあなたはそうしないのか」というものだ。
5. どの世代も、一番苦労しているのは自分たちだと考えている
マイナカーはペンネームだったかもしれない。しかし、この本を書いたのが誰であろうと、著者は当時の若者をやや見下しているようだ。その若者たちとは、数年後に第2次世界大戦に参戦した世代だ。
1930年代ならびに1940年代の若者と、それより上の世代の意欲にあふれた起業家たち比較した文章を紹介しよう。私はこれを読んで思わず笑ってしまった。
いまどきの普通の若者と、いかに異なっていることか。いまの若者はたいてい、自ら事業を興して地位を確立するより、楽しむことに関心がある。…(中略)…楽しむことばかりに気を取られ、明日は明日の風が吹くと、のんびりと構えている。
この文章の「いまどきの普通の若者」を「ミレニアル世代」と置き換えてみてほしい。時代は変化しても、人間性は基本的に変わらないのだ。
原文はこちら(英語)。
(執筆:Bill Murphy Jr./Contributing editor, Inc.com、翻訳:遠藤康子/ガリレオ、写真:themacx/iStock)
©2018 Mansueto Ventures LLC; Distributed by Tribune Content Agency, LLC
This article was translated and edited by NewsPicks in conjunction with IBM.
