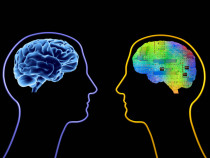
機械学習研究者2000人が、Natureの新しい有料論文誌への投稿を拒否
コメント
注目のコメント
ジャーナルはお金になりますからねぇ、上手く行けば 著者も査読者も編集者もタダ働きなので 著作権もタダで手に入るし なので上手く行かなくてもリスクはほとんどない、よいビジネスモデルです
タダ働きで言えば、会議もそうですねぇ 大きな会議では百人単位でPhDがタダ働き+実費参加、その結果出た利益は主催学会に返納です 勿論赤字になることもありますが、大きな会議では予算計画のチェックが厳しく、企業スポンサーも付くため、稀です ただ、学会は大抵 non profit なのであんまり利益出るとマズいため、会議ロゴ入りバッグやUSBメモリなどのオマケをつけて調整しますねぇ だったら参加費安くしてほしいんですが、赤字リスクをほぼ無くすために、conservative な価格設定になりがちです。。。
で、なんで学者がこんなにタダ働きをするかというと、結局は学問を進歩させたいからなんですよねぇ なので当該コミュニティが、自ら質を保証した(コレが一番タイヘン)研究結果の共有、意見交換の場を独自に確保できれば、出版社や学会に頼らなくても良いんでしょうねぇ
ご参考
https://newspicks.com/news/2961287国の研究費に頼ることなく、自分の研究成果がお金を生むシステムになれば研究者にとって良いですね。
Saitou先生がおっしゃる通り、雑誌に投稿する研究者は報酬なしで著作権は雑誌社に献上、投稿された論文を評価する査読者はタダ働き、掲載された論文を読んで次に論文を書く読者は有料という、とんでもないビジネスです。しかも最近はオンラインでしか読まないので、紙の雑誌発行さえなければコストはかなり低いはず。
研究者は国のお金で研究して、膨大な時間をつぎ込み1本の論文を完成させる。それを投稿して掲載されると著作権は雑誌社にある。カラーの図や字数オーバーで逆に雑誌社にお金を払ったりする。
査読は突然来て、早くしろと期限を言い渡され、査読完了までの日数で評価すらされる。忙しい時に査読依頼が来ても、科学の進歩のために断らずに、期限内に返答するという、純粋な科学者のボランティアにより成り立ってる。
読者である研究者は掲載された論文を有料で読み、次の論文を報酬ゼロで雑誌に掲載する。
研究者は雑誌社に搾取されすぎです。機会学習の世界は、UNIXやブロックチェーンの非中央集権思想のようにオープンであるということが好まれる世界ですからね。Saitou先生のコメントは必読です。
有料の学会誌はそれなりには品質維持にコストをかけていたりします。IEEE(米国電気電子学会)の論文誌なんかは誤字脱字や図表のレイアウトなどを出版前にチェックしてくれます。アジア系の投稿も多いので欠かせない作業でしょう。(あまりに英語がPoorな論文は査読者への心証が悪いのでそもそも通りません。あくまで仕上げの意味で。)相対的に論文のクオリティも高いため、その信頼性が有料を正当化しているところはあります。
それでも査読や学会委員がタダ働きなのは事実で、特に企業からはあまり評価されないんですが、最新の情報が入手できるメリットとコミュニティを求めて引き受けたりします。レベルの高い学会であれば委員自体がキャリアとして認められたりもします。そういった個人的なインセンティブが伴いつつ、論文や学会運営の根底にあるのは「学問の発展と人類への知的資産への貢献」なんですよね。
