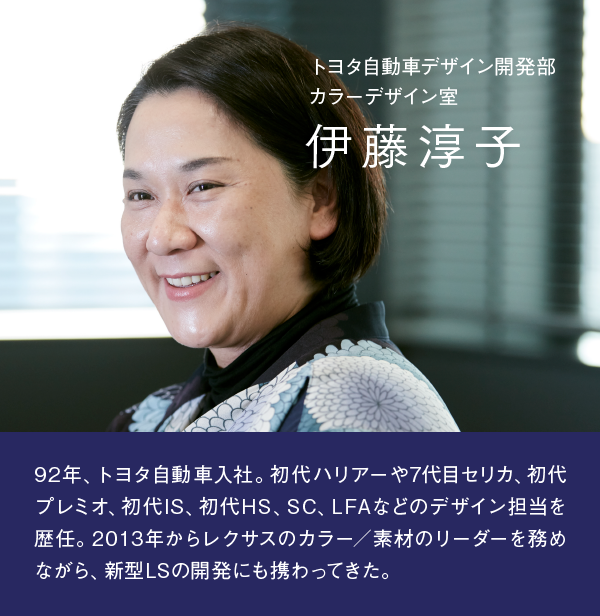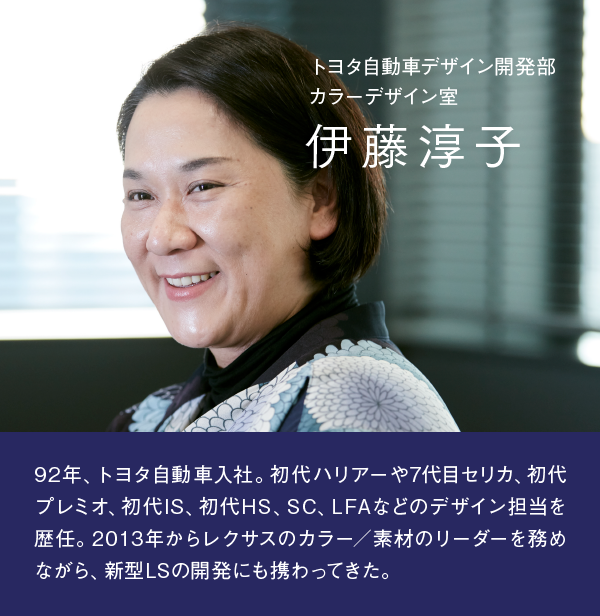【レクサス】切子調ガラスがクルマの内装に。そのラグジュアリーな革新性とは
2018/3/8
新型レクサスLS500hのドアトリムに採用された世界初の切子調ガラスオーナメント。工業製品であるクルマと日本の伝統工芸・切子という異色のコラボレーションを実現したのがAGC旭硝子の最新技術だ。レクサスLSの内装担当デザイナー・伊藤淳子氏と切子ガラス作家・中村敏康氏が、この革新的なプロジェクトへの思いを語り合う。
タブーを超えた、プリズムの光の美しさ
──レクサスブランドのフラッグシップモデル、レクサスLS500h。日本発信のプレミアムブランドで、ラグジュアリーを追求したLSのドアトリムに、日本の伝統工芸である切子調ガラスが採用されました。クルマの内装にガラスというのは、意外なイメージがあります。
伊藤:クルマの装飾品としてガラスを使うのは、正直、タブーと言えるくらいハードルが高くなります。
クルマは安全が最優先。万が一、事故が起きた場合でも、安全性が保てるという保証がなければ、採用は難しくなります。
実際、私たちが最初にガラスを提案したときも、社内的な反応は「えっ? ガラスを内装の意匠にするって一体どういうこと?」というようなものでした。
──切子ガラスに着目した理由を教えてください。
伊藤:ガラスの光が共鳴して作るプリズム、虹色の世界を作りたいと考えていました。
それにはガラス自体の厚みが必要ですが、切子の技術を使えば薄くてもプリズムのような光の美しさを作れるのでは、と思ったからです。
──中村さんは「クルマの内装に使う切子調ガラス」というオーダーを聞いて、どんなイメージを浮かべましたか?
中村: クルマというのは、普段、僕がやっていることとは全然違う世界なので、内装に使いたいと言われても、最初はまったくイメージがわきませんでした。
ただ、家や建物の内装にガラスを使うことはよくあるので、それの延長線で考えたらいいのかな、とは思っていました。もちろん、安全性などの条件の厳しさもいろいろ想定していました。
伊藤:ガラスの代わりにアクリルを使えばいいのでは、という声もありましたが、私としてはガラスでなければ出せない輝きの美しさ、触れた時の触感にこだわりたかった。
ですから、そこは「本物のガラスを使いたい」ということを社内でもかなり強く主張しましたね。
その後押しになったのが、旭硝子の強化ガラスです。その高い技術を使えば、クルマの内装に採用することもできるはずだ、と。
社内の評価もクリアし、旭硝子さんにも無理なお願いを聞いていただけたことで、なんとかプロジェクトがスタートしました。
ガラス作家の中村さんを見つけて紹介してくださったのも旭硝子さんです。
繊細なカットが生み出す光の反射
──具体的に切子調ガラスを使って、どんなデザインをイメージしていたのですか?
伊藤:想定していたのは、ドアを開閉したときに光の変化が感じられるようなデザインです。そのためにカットの角度や面の作り方は、相当に工夫していただいたと思います。
中村:ガラスがクルマのドアに固定されていて、ドアの開閉時に横に水平に動くだけというのが基本条件。
その場合、直線状の線では、光の動きが単調になるので、キラキラとした光を出すことができません。
そこで、伊藤さんたちが考える光のプリズムや虹を生み出すために、面をねじったような太い線を彫り、模様の面に角度をつけました。
さらに線を細くしたり、太くしたりすることで、よりラインを複雑にしています。
同じ角度の線は一本もなく、すべて向きが違うので、ドアを開閉するたびに一本一本が光を放っているようにキラッと光るんです。
それを生み出しているのが、ガラスの持つ透過性、反射性、屈折です。
伊藤:意匠は全体の内装デザインとの調和も重要になります。中村さんには、その部分を本当にバランスよく美しく作り上げていただけました。
工芸品を工業製品として生み出す
──工業製品であるクルマ、伝統工芸である切子ガラスのコラボレーションがすばらしい成果を上げたということですね。プロジェクトの成功はどこにポイントがあったと思いますか?
中村:工芸品である切子ガラスを、工業製品がどこまで再現できるのか。最初は半信半疑なところもありましたが、それを実現できたのは、やはり旭硝子さんの熱意が大きかったと思います。
工業製品として手間を省くのではなく、機械を使って工芸品のやり方をいかに再現するか──。
そこに真摯に取り組んでくれていた。単純に「工業製品」という言葉でくくれないくらい、僕のやり方に旭硝子が歩み寄ってくれていました。
伊藤:中村さんが原盤を作り、それを旭硝子がスキャンしてデータ化、工業製品として量産します。これだけの細かい面、複雑な線をデジタル化するというのは、本当に大変だったと思います。
仕上げの磨きも人の手でやる高度なレベルを実現するために、新たにロボットを開発してくれたほどです。
中村:カットに関しては手で彫ったのか、機械で彫ったのかわからないほど精度が高い。これまで見てきたような型押しの工業製品とは全く違っていて、ここまで機械ができるのかと、正直驚きました。
伊藤さんのおっしゃる磨きにしても、普通の工業製品なら薬剤で処理するところです。
それを、磨く機械の設計者がわざわざ工房まで来てくれて、僕のやり方を実際に見て、自分で磨きを体験してから設計してくれています。
工房でやることをロボットが再現するイメージにとことんこだわってくれました。
そこまで熱意を持ってやってくれると、やはり単純に工業製品とは言い切れないですよね。
伊藤:工芸品を工業製品で実現していると言ってもいいでしょうね。私がよく旭硝子さんに「そのまんまコピーしてもらえませんか?」とお願いしていたんですが、それが一番難題だったはずです(笑)。
量産化するにあたってもガラス1枚を1時間かけて磨き上げるなど、本当に手間と時間がかかっていて、私としてはもはや「作品」と呼びたいくらいです。
中村:今回のプロジェクトに関わることで、工業製品には何ができて、何ができないかというのが学べたのも、僕にとっては大きな収穫でした。
また、機械がここまでレベルが上がっているという現実を知ることで、自分ももっと頑張らなくては、という励みになりましたね。
ヨーロッパから日本、再び世界へ巡るデザイン
──ご自身の手がけたものが、レクサスLSとして世の中で多くの人の目に触れる点については、どのような感想をお持ちですか?
中村:単純に、自分のデザインが世界的な場所で発表されたのは、すごくうれしいです。ヨーロッパで生まれたカットガラスが日本で切子調ガラスとなり、それがまたクルマの一部として世界に広がっていく。
デザインが世界を巡っているようで、感慨深いですね。
僕の作風は、切子といっても、木版の技術を生かした手法を取り入れたオリジナルです。

中村氏の切子ガラス作品
江戸切子は面を切るといいますが、僕は筆で書いたようなラインで、彫る。そこにひねる技術も加えたりしています。
そういう僕なりの技法が、今回のレクサスの切子調ガラスにうまくマッチしたと思っています。
伊藤:基本に忠実な作家さんでは、今回のような内装は実現していなかったと思います。
中村さんはいろいろな工夫、アイデア、チャレンジへのマインドをお持ちなので、この難しいプロジェクトも実現できました。
そこにかけた思いの強さにも、とても感謝しています。
──完成したレクサスLS500hをご覧になって、どんな印象をお持ちになりましたか?
中村:クルマの全体像を初めて見たのは、2017年5月の連休くらいでした。実物を見ると、やっぱり「おおーっ」と思いますよね。夜の街や高速を走ったら、光がきれいだろうなと。
伊藤:そのフレーズはうれしいですね。官能的というキーワードは、ナイトシーンをイメージしていたので。ちょっとした街灯の下でキラキラと宝石のように輝いてくれると思っています。
ガラスの面がこれだけ細かくあるので、ほんの少しだけキラッと輝く。その光が上品ですてきだと思っています。
実際、社内でもとても反響が大きくて、「こんなすてきなデザインを実現してくれてありがとう」とお礼を言われたりもしました。
日本の文化を生かしたということでも、外国では非常に注目を集めています。
ニューヨークやロサンゼルスのイベントで、日本の匠とのコラボについて話す機会があったのですが、みなさんに「すばらしい」という声をいただきました。
匠とのコラボが工業製品の可能性を広げる
──今回のプロジェクトを通して、企業とクラフトマンシップのコラボレーションのあり方について、今後にどのような期待を感じていますか?
中村:トヨタや旭硝子という大企業のプロジェクトに参加させてもらったことで、これまでとは全く違う世界を見せてもらえたと思っています。
ガラスの世界で僕の名前を知っている人はいても、世の中の多くの人は知らないはずです。
そんな僕のような存在の人間と組んでくれたことが、企業と匠がコラボする、いい前例になってくれたらうれしいですね。
有名作家より、地道にコツコツ頑張っている工芸作家のほうが、自由なアイデアが豊富だったりもします。
才能とやる気にあふれた匠を企業が見つけ出してコラボすることで、工業製品のレベルもどんどん上がっていくのではないでしょうか。
伊藤:今回、ブランドとして掲げたもののひとつに、「クラフトマンシップ」があります。そこに切子調ガラスがうまくコミットして、すばらしい形となって発信できました。
これからも、レクサスブランド全体として、匠とのコラボレーションにチャレンジし続けていきたいですね。
(編集:奈良岡崇子、構成:工藤千秋、撮影:尾藤能暢、デザイン:九喜洋介)