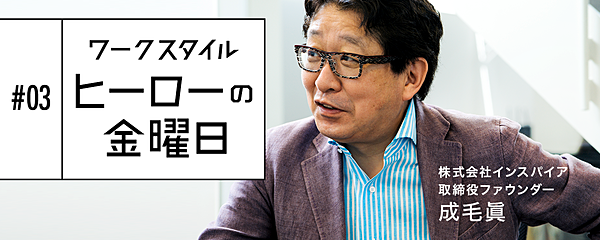
「面白いこと」を追い続ける、キャリアプランの組み立て方
アメリカン・エキスプレス | NewsPicks Brand Design
2017/6/9
政府がプレミアムフライデーを提案するなど、日本全体で「働き方」が見直されている昨今。誰かに決められるのではなく、自らワークスタイルを規定し、実行してきた“ヒーロー”たちの多様なポリシーに学ぶ。(全4回、毎週金曜日掲載)
元マイクロソフト社長として、黎明期のPC市場を牽引したトップマネジメントとして知られる成毛眞氏。
退任後は投資コンサルティング会社を創業、スルガ銀行をはじめ多くの企業の顧問・社外取締役を歴任するかたわら、書評サイト「HONZ」の代表を務め、さらにはジャンルを横断して多くの書籍を執筆する文筆家としても知られている。
その働き方のスタンスは、まさに自由奔放。いわゆるビジネスパーソンの枠組みに収まらないほど、成毛氏のキャリアは幅広い。
新卒の頃から「面白いことしかやりたくなかった」というポリシーを貫いてきたと語る、その真意とは──。
新しく、面白いことを探し続ける
──成毛さんのこれまでのキャリアにおいて、一貫した働き方のポリシーはありますか?
成毛:すごくシンプルに言えば、「新規性があって、面白いことだけ追いかける」ということですね。
小さくても面白そうな会社に入って、好きなだけ働き、面白くなくなったら即座に辞める。これまでずっと自分の興味本位に働いていただけで、いわゆる「仕事をしてきた」という感覚があまりないんです。
私はとにかく、新しい物事を追いかけて手に入れた時、新しい仕事や遊びを構想したり作ったりしているときが幸せなのです。仕事が遊びになる。いや、遊びを仕事にしていたのです。
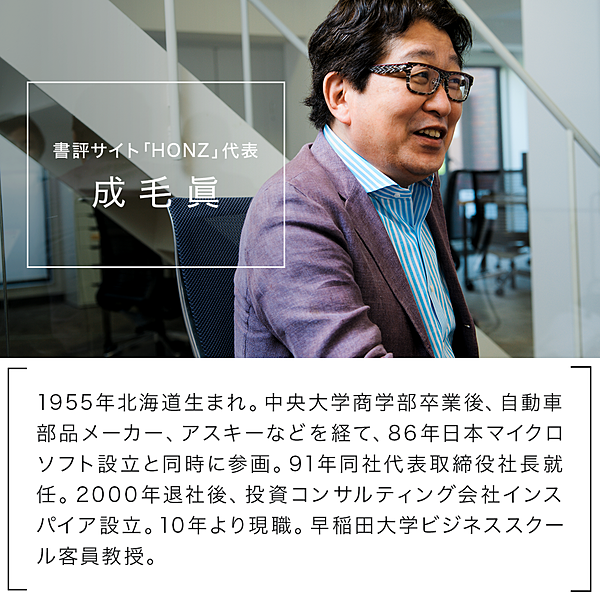
仕事の内容が安定してくると、やがて飽きてしまう。そうなったら次へ行く、ということをやってきました。
マイクロソフト時代も、何度も飽きて辞めようとしたんです。でも、そのたびに新しいことが起こるから、なかなか辞められなかった。
BASICを売るだけの会社かよと飽きてきたら標準OSとなるMS-DOSが出てきた。それにも慣れてきた頃にはWindowsが登場し……いよいよ辞めようと思ったら社長になれと言われたりね。
──たとえば、「世の中を変えるような仕事を成し遂げたい」といった気持ちはなかったんですか?
基本は自分本位です。私は偉人にはなりえません。私自身が興味を引かれることを追ってきただけですね。
人生は一回きりだから、絶対に「面白い仕事」以外はやりたくない。学生時代からそう決めていました。
ただ、あんまり面白いから若い頃は24時間会社にいて、目が回るほど働いていたので、周囲からは「ものすごく頑張っている」というふうに見られたかもしれません。
でも、本人としてはテレビゲームに熱中することと違いはなかったんです。
夢中になれる会社を選ぶ
──成毛さんが20代、30代の頃といえば、「頑張ること」で生産性を上げるのが当然というモーレツ時代ですよね。
そうですね。ただ、「しんどさに耐えながら嫌々頑張る」のと、「面白いことに夢中になってのめり込む」のでは、同じハードワークでも意味がまったく違う。
当時はバブル時代の真っただ中だったのですが、まったくバブルを体験しなかった。オフィスで仕事をしていたんです。
すでに成熟している産業では競合会社も多く、社内でも出世競争がある。どうしたって頑張らないと勝てません。新しいこともそれほど起こらない。

成毛氏のここ数年間の著作。作品ごとにジャンルもテーマも異なる点から、興味の移り変わりの激しさがわかる。
しかし、マイクロソフトが立ち上がった1970年代後半には、世界にパソコン業界そのものがなかった。初年度の売り上げなんて数万ドルです。お客といえば秋葉原電気街に集まるようなマニアだけだった。
それがたった20年間で時価総額70兆円の大企業に成長した。もとがゼロだったんですから、その成長のスピード、勢いというのはすさまじいものでした。まさに目くるめく時代に身を置いてきました。
偶然とはいえ、自分が夢中になってのめり込める領域で、未来に向かってゼロから成長し続ける会社に入ったということが、私のキャリアにおいては重要なポイントだったと思います。
もし、いまもう一度会社に入るんだったら絶対にベンチャーですね。日米のAI系ベンチャーなどを見てると、どんどん新しいことが起きている。まさに秒進分歩。間違いなく新しい産業が勃興しつつあります。

そのなかで、はたから見れば粉骨砕身働いて会社を成長させて、事業が成熟したら(絶えず新しく面白いことをしていたいので)別の何かを始めると思います。
子育てに合わせたジョブホッピング
──「面白さ」を追求して夢中になって働くとなると、やはりハードワークになりますね。
それが難しいところですね。私にとって仕事は面白いことですが、一歩引いて人生を俯瞰してみると、「これは面白い!」と思うことは仕事だけじゃないからです。
たとえば「子育て」は、その最たる例ですね。子育てはめちゃくちゃ面白いですよ。こんなに面白いことを、仕事で犠牲にするのはもったいない。
私の子育てとは、徹底的に子供と遊んで、自分が楽しむということです。一人娘には中高一貫して進学塾などに通わせなかった。
そのかわり、彼女が高校時代には二人でゲーム部屋に引きこもって、「ファイナルファンタジー11」というオンラインゲームをやってました。
総プレー時間は3000時間を超えてますから、おそらく日本でもっとも高校生の娘と二人で遊んでいた男といえるでしょう。

たまたま、これがインスパイアという会社を立ち上げた時だったので、社員は大変でした。出社しないで娘と遊んでいる社長に事業報告をするため、ゲームのキャラクターになってモンスターとの戦場に登場し、チャットしていたこともあるほどです。
結局、彼もそのゲームにハマりましたが、いまでは立派に更生して、インスパイアの社長をしています(笑)。
──とても面白いですが、多くの現役ビジネスパーソンにとっては、ちょっとまねできないですね……。
そこで最近、若い人たちによく言っているのは、年齢とライフステージによって、ワークスタイル自体をガラリと変えるという提案ですね。
これまで私が見てきたなかで、いわゆる「成功している人」は、社会人最初の3年間でとにかくがむしゃらに働いた人が多いように思います。自主的なブラックワーカーとでもいうべきでしょうか。
社会人のはじめの3年間というのは、何も考えずフルパワーで働いた方がいい。その結果として、3年後には同級生と比べて10年分くらいの圧倒的な差がつくからです。
そうやってしばらくすると結婚して、子どもができたら転職する。育児休暇は次の会社に移るまでの期間を利用できるはずです。
子育ての時期はきっちり9時17時で働いて、休日もしっかり休める仕事がいいですね。

その後、40代半ばになって子どもが高校に入る頃が、再び仕事に打ち込めるチャンスです。ゆるく働きながら子育てして、そのあとに再びバリバリ働くためにジョブホッピングする。
ワーク・ライフ・バランスを両立させるなら、「仕事に夢中になるピーク」を意識しながら、メリハリをつけて働くのがいいと思いますね。
次へ移るための「支流」をつくる
──成毛さんご自身は、どんなキャリアプランを考えていたのでしょうか?
プランなんて何もなかったですよ。全部が流れ、偶然です。だけど、いまの仕事に飽きたときに「次はどうするか」という準備だけは常にしてきましたね。
具体的には、本業の流れ以外の「支流」を作るということをやってきました。
ずっと会社で仕事をしていると、その会社が進む方向の「流れ」に乗ってしまう。それは社会のごく一部の流れでしかない。それじゃ先が見通せません。
たとえばマイクロソフトにいた頃は、「フォーラム・フィフティ」という1950年代生まれを集めた勉強会を主催していました。
スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツ、ティム・バーナーズ=リー……この3人が1955年生まれなんです。「この世代は天才だ!」という酒場でのバカ話をきっかけに、異業種の同世代を集めた勉強会、という名のざっくばらんな飲み会です。
参加者は私の知り合い限定で、あいさつなし、セレモニーなし、自己紹介なしで、わらわらっと集まって、ただ飲み始める。毎回、20人くらいが集まってました。
そこに来ていた人同士がつながりあって、情報交換をしているうちに、半数は役所や会社を辞めて別のことを始めましたね。
海外留学して学者になったり、起業したり、国会議員になりました。彼らも「次の面白いこと」を見つけたわけです。

──成毛さんがハブとなっていたわけですね。
私は最初に流れをつくるだけ。みんなが好き勝手に動いているのを眺めて、「なにか面白い人はいるかな」と見ている感じでしたね。
仕事の利害関係なしに集まって酒が入ると、みんな何かしら自由に話し始めるんですよ。「こんな話、興味ないでしょうけど……」って。
それがネットには出てこないような面白い話だったりする。結果的には新しいビジネスや、次のキャリアにつながるヒントになるんです。
ちょっと面白そうな支流があるぞと思ってそっちへ流れると、意外と太かったりする。そんな感じで面白いことを探しながら、私自身もこれまで転々としてきたんです。
──今62歳でいらっしゃいますが、ワークスタイルはどう変わりましたか?
今の私は、過去の遊びで学んだことを仕事にするフェーズですね。その結果としてさまざまなジャンルの本を書くようになりました。
遊びから得た知識をさらに強化するために、ワーッと調べて、じーっと考える。そうすると、あっという間に本の一冊なんて出来てしまう。
さっき仕事には「ピークがある」と言いましたけど、60歳になったら次のステージに移って、さらに本格的に遊びを仕事にする。
この目標を達成するためにジョブホッピングするというのが、私の働き方の軸になっていたのかもしれません。
(編集:呉 琢磨、構成:宇野浩志、撮影:岡村大輔)
アメリカン・エキスプレス | NewsPicks Brand Design


