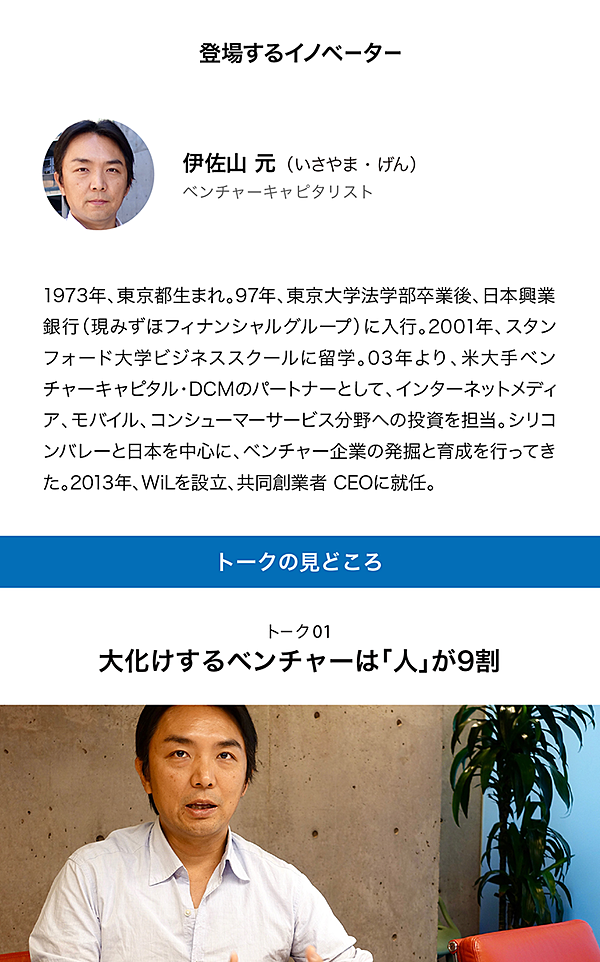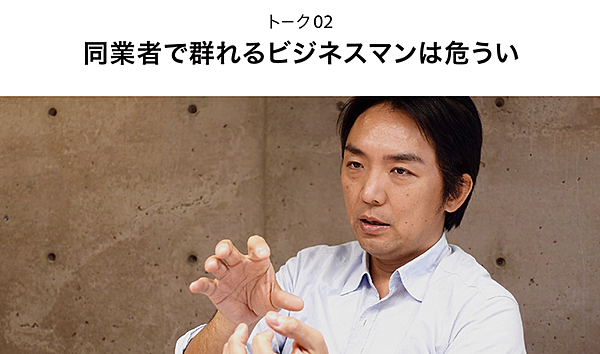シリコンバレーの投資家・伊佐山元が説く「1兆円企業」の作り方
2016/12/19
独自の視点と卓越した才能を持ち、さまざまな分野の最前線で活躍するトップランナーたち。彼らは今、何に着目し、何に挑もうとしているのか。連載「イノベーターズ・トーク」では、毎週注目すべきイノベーターたちが、時代を切り取るテーマについて見解を述べる。

第57回はシリコンバレーのベンチャーキャピタル「WiL」を経営する伊佐山元氏が登場する。
テーマは「1兆円産業の作り方」だ。
昨今、日本では、2000年前後以来の「ベンチャーブーム」が起きている。
新規上場会社数はリーマン・ショック翌年の2009年には19社まで落ち込んだが、その後6年連続で上昇し、2015年は98社にまで到達。2016年は87社と前年を下回る見込みだが、依然として高水準を保っている。
しかし、日本のベンチャーは「小粒」だという声も頻繁に耳にする。たしかにアメリカでは、Uber、Snapchat、Airbnbといった評価額100億ドル(約1兆円)を超えるベンチャーが相次いで誕生しているが、日本でそこまで成長したベンチャーは、90年代以降は楽天1社のみである。
そうした状況に危機感を抱くのは、海外から日本企業を見つめ続けてきた伊佐山氏だ。
同氏はメガバンク社員時代にスタンフォード大学のビジネススクールに留学し、以後15年、シリコンバレーを拠点に活動している。
過去のインタビューでは「私のシリコンバレー生活の15年は、日本のプレゼンスが下がっていく15年だった。もう一度『日本はすごい』と言わせたい」と発言するなど、日本に対する危機感は強い。
そんな伊佐山氏のアプローチは、ある意味ほかのベンチャーキャピタルとは一線を画す。
日本の大企業から預かった投資資金をベンチャーに出資するだけではなく、大企業の社員を自社に出向させて教育研修を行ったり、大企業内の技術を使ってジョイントベンチャーを立ち上げたりしている。
つまり、「大企業のポテンシャルを十分に発揮させること」を、ビジネスを主眼としているのだ。
WiLのオフィスには、日産自動車や全日空、博報堂DYグループ、みずほ銀行といった日本の名だたる大企業の社員が机を並べ、新たなビジネスアイデアについて議論を交わしている。
そんな伊佐山氏に今回、日本のベンチャーが「時価総額1兆円」を目指すために不可欠な要素について語ってもらった。
シリコンバレーの第一線で活躍するベンチャーキャピタリストには、日本企業の課題と可能性はどのように見えているのか。
1兆円企業を作るときには、まず「人」に重視すべきだと伊佐山氏は言う。
中でも、創業者ファウンダーの資質がベンチャーの命運を決める。ファウンダーが大きなビジョンを掲げれば掲げるほど、そのビジョンに共感した人材が集まり、その人材がさらなる人材を呼ぶ、という好循環につながるからだ。
その上で伊佐山氏は、グーグルが「人」に着目して断行した、ある巨額買収について具体例を示す。
数年前まで「シリコンバレー企業に自動車産業は不可能」というのがビジネス界の常識だった。しかし今では、テスラモーターズが自動運転車を開発し、グーグルやアップルも自動車分野に参入している。
伊佐山氏はこの事例から、「インテリやエスタブリッシュの常識が、明らかに実態からずれ始めている」と分析する。
インテリやエスタブリッシュは、似たような層の人間とばかり接し、それ以外の層の実態を見ようとしない。伊佐山氏は「狭い群れの中だけで議論して、世の中をわかった気になるのは、非常に危険」と警鐘を鳴らす。
では、そうした状況を回避する手立てはあるのか。
異なる背景を持つ人々が集まり、「知と知の組み合わせ」を起こすことを目的としてWiLを立ち上げた、と伊佐山氏は言う。
そのときヒントとなったのは、シリコンバレーの大通りにある数々のコーヒーショップだ。会議室でミーティングするのではなく、コーヒーショップで雑談しながら、新たなビジネスの話が生まれている現状がシリコンバレーにはある。
「そうしたサロンを作りたい」と語る伊佐山氏。イノベーションを生む「場づくり」に対する思いが明かされる。
伊佐山氏は「日本の優秀な人材は大企業のR&D部門にいる」という持論をもつ。
真意を聞くと、伊佐山氏は自身がこの事実に気づいたきっかけを述べる。そしてそのような人材が活用されていない現状について、「なんてもったいないんだ」と本音を語る。
では、大企業に眠るリソースを有効活用し、新たなビジネスを起こすためには、何が必要なのか。
「大企業と新規事業」と言えば、2000年代に起きた「社内ベンチャーブーム」が想起される。
しかし当時の社内ベンチャーは、ほとんどが失敗に終わり、現在まで残っている事業は数えるほどしかない。
その点について問われた伊佐山氏は「社内ポリティクス(政治)が判断をゆがめている」と彼らの経営姿勢を一刀両断する。その上で、「社内ベンチャーブーム」の教訓を生かして、自身が取り組んでいることについて話を進める。
(聞き手・構成・撮影:野村高文、デザイン:名和田まるめ)
眠れるリソースを大企業から探せ
1兆円企業の作り方──伊佐山 元