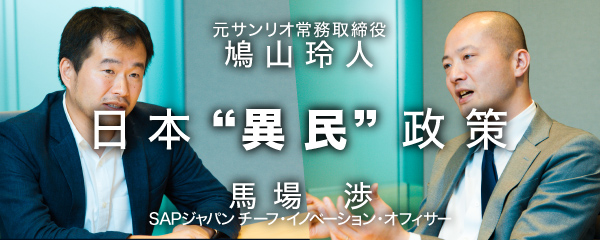
日本企業は変革できるか
鳩山×馬場 イノベーションには“異民”が必要だ

2016/6/22
日本企業がイノベーションを起こすには、何が必要なのか──。三菱商亊、サンリオと日本企業においてイノベーションをけん引してきた鳩山玲人氏と、グローバル企業であるSAPでチーフイノベーションオフィサーを務める馬場渉氏が、イノベーションを語り合った。

社外取締役に求められるもの
馬場渉:鳩山さんは、6月末でサンリオの常務取締役を退任されますが、以前からDeNA、LINE、ピジョン、トランスコスモスと複数の企業で社外取締役を務めています(NewsPicks注:DeNAは2016年6月退任)。やはり、それらの企業はイノベーターとしての鳩山さんに期待されているわけですよね。
鳩山玲人:企業のグローバル化、コーポレートガバナンス強化といった側面以外にもそうした側面もあると感じています。僕は、日本企業にとっては、すごい異質な存在でしょう。受け入れてくれる会社がある意味、すごいと思ってます(笑)。
イノベーションについて考えるときに、「どこで」イノベーションを起こしたいのか、というのは切り分けて考えるべきだと思っています。現場からのイノベーションなのか、経営戦略においてのイノベーションなのか。それによってイノベーションを起こすべき「場」が違ってくるんですよ。
経営戦略にイノベーションを起こすなら、それは取締役会や経営戦略を議論する「場」でイノベーションを起こすリードをしていく必要があります。取締役会からイノベーションを起こすというのは、取締役会の大事な役割の一つです。
イノベーションのやり方っていうのは、現場でも経営戦略でも基本的に同じなんですよ。経営や商品のライフサイクルを考えながら、異質なものを見たり聞いたりして考えていく。
でも、日本の場合、経営戦略にイノベーションを起こそうとしても、取締役会レベルで異質なものを入れないんですよね(笑)。その極端な例が、社外取締役を入れないとか。会議室で同じ人が話すだけという経営スタイルが、イノベーションを起こす可能性をどんどん少なくしている。
馬場:それは本当にその通り。非常に共感しますね。
鳩山:海外は経営戦略でイノベーションを起こしたいという気持ちが強いから、取締役会にもどんどん異質なものを入れていく。ここで言う異質というのは、多様性がある視点。「経営者がディスカッションする場」に異質なものが入る、そこが極めて重要なんです。
馬場:社外取締役が日本で機能するのか、という議論は昔からあります。日本企業が得意な「精度を高める」という分野では、異質なものは邪魔で、「あ・うん」の呼吸が効率的だったりする。そういう環境で社外取締役が機能するのかというと、クエスチョンですよね。
でも、精度を高めるよりも、今は、本当の意味でのイノベーションが必要。だからこそ多様なボードメンバーで経営戦略を話すことが不可欠だと思うんです。
そういう多様なボードメンバーを自前で調達できるんなら、もちろんそれでもいい。でも、自前が難しければ社外取締役なりなんなり、外の人脈に頼るしかない。
鳩山:僕が社外取締役として会議に参加するときは、そこの会社が持っていない視点で発言をするよう心がけています。その会社にとって自社の視点や、株主の視点に加え、外からの視点や、他の産業からの視点、世界レベルのグローバル視点といった異質な視点や考えが、向こうにとって驚きであり、インパクトがある。
異質の視点も回数を重ねて場慣れしてくると、徐々に話がすごく通じやすくなるものです。事前に何か準備するわけじゃないけれど、取締役会の場でできるだけそういうダイナミズムやインパクトを与えるような努力はものすごくしてますね。
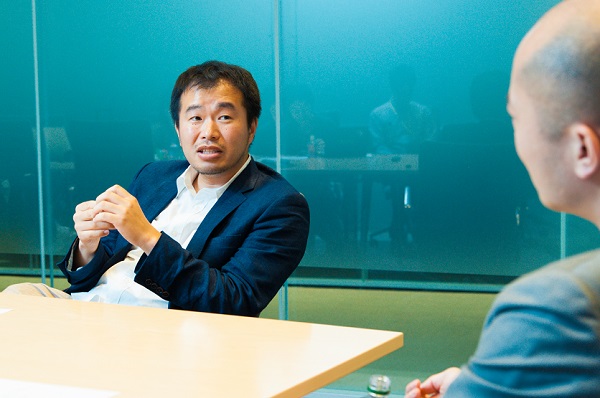
鳩山玲人(はとやま・れひと)
元サンリオ常務取締役
1974年生まれ。青山学院大学を卒業後、三菱商事に入社。2008年にハーバード・ビジネススクールでMBAを取得。同年、サンリオに入社。常務取締役として新規事業の創出に貢献したほか、LINE、ディー・エヌ・エー(DeNA)、ピジョン、トランス・コスモスなどの社外取締役を歴任
「ITプロジェクト」は存在しない
馬場:僕もJリーグの特任理事として委員会に参加しているので、鳩山さんの言っていることにすごく共感します。Jリーグに限らず、どこの企業でも長年培ってきた社風なり伝統があって、僕らが「普通に考えたら、こう思うんですけど」というようなことがいっぱいある。
それでも、経営にイノベーションを起こすというゴールを決めたのなら、多様な視点での経営会議が絶対必要だし、そこに社外役員がいれば機能するはずなんです。
鳩山:コンサルだったらもっと高い費用が発生するところを、責任ある立場でもっと安価な形でイノベーションにも貢献してくれるのが社外取締役の責務の一つ。企業にとってはすごくメリットの大きい存在ですよね。異質な視点を入れる絶好のオポチュニティだと思います。
馬場:本当にそう思いますね。
鳩山:たとえばデジタルシステム化なんて、会社によって全然ちがう。
コンビニのようにデジタルシステムが最先端の小売企業になると、リアルタイムマーケティングなんて、当たり前。在庫や商品の流れがリアルタイムでわかるから、それに合わせて意思決定の速度もあがり、もすぐその場で決断できるようになる。
一方で、同じ小売りでも商品を発売してマーケティングデータになるのが1週間後という企業だってあります。自分たちにしてみると、昔に比べると「ずいぶん早く」なったという感覚なんだけど、リアルタイムのコンビニ側と比べると、あきらかに遅いですよね。
馬場:企業の外から見ていると、そういうシステムやイノベーションへの感覚が、どれくらいのレベルなのかよくわかりますね。「5段階評価の2だな」とか、こっちは「4だな」とか。
そこで問題になってくるのが、ITリテラシーへの感度です。ITが評価2だからといって、それを積極的に4とか5にしたいと思わなかったりするんですよ。それより「営業や人事、マーケティングのレベルを上げるぞ」と考える企業が少なくない。
われわれにしてみると、営業も人事もマーケティングもすべて同じITじゃないか、と。3から4に変えたければ、優秀な工場長を探してくるより、ITを使うほうがよっぽど手っ取り早く成果が出せるはずなんです。
そもそも、僕は「世の中に“ITプロジェクト”なんて存在しない」と、ずーっと言い続けている。でも多くの人が、「ITプロジェクト」だと思っている。そういう説明をしてきたIT業界が悪いですよね。
実際には、売り上げを伸ばすことに直結するビジネスプロジェクトなんです。それが、ITを導入することで、リアルタイムに見えるようになるということ。
ここを理解できない企業だと、「人間VSコンピューター」的な、根性論とデジタルを対立軸に置きがちです。
いいリーダーがいる組織は、人間的な部分もデジタルも、上手に取り込んでいます。得意なところは自分でやり、苦手なところを理解して取り込む姿勢です。

馬場渉(ばば・わたる)
大企業組織におけるイノベーションとそれを可能にするリーダーの開発とテクノロジーの採用を専門とし、SAPアジアで初のチーフイノベーションオフィサーを務める。デザインシンキングの方法論とSAPの最新クラウドサービスを組み合わせ、大規模組織にイノベーション文化を経営戦略として取り込む提案活動に従事。SAP本社から声がかかり、昨年10月からアメリカで働いた
だからアメリカでスタンプがなかなか定着しない
鳩山: デジタル感覚ということでいえば、最近、息子を見ていて面白いと思ったことがあります。
うちの長男は10年アメリカで暮らして、この春から日本の中学校入学のために帰国しました。帰国子女ということもあり、日本語を書くのがすごく苦手だったんです。ところが、LINEがあるおかげで、しょっちゅうテキストを打つ。文字数としてはものすごい量で、日本語の吸収スピードが全然違う。書くから早いんです。
電子辞書で古典の百人一首をリピートして耳から覚えたり、漢字だってグーグルで文字認識させたり、タッチペンで書いたものを画像検索すればいい。
今の人はデジタルで全然いいし、その辺の感覚が日々の積み重ねで変わっていくのでしょう。
長男がスマートフォンを使っているのを見て、日本語と英語の変換機能についても気づいたことがあります。
アメリカにいると、ライティングはアルファベットだけだから変換機能は使わない。でも、日本語って変換するじゃないですか。テキストを打つのは英語のほうが楽で、日本語は極めて複雑で時間もかかる。その変換の中にスタンプが入るわけです。
「はぴば」と打つと、スタンプ候補がわっと出る。アメリカでは「happy birthday」ってテキストを打つだけで変換はない。わざわざ絵のリストの中から、ハッピバースデーに合う絵を探す必要がある。だから、アメリカではスタンプがなかなか普及しない。
アジアで変換文化があるところは、それをうまくインターフェースに入れているからスタンプ文化が出てくるんです。
文化的思想は教育とかアプリケーションとか、小さい頃からの積み重ねで変わるんですね。インターフェースを変えて問題を解決していけば、アメリカでもスタンプが定着する可能性はあるでしょうね。
違うものを体験したり、見る経験を経て、「こういうことなのか」と長男を通じて感じています。
NewsPicksには「異民」が多いが…
馬場:アメリカで成功している大企業なんかみれば、移民2世が本当に多いですよね。グーグルやアップルも移民2世です。
イノベーションを起こしているのは、「異民」つまり異なる民です。歴史上のイノベーションなんて、人が移動して異なるものが交わることから生まれています。
鳩山:昔は港なり、シルクロードなり、川の流れている場所だったり、異質な人やものが交わり合う場があって、そこからイノベーションが起きた。
でも、今の時代、いろんなものが交わる場所を見つけるほうが難しい。その理由のひとつはデジタル化です。モノの流通が重要じゃなくなったということ。
世界中大都市はどこも似通っているし、すぐに何でも世界的に普及する。「本当のイノベーションって何なの?」というときに見るべきもの、感じるべきものを見つけるのが本当に難しい。
馬場:日本は移民そのものがほとんどいないし、労働の流動性も低い。国としても会社としても異民と交わる機会が圧倒的に少ないんです。
何とかして、この異なるものとの交わりをつくるような環境を整えないと、この先、イノベーションなんて起きないですよ。そこは相当、意識して気をつけないといけないところです。
鳩山:どこかの場所に出かけて、異質なものを感じ取ることができないから、自分たちで打ち破っていく環境を作らざるを得ないんです。
さらにそのときに全体のエキスパート感も高くないと、イノベーションにはならない。英語ができる人やIT系が1人いるくらいでは、ダイバーシファイじゃないですから。
大きい意味でのイノベーションをつくるというのがすごく難しいだけに、馬場さんのいうように、よっぽど気をつけてイノベーションを考えていかないとイノベーションなんて起きない。自分ではイノベーションをやっているつもりでも、「それって全くイノベーションじゃないよ」という例は、いっぱいありますから。
馬場:本当のイノベーションを起こすのに異民の存在は必要。でも、だからといって、ほかと交わらない異民では意味がないですよね。何に対して異なるのか、その違う何かを理解しようとしなければ、イノベーションなんて成り立たない。
これまでの日本の教育は異なるものを排除してきた。効率よく経済を拡大していくにはいい教育だったのだと思う。今、本気でイノベーションが必要なのであれば、教育から変えることも考えないと。
NewsPicksの読者って、異民が多いでしょう。「異民政策」を進めたいという思いが強いからあえて言うと、異民だけが単体でいても、異民もへったくれもない。何に対して異なるのか。自分の何が違うかを理解して初めて「異民」なんです。
個人的に、交わらない異なった人はそんなに好きになれない。こっちはニューエコノミー、あっちはオールドエコノミー、交わりません、ともすれば破壊しあいます、みたいな。
これがアメリカなら、片方が「あいつらくそくらえだ」ってぶっ壊して、壊している人たちはニューエコノミーかというと、オールドエコノミーの人だったりする。平気で循環する。
でも日本はそうじゃない。明らかに古い世代、若い世代で分断されていて循環もしない。若い人がドーンと勝ったら、古い人はぼろ負けしている。個人や会社単位では循環するけど、社会全体では循環しない。
異民が意思決定をリードしながらも、もう一方と交わることで大きなイノベーションが実現していくし、そこから日本の社会や経済全体が循環していくはずだと思っています。
(構成:久川桃子、工藤千秋、撮影:岡村大輔)

