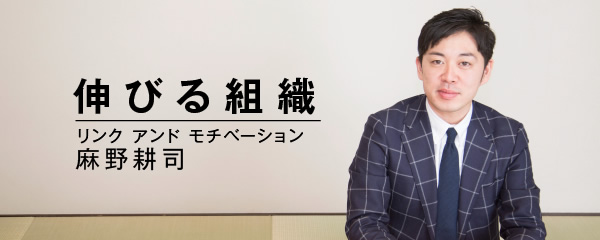
組織変革のプロが語る組織論
自分に合う「良い組織」はこう見抜く

2016/2/29
人は誰しも「良い組織」で働きたいと思うもの。では、どのように良い組織を見抜けばいいのだろうか。総合的な切り口から組織変革に取り組む、リンクアンドモチベーション執行役員で NewsPicksプロピッカー・麻野耕司氏に、良い組織と悪い組織の見極め方、企業選びのコツを聞いた。
事業を推進するのに良い組織
私はコンサルタントとして100社以上の企業を訪れ、さまざまな組織を見てきました。よく「どういう組織が良い組織ですか?」と聞かれますが、良い組織には2つの定義があります。
一つは、「事業を推進するのに良い組織」。つまり、ビジネスモデルや事業戦略が実行しやすい組織です。これには「絶対解」はなく、その事業モデルに対する「最適解」がある。
たとえば、EC事業に特化したA社と、インターネットの最先端で新規事業を次々と生み出すB社を同時にお手伝いしたときのこと。
A社を訪問すると、すれ違う社員みんなが挨拶をしてくださるんです。そして、いざ会議が始まると、社長のトップダウンで物事が決まる。
一方、B社は訪問しても誰も挨拶をしないんです。だけど、会議が始まると、新入社員だろうが遠慮なく社長に物申す。「これ、おかしくないですか? こうした方がいいと思います」「確かにそうだね、そうしよう」と。
A社の事業に求められる徹底した「オペレーション」は、社長の「トップダウン」とメンバー同士の「チームワーク」を軸にした組織によって生まれ、B社の事業に求められる「イノベーション」は、社長も新入社員も壁がない「フラットなコミュニケーション」を軸にした組織によって生まれていました。
面白いくらいに組織のカラーは違いますが、どちらの会社も急成長しており、今では日本を代表するベンチャー企業になっています。逆に、はっきりしたカラーがない組織は、どんな事業も中途半端に終わることが多いと感じています。
人材にとって良い組織
もう一つの定義は、「人材にとって良い組織」であること。「人材が求めるもの」と「組織が提供できるもの」が合致している場合、人材から見た良い組織といえます。
人材が組織に求め、組織が人材に提供できるものは4つあります。「フィロソフィー(Philosophy=理念)」「プロフェッション(Profession=活動)」「ピープル(People=人)」「プリビレッジ(Privilege=待遇)」。これを「4つのP」と呼んでいます。
たとえば、大学でサークルを選ぶとします。「プロフェッション」を求める人は「サッカーをするか、バレーボールをするか」といった視点でサークルを選びます。「ピープル」を求める人は「先輩たちと合うかどうか」、「フィロソフィー」を求める人は「しっかりした目標を掲げているかどうか」、「プリビレッジ」を求める人は「就職に有利かどうか」といった理由で選びます。
自分が4Pの何を重視するかによって、選ぶ組織が変わるのです。よって、自分に合う良い組織を見抜く前に、「自分が何を大切にしたいのか」を明確にする必要があります。
企業の視点から見ると、4Pすべてを提供するのは難しくとも、わが社は「これを社員に提供できる」というのがはっきりしているとミスマッチが起こりにくい。
たとえば、マッキンゼーは「若くして、大きくて難しい仕事ができる」という「プロフェッション」に魅力を感じる人が多そうですし、リクルートは「優秀な人材が、自由闊達(かったつ)に仕事をしている」という「ピープル」に魅力を感じる人が多そうです。直接見たことがなくても、頭の中で職場の風景が浮かんできます。
こういう会社はミスマッチも少なく、モチベーションにドライブがかかりやすい構造になっています。

麻野耕司
1979年生まれ。慶應義塾大学法学部を卒業後、リンクアンドモチベーションに入社。採用コンサルティング業務、人事マネジャー、社長室マネジャーを経て、現在は執行役員として中小ベンチャー企業向け組織人事コンサルティング事業を担当。2013年に投資事業を立ち上げ、複数の投資先企業の社外取締役、アドバイザーを務める。著書に「すべての組織は変えられる〜好調な企業はなぜ『ヒト』に投資するのか〜」(PHP研究所)、「就職活動の新しい教科書」(日本能率協会マネジメントセンター)がある。
経営陣の考えが、どれだけ現場に浸透しているか
反対に悪い組織とは、どんな組織なのか。
経営陣のポリシーがぶれていたり、その方針が現場にしっかりと伝わっていない場合は、あきらかに組織としてうまくいっていません。
そういう組織は外部向けには「顧客を大事にする」というイメージをアピールしながら、実際は業績の数字重視で顧客のことが後回しになっていたりします。
良い組織を見極めるには、経営陣のポリシーがしっかりしていて、社内のコミュニケーションがとれているかを知る必要があります。
たとえば、短時間で組織の良しあしを判断しないといけない面接・面談の場では、以下3つのポイントで判断できます。
まずは、経営陣に会ってその考えをしっかりと聞くこと。特に、リーダー次第で大きく変わるベンチャー企業の場合、社長に会わずして入社するのは、論外といえます。
次に、面接・面談に時間を割いてくれるか。丁寧に時間をかけて自社に合った人材を採用しようという姿勢があるかを見ます。それで社内のコミュニケーションをどれくらい重視しているかも分かります。
最後に、現場の社員に会うこと。経営陣と現場の社員、両方に会うことで、トップの考えがどこまで現場に浸透しているか、つまりは内部のコミュニケーションがうまくいっているか判断できます。
自分が成長できるかどうかは、「成長率」「平均年齢」「粗利率」で決まる
良い組織を見抜く前に、自分が何を大切にしたいのかを明確にする必要がありますが、自分の「やりたいこと」がはっきりしない人もいると思います。そんなときは無理に「やりたいこと」を探すのではなく、自分が「やれること」を増やすことをおすすめします。
しかし、「やれること」を増やせる組織かどうか、つまりは自分が成長できるかどうかを見抜くのは大変難しい。なぜならば、どの企業も「ウチには成長できる環境がある」と言うからです。
私は成長できる環境があるかどうかを判断する指標として、「成長率」「平均年齢」「粗利率」が参考になると考えています。
成長率が高いほど、企業の中で新しい仕事が増えているということですから、入社直後でも大きな仕事を任せてもらえる可能性が高い。
また、平均年齢はその会社で中核となって働く社員の年齢といえます。それが自分に近いほど活躍しやすいはず。
そして、粗利率が高いほど、難しい仕事を手がけるチャンスに恵まれやすいといえます。たとえば、9000万円のものを仕入れて1億円で売るよりも、ゼロから自分で作ったものを1億円で売る方が、粗利率は高い。一概には言えませんが、多くの場合、後者の方が求められる付加価値が大きく、難しい仕事だといえるでしょう。
「自分のタイプを知る」が、企業選びの前提条件
ところで、今の組織がなんとなく合わないな、と感じたことはありませんか? 組織は生き物なので、事業内容だけでなく、企業の成長ステージによって求められる人材が違ってきます。
業績の立て直しを求められているのか、新しい事業を作るのか、ある程度成熟したレールの中でさらに業績を伸ばすのがミッションなのか。
特にベンチャー企業の場合は30人規模のアーリーステージ、100人規模のミドルステージ、数百人規模のレイトステージでは、同じ会社でも組織はどんどん変わっていきます。
当然、求める人材もそこに集う人も大きく変化し、時には現場だけでなく経営陣も入れ替わっていきます。
そういう状況を踏まえると、自分は一体どういうタイプで何が好きなのか、どのような環境で力を発揮するのかを知っておくことは、非常に重要です。誰しも、自分のことは意外によくわかっていないもの。
「なんでもやる」のアーリーステージのほうがやる気が出るタイプなのか、大きな枠組みが決まっている中で仕事を進めるのが得意なのか。
自分のタイプと会社の規模やステージが合っていないと感じたことがきっかけで転職を検討するならば、それはお互いにとって幸せな決断です。
「伸びている企業」は、世間の「人気企業ランキング」とは違う
最後に、いわゆる「世間的な評価」と実際に「伸びている企業」は、大きく乖離(かいり)していることも言及しておきます。
先ほど、成長できるかどうかは「成長率」を参考にできると述べましたが、学生の人気就職ランキングの上位企業は、必ずしも将来性や成長率が高いとはいえません。むしろ、業界別で見た成長率の高い企業はほとんど入っていない。
大手企業で働く人のなかには、ベンチャー企業に行ったほうが能力を存分に生かせるはずだと思う人が、結構な割合でいます。
もちろん、大手企業での仕事の進め方が合っている人は、ベンチャー企業に行くと不幸な結果になる。
企業選びは、いわゆる世間の評価ではなく、自分に合った規模と仕事の進め方であることを判断軸にすると良いでしょう。
(聞き手:田村朋美、構成:工藤千秋、写真:福田俊介)

