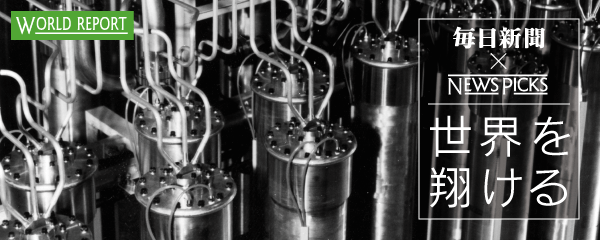
日本の核武装は本当にあり得ないのか
核開発:平和国家・日本が挑んだ「幻」の濃縮法
2015/9/18
戦後、一貫して平和国家を目指してきた日本では、多くの人が「核武装なんてあり得ない」と思っている。しかし実は、日本は濃縮、再処理、高速増殖炉など軍事転用が容易な技術をすべて保有する国でもある。海外で取材すると「日本の本音は核武装にあるのではないか」という声に接することが多い。「原子力の平和利用」を掲げる国なのに、なぜそんな技術まで持つ必要があるのか──? 欧州などを拠点に長年、核問題を追い続けてきた会川記者が、日本の開発史に切り込む。
太平洋戦争中に始まった日本の核兵器開発
「橋などかかっていないと聞いていたが、橋がかかっている。不思議だ」
宮崎県日向市の旭化成の工場を1980年代に訪ねた通産省(現経済産業省)の担当課長は、こう言ってしきりに首をひねった。目の前にあるのはウラン濃縮プラント。総合化学メーカーの旭化成は、持てる技術や人材を投入。イオン交換原理を使った化学法と呼ばれる独自手法で世界初の濃縮に成功した。
原子力政策に影響力を持つ物理界の大御所たちが「理論上、実現するはずがない。ウラン濃縮が成功したというのはうそではないか」と口をそろえて批判する中、この課長は実際に現場に足を運び、濃縮ウランができあがっていく有り様を見て驚く。
ウラン濃縮は、もともとは原爆を製造するために第2次世界大戦中に研究開発が始まった。核分裂しやすいウラン235と、分裂しにくいウラン238を分ける作業だ。ただ、質量の差がごくわずかなことに加え、ウラン235が全体の0.7%しかないことが技術的な壁になる。
世界でさまざまな手法が試され、日本でも戦時中は熱拡散法、戦後はガス拡散法、遠心分離法、レーザー法のほか、化学法などに挑んだ。
原爆には濃縮度が90%以上の高濃縮ウランが必要になる。だが「原子力の平和利用」を掲げる日本は、原子力発電の核燃料に使う3~5%の低濃縮ウランを製造できさえすればよい。
それ以上に濃縮する技術を持てば「日本は核武装を狙っているのでは」などと痛くもない腹を探られかねない。「軍事転用が極めて難しい技術」と専門家が指摘する化学法は、平和国家・日本に最も合致する技術といえた。
なぜ軍事転用に向かないのか。ひとつは、原発向けの装置を転用する場合、大幅な装置の改変が必要になるからだ。「核の番人」と呼ばれる国際原子力機関(IAEA)は、非核国の核兵器保有を未然に防ぐため、各国の濃縮施設を厳しく監視している。
今年7月に核交渉が決着したイランの濃縮施設には監視カメラが設置され、原爆製造につながる高濃縮ウランを製造していないか24時間態勢で監視している。遠心分離機による濃縮法の場合、接続するパイプを短期間に付け替えることが可能で、高濃縮ウランの製造が可能になるからだ。
だが、化学法では装置の大規模な改変が必要になる。北朝鮮のようにIAEAの査察官を追い出し、監視カメラも撤去しない限り、軍事転用は不可能だ。つまり、こっそり原爆を製造するには向かない。
可能性のあった化学法。時流には乗れず…
さらに、臨界しやすいという問題点がある。読者の中には、1999年9月に茨城県東海村で起きたJCO事故を覚えていらっしゃる方も多いだろう。この事故は、約19%に濃縮したウラン溶液を混ぜ合わせる際に起きた。
化学法も液体を使って濃縮するため、濃縮度が高くなると同様の事故が起こりやすい。下手をすれば工場ごと吹き飛ぶ。
藤井靖彦・東京工業大学名誉教授によると「濃縮度50~60%で臨界してしまう。だから安全性を考えればその半分以下が好ましい。旭化成は10~15%が最適だとみていた」と話す。
これでは90%以上の高濃縮ウランを使う原爆はできない。藤井名誉教授は「もし私が原爆製造を命じられたら、化学法は絶対に使わない。遠心分離法を使う」と言い切った。
「化学法は可能性があった。だが、技術は一度流れができると止まらない。早く実用化に乗ったほうが強い」
東芝でウラン濃縮を手がけた諸葛宗男・東京大学公共政策大学院元特任教授は話し始めた。VHSとベータが激しく競い合ったビデオ戦争や、レシプロエンジンとロータリーエンジンなど、いくら優れた技術であっても時流に乗らなければ主流になれない。
化学法による濃縮が成功したのは1980年代前半。岡山県の人形峠では、1979年から動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力研究開発機構)が中心となり開発した遠心分離法による濃縮が軌道に乗り始めていた。旭化成は、後手に回っていた。
旭化成で開発に当たっていた武田邦彦・中部大学特任教授は、それでも諦めなかった。当時の日本は、年2基ずつ新しい原発が運転を始める時代。濃縮ウランの需要が急速に伸びると思われていた。武田氏は「東日本と西日本にタイプが異なる濃縮施設をつくり、それを競わせることができるのでは」と望みをつないだ。
だが、それを打ち砕く大事件が起きる。ベルリンの壁崩壊だった。それまでは主に、東側諸国の原発用に使われていたソ連製の低濃縮ウランが西側市場に流れ込み、濃縮ウラン価格は暴落した。「新規事業の柱に据えたい」。そんな旭化成の夢はついえてしまった。
日本の核武装は「あり得ない」のか
日本が独自に開発した化学法に注目する国があった。電力の7割を原発で供給する原子力大国フランスだ。同様の手法を試みていたが技術的困難を克服できず、旭化成が撤退を決めたことを知り接触を試みた。
武田氏によると「数百億円で技術者ごと買い取るという提案だった」が、有能な研究開発陣をほかの分野に振り分けることを決めていた旭化成は、この申し出を断る。
それでも「原爆開発には最も向かない」という特性にこだわり続けた男がいた。
旭化成の機器を東工大に持ち込んだ藤井名誉教授だ。東工大初のベンチャー企業を設立し、総合プラントメーカーに設計を頼みプランをまとめた。その資料を携え、経済産業省資源エネルギー庁を訪れる。2011年の早春のことだった。
エネ庁の担当者は興味を示し「詳細な提案をしてほしい」と促す。だが、直後に起きた福島第1原発事故で、日本の原子力政策は根本的な見直しを迫られる。新たな濃縮法を検討する余地などあるはずもなかった。
戦後、一貫して平和国家を目指してきた日本では、多くの人が「核武装なんてあり得ない」と思っている。その一方で日本は、濃縮、再処理、高速増殖炉など軍事転用が容易な技術をすべて保有する国でもある。
海外で取材すると「日本の本音は核武装にあるのではないか」という声に接することが多い。「原子力の平和利用」を掲げる国なのに、なぜそんな技術まで持つ必要があるのか。15日から毎日新聞朝刊で連載を始めた「核回廊を歩く 日本編」で、その謎を追いかけている。
【プロフィール】
会川晴之(あいかわ・はるゆき)
編集編成局編集委員
1987年入社。盛岡支局、東京本社経済部、政治部を経て、2003年から07年までウィーン特派員。国際原子力機関(IAEA)を担当し、これを機にパキスタンのカーン博士が関わった「核の闇市場」などの核問題を担当する。2009年から12年までの欧州総局(ロンドン)特派員時代も、引き続き核問題を取材。日米政府が共同で進めたモンゴルへの核廃棄物計画の特報で、2011年度のボーン・上田国際記念記者賞を受賞した。朝刊の連載「戦後70年に向けて」で、「核回廊を歩く」を執筆。パキスタン編、イラン編に続く日本編を始めた。近著に『独裁者に原爆を売る男たち 核の世界地図』(文藝春秋)
*会川記者のネット独自記事はこちらで読むことができます。
*本連載は月5回掲載の予定。原則的に毎週金曜日に掲載し、毎月第5回はランダムに掲載します。
