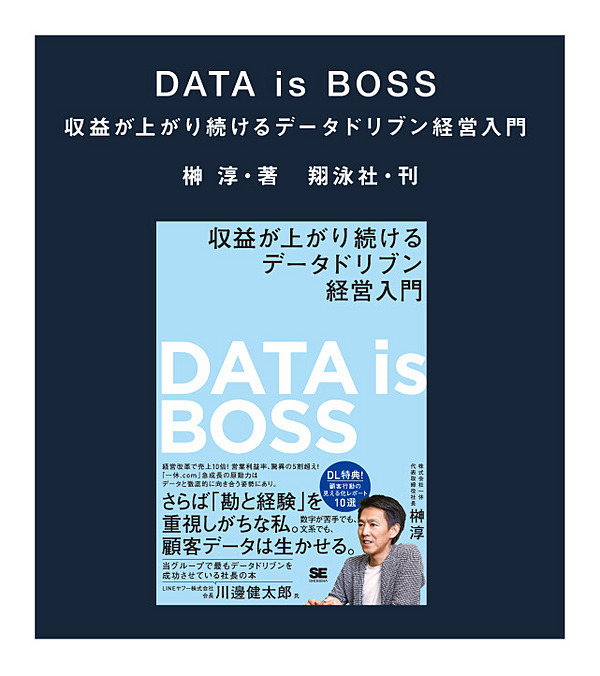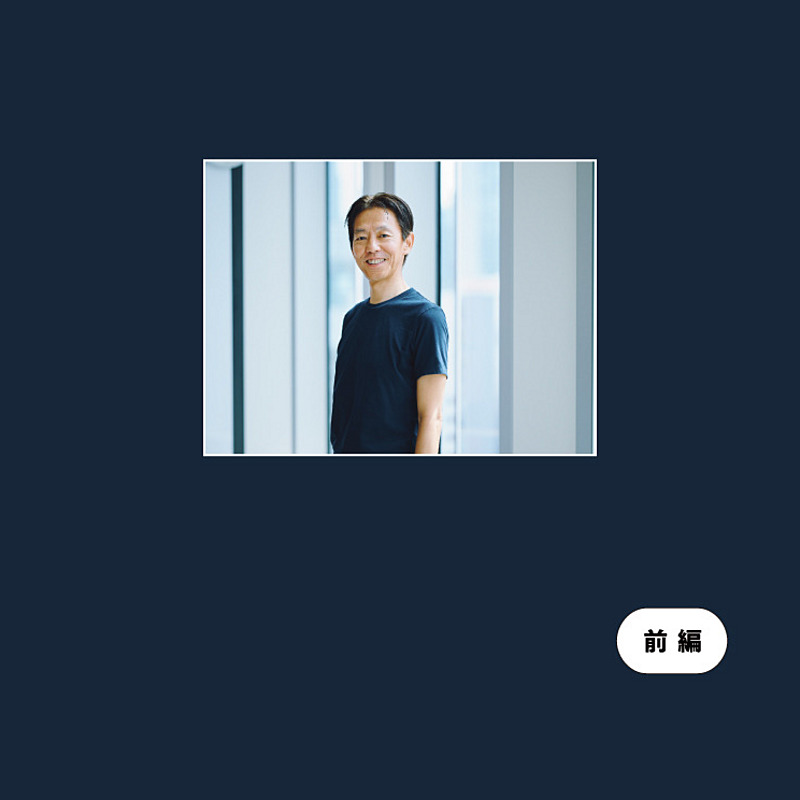
2024/6/26
【一休・榊淳】売上高10倍、営業利益率5割超え。「データドリブン経営」とは
厳選されたホテルや旅館の宿泊予約サイト「一休.com」などを展開する、株式会社一休。
代表取締役社長を務める榊淳さんは、2012年に外部コンサルタントとして経営に参画以降、サービスを手がけるなかで集まったデータを駆使する「データドリブン経営」によって10年あまりで同社の売上高を10倍、営業利益率は5割超えという成長を実現しました。
そんな榊さんが、『DATA is BOSS 収益が上がり続けるデータドリブン経営入門』(翔泳社)を出版。一休で取り組まれてきた実例を挙げながら、データドリブン経営とはなにか、いかにして取り組めばいいのか、その考え方や手法を網羅的に書いています。
どうすれば日本企業にデータドリブン経営が浸透するのか、ビジネスパーソンが日常の仕事のなかでデータを使ってできる取り組みなど、榊さんに話を聞きました。
代表取締役社長を務める榊淳さんは、2012年に外部コンサルタントとして経営に参画以降、サービスを手がけるなかで集まったデータを駆使する「データドリブン経営」によって10年あまりで同社の売上高を10倍、営業利益率は5割超えという成長を実現しました。
そんな榊さんが、『DATA is BOSS 収益が上がり続けるデータドリブン経営入門』(翔泳社)を出版。一休で取り組まれてきた実例を挙げながら、データドリブン経営とはなにか、いかにして取り組めばいいのか、その考え方や手法を網羅的に書いています。
どうすれば日本企業にデータドリブン経営が浸透するのか、ビジネスパーソンが日常の仕事のなかでデータを使ってできる取り組みなど、榊さんに話を聞きました。
INDEX
- 日本でデータドリブン経営が浸透していない理由
- 「ひとりの活躍」に賭けられない、日本人のメンタリティー
- オンライン・オフライン問わず、データを生かせる時代
- データドリブンによって現場から会社を動かせる

日本でデータドリブン経営が浸透していない理由
経営者という立場で考えたときに、「顧客を理解すること」が最も大切だと思っています。そうしたなかで一休という会社は、インターネットを通じてサービスを提供しているため、顧客の行動履歴がすべてデータとして残っているという特徴があります。
つまり、「顧客を理解する」=「顧客の行動データを理解する」ということです。
顧客行動のデータの理解を競争戦略上の最優先事項と位置づけているかを尋ねれば、インターネットサービスを手がけているアメリカの企業はイエスと答えるでしょう。
いまではさらに領域が広がり、例えばウォルマートのような小売業界の海外大手企業も、「誰がどの商品をいつ買ったか」という顧客行動データを駆使したデータドリブンカンパニーへと変貌を遂げています。
世界の潮流がそうなっているので、日本でもデータを活用した経営、「データドリブン経営」がどんどん広がっていくのではないかと思いますね。

日本でまだデータドリブン経営が浸透していない大きな原因のひとつは、年功序列を主とした人事制度にあるのではないでしょうか。
日本の多くの伝統的企業では、トップマネジメントを務めているのが年配の方々です。情報化が行き渡った時代を過ごしてきておらず、業界の慣習、商品の販売を担当している営業マンの声や卸売業者の反応、CMの評判といった定性的な情報をもとに経営判断をすることが主流でした。
長い間にわたってそのような状態だったので、ここ数年で顧客のデジタルデバイスに対するタッチポイントが増えてデータを取れるようになっても、経営に生かそうという発想に至っていないのです。

(写真:ijeab / gettyimages)
また、柔軟な人材登用が起きないことも一因でしょう。トップマネジメントがデジタルに精通した人材を採用しようとしても、企業の外部から招聘することが難しい。本来であれば、例えば買収した子会社で社長を務める20代の若者を本社の社長に就かせてもいいわけです。
海外では、むしろこういったケースは日常茶飯時に起きていますよね。
「ひとりの活躍」に賭けられない、日本人のメンタリティー
一休の経営に参画する前はボストン コンサルティング グループで大企業幹部を相手に仕事をしていたので、伝統的な経営スタイルについても理解しているつもりです。いかに社内で情報を吸い上げて、事業展開の力にしていくか。
例えば、営業担当者が取引先企業へのセールスの際にどういうことを言われたのか、日報に書いて経営陣にFAXで送る。そして送られて集まった内容を見ながら、そこで得た見解をもとに意思決定する。
こうしたプロセスはこれまで当たり前とされてきましたが、いまはそれだと勝てません。

現在では、どんな属性の顧客がどの商品を比較して購入に至ったか、データですべてわかってしまいます。従来と比べて段違いで精度の高い情報が集約されているので、その情報を理解したうえで、最も理解している人が独断で意思決定したほうがいい結果が生まれるのです。
イーロン・マスクは顕著な例ですよね。ひとりの有能な人材に権限を寄せる経営スタイルが競争力を持つようになっているのですが、日本人のメンタリティーに合わないという実情があります。
メジャーリーグで活躍している大谷翔平選手は、ドジャースと10年で約1000億円という巨額の契約を結びました。アメリカ人のようなこうした極端なリソースの配分は、みんなで力を合わせることを美徳とする日本人にはなかなか難しいのかもしれません。
ただ、データを扱うことにおいて、一人ひとりに環境の差はありません。例えば一休のデータは、私だけがアクセスできるわけではなく、他の社員も同じデータを見ることが可能です。
また使っているパソコンも、クラウド環境が整っているため、分析の機能に差はありません。つまり個人が活躍できる土台がそろっており、ひとりの人間がデータを駆使して隣の席の人間の1万倍の成果を出すような仕事をできるようになっているのです。

(写真:Kobus Louw / gettyimages)
オンライン・オフライン問わず、データを生かせる時代
私自身、データを仕事に生かそうとし始めたのは一休に入ってからです。それまで事業に取り組んできた社員にとって顧客行動データがあるのは当たり前で、一休の社内ではその有用性が認識されていませんでした。しかし私は、そのデータを大いに事業に生かせると考えました。
それまではコンサルタントとして企業の経営改善に取り組んでいましたが、必ずしもデータを活用していたわけではありません。データドリブン経営をうたっているので「データを使わない経営は下手なのでは?」と思われるのですが、そちらもまあまあ得意だと一応お伝えしておきます(笑)。

世の中では、伝統的な経営手法とデータドリブン経営は対極の位置にあるものだと勘違いされていると感じます。決してそのようなことはなく、私自身、データを見る一方で顧客や営業マンの声といった定性的な情報も大事にしています。
これまで手に入れてきた情報に加えてデータを取れるようになったという話で、データを活用するかしないかを問われたら、それは使いますよね。つまりデータドリブン経営というのは、伝統的な経営の上位互換の手法なのです。
日本の多くの企業が直面している課題は、データはあるけど生かせていないことだと思います。それも、なぜ生かせていないかを把握できていない。
私の見る限りでは、データをうまく扱える人がいなかったり、データをそろえられても経営判断に使えなかったりというケースがほとんどのように思います。
インターネットサービスに限らず、支払いの手段が現金からデジタルに移ったことで、リアルで店舗を構える業態をはじめ多くの企業にデータが蓄積されるようになりました。
そうしたデータによって顧客の像が明瞭になり、どういったターゲットにどのような施策を講じるかを考えられるわけです。顧客の理解が、経営戦略を大きく分けますよね。

データドリブンによって現場から会社を動かせる
経営に関わる立場ではなく、現場に近い仕事に励んでいる方々も、データドリブンを意識して取り組めることはあります。
私はもともとコンサルタントとして、企業の経営をどう改善するかを考える仕事をしていました。こうした観点で考えることは、実は入社1年目のビジネスパーソンから社長になる一歩手前の副社長クラスの人まで、誰でもできますよね。
また、先にもお話ししたとおり、データは誰でもアクセスできるものです。私であれば、データを使って経営層も気づいていないようなインサイトを得て、それを伝える努力をすると思います。
例えば牛丼チェーンを手がける企業で、社長は経験と勘から週5回の頻度で食事にきてくれるヘビーユーザーを重視しているとします。
しかし実は来店頻度の低いライトユーザーのほうが売り上げを伸ばしていて、そちらに施策を講じたほうが事業の成長可能性が高いとデータで示せれば、社長はその提案をした人材を重用するのではないでしょうか。
データを駆使して提案する経験を積むことは、いちばんのおすすめですね。

そうした提案が生まれる環境をつくることは、企業にとっても大切だと思います。
日本の企業だと、社長に提案する前に何段階か役職者を通す必要があったりしそうですが、フラットに意見を言えるようにすることは、年功序列をはじめとする構造的な課題を解決する嚆矢(こうし)になり得そうです。
本当に面白い提案であれば、社長は喜ぶはずです。自分もいまは社長の立場なので、データをふまえた提案をもらったら目を通すでしょうし、それが的を射ていたら経営に役立てようと動くと思いますね。
後編では、データドリブン経営の先に待つ「AIドリブン経営」について、そしてテクノロジーの進化にビジネスパーソンはどう向き合えばいいか、榊さんに話を聞きます。
執筆・編集:加藤智朗
撮影:大橋友樹
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
撮影:大橋友樹
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)