金剛組、「日本最古」を支えるのは古来の実力主義

全国の長寿企業を調査する日本経済大学の後藤俊夫特任教授が「日本最古の企業だ」と認定しているのが大阪市で社寺建築を手がける金剛組だ。578年の創業で1400年以上の歴史を持つ。飛鳥時代に社寺建築に携わる集団が存在したことが日本書紀に記述されており、聖徳太子ゆかりの四天王寺にも口伝があることなどから、帝国データバンクや東京商工リサーチの調査でも日本で一番古い会社とされる。
聖徳太子が初代を招く
飛鳥時代から、現代までの歴史をひもといてみよう。金剛組によると、578年に聖徳太子の命を受けて、朝鮮半島の百済から3人の工匠が日本に招かれ、その1人が初代の金剛重光だった。招かれた工匠たちは官寺として計画された四天王寺の建立に携わった。完成後も金剛組の初代はこの地にとどまり、「正大工」として寺を守り続けた。四天王寺では奈良時代に講堂などの建設も行われた。
戦国期の1576年になると、四天王寺は織田信長と石山本願寺の戦いに巻き込まれ、伽藍(がらん)全体が焼失。天下を統一した豊臣秀吉の下、1597年に四天王寺の支院に多宝塔が再建された。この多宝塔の雷よけの銅板には、金剛組に連なる総棟梁(とうりょう)として金剛匠の名が残されている。1614年の大坂冬の陣で四天王寺が焼失すると、江戸幕府は四天王寺を再建。金剛家の25代目の是則が伽藍の再建を命じられたという。
江戸時代までの金剛家は四天王寺のお抱えの宮大工であり毎年、定まった扶持(ふち)米を得ていた。しかし、明治に入ると1868年に神仏分離令が出されたことなどで、四天王寺が寺領を失い、事態が一変する。金剛組は定まった扶持米を失い、他の寺社の仕事にも進出することになった。
昭和に入って棟梁を務めた37代目の治一は職人としての仕事へのこだわりが強く、営業活動が苦手であったとされる。経営は苦しくなり、1932年に治一は祖先にわびて先祖代々の墓前で自ら命を絶った。窮地に妻のよしえが初の女性棟梁となり、38代目を継いだ。34年には室戸台風で四天王寺五重塔が倒壊。金剛組はその再建を担いながら事業を維持した。第2次大戦中は企業整備令によって整理対象の危機となったが、軍事用の木箱を製造するなどしながら命脈を保った。
戦後の55年に株式会社に転換した。戦後復興にあたって、防火・防災などの観点から社寺は鉄筋コンクリート工法のニーズが高まり、金剛組はいち早くコンクリートで木造風に見せる建築工法の開発を進めた。
だが、時代の流れには乗り切れず、経営は徐々に苦しくなっていく。39代目の下、80年に埼玉県に拠点を開き、関東エリアにも進出した。加工センターも開設し、関東で本格的な木材加工を始めている。しかし、競合が多く、知名度を上げるために厳しい条件で受注することも多かったという。
全社的に規模の拡大を急ぎ、一般建築にも参入した。外部の設計事務所と組み入札に参加し、マンションなどにも取り組み始めた。しかし、ゼネコンとの競争では採算の厳しい工事が多く、多額の借り入れで資金繰りが悪化。倒産寸前となった。
サポートに乗り出したのが、同じく大阪が地盤の高松建設だった。メインバンクが同じだったこともあり、「歴史や技術は国の宝であり、一度なくなると二度と元に戻すことはできない。地元の会社として見すごすことはできない。金剛組をつぶしたら大阪の恥や。古来の建築技法を伝承したい」と申し出た。
2006年に高松建設が設立した新会社に事業を譲渡し、金剛組は継続された。1400年以上培った技術、従業員、宮大工の組織が引き継がれた。08年には親会社の持ち株会社化に伴い高松コンストラクショングループ(CG)の一員となった。信用度は上がり、平成の期間に五重塔で9基ほどあった国内の新築工事のうち、3基を受注している。総合建設業の許可を持つが、高松建設の傘下に入ってからは原点回帰し、社寺の建築や国宝、重要文化財の修理などに専念している。
木造とコンクリートの両方を手がけるが、最近は発注側の木造志向が強まっている。コンクリートは木造に比べると耐用年数が短く、耐震基準が変わると使い続けるのが難しくなることもある。一方、木造は最古の木造建築である法隆寺が1400年以上経過しているほか、定期的な修理や大改修により500年以上経過している木造建築も国内に多くある。コンクリートに比べると火災などに弱いが、防火対策に取り組めば長持ちしやすい。

技能と運営の両面に強さがあった
歩んできた道のりを踏まえると、金剛組が長く事業を続けられてきたいくつかの理由が浮かぶ。長寿企業の調査・研究をしている静岡文化芸術大学の曽根秀一准教授は「大きいのが四天王寺の存在だが、もちろんそれだけではない。技能と運営の両面の理由が考えられる」と指摘する。
技能面で大きいのは職人集団の存在だ。社寺建築を手掛ける社外の専属の宮大工は技能組織としていくつもの組に分かれている。戦後間もなくは4組だったが、現在は8組ある。複数の職人集団を持つことによって組同士に競争意識が働き、技術が高まった面がある。曽根准教授は「長くこうした形を続けてきたことがコアコンピタンス(競争力の源泉)になっている」と指摘する。一方で8組は作業現場では一緒になるため、技術交流は自然と進んできた。
祖父も父も金剛組の仕事をしてきた人もいて、それぞれが金剛組と強い関係で結ばれている。基本的に、8組の棟梁はお互いに職人を応援に出したり受け入れたりしながら、金剛組の仕事を行っている。

運営面では必ずしも直系のファミリーにこだわらなかったという特徴が挙げられる。江戸時代になると、大阪にはほかにも社寺建築を手掛ける有力な大工の集団があり、金剛組も仕事を侵食されかねなかった。大工としての実力と同時に人の上に立つリーダーとしての資質が求められ、それぞれの時代に合った後継者を選ぶ必要があった。
後継者としてふさわしくない場合は長男であっても外してきたことが江戸時代の資料などから分かっている。過去にはいったん棟梁を引き継いだものの、仕事に身が入らなかったために名前を削除されるケースもあったという。婿養子をむかえることもあるほか、本家と分家がお互いに支え合う時期もあった。娘婿だった39代目も「後継者は長子相続ではなくて実力で選んできた」といつも話していた。

営業などは新体制で見直し
超長寿企業といえども、長い業歴の中では時代の変化に対応しなくてはいけない。金剛組の最大の変化は独立系から高松建設の傘下に入ったことだった。高松建設出身で会長を務める刀根健一氏によると、このときポイントになったのは「普通の会社に戻す」ことだった。
社寺建築の原資は氏子や檀家(だんか)の寄付が基本のため、時間をかけて集める。5年、10年計画で進むことも多い。工事が始まってから遅れが出たとき「工期を延ばしてほしい」とお願いすると認められることが少なくなかったという。しかし、これでは工程管理も原価管理もできない。「売り上げは自動的についてくるという感覚があった」と刀根氏は話す。
高松建設の傘下に入って取り組んだのが、情報の見える化だ。社員は会社の経営状態に疎かった。これを改め、経営情報をガラス張りにして社員に共有している。図面の共有や、材木の発注時期といった工程のマニュアルやフローチャートも整備した。原価管理も徹底。例えば材木は奈良県吉野町などの業者から購入するが、高松建設と同じように原価管理部門が発注する仕組みを取り入れた。
旧体制では仕事の掘り起こしに熱心と言えず、営業員もいなかった。新体制になってからは高松CGと同じように、開発提案から始める営業員を導入。過去に施工実績のある社寺を回ったり新規案件を開拓したりするようになった。営業担当者は大阪に10人、東京に7人いる。発注元の社寺は出入りの社寺工事の会社との付き合いがあるため、急に取引先が増えることはないが、少しずつ需要を広げている。
一方、職人の現場には手をつけなかった。宮大工は手作りの世界であり、一般的な建設現場との違いは大きい。天候によって道具の刃を研ぎ続ける日もあれば、加工した小口の処理を非常に丁寧に行う日もある。一般建築を歩んできた刀根氏は「最初はもう少し早く作業ができないかと思ったが、いろいろ話してみて急がせてはいけないことが分かった」と話す。
技能の強さは残り、体制が変わっても社寺との関係を維持している。長く続いてきた金剛組の名前には信頼感があり、社名も元のまま残した。
金剛家出身者も在籍
金剛組の年間売上高は約40億円。社寺からの大規模な仕事が入るかどうかで年によって違いが出てくるが、高松建設傘下で経営状態は安定しており、黒字を回復している。引き継ぎ前に社員は80人ほどだったが、現在は110人ほどに増えている。
金剛組はかつて四天王寺の境内にあったという。古い資料は失われたものもあり、未解明の部分もあるが、刀根氏は「四天王寺様の大工として1000年以上事業を維持しており、四天王寺様があることが続いてきた証拠だ」と話す。かつては四天王寺関連の仕事がほぼ100%だったが、明治以降は次第に比率が下がり、最近は10~15%ほどになっている。それでも四天王寺とのつながりが重要であることには変わりがない。
金剛組には金剛家の出身者が1人在籍している。40代目の娘にあたる人物で、金剛家の41代目の当主を務める。四天王寺が寺を守る「正大工」職を与えるのは金剛家に対してであり、四天王寺での職人の仕事始めの儀式「手斧(ちょんな)始め式」も金剛家と宮大工の行事のため、金剛組の社員は裏方スタッフを務める。経営にはかかわっていないが、金剛家の出身者は金剛組の象徴であり、宮大工にとっても四天王寺とのつながりにとっても大切だ。宮大工に仕事を発注するのは金剛組だが、師匠にあたる金剛家との間には強い絆がある。
1000年を超える業歴を持つ金剛組も新型コロナウイルスへの対応を迫られる。今期は受注残で仕事を続けているが、来期以降はコロナの影響が出てきそうだ。参拝や法要が減っており、葬式を簡素化する動きもある。社寺の工事を先延ばしするケースも出てきている。培ってきた強さは比類ないものだ。コロナを含めた世相の変化にどう対応するかが問われることになる。
(日経ビジネス 中沢康彦)
[日経ビジネス電子版2020年12月10日の記事を再構成]
関連リンク
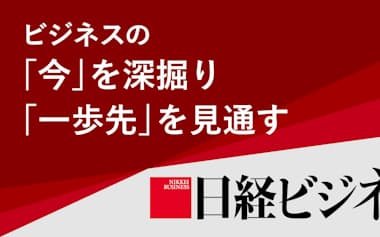
企業経営・経済・社会の「今」を深掘りし、時代の一歩先を見通す「日経ビジネス電子版」より、厳選記事をピックアップしてお届けする。月曜日から金曜日まで平日の毎日配信。













