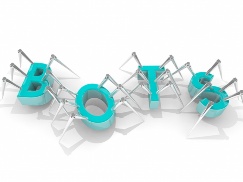ネット企業で導入が先行していた観のある軽量仮想環境の「コンテナ」だが、2021年はいよいよ一般企業を含めた本格的な普及フェーズに入りそうだ。取材のためコンテナを本番環境に導入している国内の大手企業を調べたところ、アサヒグループホールディングス(HD)、コニカミノルタといった製造業に加え、三井住友銀行、三菱UFJ銀行というメガバンクもリストに挙がった。
統計データの裏付けもある。IDC Japanが2020年2月に国内の企業および組織458社を対象に実施した調査によると、コンテナを「本番環境で使用している」と回答した企業は14.2%に上った。前年比で5ポイントの増加だ。
「導入構築/テスト/検証段階」「導入する計画/検討がある」「情報収集や勉強をしている」という導入に前向きな回答も足し合わせると、前年比で18.7ポイント増の66.2%に及ぶ。つまり3分の2の企業が、既にコンテナを導入済みか、前向きに取り組んでいる計算である。近年、IT基盤の新技術が次々と登場しているが、コンテナは企業の支持を得て着実に普及していきそうだ。
DXのIT基盤として威力を発揮
なぜコンテナの導入企業が増えているのか。背景には、オープンソースソフトウエア(OSS)のコンテナ管理ツール「Kubernetes」を中核とした、コンテナ基盤のクラウドサービスやパッケージソフトが充実してきた点が挙げられる。ただしそれ以上に大きな追い風になっているのが、企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展だ。DXのIT基盤としてコンテナは威力を発揮する。
DXではアプリケーションの開発・改変、テスト、デプロイ(配置)を繰り返す。いわゆる「CI(継続的インテグレーション)/CD(継続的デリバリー)」だ。コンテナはこのCI/CDを効率化する。
コンテナではアプリケーションとその実行に必要なライブラリー、設定情報などをまとめて「コンテナイメージ」として保存する。コンテナイメージは実行環境への依存性が低く、ITエンジニアのローカルの開発環境でも、クラウド上のテスト環境や本番環境でも同じように動作する。そのため「開発環境、テスト環境、本番環境でライブラリーのバージョンが異なり、正しく動かない」といった問題が解消される。
この特性を生かして、開発の委託先からアプリケーションをコンテナイメージとして受け取り、企業の垣根を越えて開発・改変、テスト、デプロイのCI/CDサイクルを迅速に回す取り組みも始まっている。