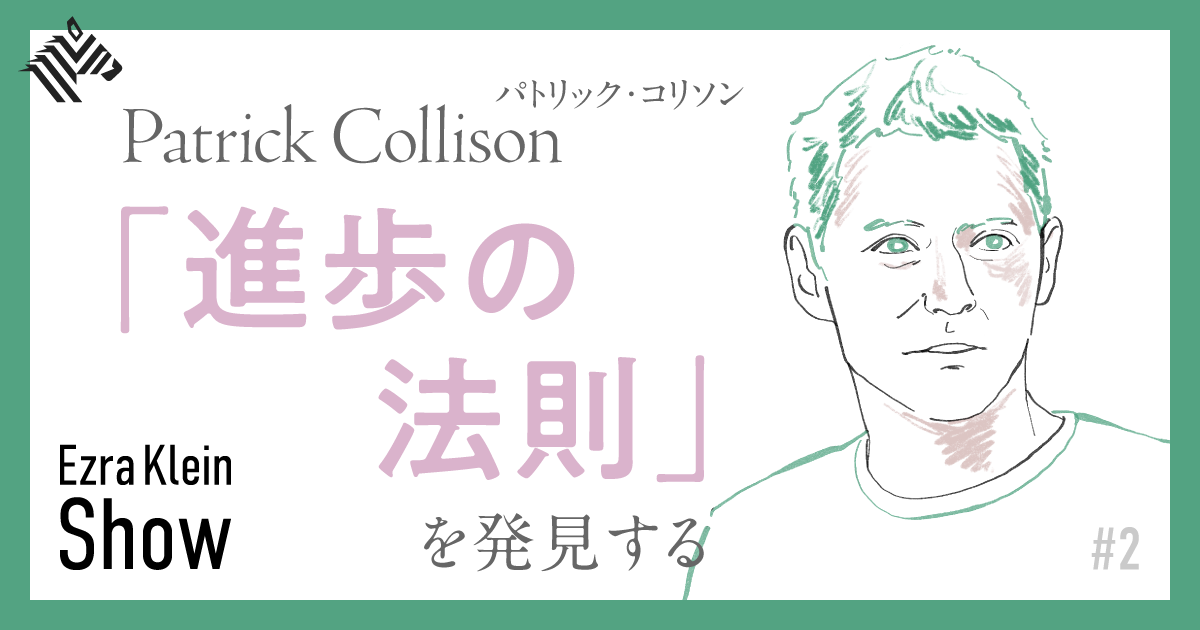【真理】進歩を後押しするのは「脅威」ではなく「希望」だ
コメント

注目のコメント
私が読んで思ったこと5つ
1)進化は少数の圧倒的な好奇心という熱量から生まれる
2)資本集約により進歩する領域やタイミングでは戦争や国家主導が機能する
3)人材流動・人材抜擢が起きると知見の融合から新たな発見が起きやすい
4)優秀な頭脳が助成金を出す人の説得やプロセスに無駄に投下されているのは同意見
5)教育が重要かつフロンティアなのは同意見
どれも当方が目下取り組んでいる社会価値創造、スタートアップ、イノベーションというテーマにも重なります。取り組みたいテーマが「どうすれば進化するか」「どうすれば進歩が加速するか」を考えて、アセット活用のスピードと質を徹底的に(※大事)こだわって考えることの重要性を感じます。
参考)
3)のテーマに関連することを以前書いたことがありました。
https://note.com/201707/n/n6aa1586b1e3e本題からはそれますが、助成金問題はアメリカもそうなんですね。ほんの一部の悪い人/間違い防止のために、1円単位で何重にもガードをかけて研究者の時間を取られるばかりか、チェック側にも膨大な作業が発生しているのが現状。雇用創出助成金なのかと思うことがあります。
例えばプラスチックも、第二次世界大戦における軍事利用の金属の不足を代替するものとして急速に発展し、利用拡大していきました。そして現代ではプラスチックの過剰利用や不適切な処理が問題であると取り上げられ、その代替素材の開発が活発化しています。イノベーションを後押しするのは、脅威でもあり、希望でもあると思いますね。
現代の助成金制度における研究テーマの縛りや、形式的で中身を伴わない作業などがイノベーションを阻む一因となっているという意見に同意です。助成金を得ることが主目的化しているプロジェクトの見分けも含め、AI技術などによる審査の最適化や手続きの効率化を進めることは、その国の競争力の強化に直接繋がるくらい、重要なことではないかと思います。