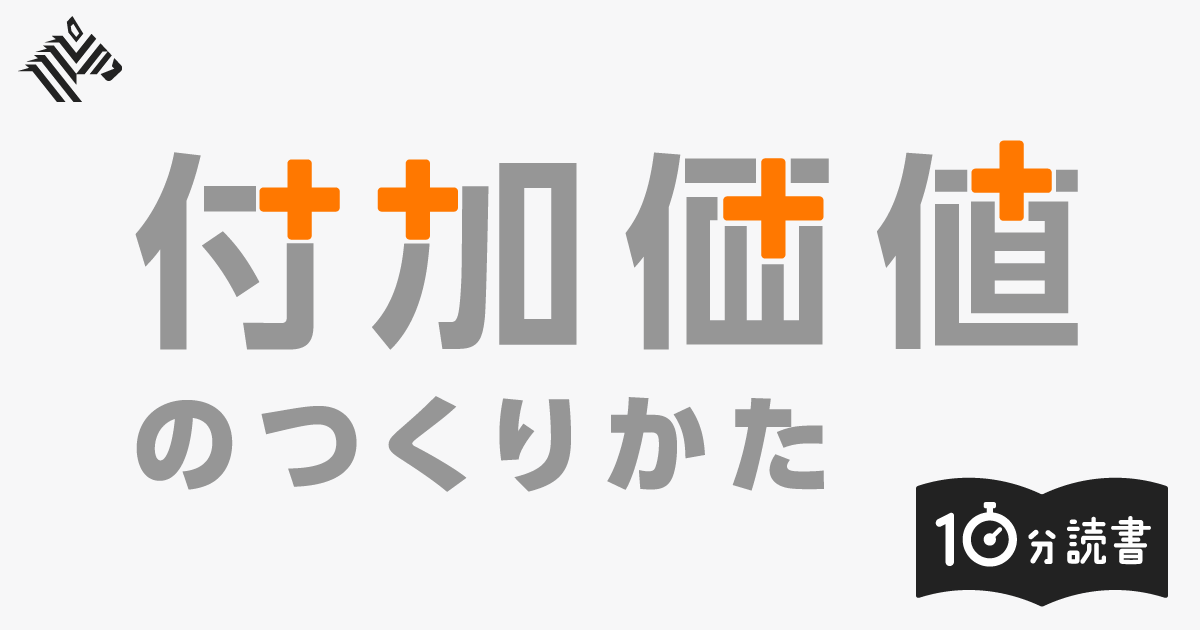【読書】キーエンス直伝、「価値」を生みだす方程式
コメント

注目のコメント
今回の10分読書は、キーエンス出身の経営者による、「付加価値のつくりかた」についてです。
大学での講義で、リアルな企業のデータを分析して提案をするプレゼンを「問題解決型学習(Problem-based Learning)」形式で行い、付加価値について考えました。
実際のところ、企業側もデータを分析してそれをビジネスに活かしているので、正直細かい分析をしても仕方がないというのが持論でした。
しかし、チームで困ったことや問題の洗い出しを行い、学生ならではの「消費者」という視点から考えると、企業のニーズに応えられる意外なアイデアが多く浮かびました。
本当に顧客が必要としているものをアイデアとして提案するーー。
「付加」価値を作り出す際には、相手に「負荷」をかけてはいけないということがよくわかる1冊でした。付加価値を考える時に色々なフレームワークがあるが、これもシンプルで分かりやすい。
記事の『お客様のニーズを超えた部分は「ムダ」になる』という図表を基に3点、私見を。
①お客様のニーズに対して、適切な価格を付けられるか
付加価値と、価格は似て非なるもの。安ければ売れるが、儲からない。高ければ、価値があっても売れない。だから付加価値・原価・価格を三位一体で設計・改善していくことが、超重要。
②価格は、競争に左右される
付加価値は製品によって大なり小なり違うし、比較検討しても結論が変わることがある。でも価格は全て金銭で比較可能。
①とも関わるのだが、売るためには競争相手との比較が重要。ただ安く売っていくと結局消耗戦になる。だから違うポジションを取ったり、買収をして競争圧力を減らしたり、徹底的につぶしてから値上げをしていくなども、事業戦略として重要。
③ムダ、は必ずしも悪いことではない
お客様の顕在化しているニーズと、顕在化していないニーズがある。またやってみることで、社内の中で知見が蓄積できることもある。なので「現在のムダ」は全て否定するものではないと思っている。
ただ、それは儲かっていることが前提。儲かっていて、投資的にムダも作り、そしてそれの一部が何らかの形でリターンとなって、競争でさらに強くなっている構造を作れるか。TikTokで「キーエンス」はバズワードのひとつ。
様々なショート動画が出てきます。
『キーエンス解剖』という本の紹介動画までよく見られていて、キーエンスの引きの強さに驚いています。