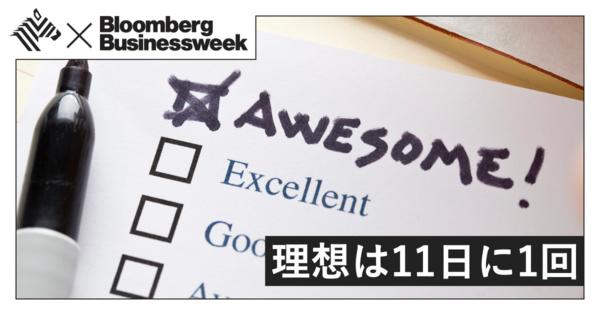【提言】「年次評価」を好きな人はいない
NewsPicks編集部
343Picks
コメント

注目のコメント
>年1回の人事評価は「5点満点で2点という評価を言い渡されるのを1年間も待つということです
本当にそうだ。普段はいい顔しといてなんなのよ、と信頼関係がもろ崩れする。
仕事は拙速遅行といいながらネガティブフィードバックを後回しにする上司には『恨み』が蓄積され、360℃評価など上司に関するフィードバックを求められるタイミングでスコアに思い切り反映される。
願わくばポジティブなフィードバックとネガティブなフィードバックを同じようなテンション、同じような心理的安全性を持って伝えられる管理職でありたい。年2回の人事評価は意味がない、半年前のことなんて誰も覚えていない、とはここ数年ずっと指摘されていることで、実態はわかりませんが2週間に1回のフィードバックに切り替えている企業が多いと欧米系のメディアは報じています。そりゃ、そうだ。
信頼があるから率直なフィードバックができるのか、率直なフィードバックから信頼が生まれるのか?ジャック・ウェルチは率直な文化づくりに10年かかり「まだまだだ」とその著書で指摘してますが、「はやり」の経営手法で踊るのが大好きな企業はとてもおぼつかないでしょう。入試や定期テストを好きな方が少ないのと類似の問題かと。
しかも、入試やテストには客観的基準がありますが、評価は基準が曖昧で評価者のさじ加減な部分が残ります。そりゃ余計に納得しにくいです。
とはいえ、年次評価の廃止はマネージャーの日常からの接し方が問われるので、組織文化と併せて取り組む必要がありますが、時間がかかる難儀な取組になります。
評価は答えのない永遠の課題ですが、システマティックなルーチン化だけは、双方にとって無意味なので避けたいですね。