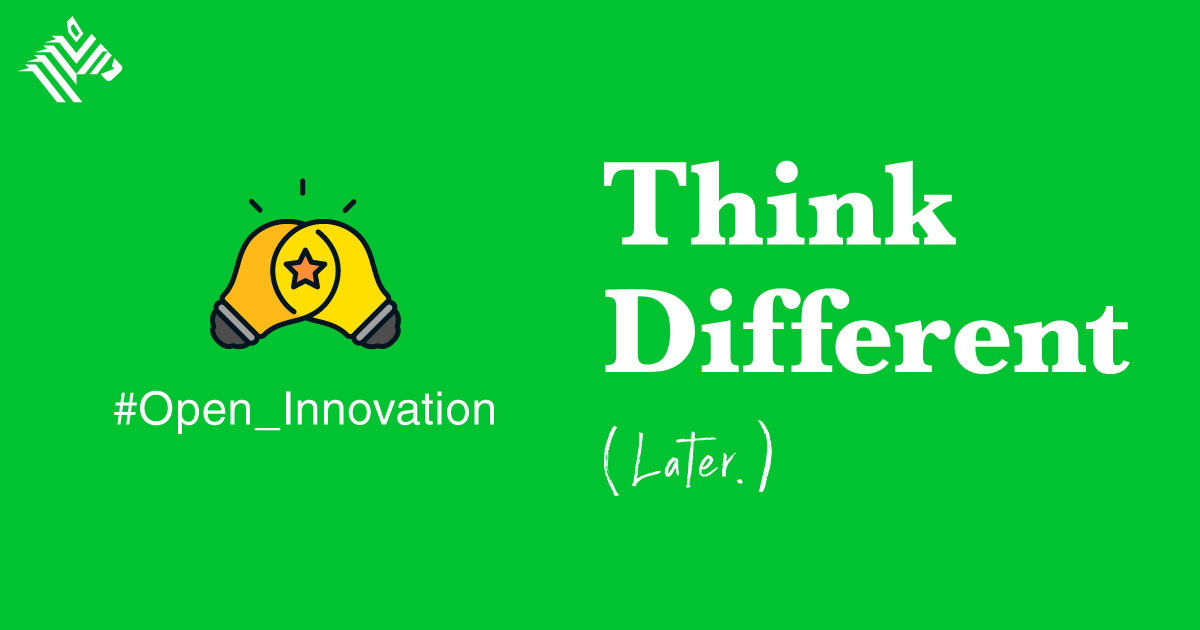【革新】中国式「野蛮発展」を取り込む、イオンモールの戦略
コメント

注目のコメント
日本なら1年かかるところが中国なら半年できる。2倍の速度でイノベーションを進める。
中国スタートアップとの協業によるオープンイノベーションに取り組むと発表したのがイオンモール。中国企業の突破力によって、自社からは生まれない新たな発想と技術を実装したいと意気込んでいます。
中国スタートアップに何を期待しているのか?イオンモールは何を変えようとしているのか?
イオンモールの中国事業責任者、橋本達也氏を独占インタビューしました。
このインタビューはマカオのテック博覧会「BEYOND EXPO」での公開取材という形式で行われています。
https://beyondexpo.com/
有料チケットを買うと、仮想空間でのオンライン対談(?)という謎の公開取材が見られるそうです。メタバース流行りですね。ただ有料なので、私も見てませんが……。
マカオはカジノマネーを使って次の産業を生み出そうとチャレンジしていますが、国際展示会もその一角。大金をぶちこんで、アジア版CESを作るという目論見でこのBEYONDは運営されているとのこと(もうすでに上海でCES ASIAはありますが)
カジノマネー・スーパーゴージャス展示会を一度生で見たいと思っているのですが、今年はコロナのためオンライン開催に。
****
チャイナテックの最前線をテーマとしたNewsPicksトピックス「デジタル・チャイナの裏側を掘る」をローンチしました。ぜひ閲覧、フォローをよろしくお願いいたします。
https://newspicks.com/topics/china/「中国から日本にDXを輸入」
これが今の日本の最適解でしょう。
日本はどうしても、外国から輸入して改良を加えることしかできないので、幸い、中国の方が先を行っている分野がある現在、模倣できる対象があります。
農業の6次産業化でも、大学の世界ランキングを上げることでも、中国の模倣をして改良するのが、確実に成果が上がります。
そのために、中国企業や中国の大学にどんどん若い日本人を送り込んで、ノウハウを学んで、日本で実践してもらうのがいいでしょう。中国でのイオングループの動きをみると、様々な分野において積極的にチャレンジしている印象です。
例えば、イオングループに属し、施設の管理・運営ノウハウを提供するイオンディライト株式会社は2018年に、中国のIT企業ディープブルーテクノロジー(深蘭科技)と合弁会社を設立し、無人店舗などの開発に乗り出しました。
「中国のベストプラクティスを日本へスピーディに水平展開」(記事引用)
様々なことに果敢にチャレンジしているからこそ、ベストプラクティスが生まれているのだと思います。
中国で生活していると、中国の消費者は完璧を求めず、ミスに対する許容度が高いと感じます。実際に、私自身も影響を受け、多少のミスに対しては「人間だもの」と笑って許しています。
このような環境だからこそ、「ミスったらどうしよう」と委縮することなく思い切ったチャレンジができるのです。
もっと多くの日本企業が、「実験場」の中国で色々と試してみて、成功事例を日本、世界へと水平展開していくといいと思います。