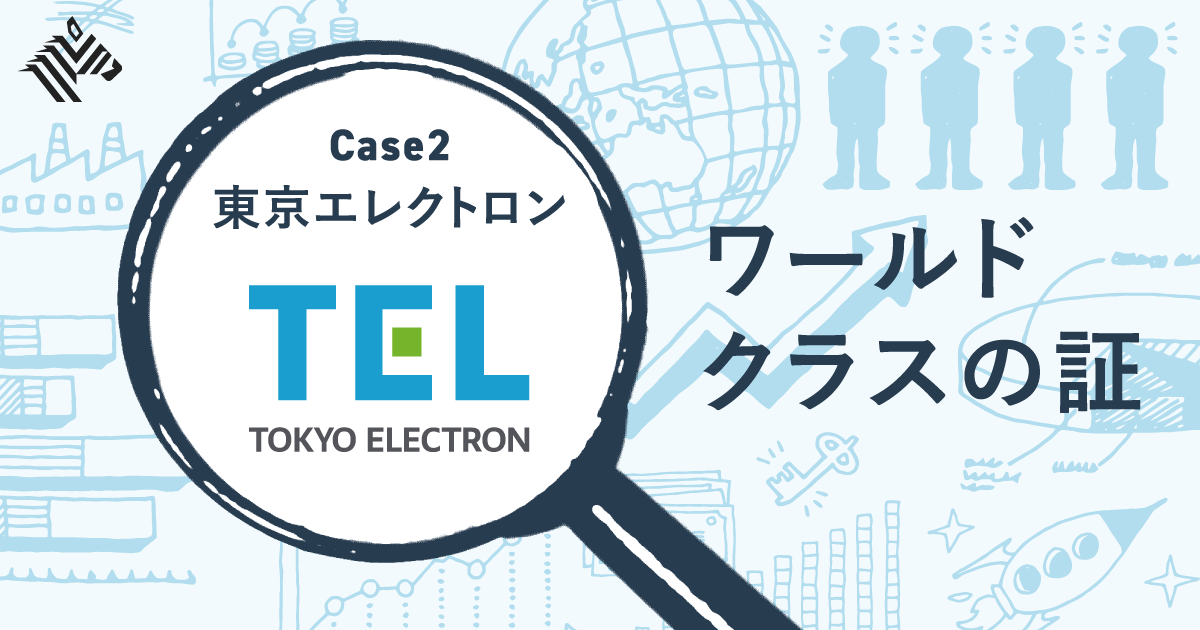【秘録】利益率20%企業が世界の「30%」に飛躍するまで
コメント

注目のコメント
市場成長率と比較せよ──。
昔、言われてハッとした言葉です。
日本人が大好きな、「増収増益」を達成したとして、競合となる企業(しかも、その多くが海外)がそれ以上に成長していたら、相対的な地位は下がっていることになります。
つまり、増収増益だから万歳、営業利益率10%近いからOK、ではなく、業界トップ企業を見据えて、規模も収益力も伍して戦う必要がある。
それができなければ、勝負する領域をより小さく絞ってグローバルニッチトップ、いわば「池の一番大きな鯉になる」になる覚悟も必要かと思われます。
そうした問題意識の中、時価総額うなぎ登り、ついでにボーナスランキングでもトップに顔を出すようになった東京エレクトロンの河合CEOにインタビュー。サッカーに例えるなら、日本代表がW杯で、いかにしてワールドクラスの戦いに挑むのか、聞きました。
追伸
前回の村田製作所も東京エレクトロンも、離職率の低さを強みにしていると感じました。
最近では、離職率(人材が入れ替わるのでターンオーバー率ともいわれます)が10%程度と、人材の流動性があった方が、組織の活力や多様性が増すとの意見もあります。
とはいえ、高度なテクノロジー企業では、離職率の低さが引き続き強みになると再認識した次第です。シンプルに、付加価値があり、それをしっかり経営できている企業は、利益率が高い。
個人的には、製造業でのざっくりの目安としては粗利率30-40%、営業利益率15%以上くらいを判断軸として持っている。記事にTELの粗利率・営業利益率が出ているが、しっかりそれに乗ってくる。また昨日特集があった村田は、粗利率が定常的に30-40%、営業利益率も15%以上。
自社で作っていて、装置は景気後退期には設備投資が減って需要が半減とかするし、電子部品は在庫サイクルもあり稼働率が下がり固定費が賄えない。そういうときはあっても、普段がこれだけ稼げていれば、資本も一定蓄積したうえで、レバレッジを利かせても経営に問題がない(2社とも意志あってではあるが、コーポレートファイナンス的には財務マネジメントはもっとしてよい会社)。
なお、製造業でも大きい自動車を見ると、トヨタの粗利率は18%前後、営業利益率8%ほど。これが悪いかというと、業態として自動車部品の仕入れが多く、自社内製率が少ない組立産業。鈴木修氏が著書で「売上大きいけど、付加価値の大部分は自社ではないと命じなくてはならない」といったことを書かれていた。
また、ソニーは粗利率3割弱、営業利益率1割ほど。ファブレスに製造委託しているAppleは、粗利率4割、営業利益率25-30%くらい。
内製率(限界利益率が変わってきて、売上の増減に対してのレバレッジが違う)や、BtoBなのかBtoCなのか(販管費が変わってくる)によって目安は変わってくるのだが、まずは上記くらいが経験則としては目安感。
そして自社の付加価値を理解して、しっかりと深めながら訴求することは経営そのもの。だから定性と併せて利益率(PLだけでなくROEなど含め)などを見ていくと、経営力は一定見えると思っている。最後のところに報酬の話が出ていますが、TELはかなりきつい成果主義を採用していることで有名です。キーエンスもそうかもしれませんが、世の中の流行に左右されず、自社の信念を貫き、その信念に共感する人が集まってくる会社は強いと思います。