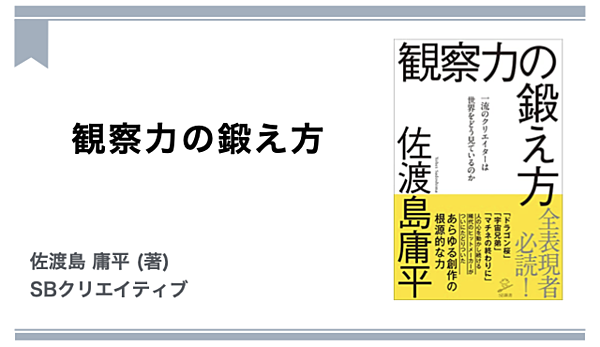【高瀬敦也×佐渡島庸平】システム型の「企画」を越えろ。未来を創る「企画」力とは何か?
2021/11/10
実際の現場で活躍する様々な業界のトップランナーをプロジェクトリーダーに迎え、「学ぶ・創る・稼ぐ」の実践を目指して生徒とともに研鑽する新時代のビジネススクールNewsPicks NewSchool。
今回は NewSchoolでプロジェクトリーダーを務めた高瀬 敦也氏の著書「
企画」のリリースに伴い、同じくプロジェクトリーダーを務めた佐渡島 庸平氏との対談が実現。
一方はフジテレビ、もう一方は講談社と畑違いではあるものの、いずれもコンテンツを生み出す世界で活躍してきた両氏。「企画」力が必要とされる世界を勝ち抜いてきた2人は「企画」をどのように捉えているのかを追ってみた。
「企画」本の名作
佐渡島 高瀬さんが執筆した「企画」ですが、この分野の本の中で一番素晴らしいと感じました。見事にMECEされており、抜け漏れがない。そのように書くことは、打ち合わせ段階ではできても、実際にはそうは仕上がりません。
高瀬 その点はかなり意識しました。
佐渡島 自分の成功体験だけだと抜け漏れが発生しがちですが、それが無く、内容についても自分が考えていることにぴったりでした。
これだけの言語化にいつから取り組んでいたのですか?

佐渡島 庸平(さどしま・ようへい)/株式会社コルク 代表取締役
1979年生まれ。東京大学文学部を卒業後、2002年に講談社に入社。週刊モーニング編集部にて、『バガボンド』(井上雄彦)、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『モダンタイムス』(伊坂幸太郎)、『16歳の教科書』など数多くのヒット作を編集。インターネット時代に合わせた作家・作品・読者のカタチをつくるため、2012年に講談社を退社し、コルクを創業。従来のビジネスモデルが崩壊している中で、コミュニティに可能性を感じ、コルクラボというオンラインサロンを主宰。
高瀬 フジテレビ時代から、バラバラとしたパーツはありました。
当時、何を言ってもフジテレビの人という肩書きがついて回ることに不自由さを感じていました。
自分の言葉で話しているつもりなのに、相手はそうとは受け取ってくれず、コミュニケーションが適切に成立しないという寂しさを感じていました。
その肩書を凌駕するために考えるようになった生存戦略が今回の内容です。
「企画」はシステムが生み出す
佐渡島 作中の「企画力はシステム」という一節に物凄く共感しました。
テレビ局・イベント会社・出版社の人たちは、みんな自分に企画力があると思っています。
でも、所属している会社が育んできた仕組みやシステムがあるからこそ企画が出せている側面があります。
例えば、講談社に勤める若手編集者たちは沢山のコンテンツを生み出しますが、それも講談社ならではの仕組みやシステムがあるからこそ発想できるわけです。
高瀬 仰る通りです。だから、自分のことを企画力があると信じるレガシーメディアの人々に対しては私も思うところがあります。
私自身、フジテレビで働いていた頃にいわゆる当たったと言われる作品をいくつか世に出すことができました。
しかし、「これは自分がつくったのか?」という疑問がいつもついて回りました。
それを紐解いた結果、会社が与えてくれるシステムと、それをうまく使う自分なりのロジックの両方で成立していると気づくことができました。
自分は閃くタイプではなく、それらを使って詰め将棋のように考えているのだと自覚できたわけです。

髙瀬 敦也/コンテンツプロデューサー・原作企画者
フジテレビ在職中「逃走中」「ヌメロン」「有吉の夏休み」など企画。ゲーム化も自らプロデュース。「逃走中」は累計100万本を達成。アニメブランド「ノイタミナ」を立ち上げ、「ノイタミナ」を命名。(株)ジェネレートワン創業後はNewsPicks「中田敦彦NEXT」や、一億再生を記録したリアリティーショー「3LDK」等ネット動画や、マンガの原作・脚本を行うなど幅広くコンテンツを企画。多業種で、新事業・商品企画、広告戦略など幅広くコンサルティングを行っており、15社以上で顧問・アドバイザーを務める。
佐渡島 そこに気がつく時点で素晴らしい。
会社に用意された仕組みが秀逸であればあるほど、ほとんどの人はその仕組みを意識できません。
でも、会社が提供しているシステム、言い換えるなら「無意識の制約」に動かしてもらっているので、そのシステムの提供元である会社を辞めると企画がいっさい思いつかなくなります。
高瀬 まさにそうですね。
佐渡島 私の運営するコルクラボでも、参加者に論理的ではない制約を課すことがあります。
最初は皆さん疑問を感じるのですが、その制約の内側にいることで徐々に行動変容が生まれます。
その行動変容は、まさにシステムが生み出しているのですが、必ずしも本人がそれを自覚しているわけではありません。
だから、そういった型や仕組みに頼る段階から本当の意味で抜け出すには、型に頼りながら型を自分の言葉にしていく必要があるのだと思います。
「企画」で人を優しく巻き込む
佐渡島 周囲を企画にどう巻き込んでいくかという考え方についても違いがあると感じました。
以前の職場で私が影響を与えなければならない相手は、一流の作家・デザイナー・映画監督といった方々で、そういった人たちの記憶に残る仕事をしようと思うと、「鋭さ」「強さ」を磨く必要がありました。
「今まで言われたことなかった」「こんな編集者はいなかった」と思ってもらえる鋭く強い発信があると、相手が「それいいね!」と巻き込まれてくれました。
高瀬 確かにプロの方・一流の方には、少し特別な言い方をしたほうが響く傾向がありますね。
通常の会話のラリーでは満足してもらえず、いきなり別のことを入れなければならないというか。
普通の方に対して同じことをすると、とても不親切な手法が喜ばれる。
佐渡島 まさにそうなのです。しかし今、自分の会社でこれまでと同じような接し方をするとインパクトが強すぎる。
それでは、巻き込みが生まれないと感じています。
しかし高瀬さんは、テレビというチームワーク重視の業界出身の方だからか、企画に巻き込むときの考え方が優しい。
出演される方たちを巻き込んで、視聴者を巻き込んでという、二重巻き込みのスタンスが身についているように感じます。
今回の本は、僕がケアできていない「優しい巻き込み方」が入っている本だと思いました。
高瀬 なるほど。そう言われると編集者の巻き込み方とは違うかもしれません。
チーム戦であるテレビと違って、どこまでいっても1対1の関係ですよね。
佐渡島 その上、編集者は作家に何か形として見せてはいけないのです。そうすると原作者になってしまう。
実際、こちらが具体的に提案した結果、説得力がありすぎてやりにくい、それよりも面白くて似ていないものを考えないといけないと感じる、と言われたこともありました。
高瀬 チームでやってきた僕に言わせると、周囲から良いアイディアをもらえるのであればむしろ有り難いくらいです。だから提案を拒む気持ちがあまり理解しにくいです。
作家さんという生き物の難しさなのかもしれませんね。
佐渡島 それも業界・会社ごとのシステムかな、と思うのです。
出版業界自体の構造が、作家が「自分の力でやらないといけない」と孤独を感じてしまう形に組まれてしまっているのです。
とはいえ、コルクではチームで編集するようになってきてアイディアの交換が自然と生まれるようになりました。結果、仲間意識も強くなっています。
編集する側が変わってきたように、今後は作家もチームでやるように変わっていくのかもしれません。
「企画」とは決めること
佐渡島 改めて本の内容に話を戻しますが、「企画は最終的な目的を決める」と定義している点もわかりやすいと感じました。
色々な会社でコンサルタントがミッション・ビジョン・バリュー、パーパスを決めたりしますよね。でも、巻き込むことまで考えると、そういった目的地は企画屋が考えるべきではないかとすら思っています。
とはいえ、最終的な目的地の認識が人によってズレることもあると思うのです。そこはどう導いているのですか?
高瀬 結局、どこのレイヤーまで上り詰めるかを共通認識にするだけの話なのかなと思います。
例えば、2年後の会社のことか、それとも10年後の社会のことか、あるいは50年後の自分の死に際のことなのかなど。
どこで止めているかがポイントで、まずはそれを理解してもらうことが重要です。
佐渡島 どこで止めるとちょうどいいのか、どれぐらいでやめると1番多くの人が巻き込めるのかを、どうやって判断するのですか?
高瀬 確かに難しいですね。社会の情勢やタイミング、相手の状況など、全てを踏まえて考えることにはなります。
佐渡島 高瀬さんはそもそも、目的地やルールなど、チームのための何かを決めることが上手なのかもしれません。
作中にも「企画とは決めること。企画がないと可能性も選択肢もあり過ぎて何をすれば良いのか分からなくなる。だから、物事を決めていくことが進むべき道筋をはっきりさせる手段だ」と書かれていました。
つまり、高瀬さんは「決定」の塩梅がちょうど良いのだと思います。
そういう感度は、どうやって磨いたのですか?
高瀬 一言で言えば自分の基準でしかないのですが、それが育まれた要因は、仕事はもちろん子供の頃からの性格だとも思います。
幼い頃から自意識過剰で、とにかく人のリアクションが気になりました。嫌われたくない、過剰に目立ちたくない、かといって無視もされたくない。
だから、他者との関わり方の試行錯誤の量が多かったのかもしれません。
佐渡島 でも、他者基準で試行錯誤してしまうと、駄目だったときにその人のせいにできてしまいませんか?
高瀬 そうですよね。だから自分で決めたことに対して、外部のリアクションがどうだったのかを気にしていたのだと思います。
決めるのはあくまで自分、でも決めた内容がどう見られているのかを考えてしまう。
それを続けたことでバランスが良くなったのかもしれませんね。
※後編に続く
(構成:赤坂太一、写真:遠藤素子)