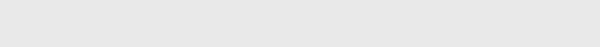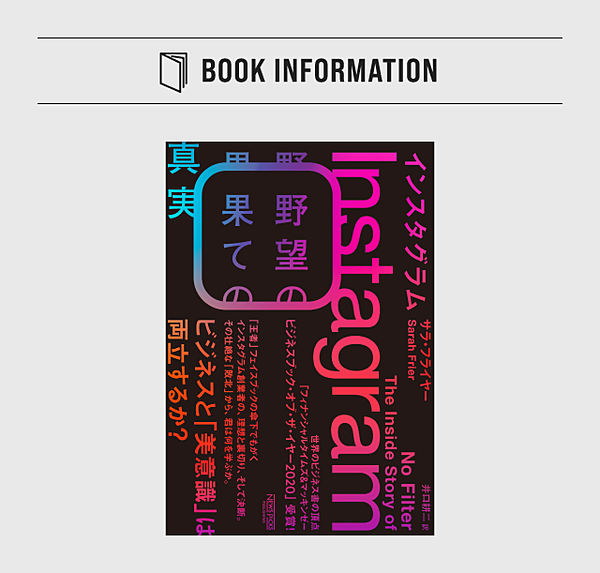2021/7/9
【受賞】米議会が注目。インスタ/フェイスブックの「確執」
インスタグラム創業者は、なぜフェイスブックによる巨額買収を受け入れたのか。フェイスブック傘下のインスタグラムはなぜ迷走し、創業者はなぜ退任したのか──。
FB・インスタの創業者ら200名以上に取材し、昨年末の「フィナンシャルタイムズ&マッキンゼー ビジネスブック・オブ・ザ・イヤー賞」を獲得したビジネス・ノンフィクション『
インスタグラム:野望の果ての真実』が、本日刊行される。
FBの寡占にメスをいれる米国下院司法委員会でも注目された本書を、日本のビジネスパーソンはどう読むべきか。NewsPicks記者、岡ゆづはによる解説をお届けする。
「生身」のインスタグラム
本書『
インスタグラム:野望の果ての真実』は、インスタグラムの誕生から、フェイスブックによる買収を経て、2018年9月に創業者2人が退任するまでを描いたドキュメントである。
物語は、インスタグラム共同創業者ケビン・シストロムから始まる。美味しいコーヒーと音楽、写真が好きで、関心の幅は広いがハマるととことん極める。エンジニア中心のシリコンバレーでは異色の、芸術家気質の創業者だ。

インスタグラム共同創業者、ケビン・シストロム(写真:Bloomberg/Getty Images)
シストロムの学生時代を描いた序盤から、登場人物はオールスター級だ。フェイスブック創業者のマーク・ザッカーバーグからは入社するよう誘われるも、シストロムは断りイタリア留学へと向かう。帰国後はツイッターの前身となるスタートアップでインターンし、7歳年上のメンター役、ジャック・ドーシー(ツイッター創業者)と仲良くなる。
シリコンバレーの舞台裏を描いた本書は、2020年4月の刊行以来、英語圏で高い評価を受けている。ビジネス系ノンフィクション賞の最高峰とされる「フィナンシャルタイムズ&マッキンゼー ビジネスブック・オブ・ザ・イヤー賞」に400以上の候補作の中から選ばれたほか、フォーチュン誌、フィナンシャルタイムズ紙、エコノミスト誌、Inc誌などの年間ベストブックに選出されている。
本書を読むと、インスタグラムやフェイスブックは、エゴや焦りを抱く「生身の人間」によって設計されていることがよく分かる。
インスタ創業者だって、人間だ
インスタグラムの知られざる物語として冒頭から読み進めていっても十分に楽しめるが、2つの点に注目しながら読むと、本書はビジネスのケーススタディとして更に深みが増す。
ひとつは、「共同創業者シストロムが下した一連の経営判断を追体験する」という読み方だ。シストロムは、大きく4つの重要な決断を下している。
- インスタグラムをフェイスブックに売却する
- インスタグラムに広告を導入する
- ライバルSNSスナップチャットの人気機能「ストーリーズ(24時間で消える投稿)」を実装する
- インスタグラムのCEOを辞める
消費者としての我々は、決断が下されたあとの結果しか知り得ない。しかし本書では、そこに至った経緯が丁寧に描かれている。
例えばインスタグラムに広告を導入する(2)という判断は、収益化に踏み切る重要なマイルストーンだ。シストロムがインスタグラムの収益化を急いだ背景には、毎週行われるフェイスブック幹部らとの経営会議での「居心地の悪さ」があった。
フェイスブックが広告で稼いだお金に頼っている限り、自分はインスタグラムのCEOとして対等ではいられない──。ザッカーバーグとその腹心らが中心の経営幹部に急遽加わったシストロムが、そうしたもどかしさに苦悩する様子が描かれている。
今やインスタグラムの人気機能となった、24時間で消える「ストーリーズ」導入(3)の裏にもドラマが隠れている。
当初、シストロムはストーリーズの導入に強く反対していた。
インスタグラムは、食べかけのサンドイッチをアップする場じゃない
確固たる美意識を持つシストロムは、ストーリーズの実装を勧める社員らの声に聞く耳を持たなかった。そんな中で、彼はなぜ一転して導入を決めたのか。
重要な経営判断に至る背景は、ユーザー数や売上の推移といった数字だけでは説明しきれない。本書を読み込むと、社内政治やエゴが渦巻く生々しい意思決定のプロセスを追体験できる。

(写真:hofred/istock)
「何を測るか」が、人のあり方を決める
もうひとつの読みどころは、「You are what you measure(何を測るかで、その人やビジネスのあり方が規定される)」という視点だ。
会社にとって最も重要な指標は何なのか。どのようなビジネスモデルを採用するのか。この選択によって、プロダクトの設計や会社のカルチャー、組織体制や人事評価制度などが大きく影響を受ける。
ザッカーバーグは、広告というビジネスモデルを選び、グロース(成長)を最も重視する文化を作った。ユーザー数の伸びやアプリ滞在時間を注視し、これを成長させた社員が評価されてきた。「素早く動き、破壊せよ(Move fast and break things)」というモットーは社外にも広く知られている。
一方、シストロムはザッカーバーグと異なる設計思想を持っていた。むやみにユーザー数や投稿数の伸びを追い求めるのではなく、クリエイティブで美しい投稿によって「コミュニティ」が醸成されることを望んだ。

(写真:fotoVoyager/istock)
プッシュ通知に対する考え方ひとつとっても、両社の違いは顕著だった。フェイスブックはできるだけ多く通知を飛ばしてアプリを開くよう促すのに対し、インスタグラムは「通知が多すぎると、意味がなくなる」と考え、内容をより厳選していた。
しかしフェイスブックに買収されてからは、インスタグラムもフェイスブックの価値観と無縁でいられなくなる。フェイスブックでは、「グロースに貢献した人」が評価されるためだ。
シストロムは、競合を潰すか、お金を稼ぐかしないとフェイスブックでは居心地が悪いと悟り、ビデオなどの新機能を開発するようになる。
「人事」はメッセージだ
だが、インスタグラムが広告収益を上げるようになってからも、シストロムの苦悩は終わらない。
インスタグラムの元幹部は、「フェイスブックは、パーティーのためにドレスアップする妹を手伝うけれど、自分より可愛くなってほしくはない『姉』のようだった」と、本書内で証言する。
2018年5月に行われた大きな組織改革からも、「インスタグラムはフェイスブック傘下」というザッカーバーグのメッセージが如実に伝わる。
フェイスブック、インスタグラム、メッセンジャー、ワッツアップという4つのアプリを統括する役職(Family of Apps)が新たに設けられ、シストロムはその下に属する体制となった。
その4ヶ月後、シストロムはCEOを退任する。退任前、彼は親しい友人にこのように打ち明けていたという。ザッカーバーグが、インスタグラムをフェイスブックの一部門として経営したいなら、そうさせてやる時期かもしれない。もう一人の「CEO」は必要ないのでは──。
本書は、シストロムら共同創業者の電撃退任で締めくくられる。
これからのインスタ、3つの論点
最後に本解説では、その後の動きを踏まえて「これからのインスタ」を考察したい。
筆者は、経済メディアNewsPicksにて2017年からインスタグラムの幹部取材を行っており、創業者退任後の経営体制について幹部陣を直撃した特集「インスタ2.0」なども手掛けている。
これらの取材をもとに、日本の読者も関心が高いであろう3つの論点を考えたい。
- 創業者が去ったあとの経営体制
- ソーシャルメディアの「寿命」
- インスタグラムにとっての日本市場
いいね数を隠した、インスタの「後継者」
まず気になるのは、カリスマ創業者が去ったあとの経営体制だ。その顔ぶれを見ると、ザッカーバーグ及びフェイスブック本体の影響力の高まりが感じられる。
シストロム退任後はCEOという役職は設けておらず、アダム・モセリが「責任者(Head of Instagram)」を務める。
モセリは2008年に入社した、ザッカーバーグの腹心の一人だ。フェイスブックのメイン機能「ニュースフィード」を長らく手掛け、「うけるね」「悲しいね」といった絵文字リアクションの生みの親でもある。
プロダクト、デザイン、エンジニアリングなど、モセリの下につく各専門の責任者も2019年頭に一新され、フェイスブック本体の社歴が長い人材で固められた。
モセリ体制下で行われた大きな取り組みのひとつが、「いいね数」の表示をなくす実験だ。
この意図について、モセリはNewsPicksの取材(2019年)に対し「特に『若い人たち』が投稿する際のプレッシャーを減らしたかった」と語っている。
インスタグラムは、フェイスブック本体よりも若いユーザー層へのリーチを強みとしてきた。しかし、若い人向けのソーシャルメディア(SNS)は「寿命」が短いのが難点でもある。
進学や就職など人間関係がリセットされるタイミングで、つながる「友達」も整理したい欲求が生まれるため、メインで使うSNSは5〜6年のスパンで入れ替わりがちだ。
2010年創業のインスタグラムは、SNS業界ではすでに「古参」の部類に入る。いいね数の非表示や、TikTokに似たショート動画機能「Reels(リールズ)」を導入するといった取り組みの裏には、若い世代へアピールし続けなければいけないという焦りもにじむ。
インスタにとって特別な「日本市場」
日本の読者にとっては、日本市場の位置づけも気になるところだろう。
日本には3300万以上のユーザーがおり、インスタグラムにとって注力市場のひとつだ。さらに2019年には、アメリカ以外で世界初のプロダクト開発拠点を立ち上げている。
そのトップを務めるのは、イアン・スパルター氏。インスタグラムの元デザイン責任者で、インスタグラムのロゴ変更を手掛けた人物でもある。
スパルター氏はNewsPicksの取材で、「日本はインスタの月間ユーザー数がフェイスブックよりも多いという点で世界的に見ても特殊な市場であり、日本ユーザーの使い方を徹底的に研究している」と話していた。
こうした調査から生まれた日本発の機能もある。アカウントのQRコード表示や、近隣の人気スポットを検索できる地図検索機能などが一例だ。
だが、ストーリーズのようにユーザー数飛躍の起爆剤となる「キラー機能」の開発には未だ至っていない。
創業から時間が経つほど「目新しさ」は失われていく中で、インスタグラムはユーザーを惹きつけるプロダクトを作り続けられるのか。
本書を読むことが、我々が普段ユーザーとして使うサービスを、経営の観点から考察するきっかけとなれば幸いだ。
執筆:岡ゆづは
編集:富川直泰
デザイン:黒田早希