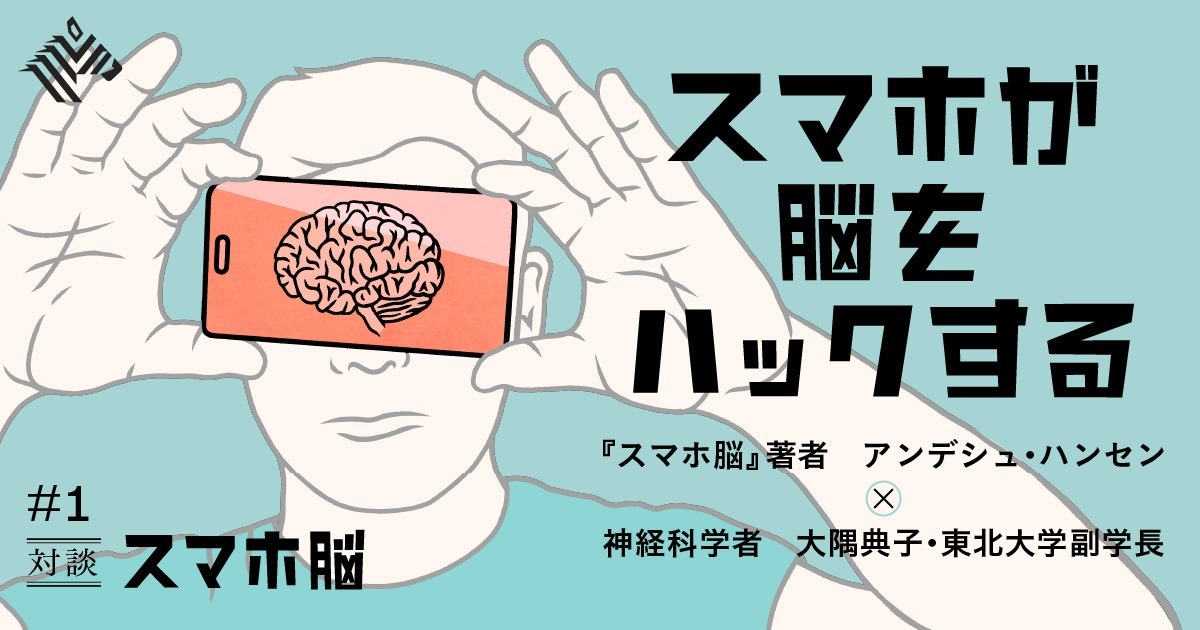【大問題】なぜ、スマホがあると「脳」は集中できないのか
コメント

選択しているユーザー
注目のコメント
コロナ禍の頃、こちらの取材対応をして記事になっていましたが、8月に関連するプレスリリースに基づく記事が出ていました。海外の方が話題になっているようです。
MIT Review:1歳時の画面閲覧時間と2歳・4歳時点の発達に関連
https://www.technologyreview.jp/n/2023/08/30/316051/
東北大学からのプレスリリース:
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2023/08/press20230822-01-screentime.htmlGoogle効果/デジタル健忘症については、電話番号、パスワードなど覚える必要がない、もしくは覚えておく価値が低いデータと、自分の知識や知恵として蓄積しておくべき情報がそもそもあることを自覚し、それぞれを分けて獲得しておくと有用に思いました。
コロナ禍で更にスマフォ・デジタル機器への依存が高まっている中で、これらへの健康的な向き合い方を心得ておくのは大変有用です。
習慣・癖をつける/直すには約3週間かかると言われていますが、スマフォを部屋の外など目の付かないところにおく、就寝前にスマフォを見ない等々、この記事に記載されていた様々な対策を取っていけると良いですね。スマホは脳をハックしにきます。ただ、私はスマホ大好きなので(今もスマホからコメントを書いています)スマホやSNSをやめることはしません。
なので、「スマホを一時休憩」することにしています。
仕事をするときは、以下のように
「もくもく会」を活用したり、1人でも応用しています。
▼生産性向上「もくもく会」
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO56627880Q0A310C2XY0000
長女がスマホ中毒気味な中学生なので(^◇^;)
家のWi-Fiは、Switch BOTというスマートコンセントを使って、Wi-Fiルーターの電源がまるっと、夜9時に切れて朝6時に入るようにセットしています。
これだけでは、子供はモバイルデータ通信ができてしまうので、データ容量が天井を迎えて超低速になってしまう前は、
私がパソコンから子供のdアカウントで、マイドコモにアクセスし、「盗難紛失はこちら」をクリックして、まめに、夜9時過ぎに、モバイルデータ通信を停止して、朝6時に、再開しています。
面倒ですが、これをやらなければならないほど、この小さな鉄の板に私たちは魅入られています。