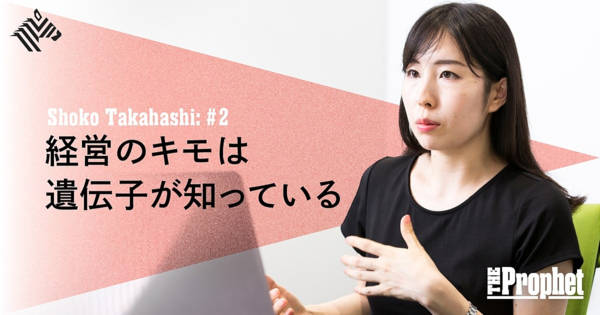【組織論】生命科学で分かる「ダイバーシティの本質」
NewsPicks編集部
662Picks
コメント

選択しているユーザー
多様性というと、ついつい女性管理職の比率、外国籍社員の比率、年代の比率など、表面的に見えやすい部分で多様性を語ってしまいがちだなと自分自身も反省。よくよく考えれば、30代男性だらけだとしても、個々人の持つ能力スキルや価値観などは全く異なるし、多様性もどの粒度で見るかや、どこから見るか(社会という視点で見れば、同質性が高い人が多いといわれる会社もあれば、多様性のある人が多い会社もあって、多様なのかもとも思う)が重要だなと。
注目のコメント
高橋さんの本!めちゃめちゃ面白い。多様性はありすぎても少なくぎてもだめですが、まさに以下が大事ですね。
【同質性、企業でいえば企業理念に共感しているとか、チームとして実現したい目標が一緒だとか、そういうところが一致した上で、さまざまな考え方や経験の人が集まっているというのが正しい多様性のあり方です。】「多様性とは、共通する部分、つまり同質性があるという前提で、一部が多様であることを指す言葉です。」「組織で多様性の話をするときには、まず『その組織における共通の遺伝子、つまり同質性は何か』を定義するのが一番大事になると思います。」この点はとても大事なのに結構見逃されてきたポイントだと思う。軸がなければ組織は発散するだけ。参考になりました。